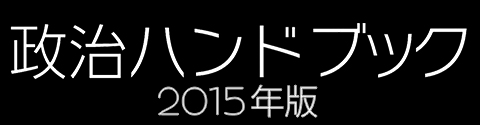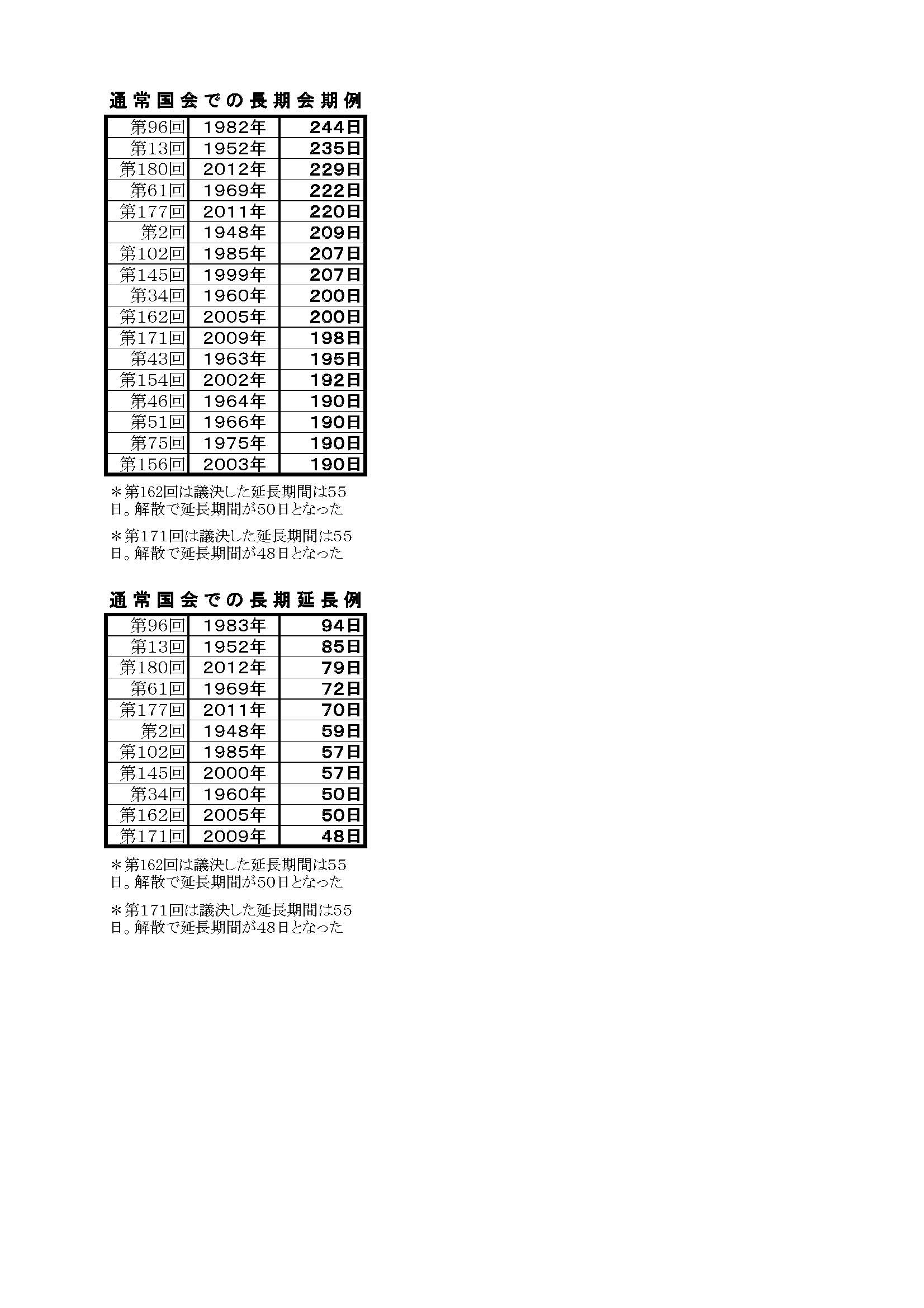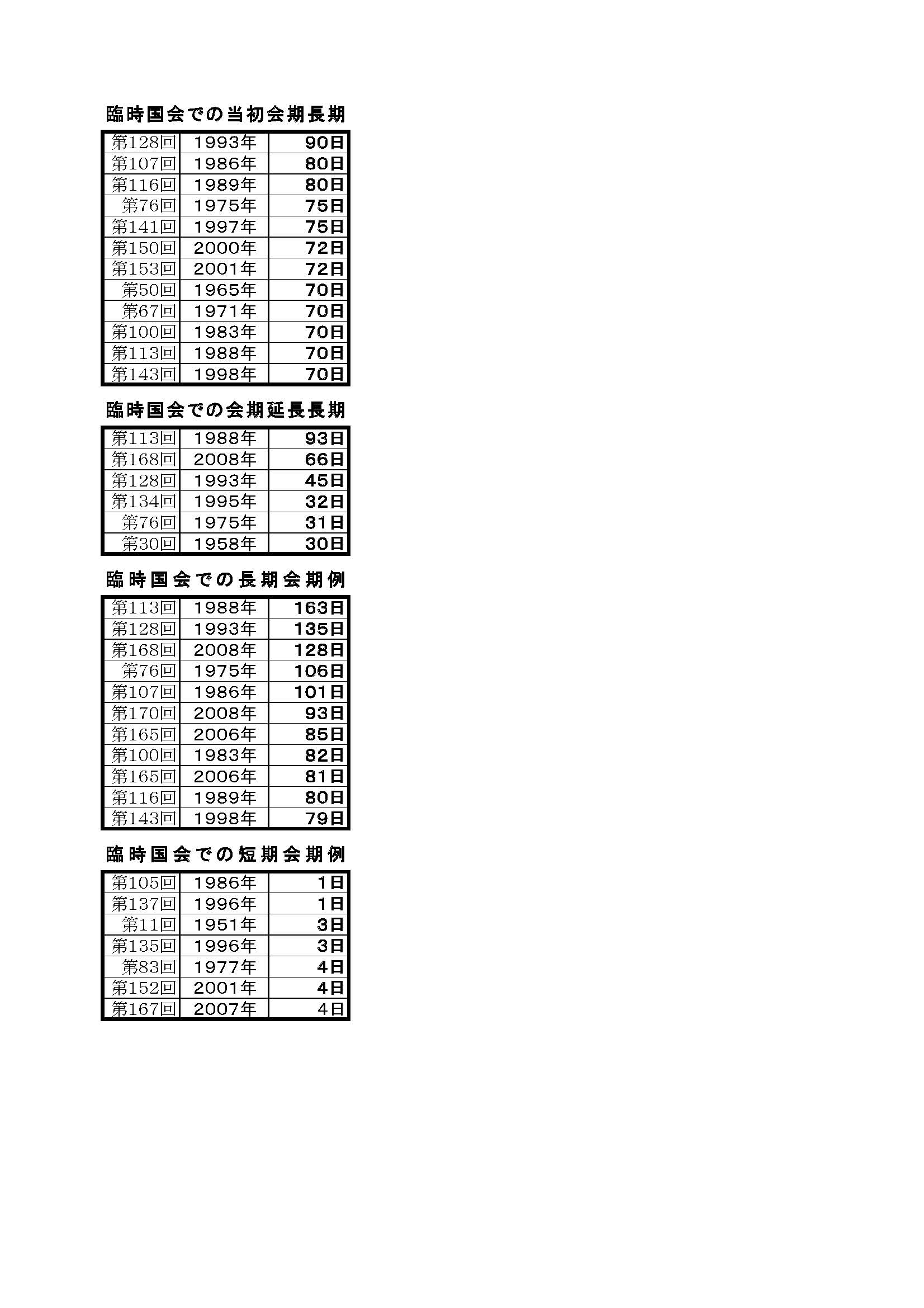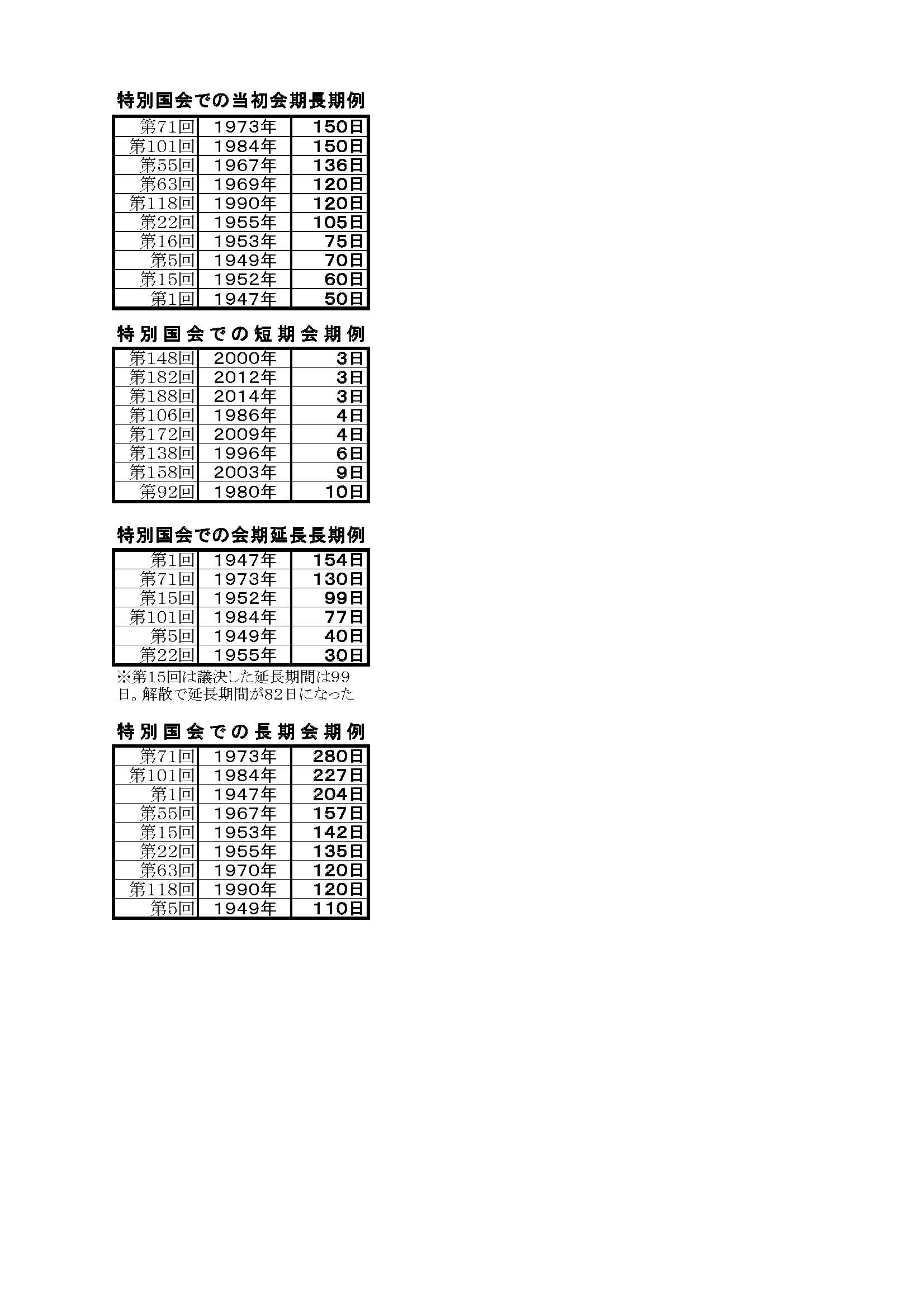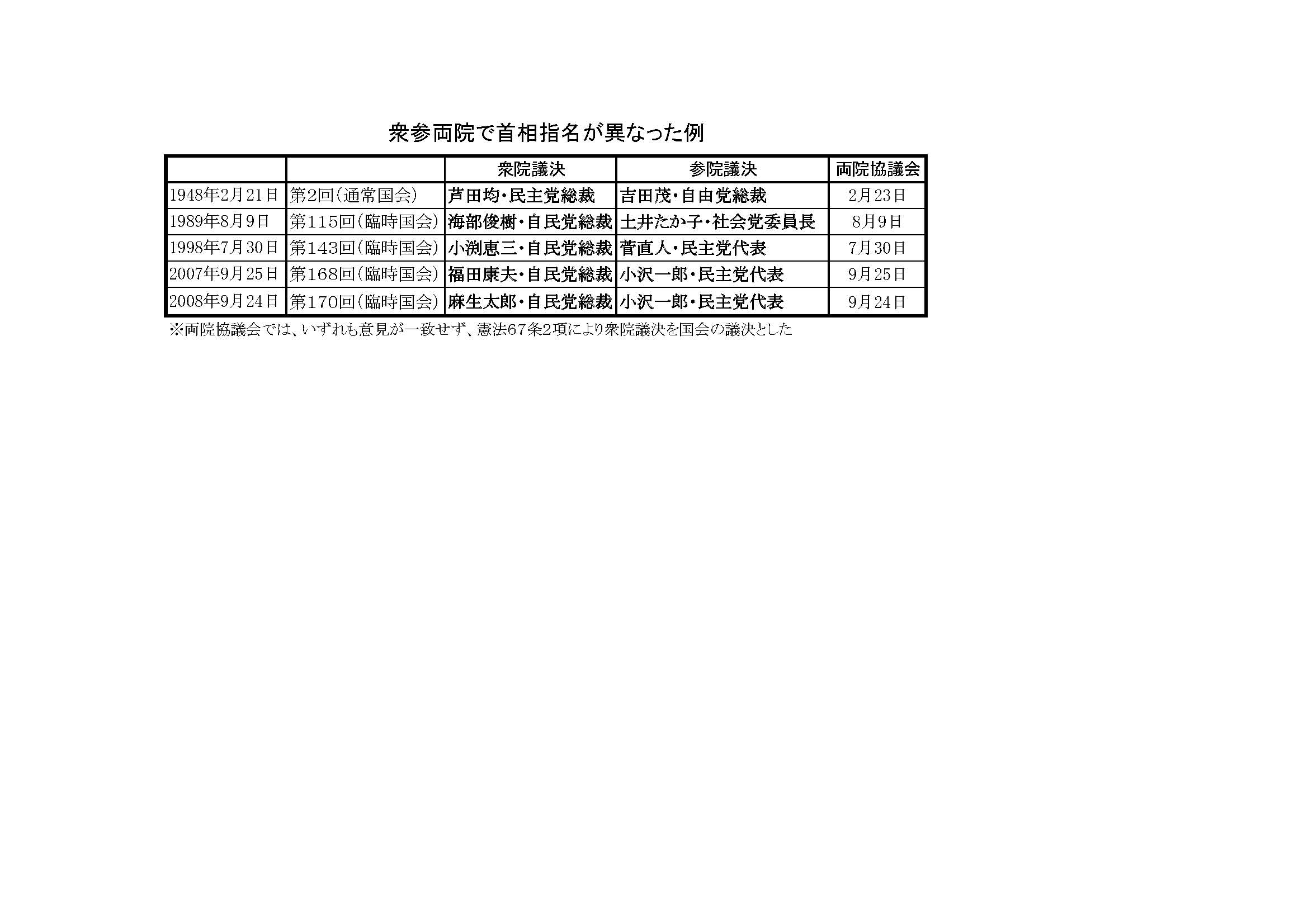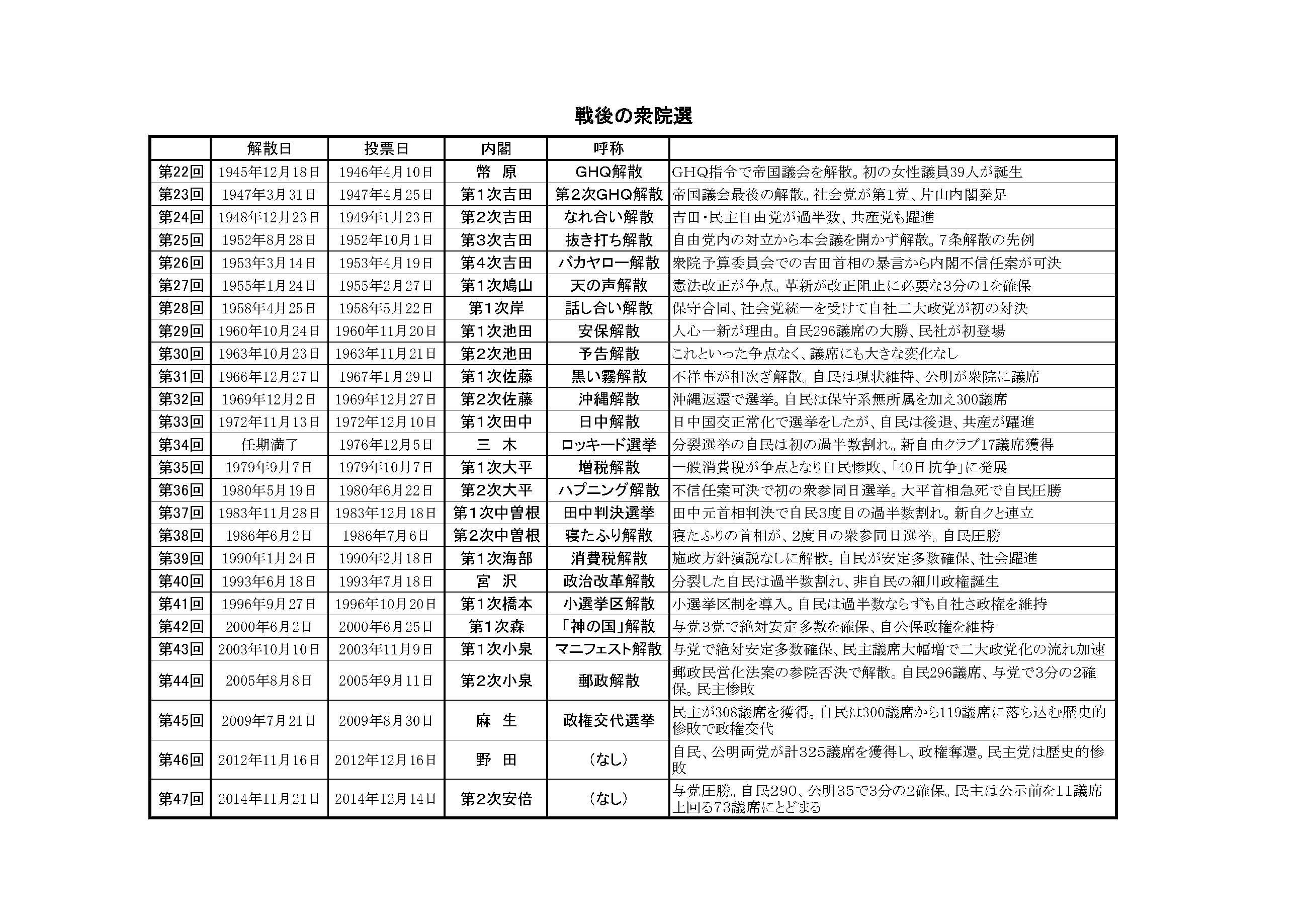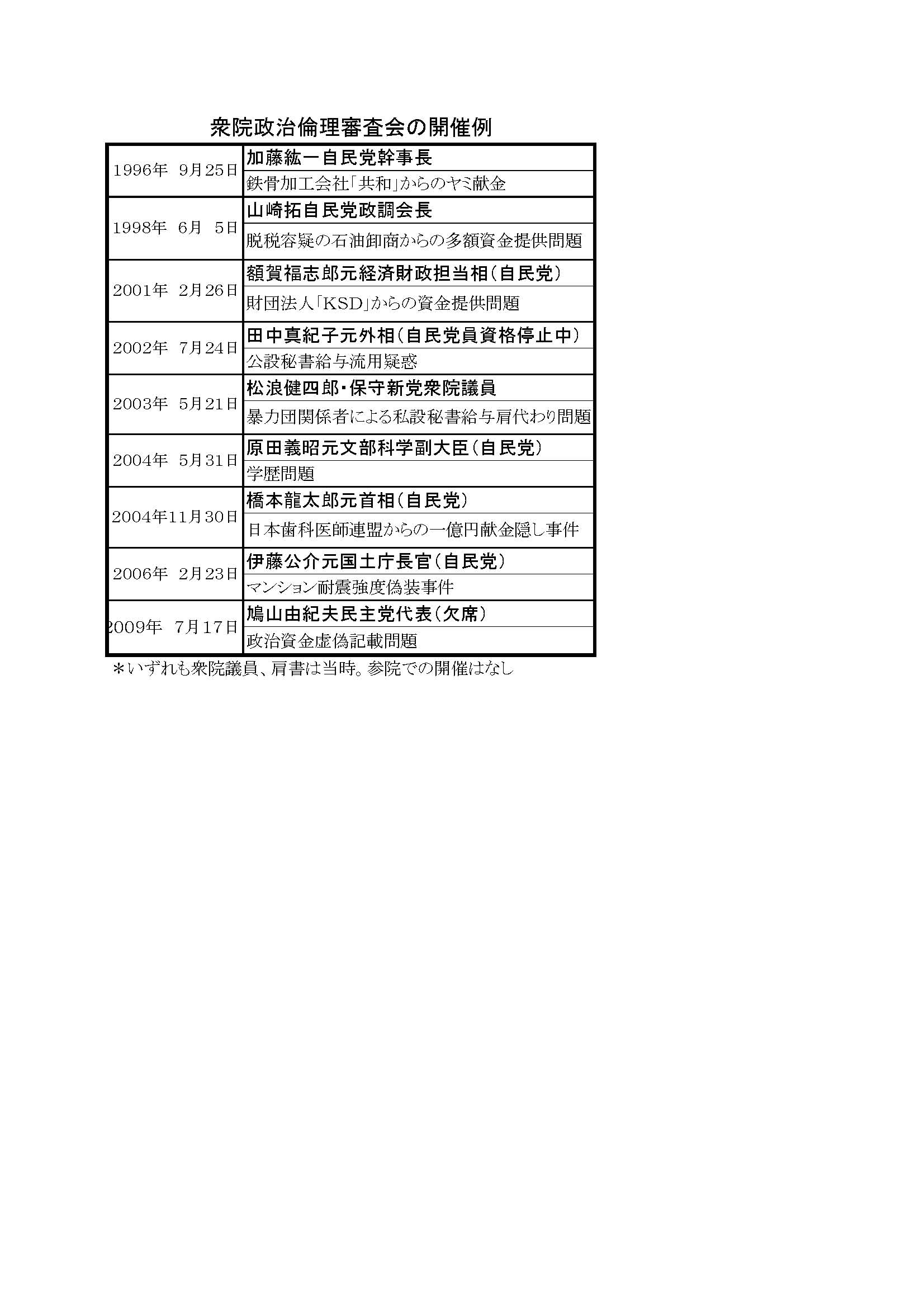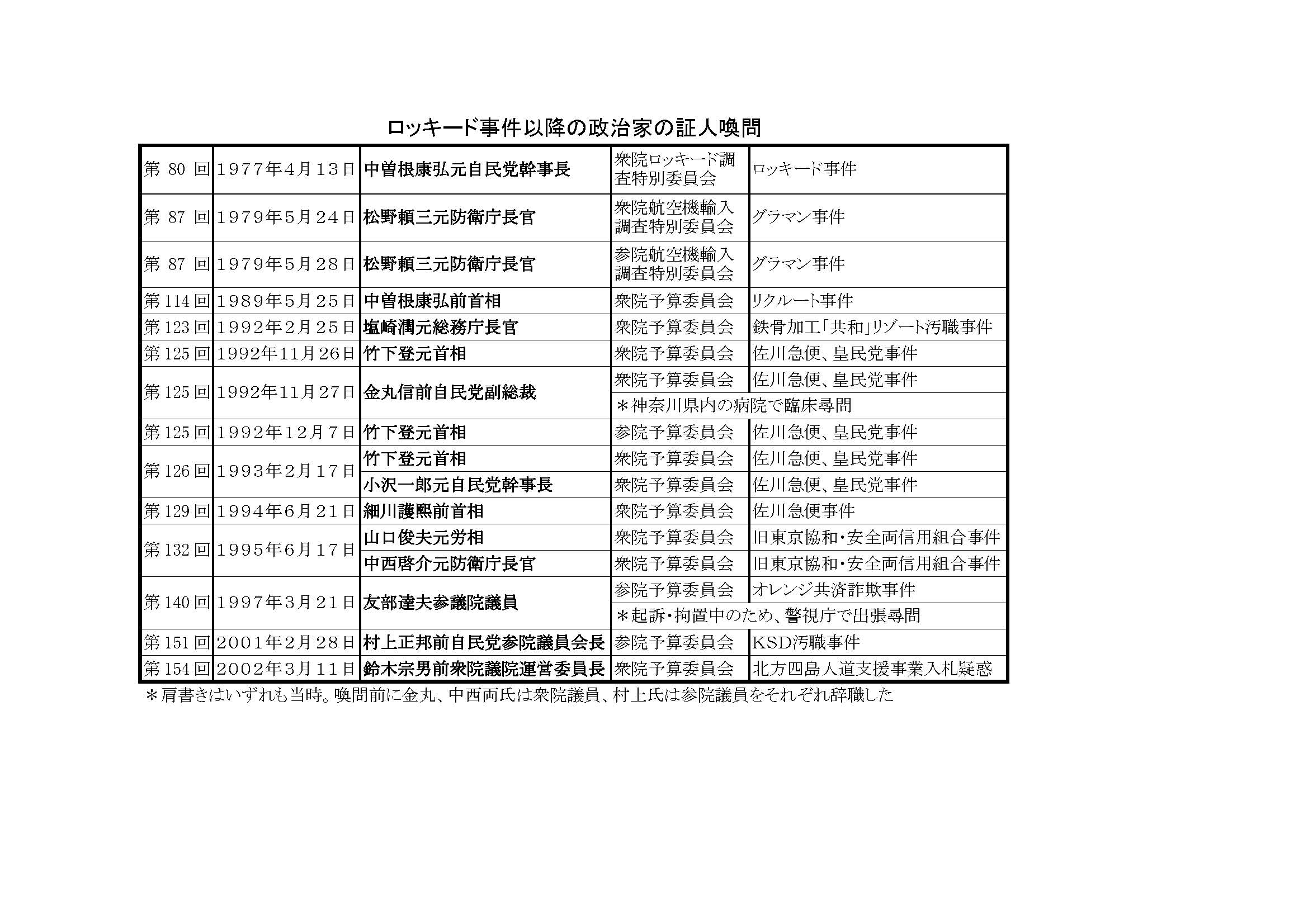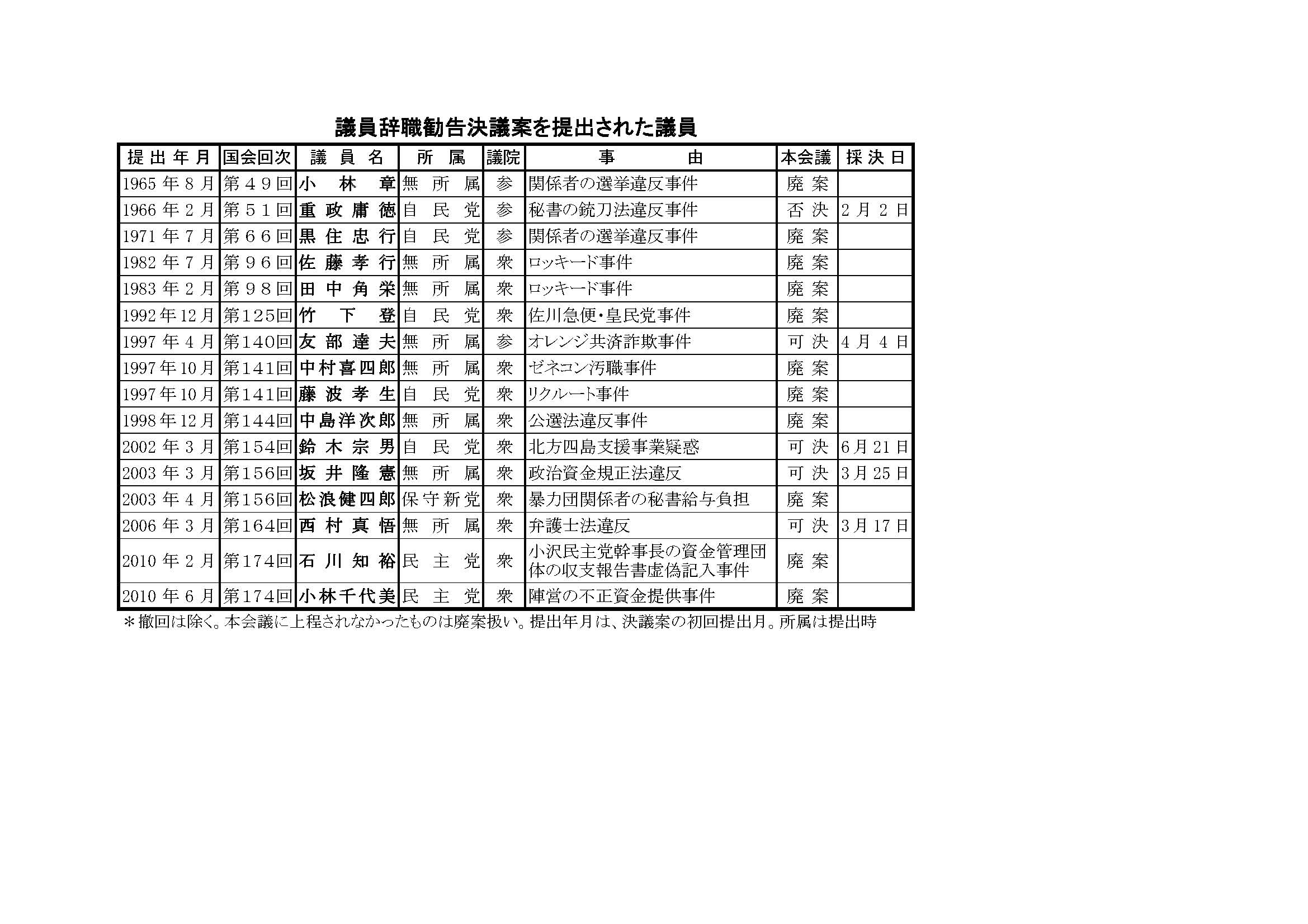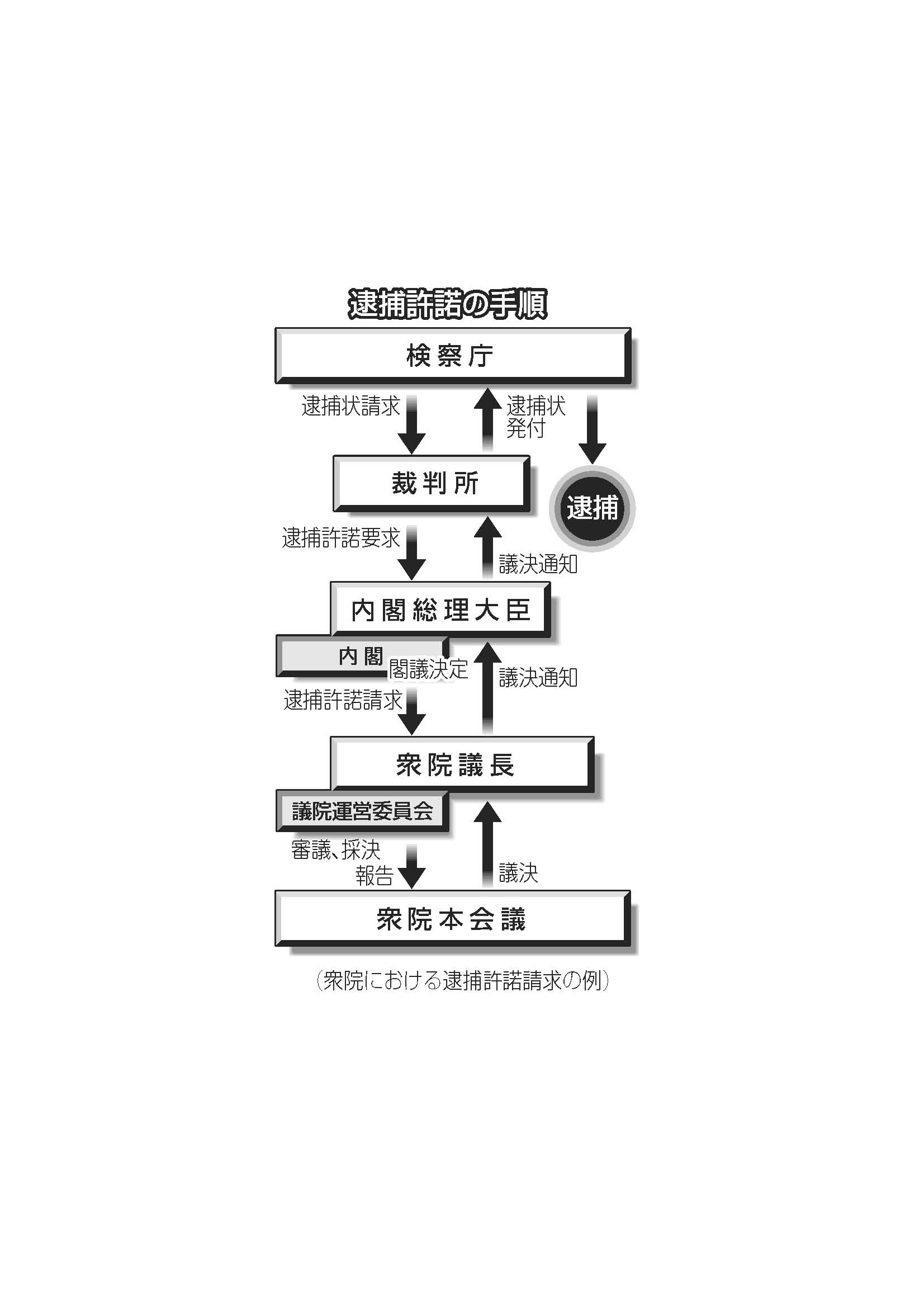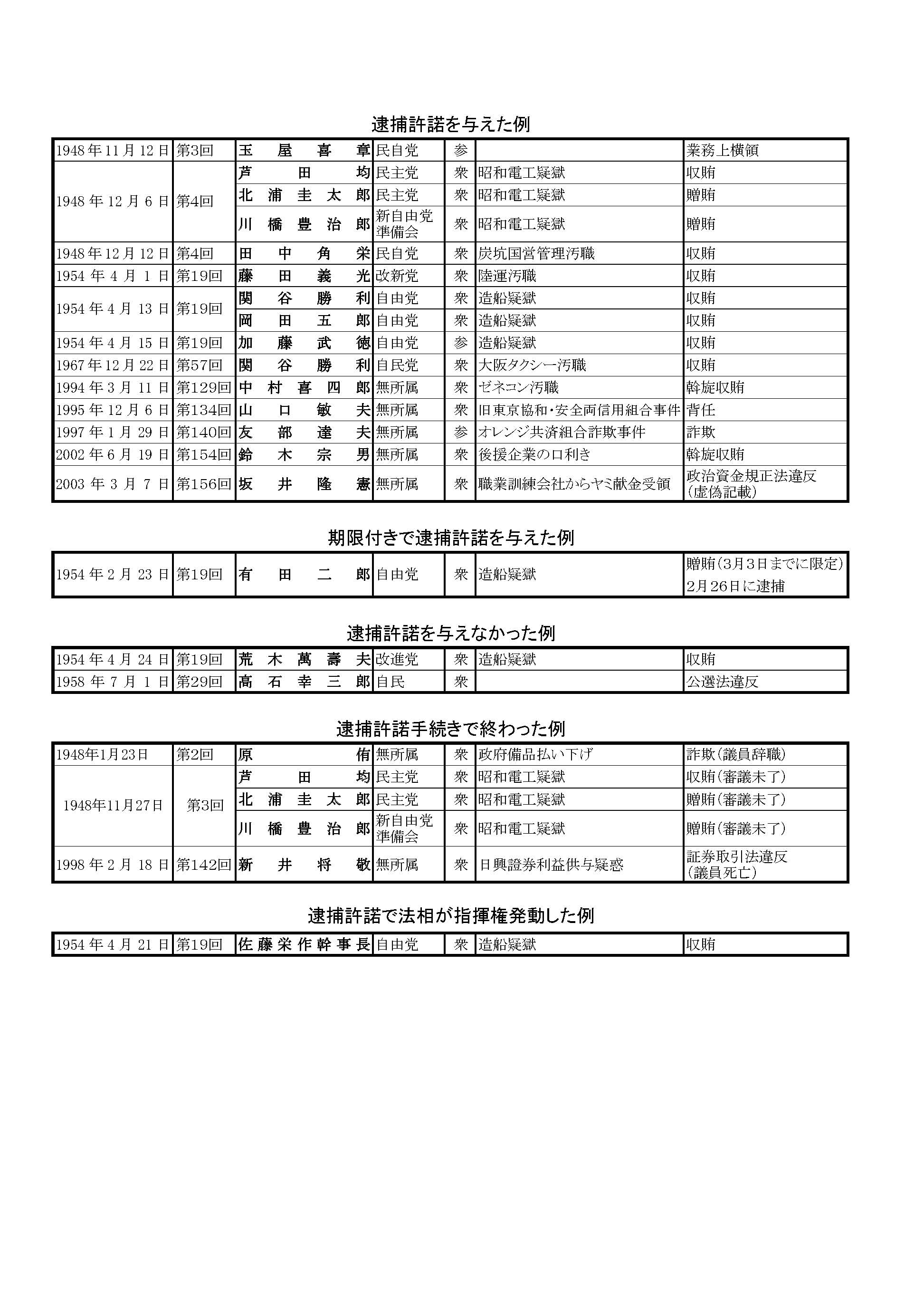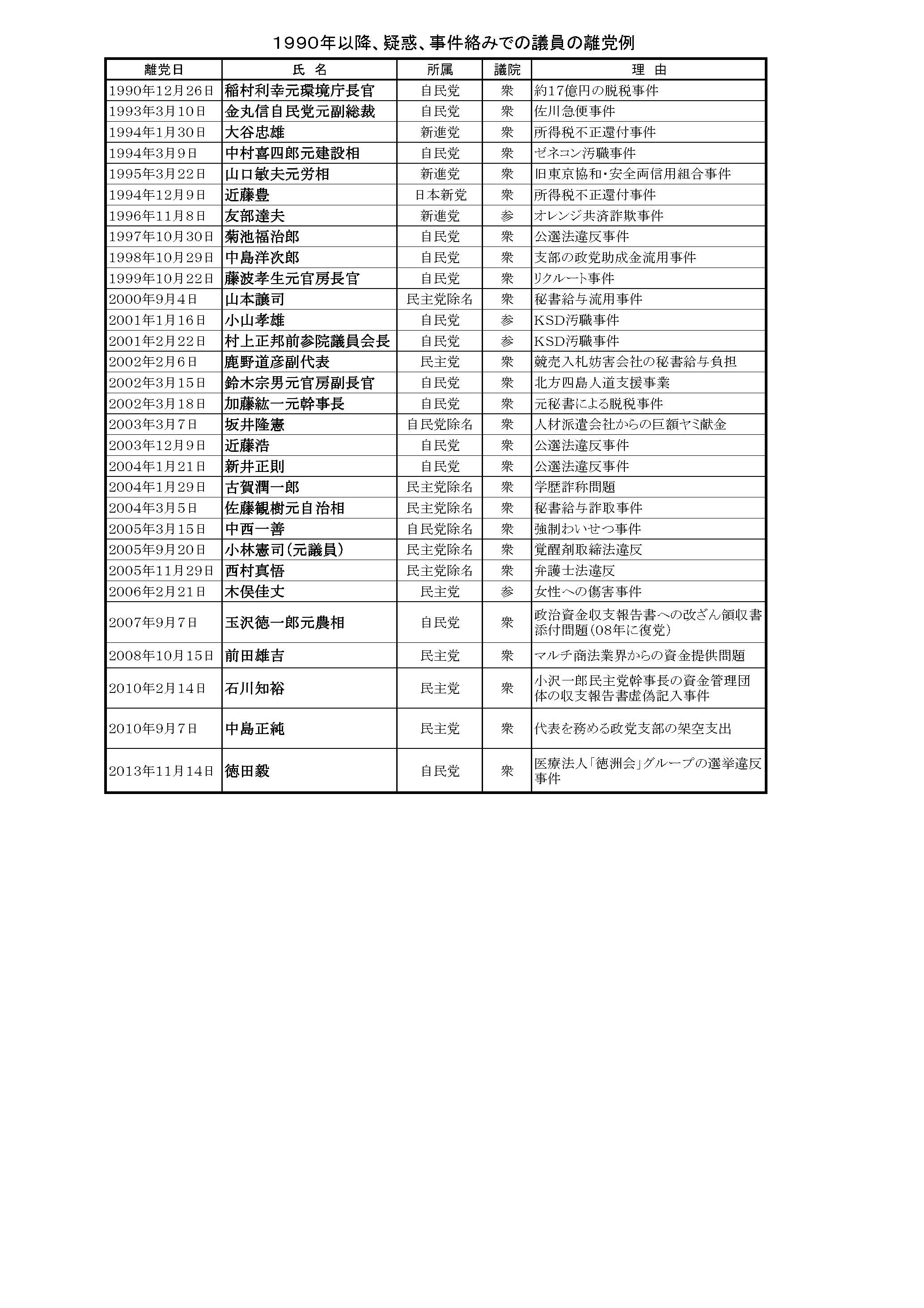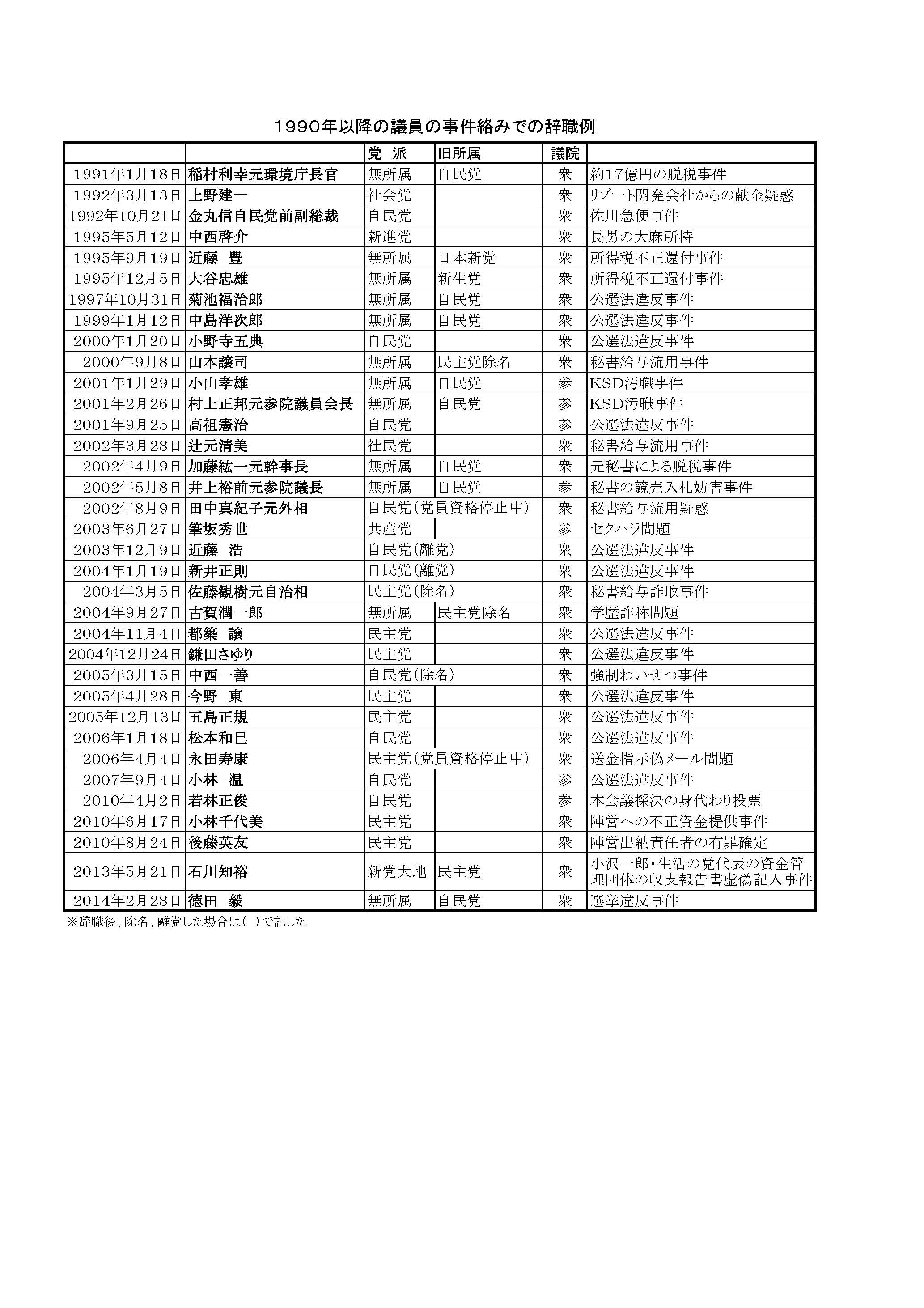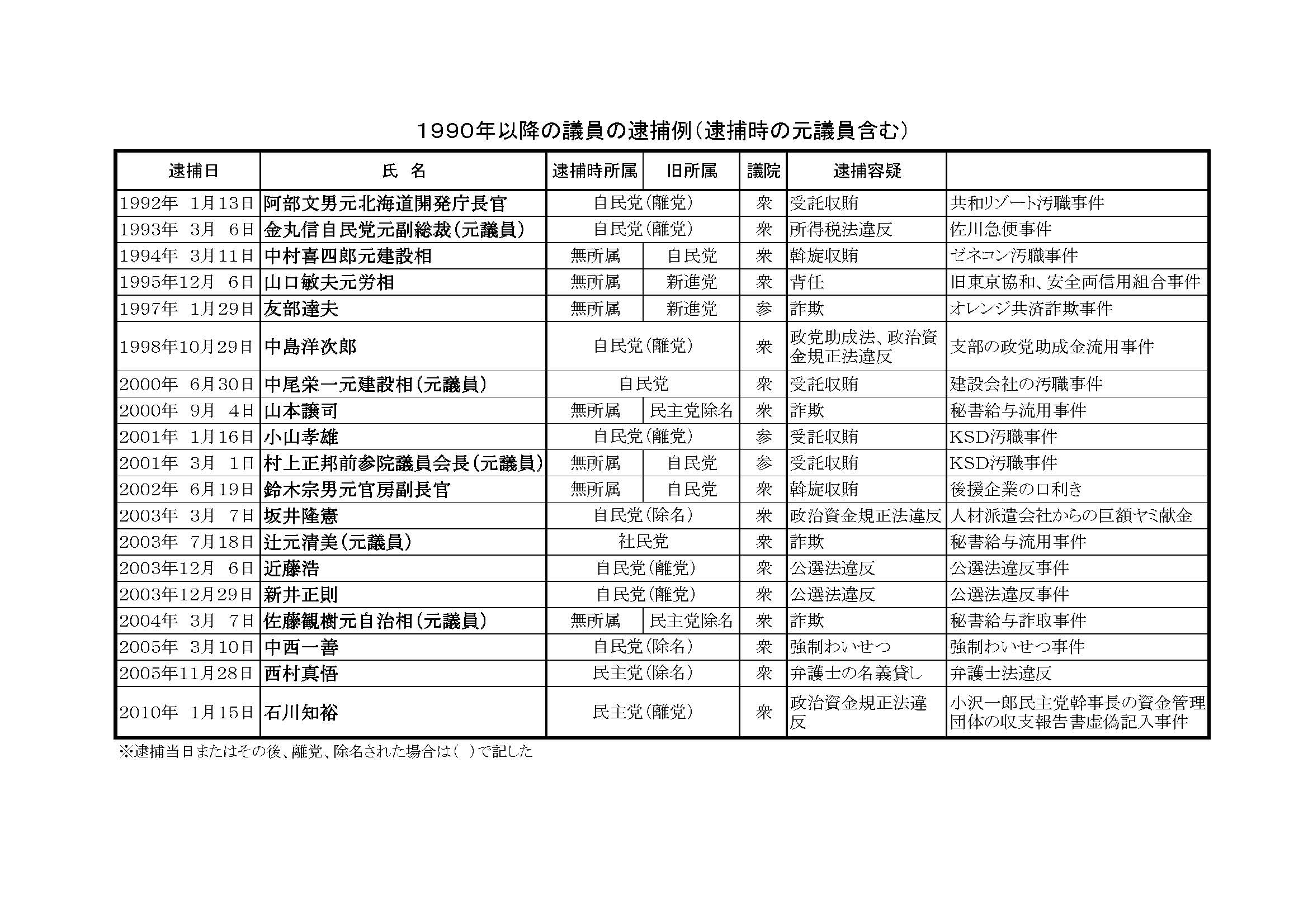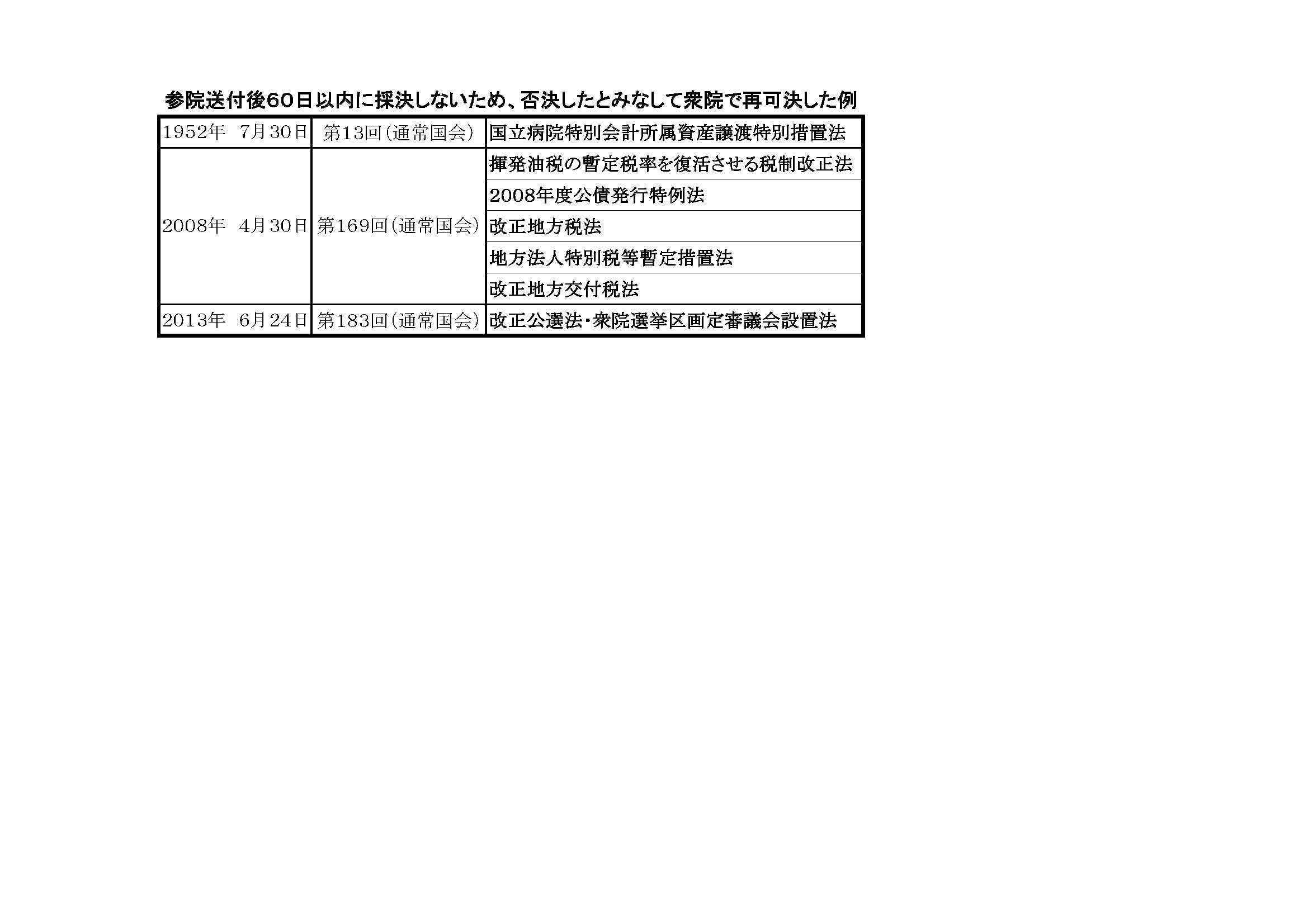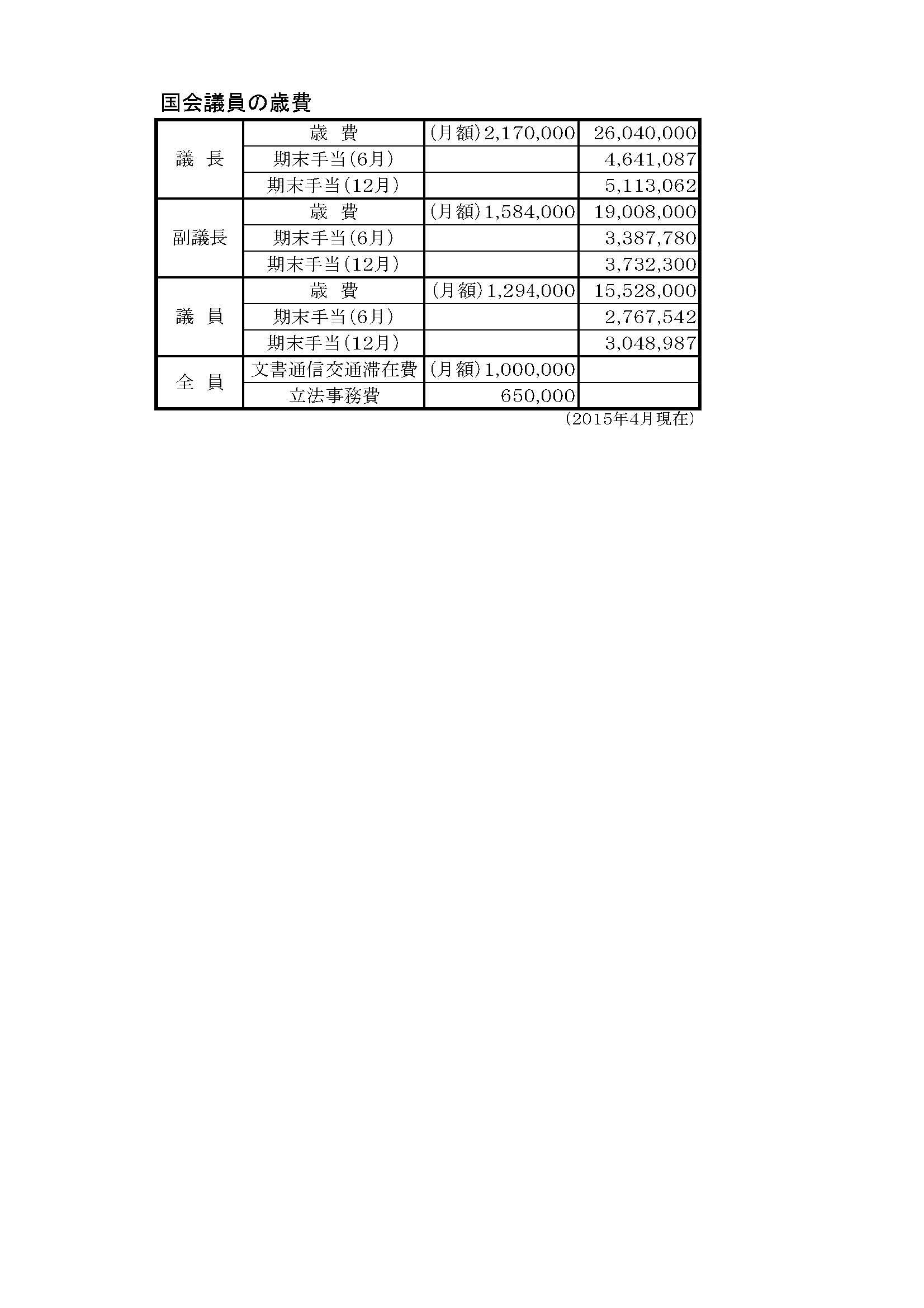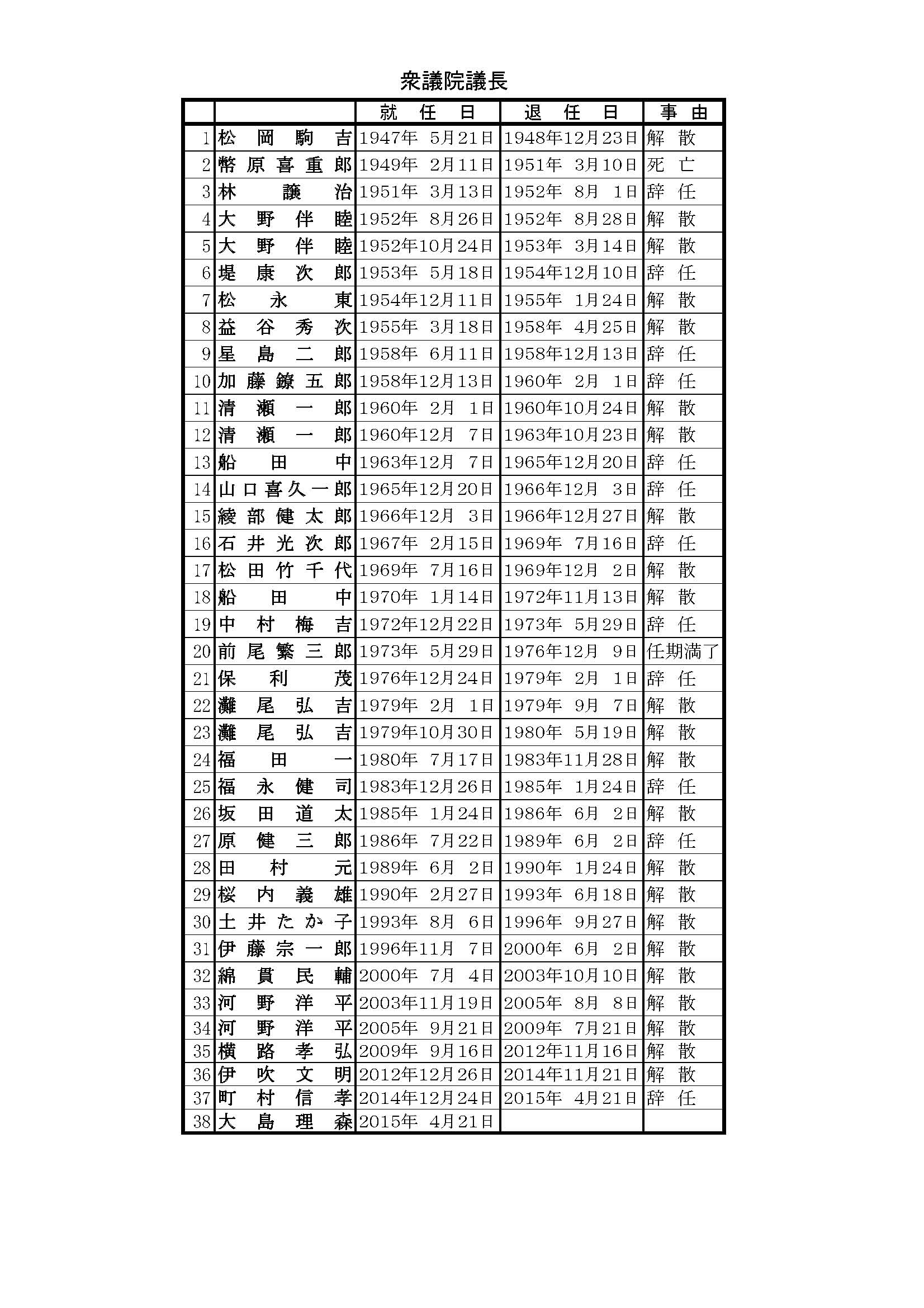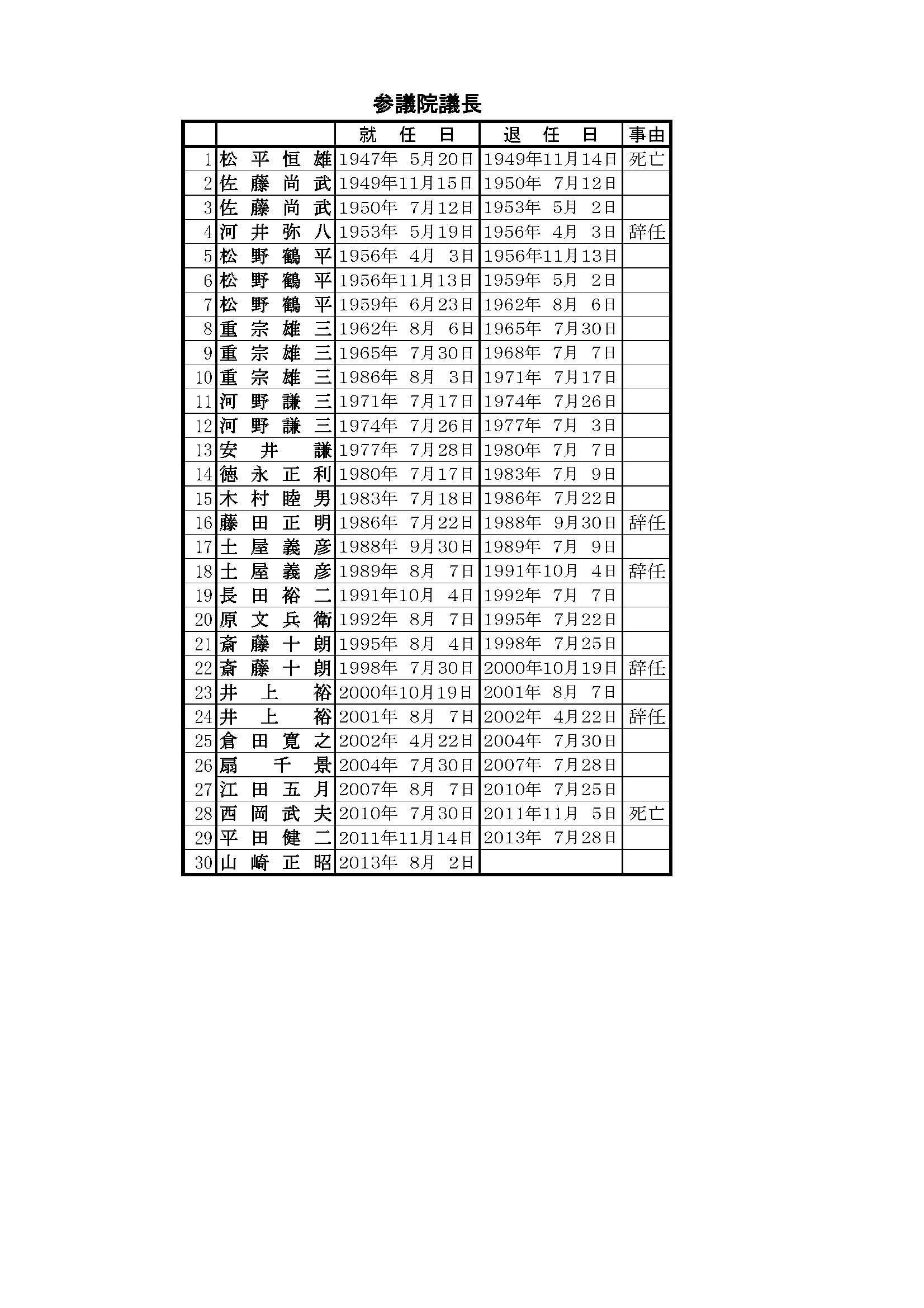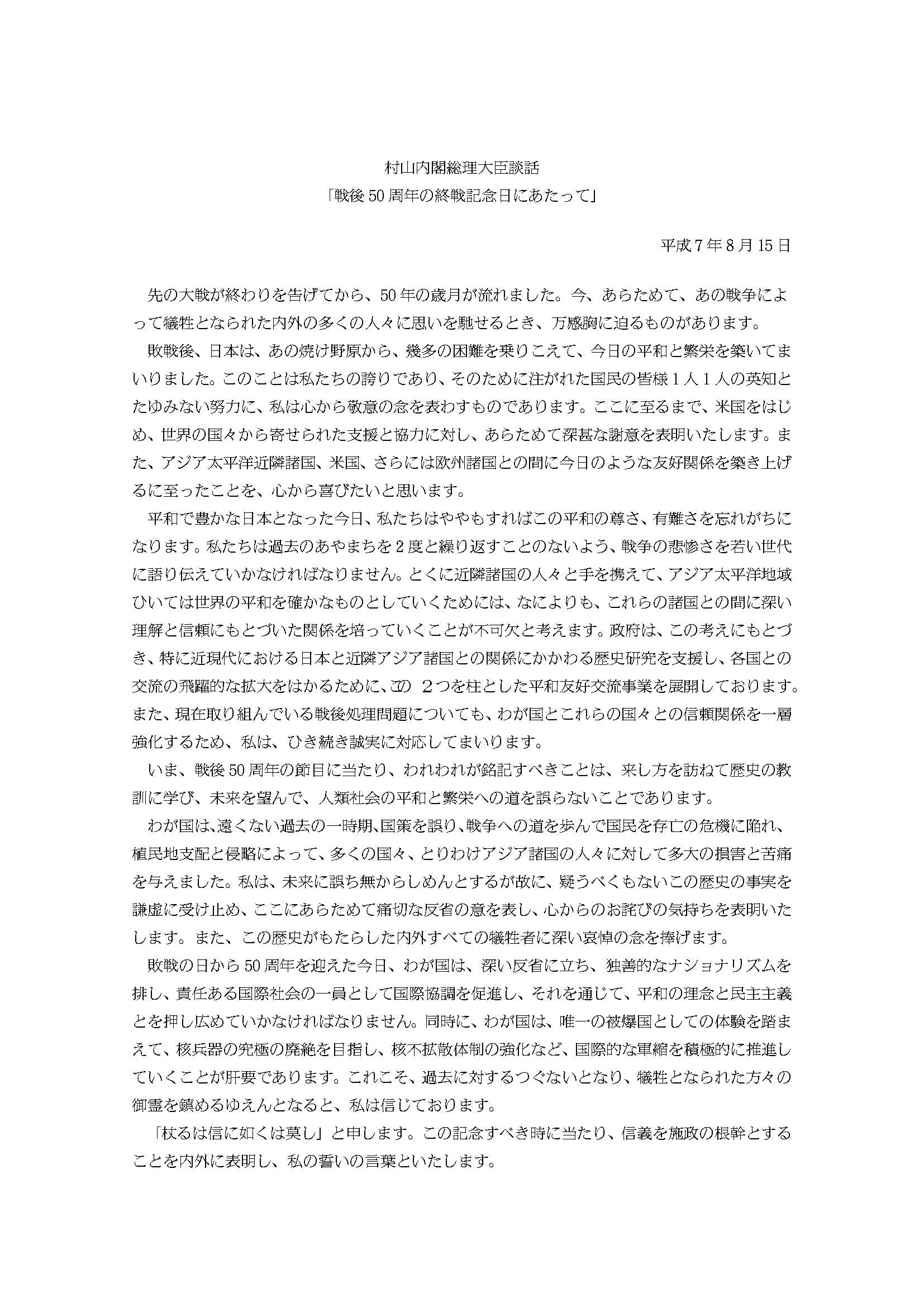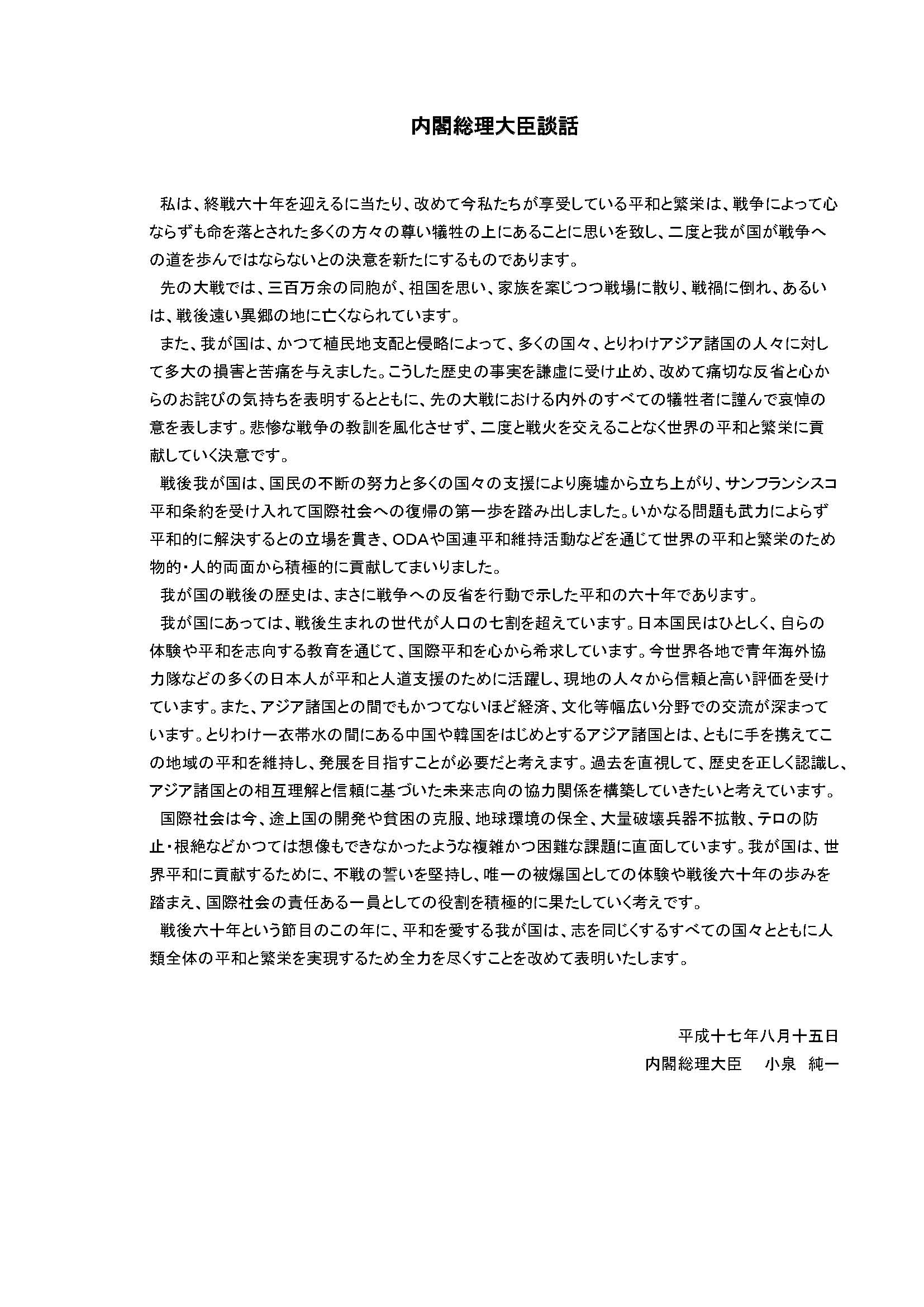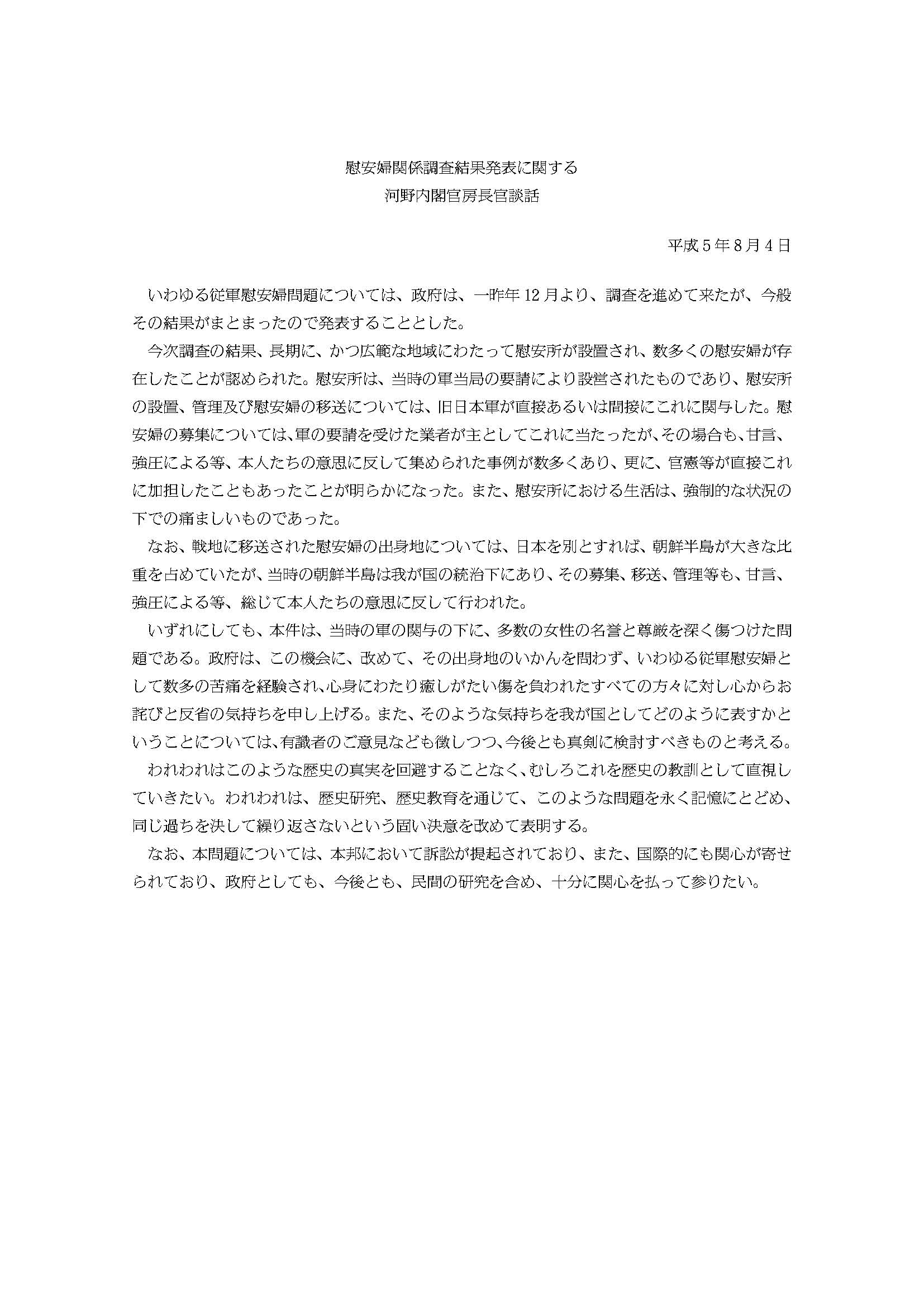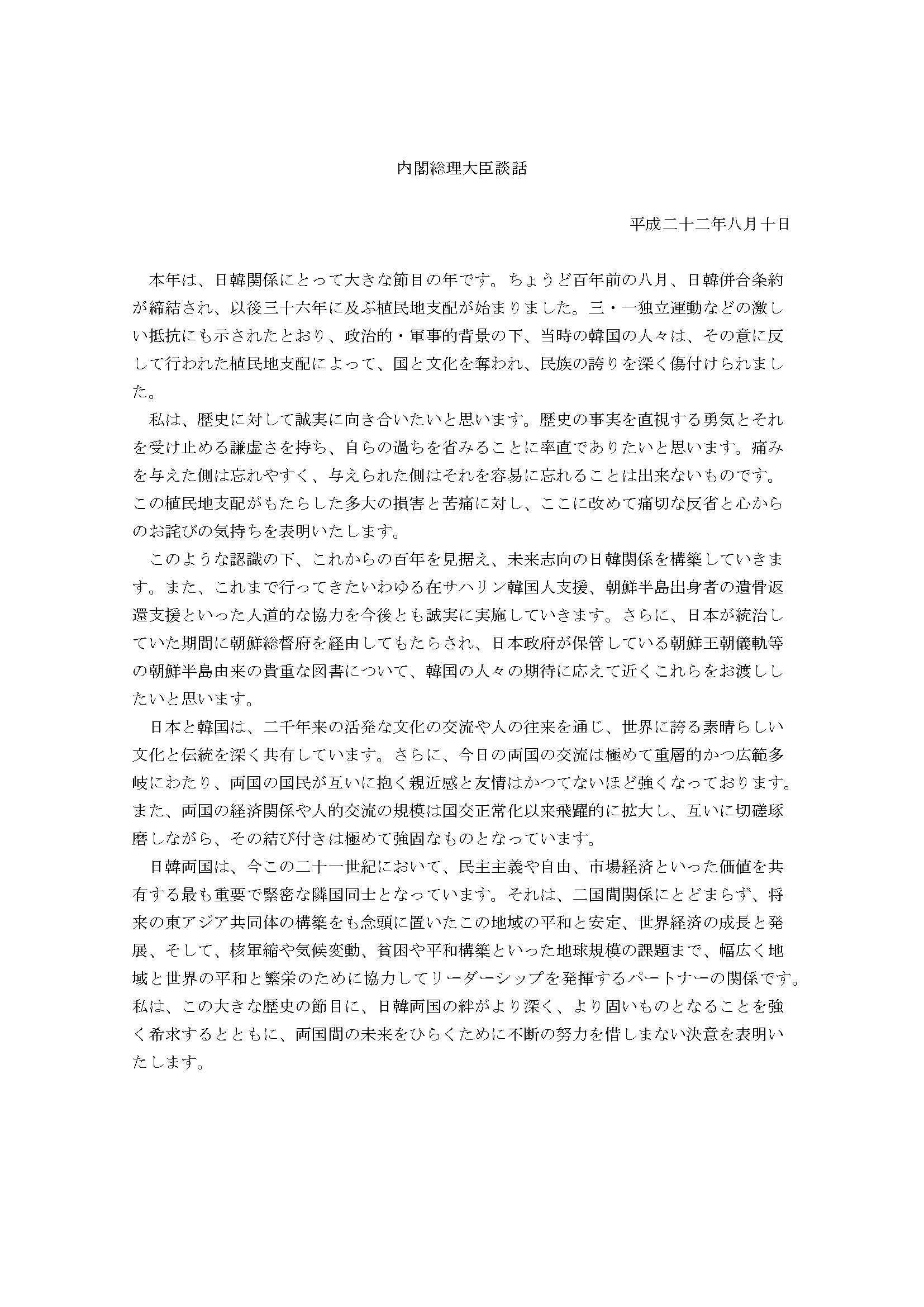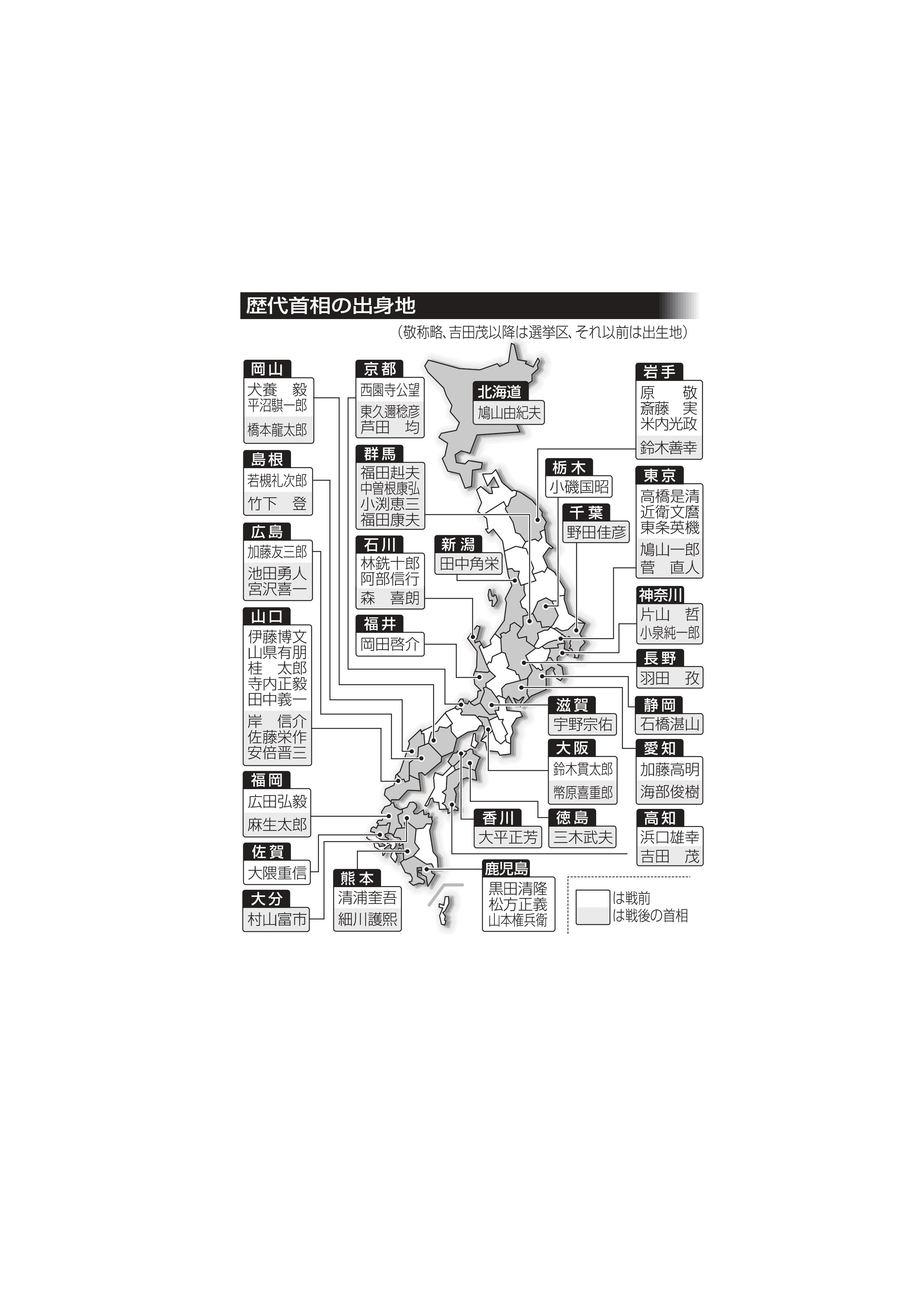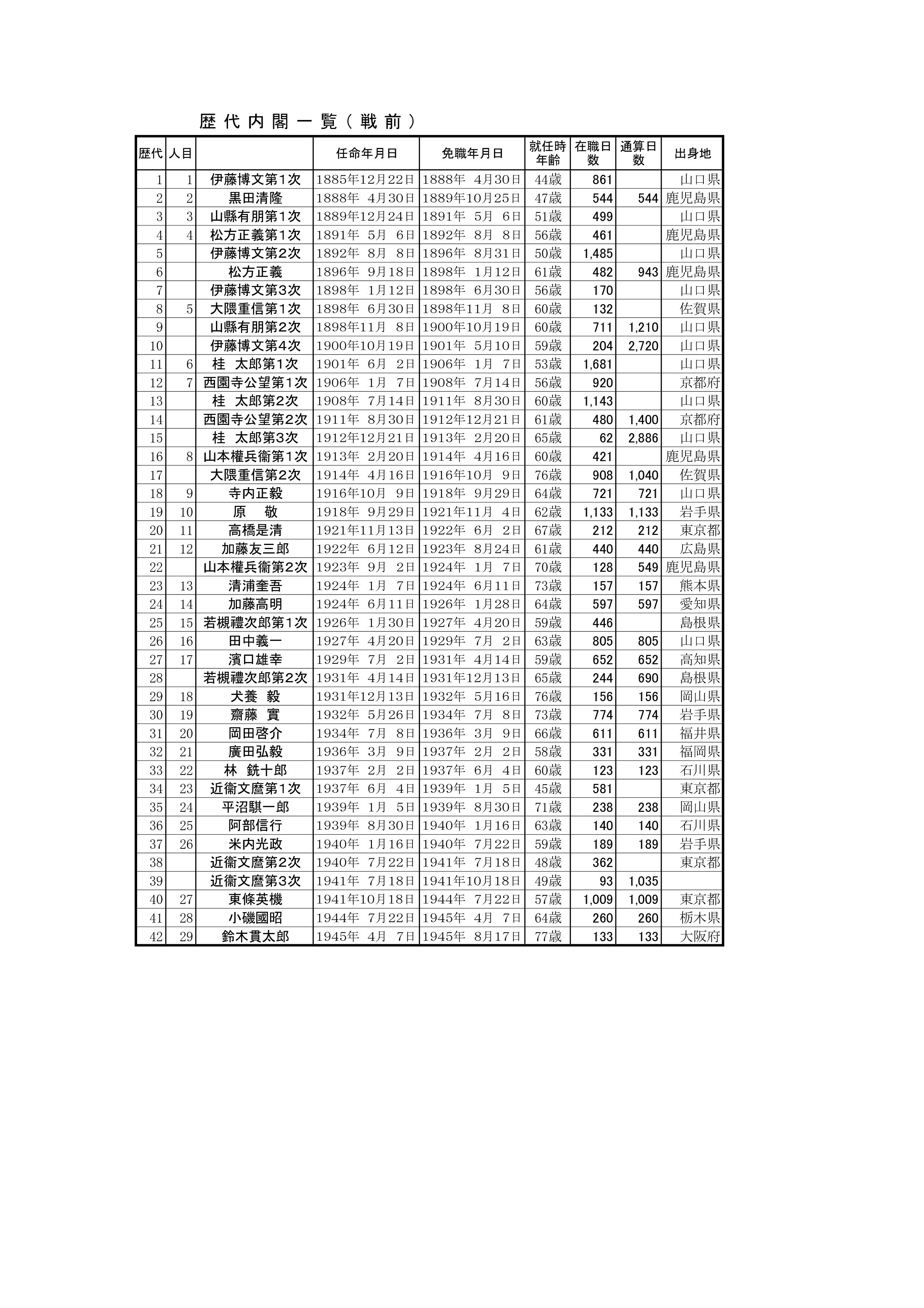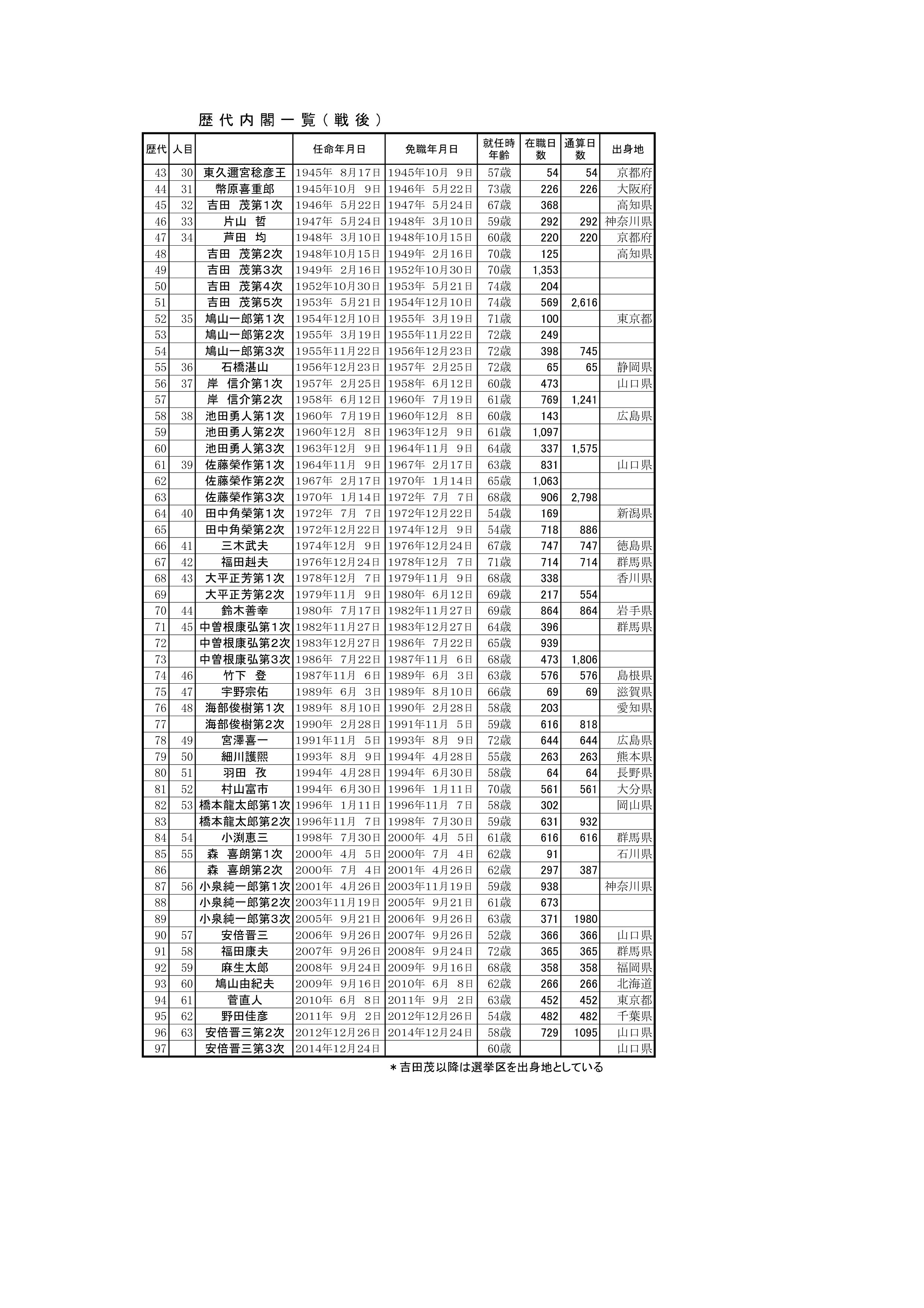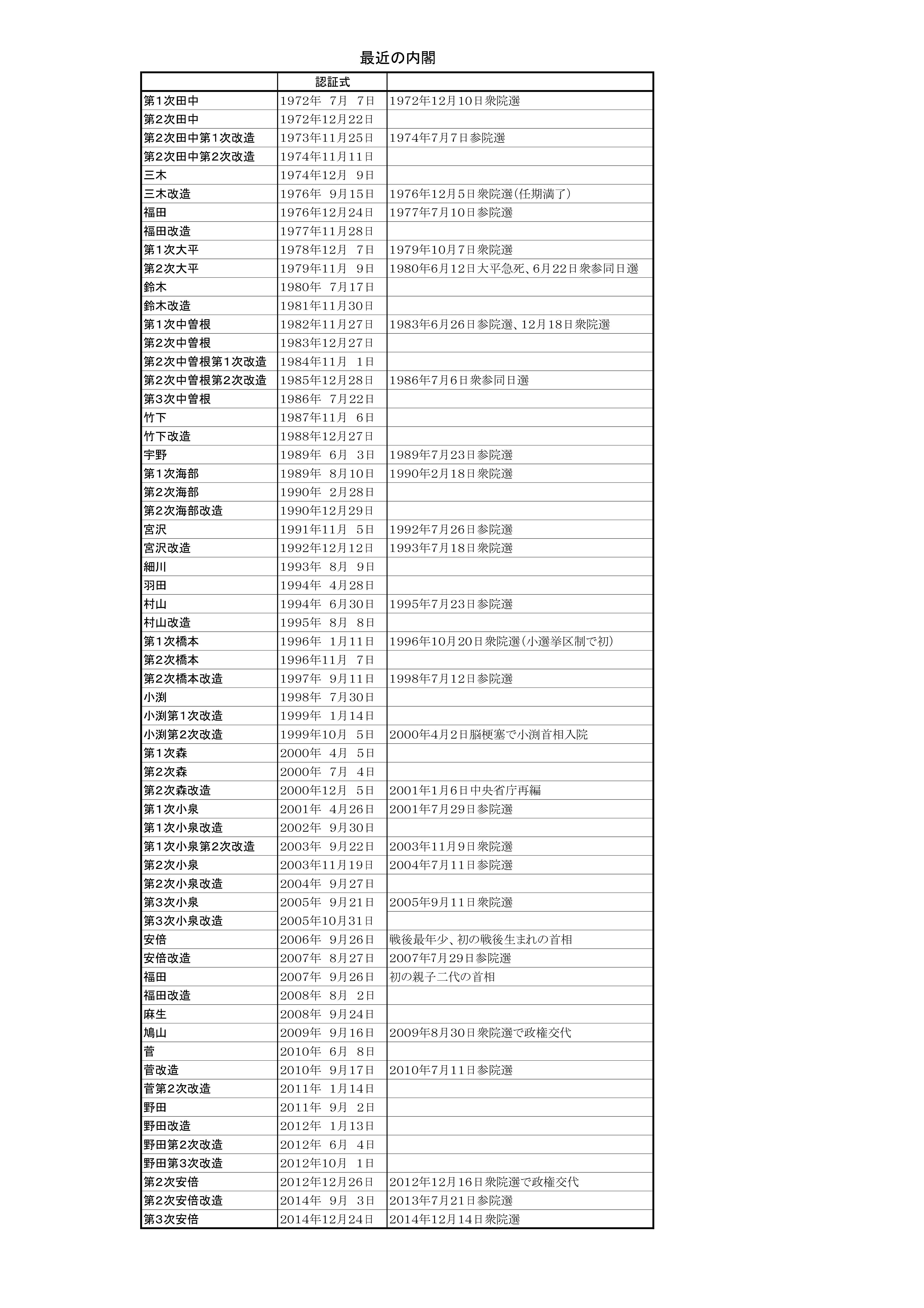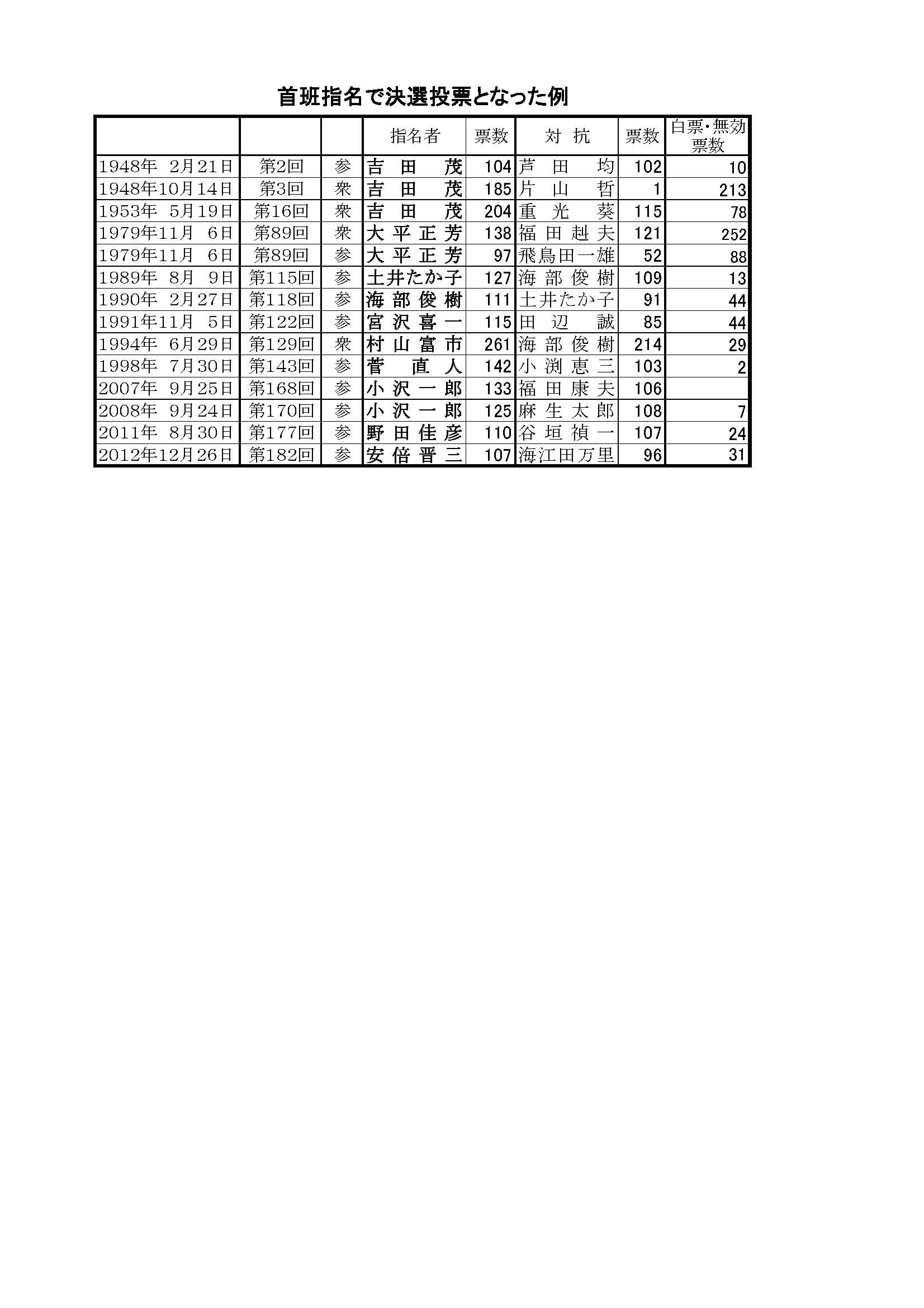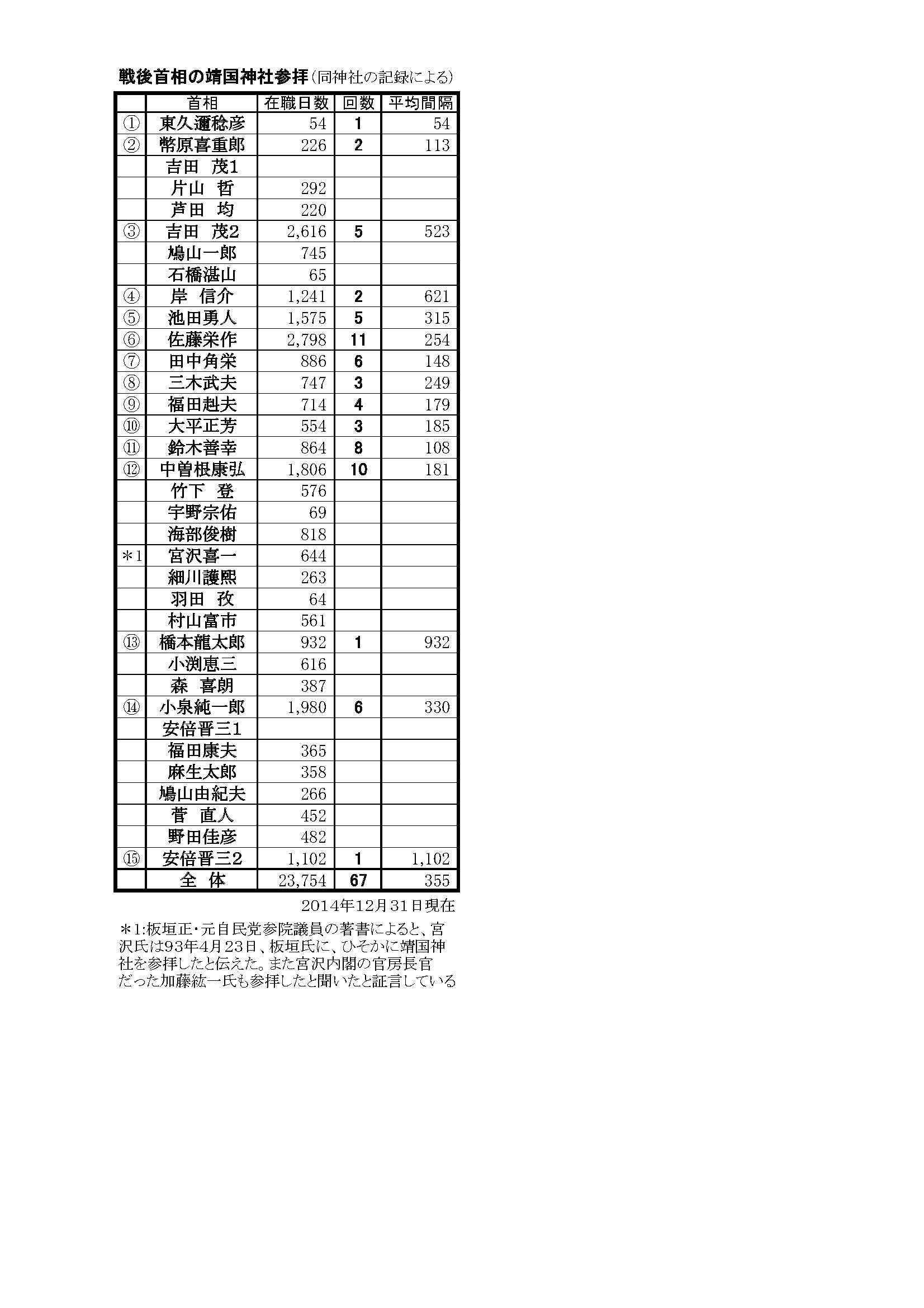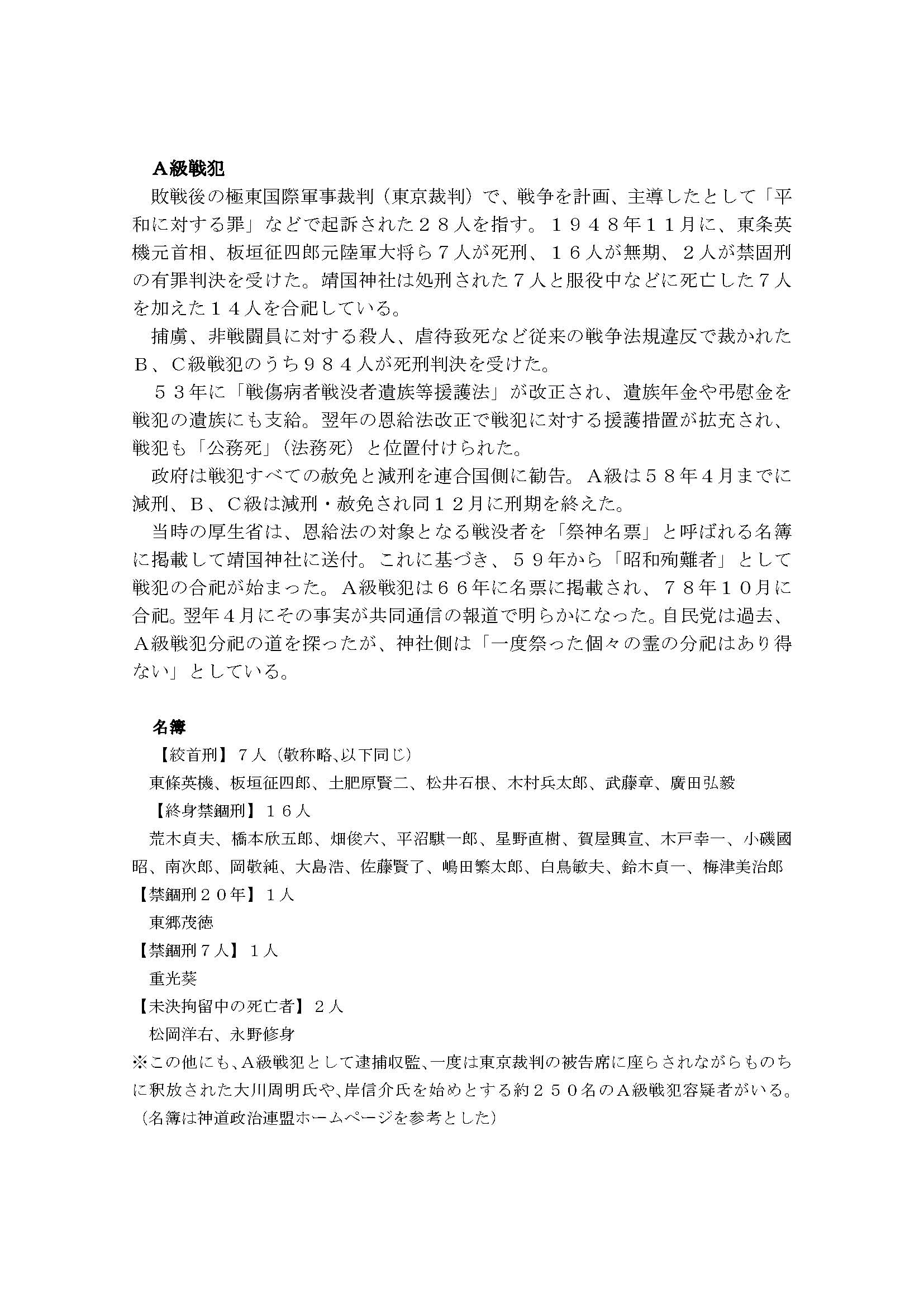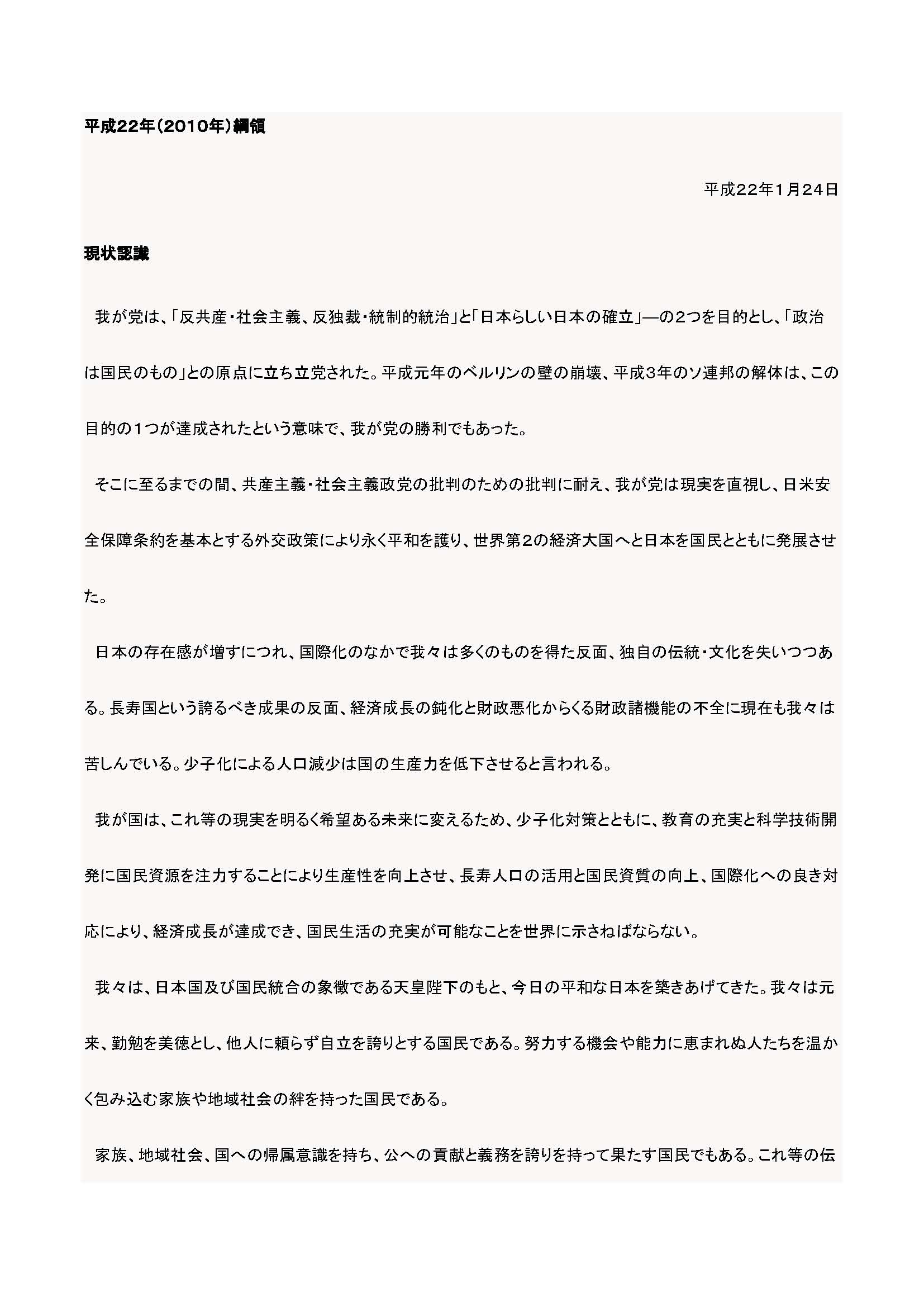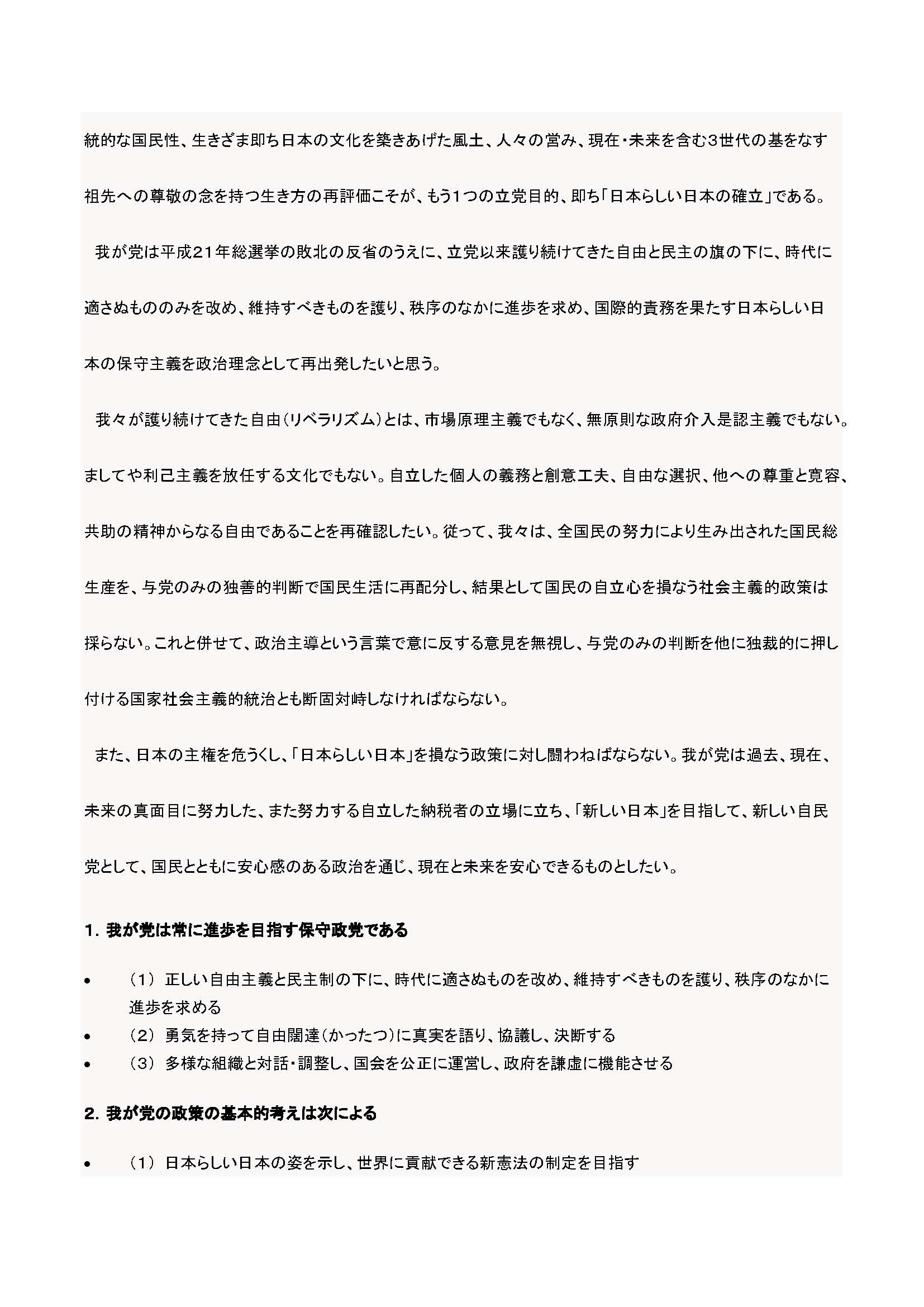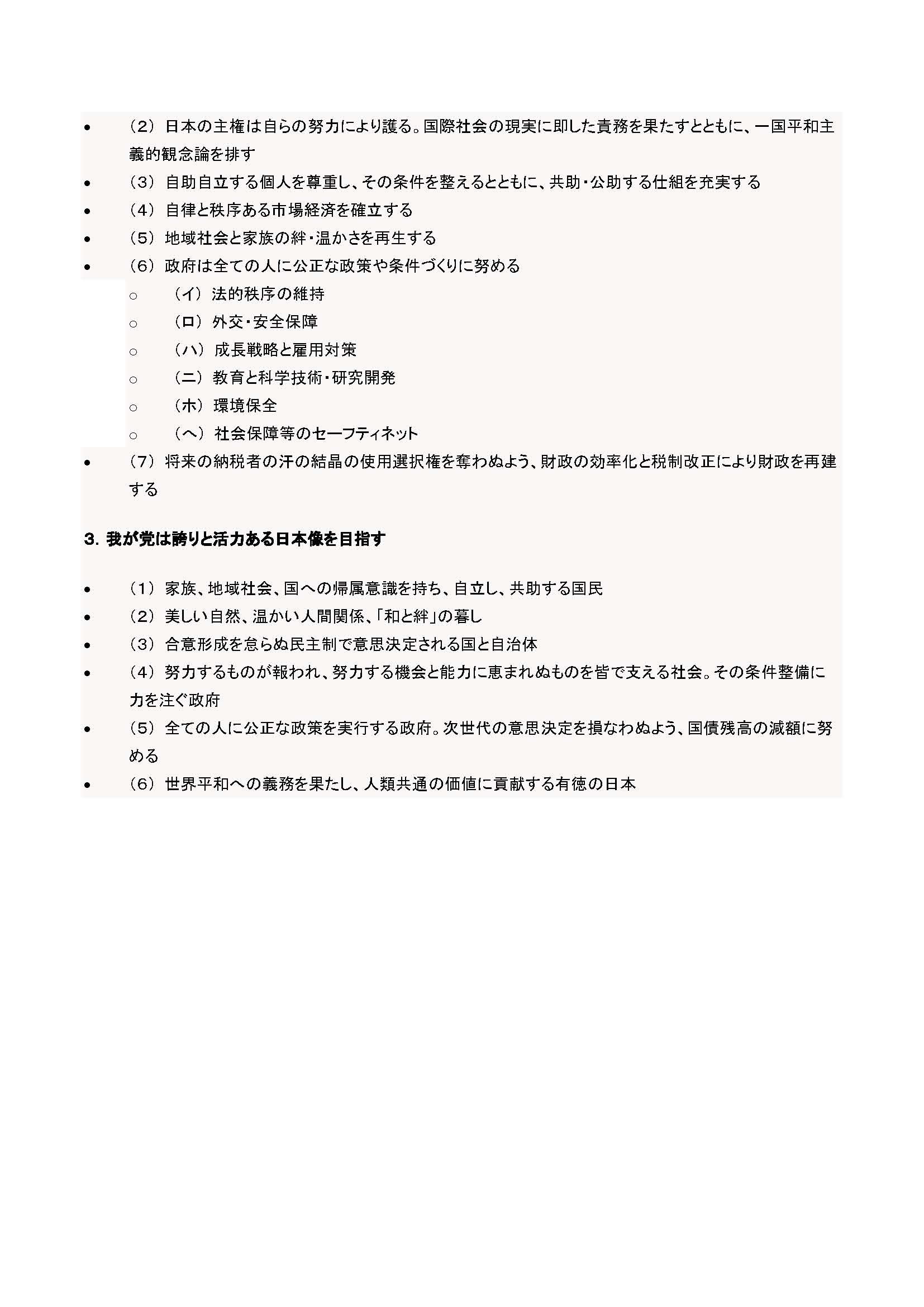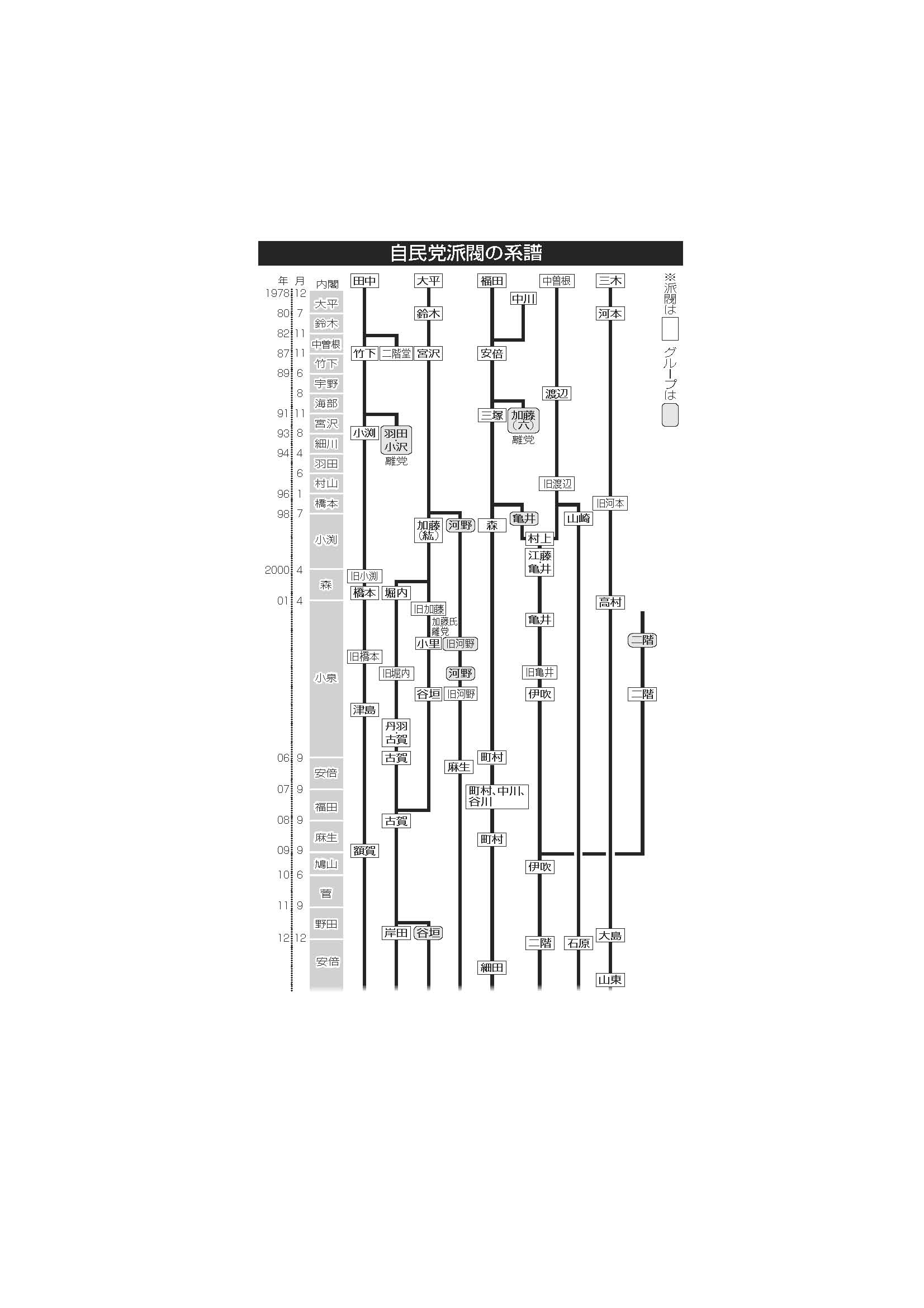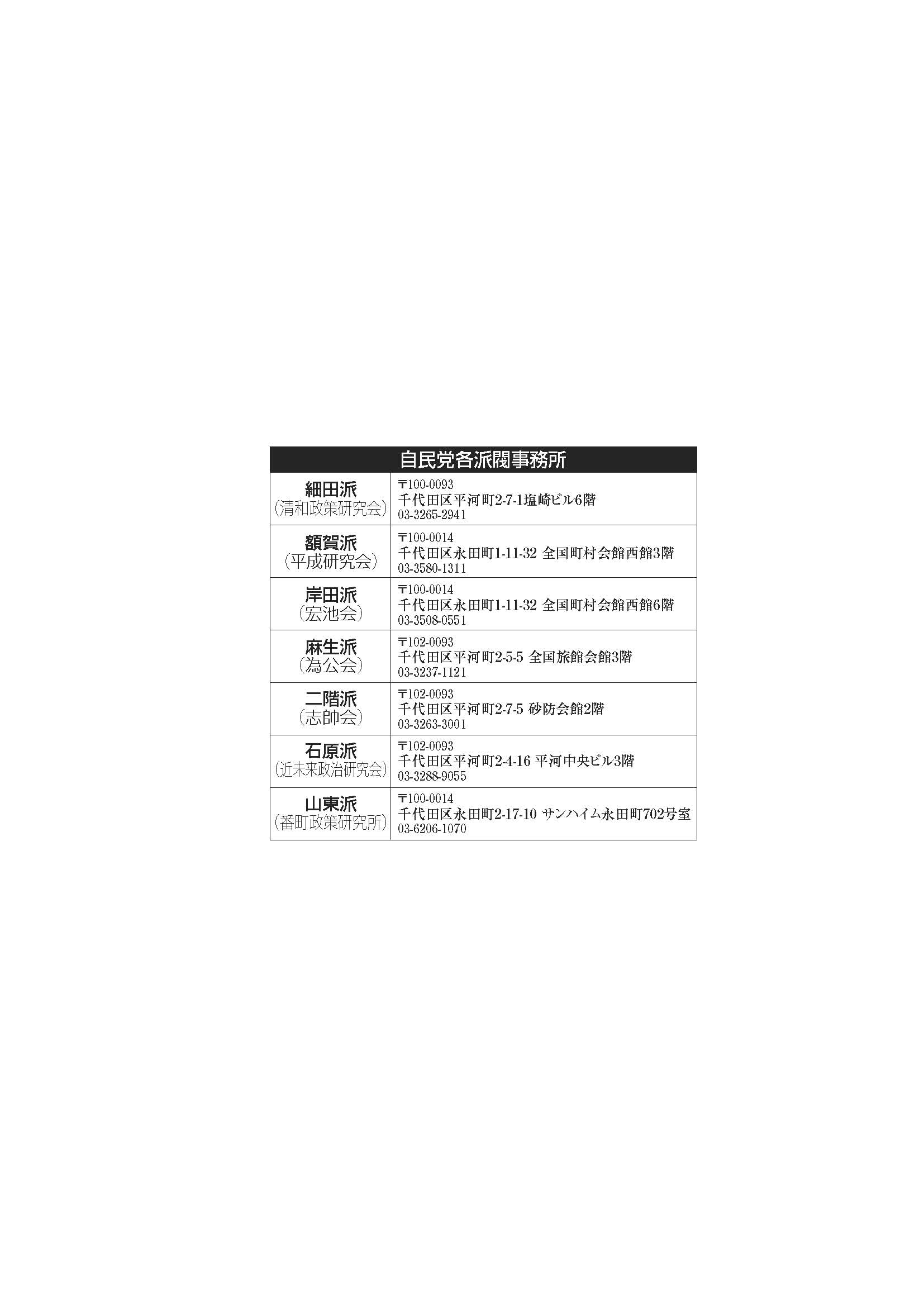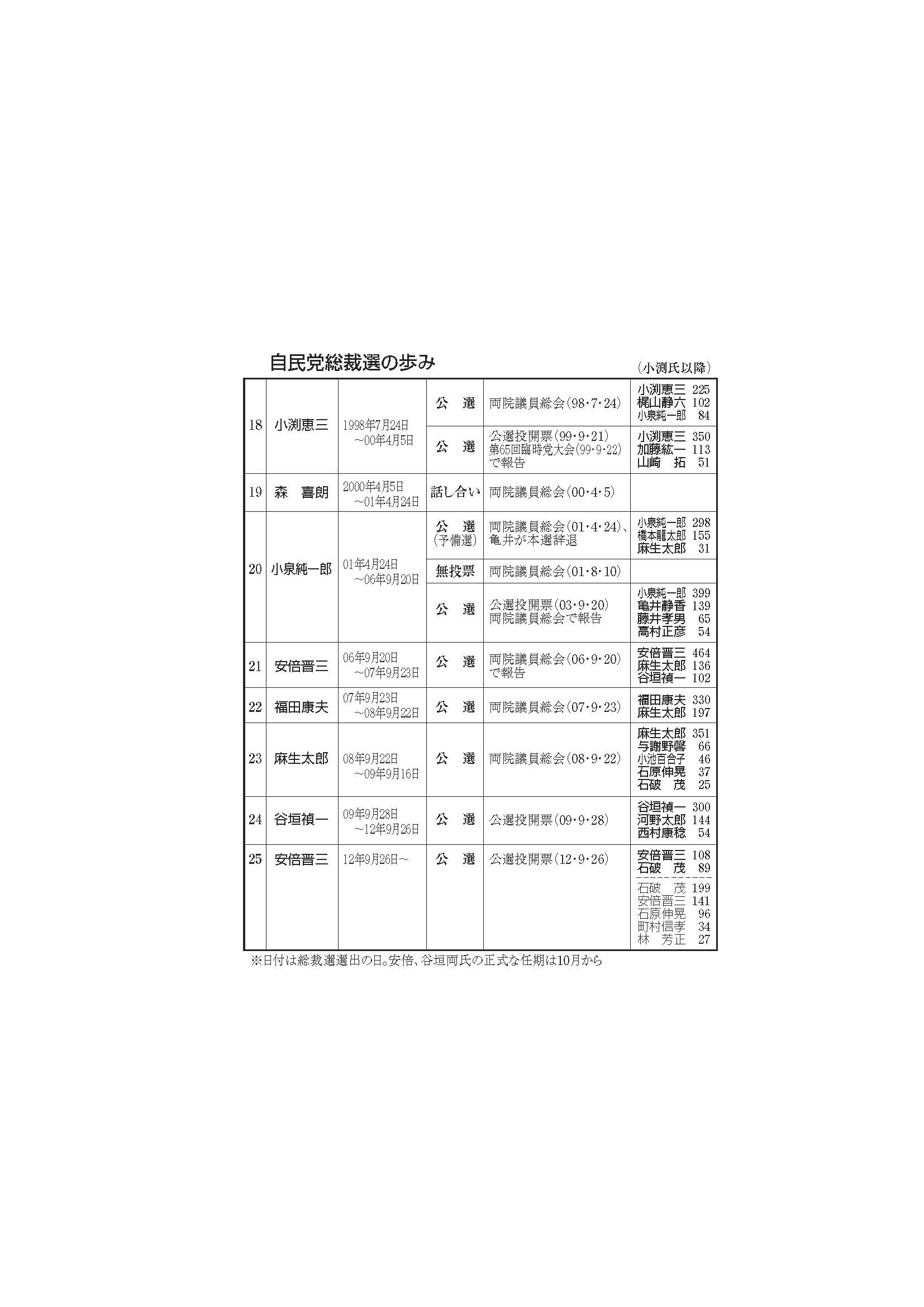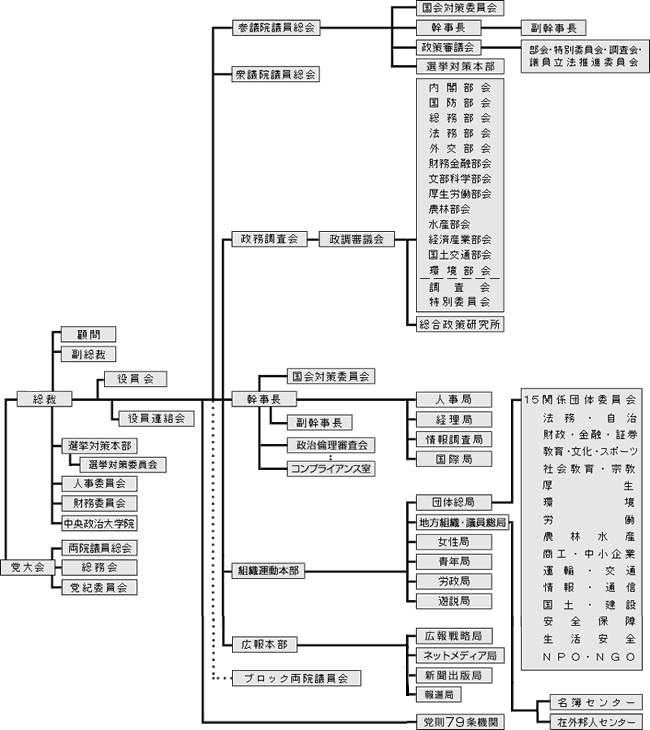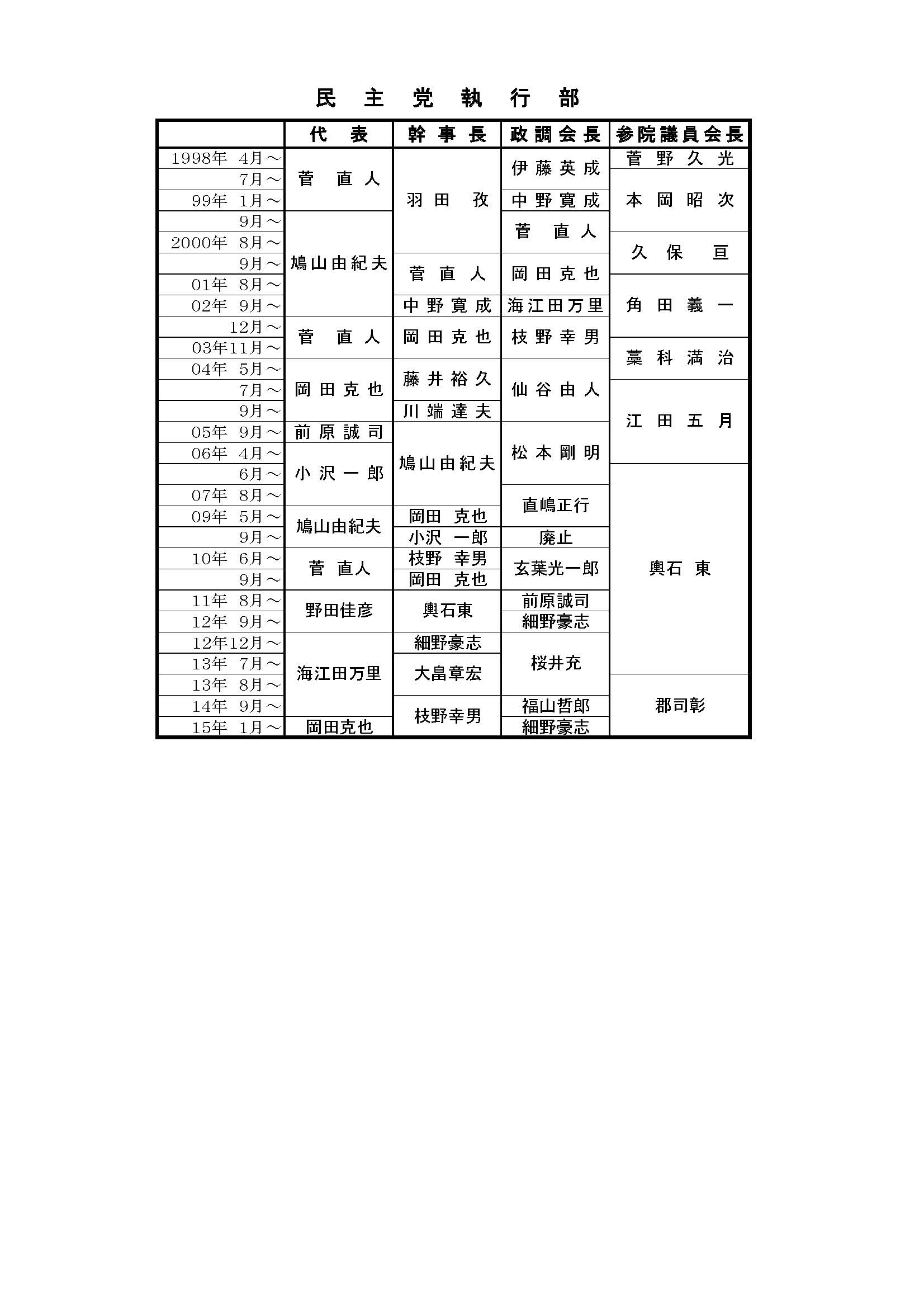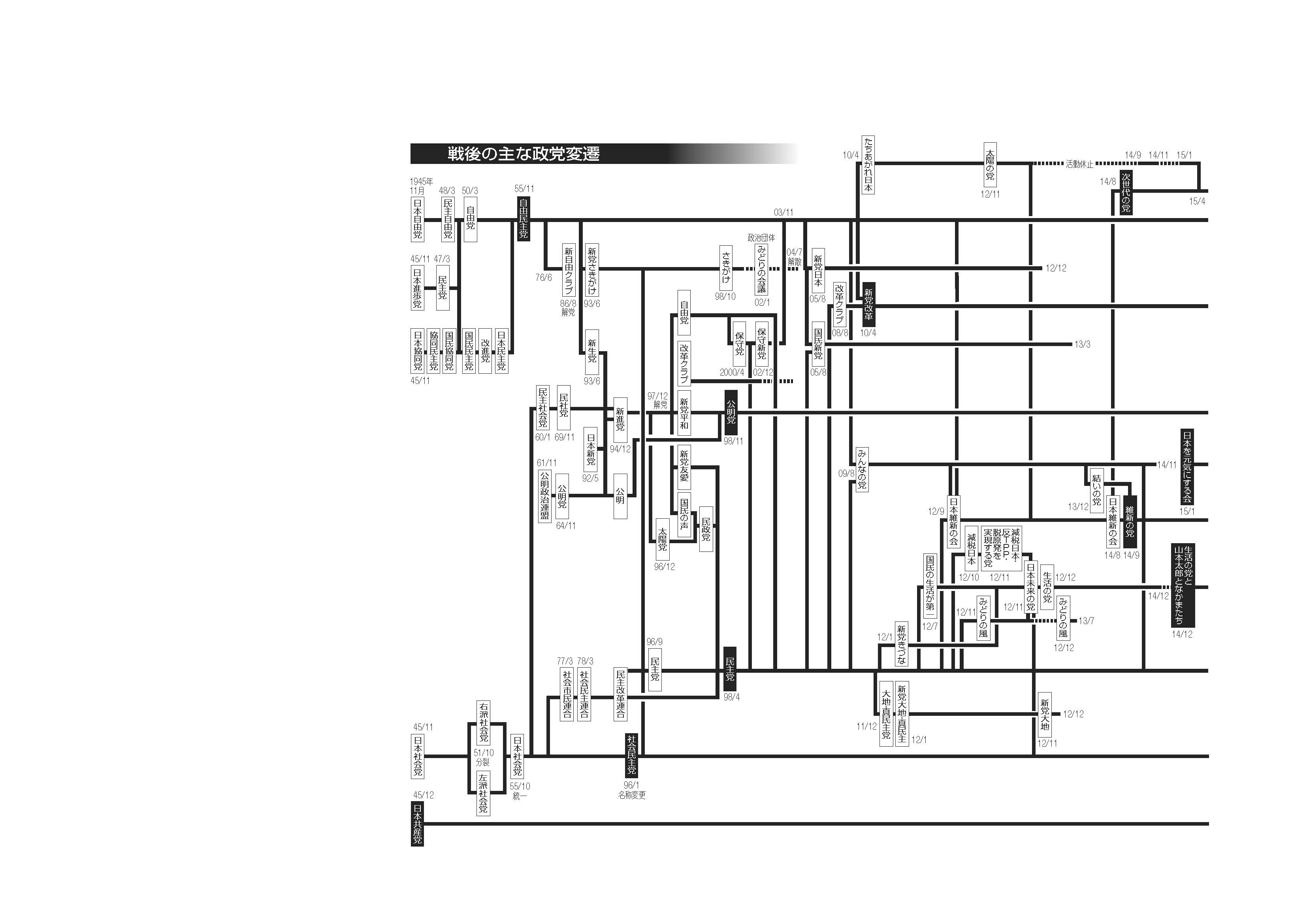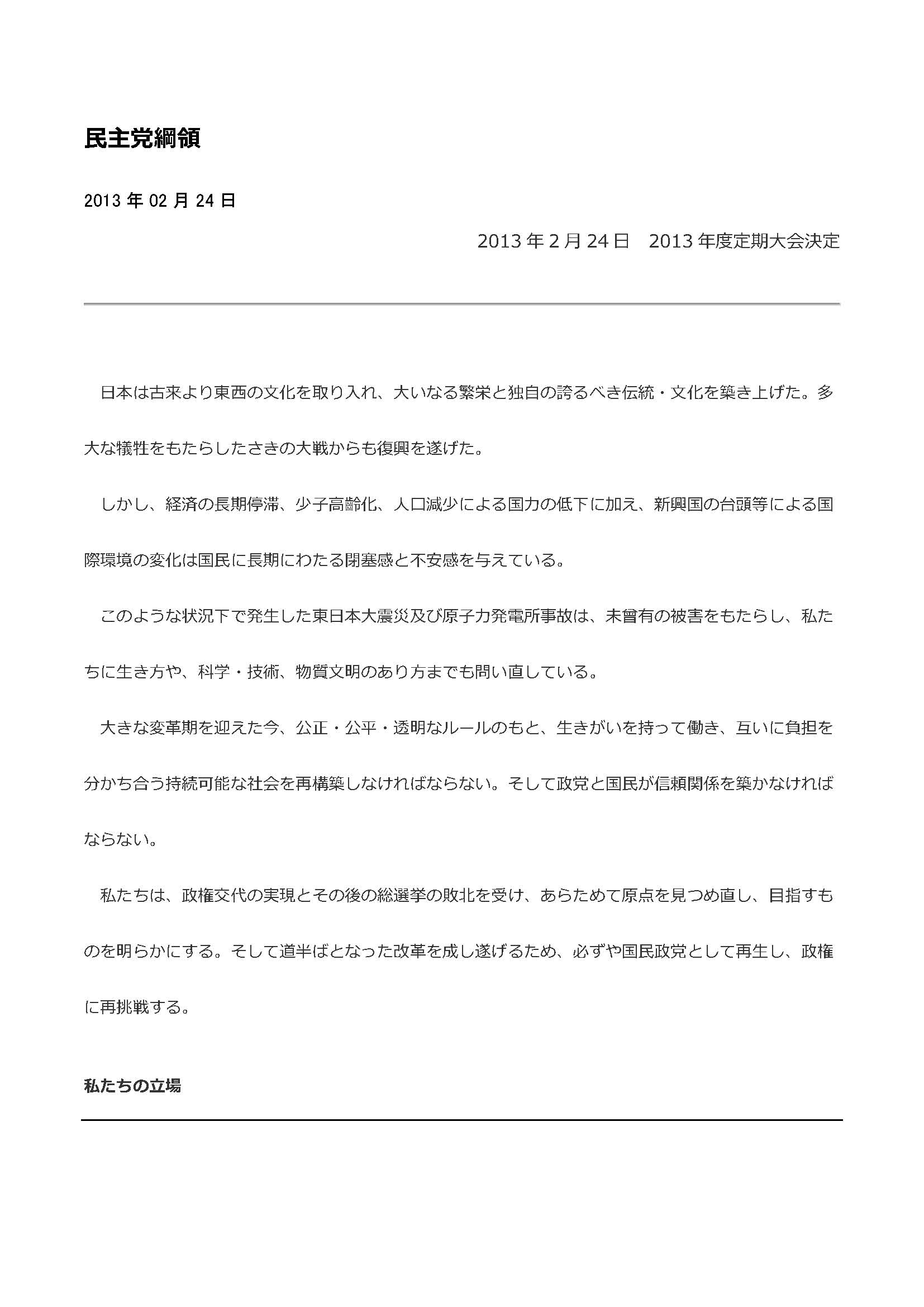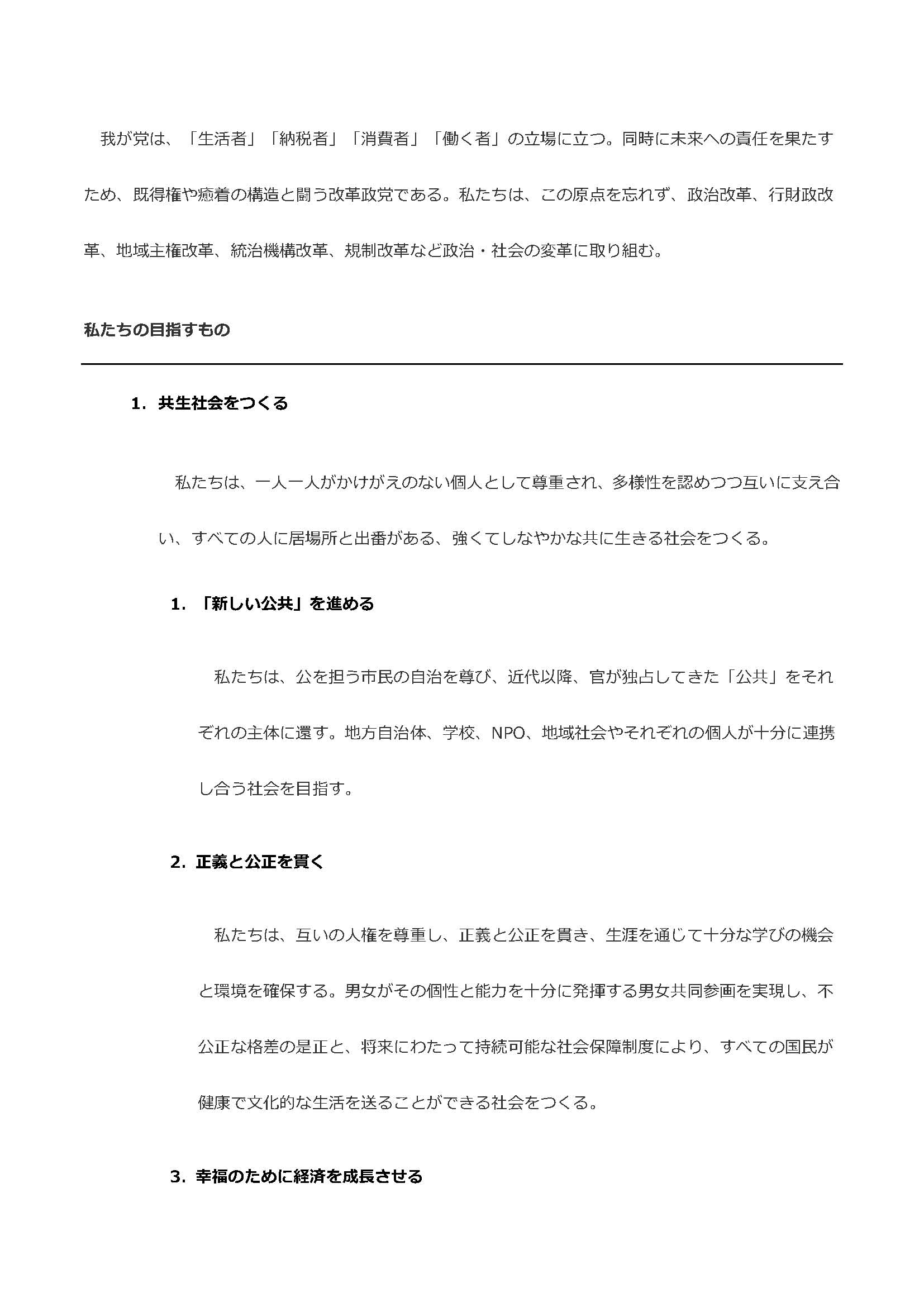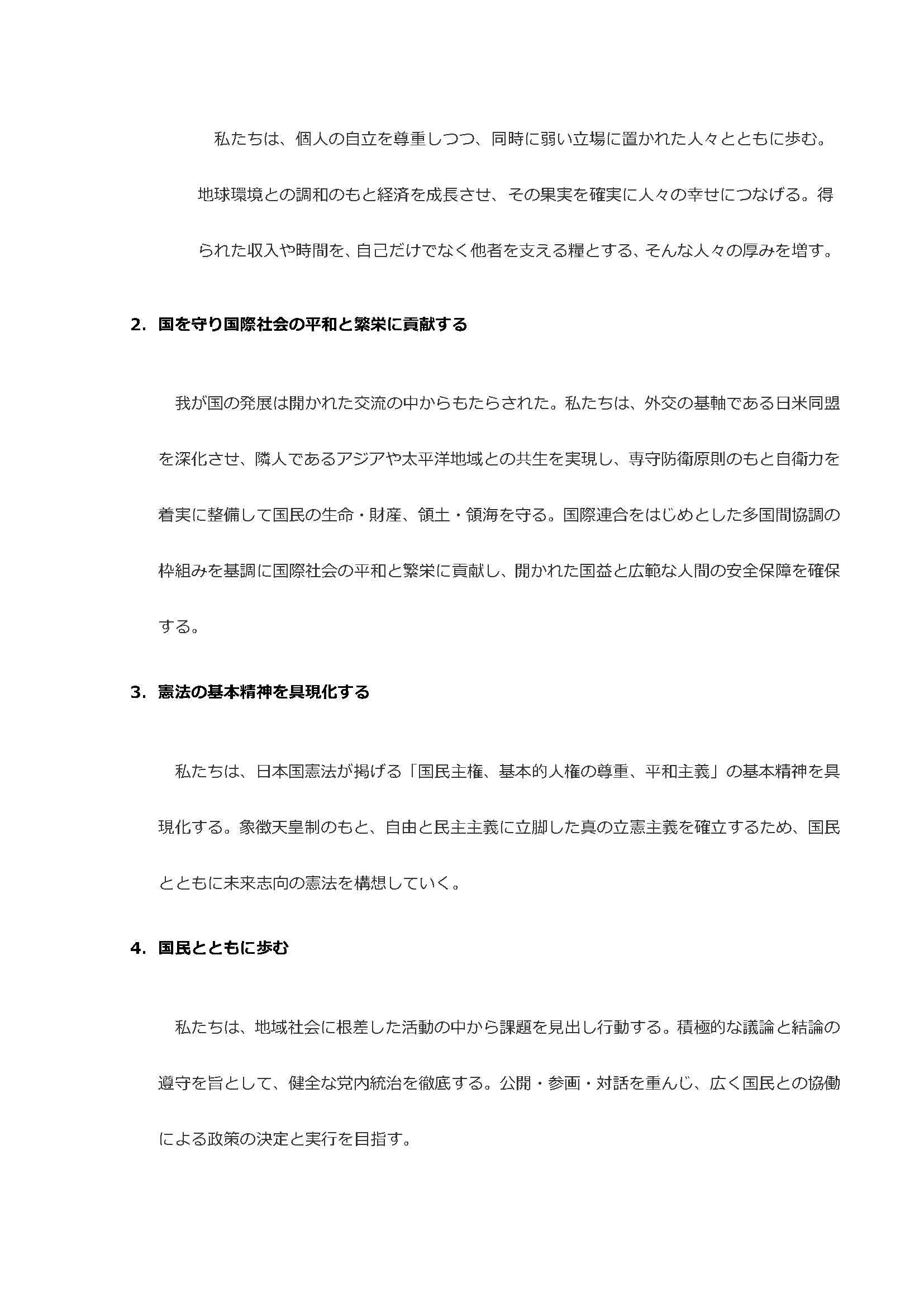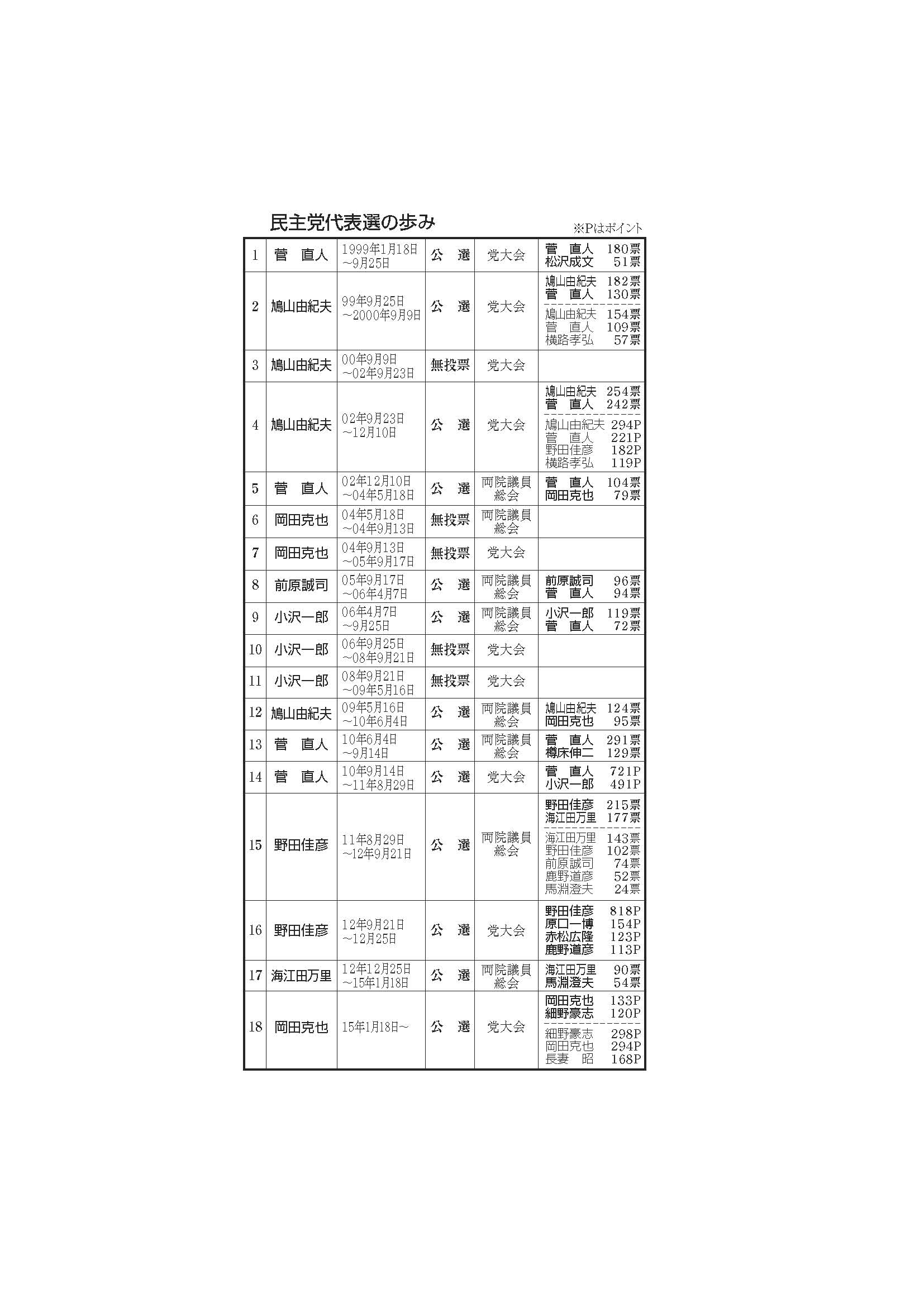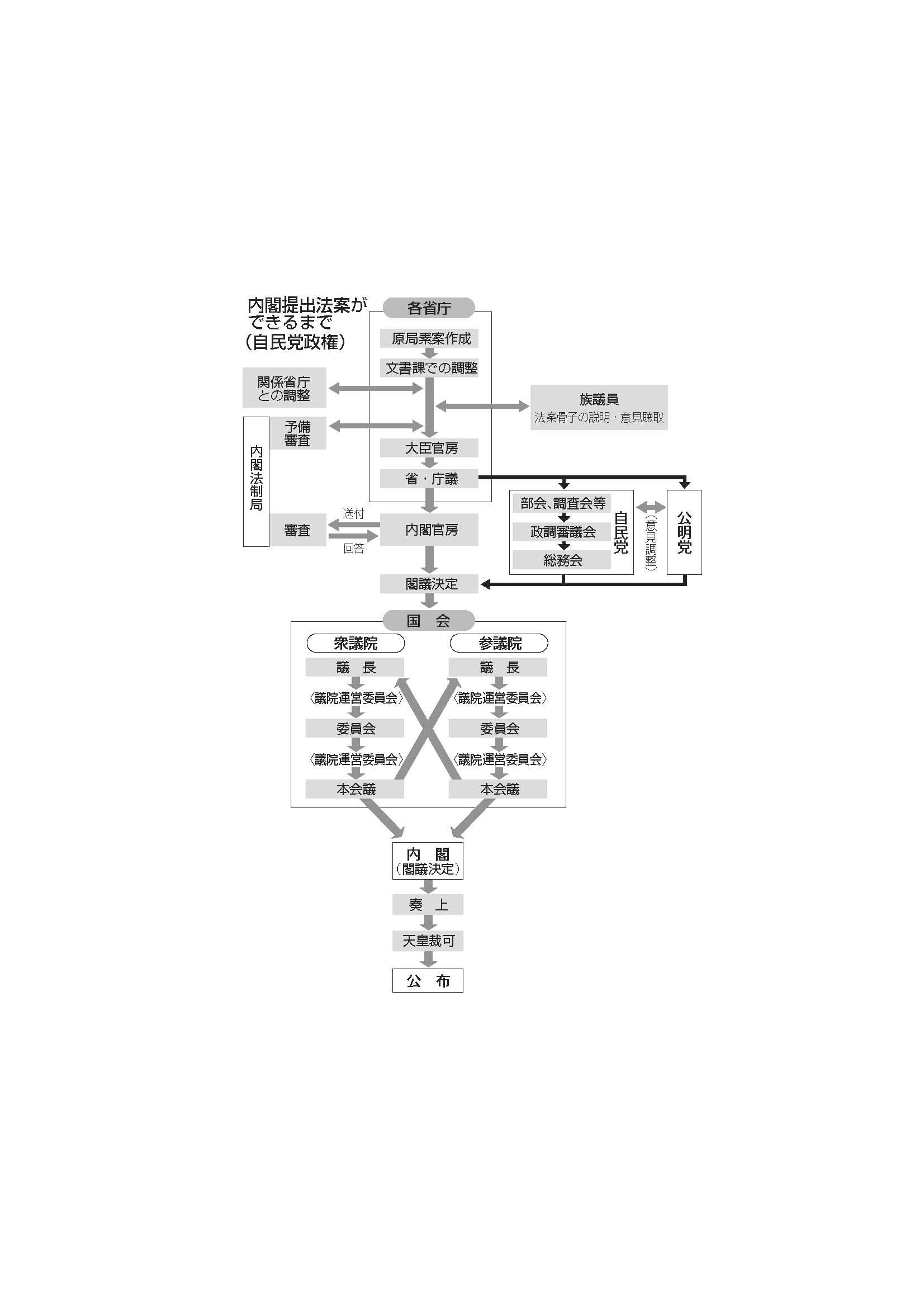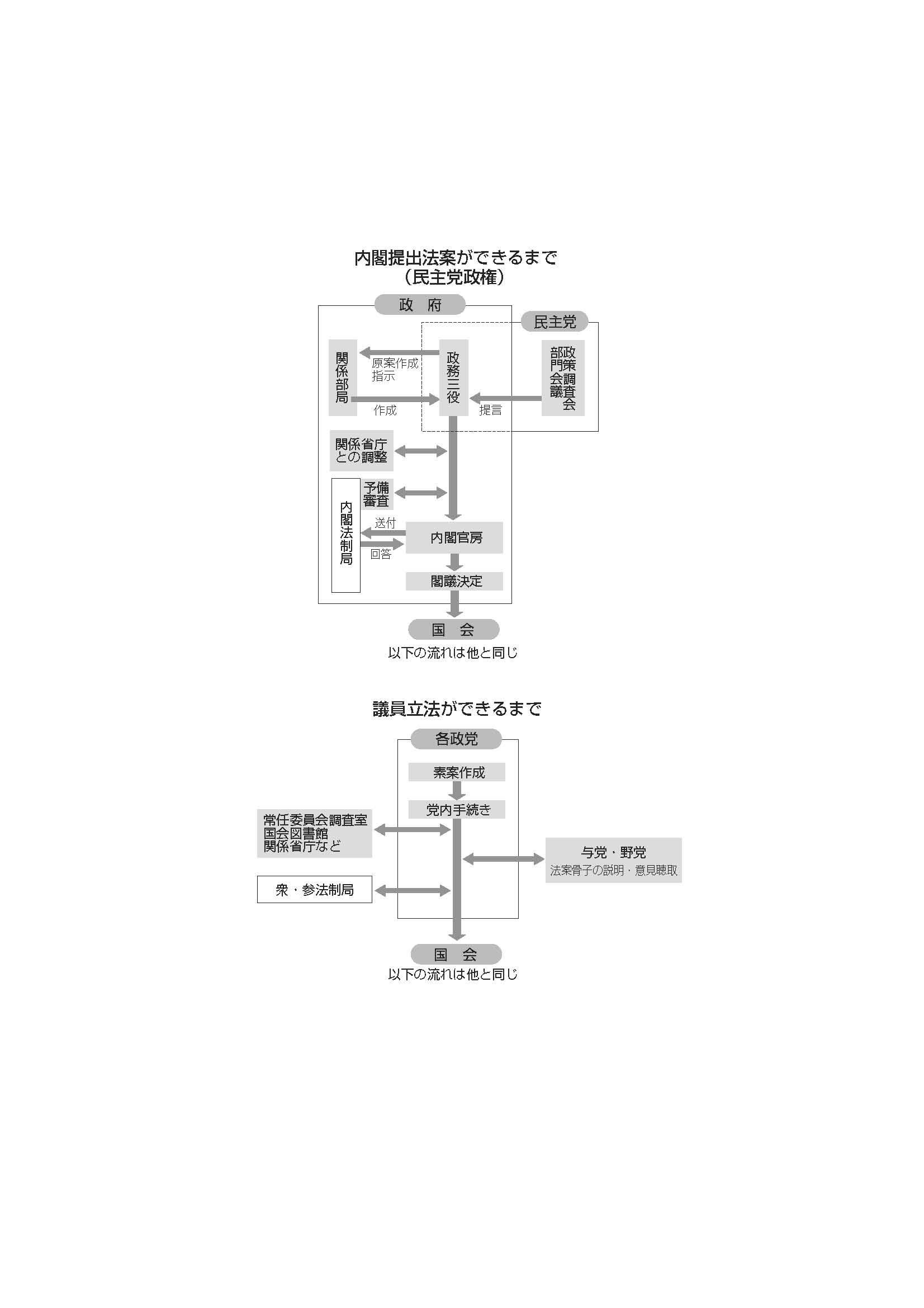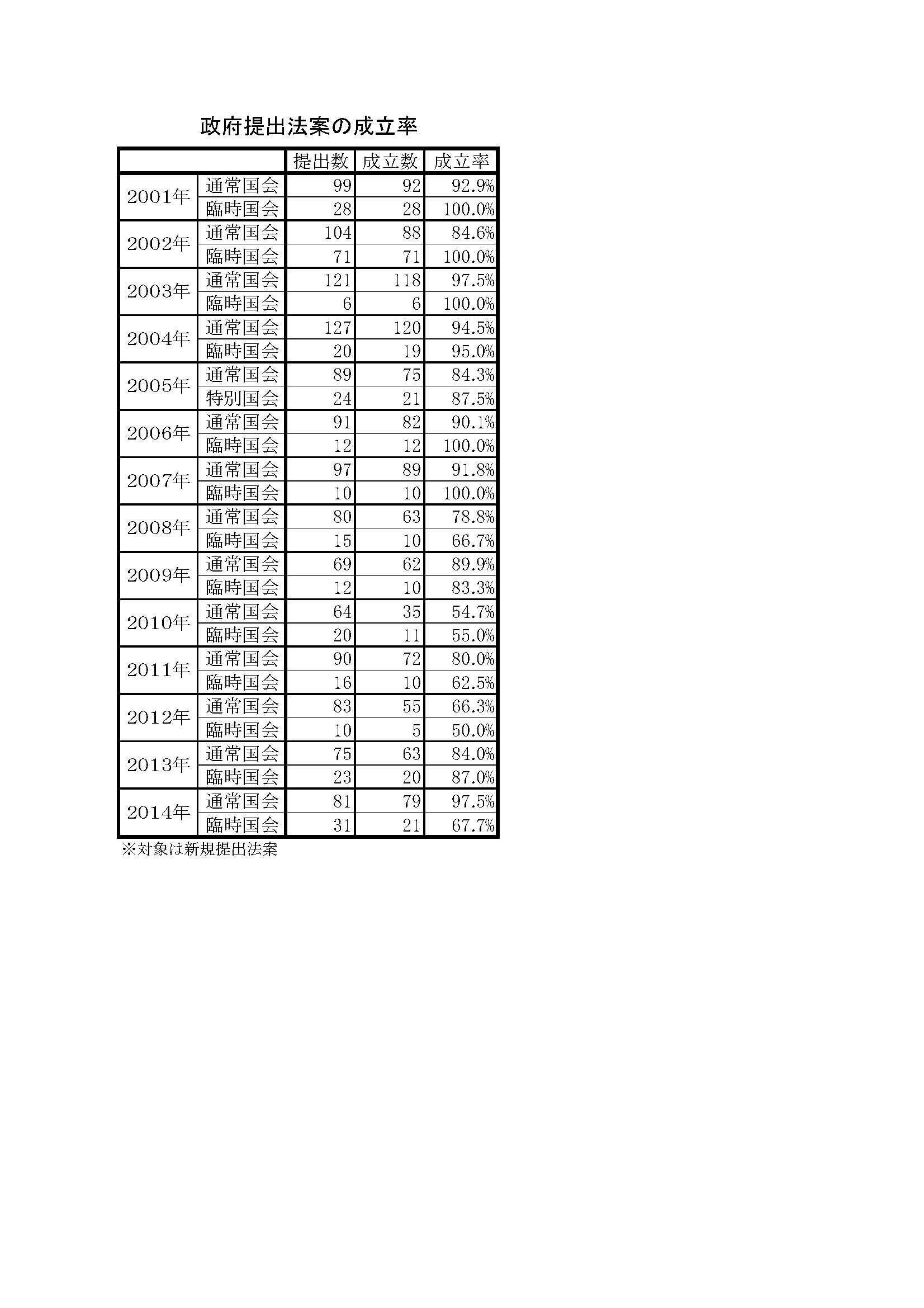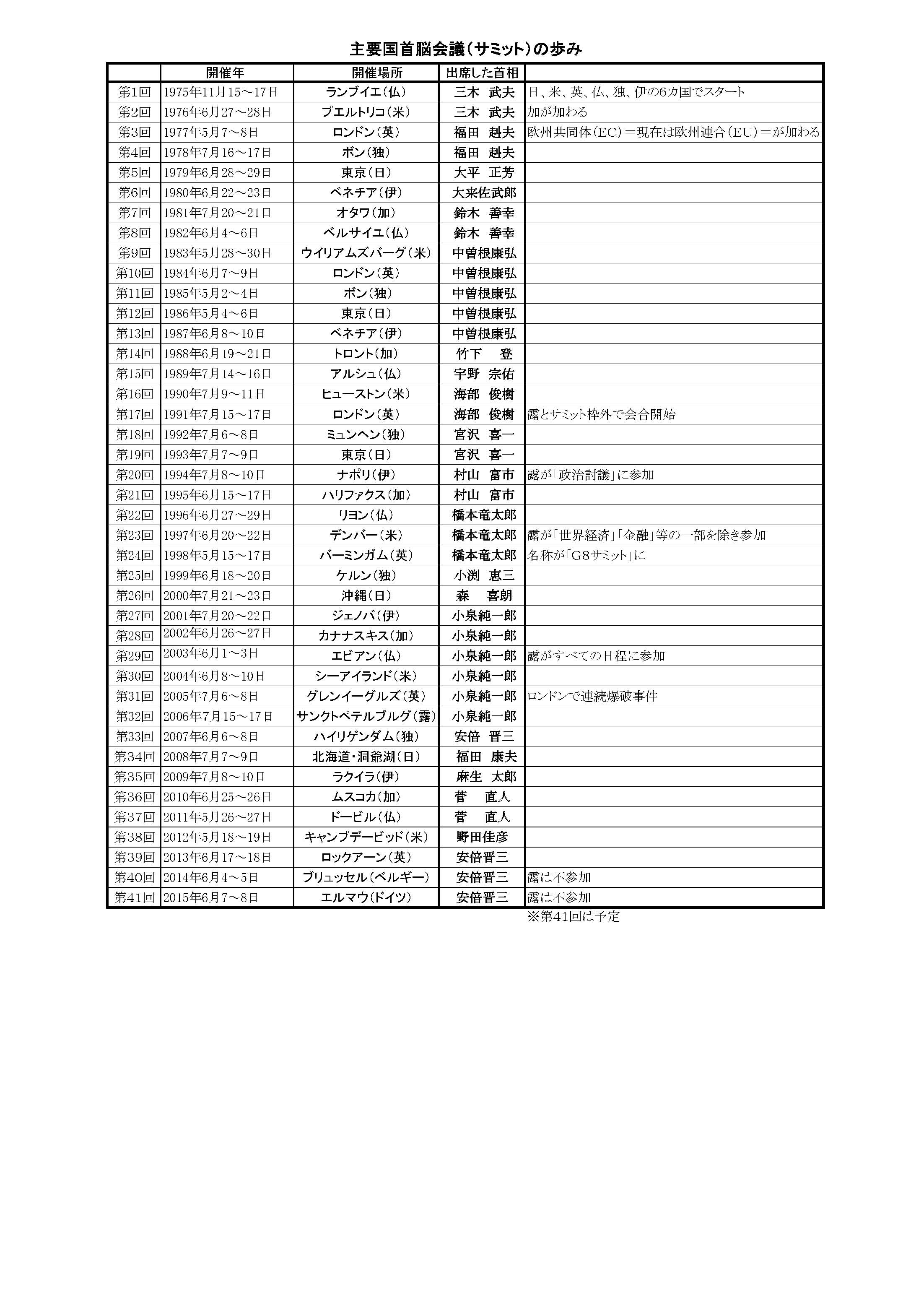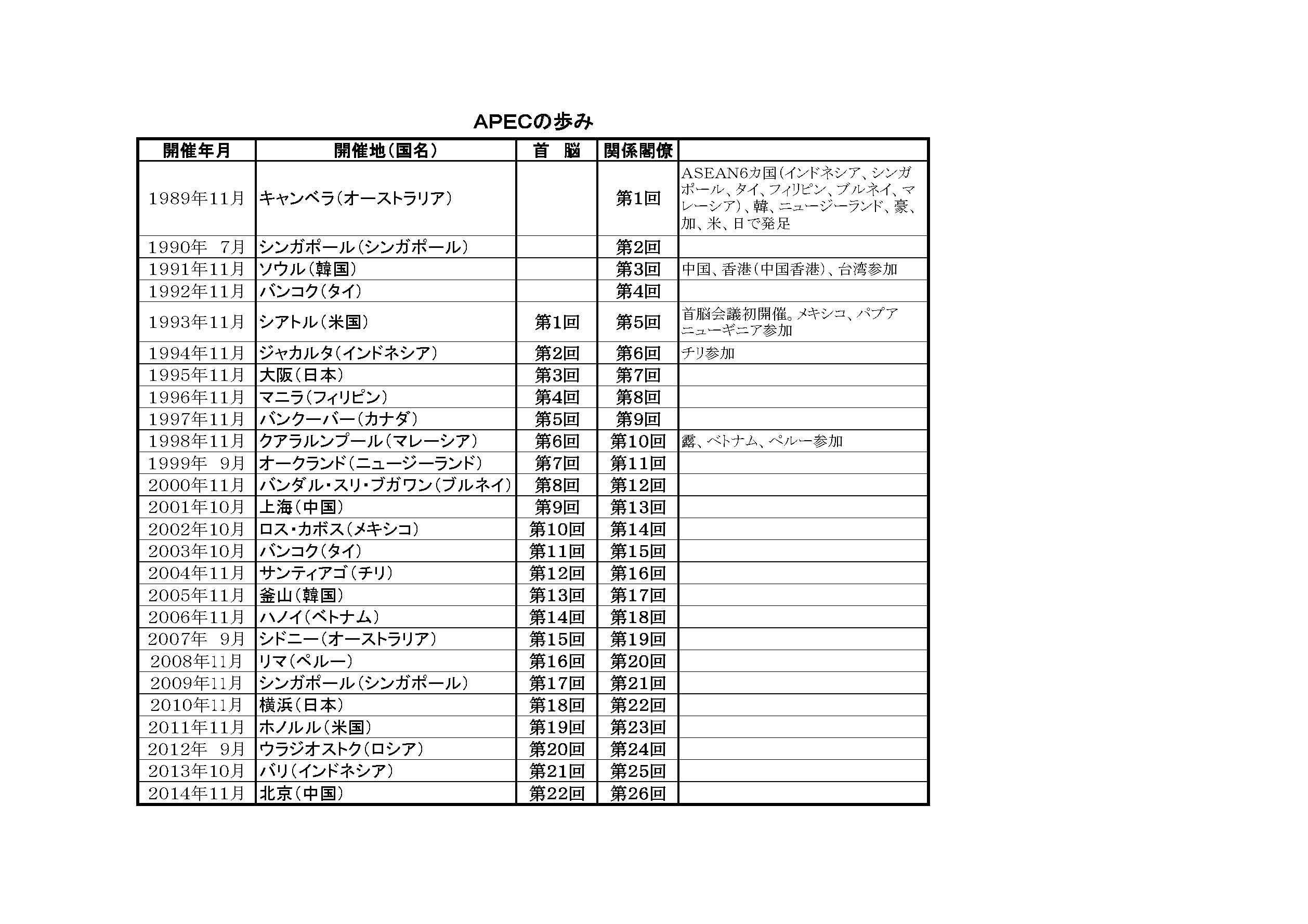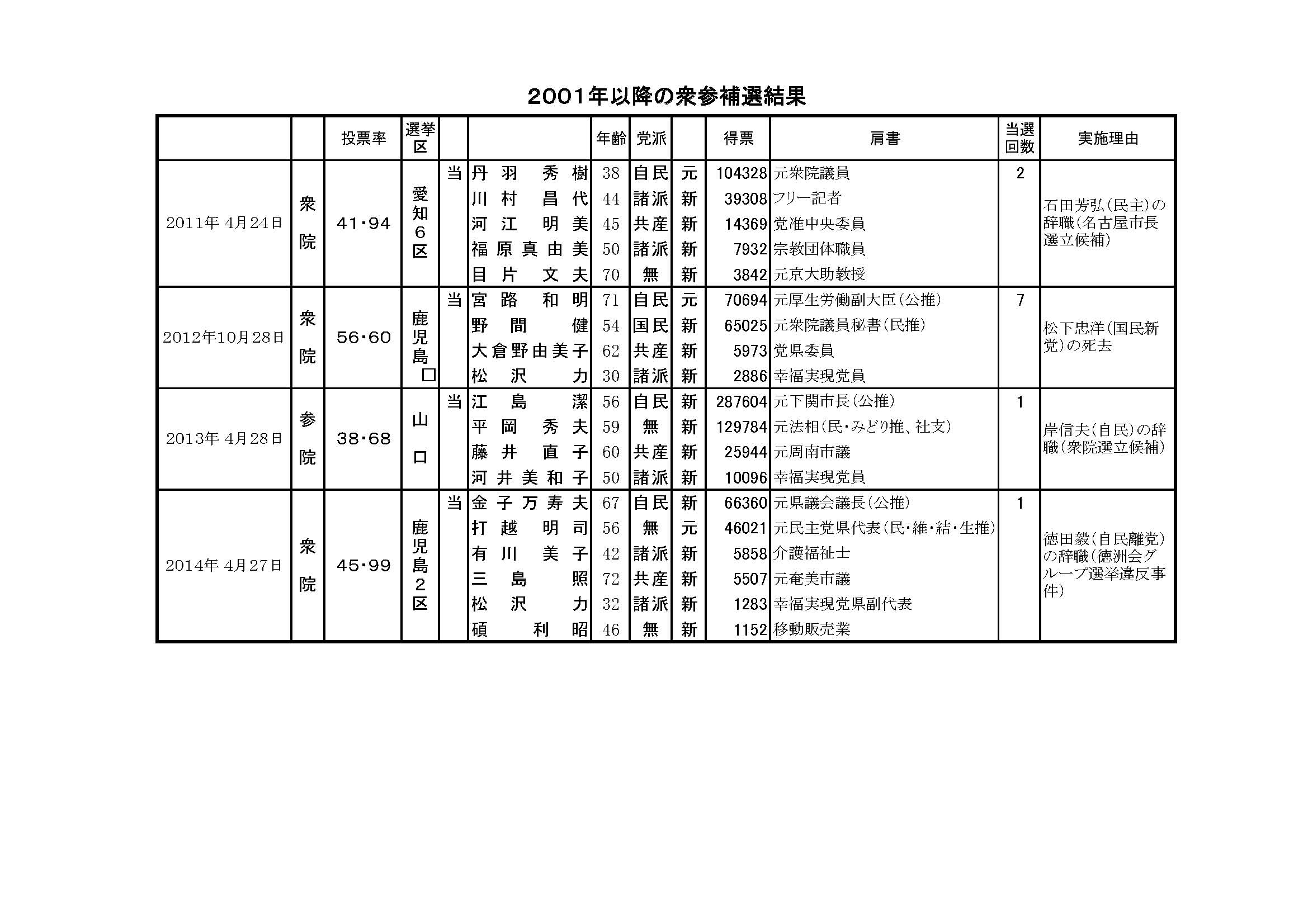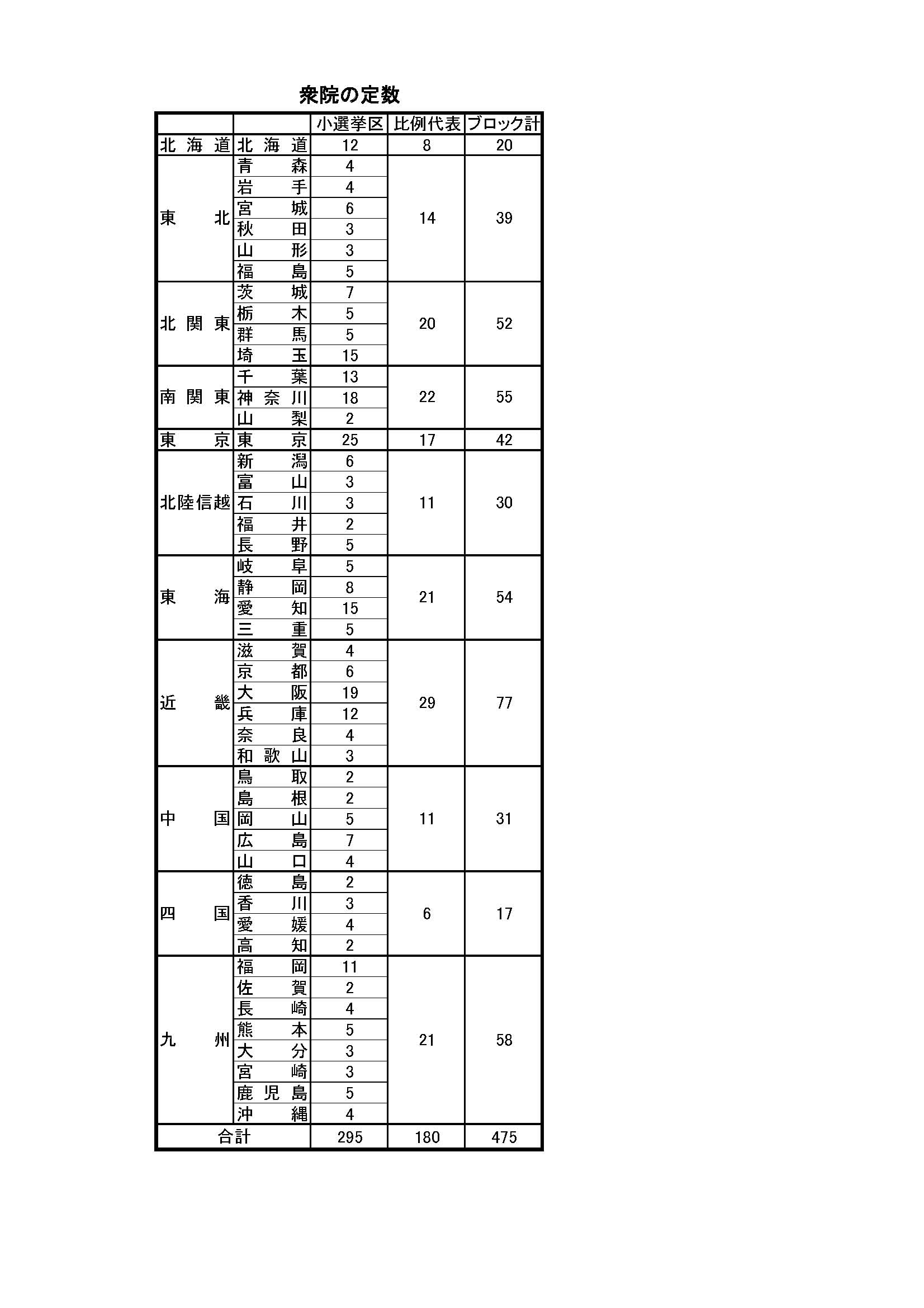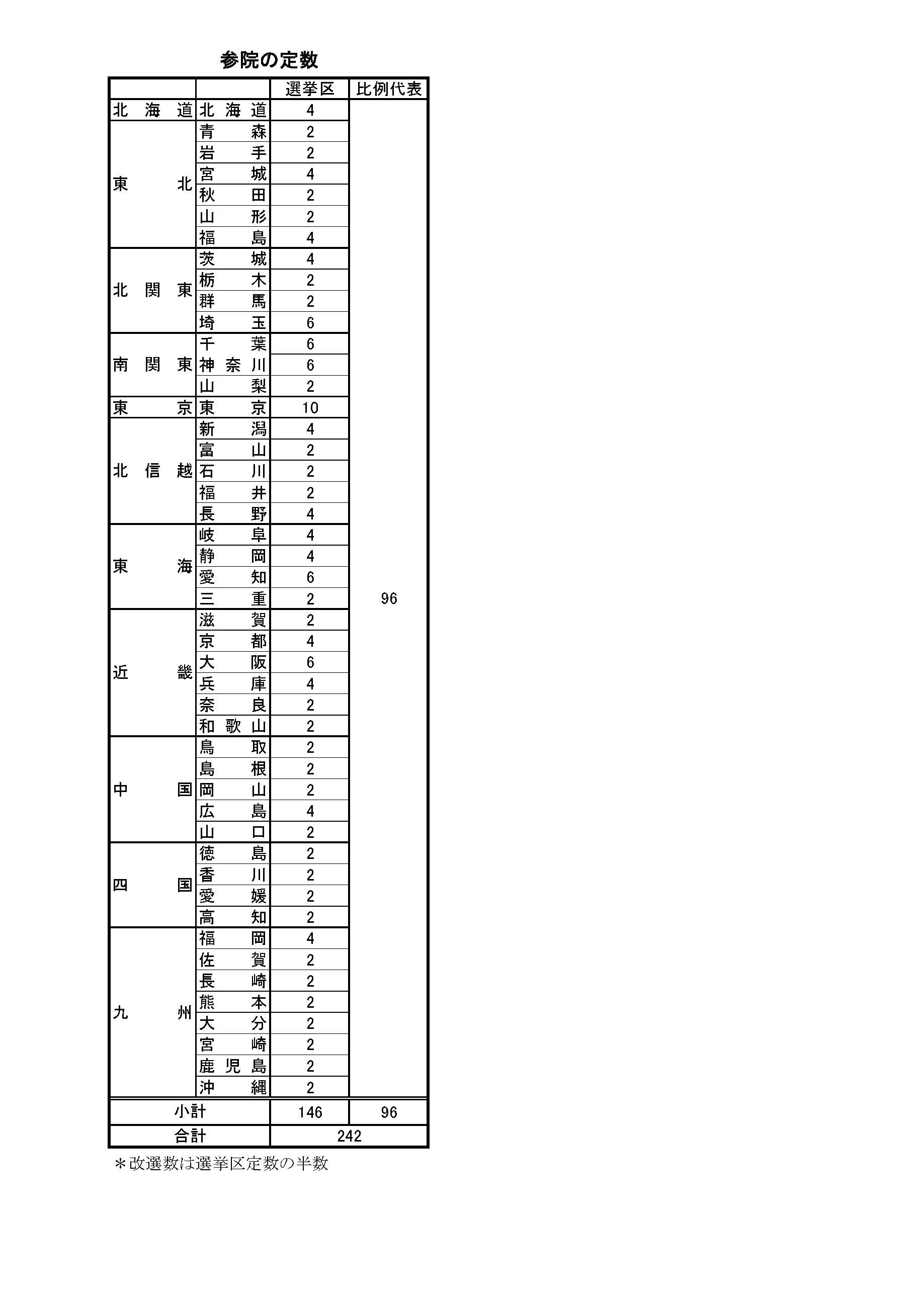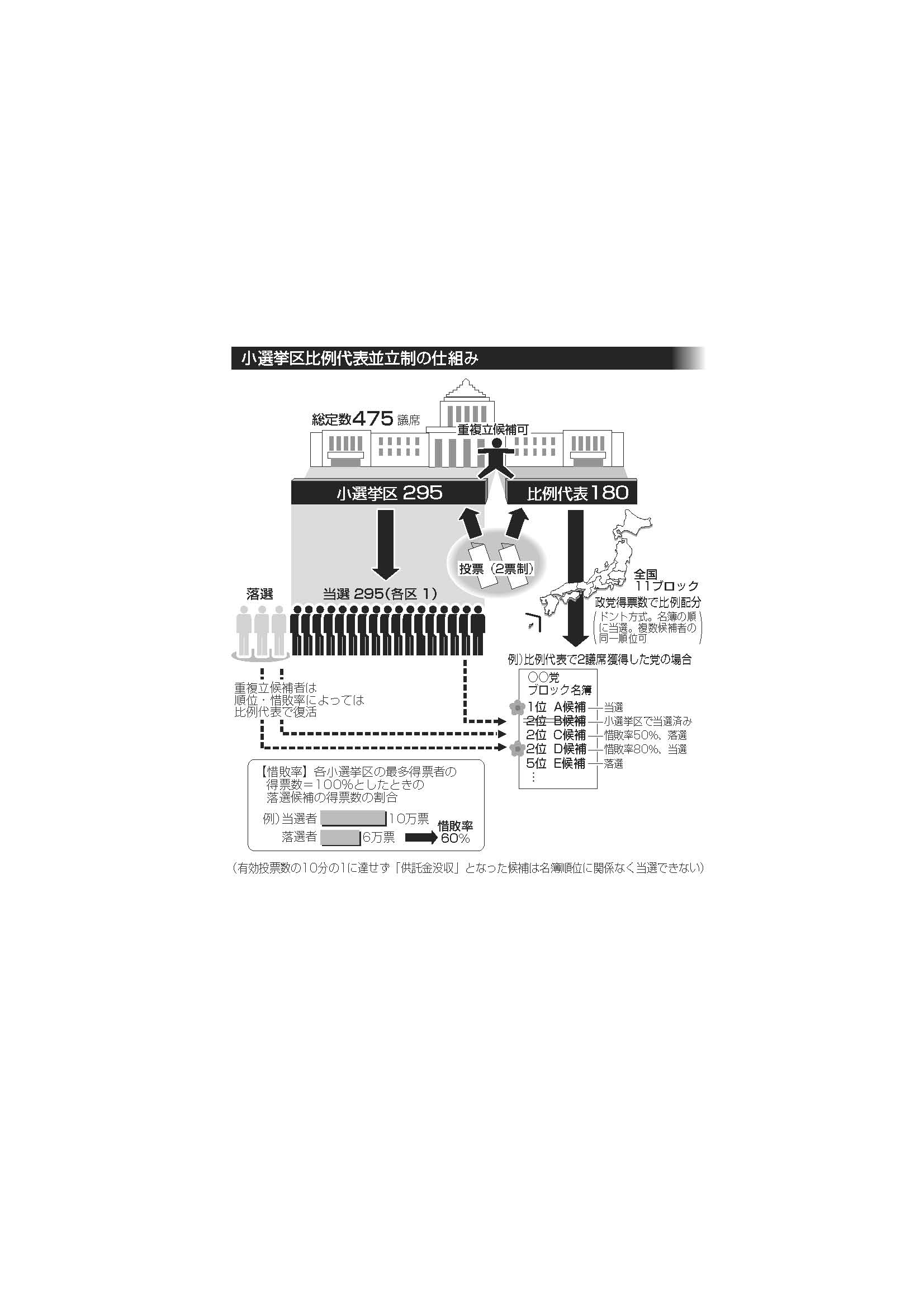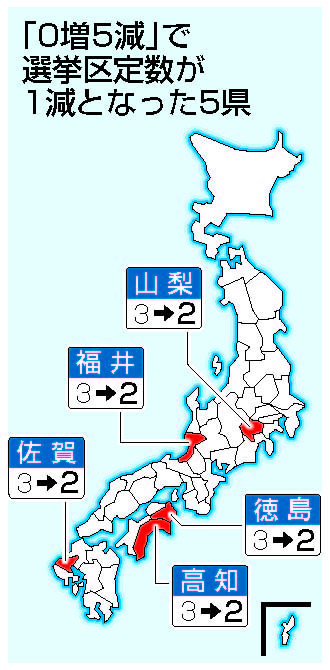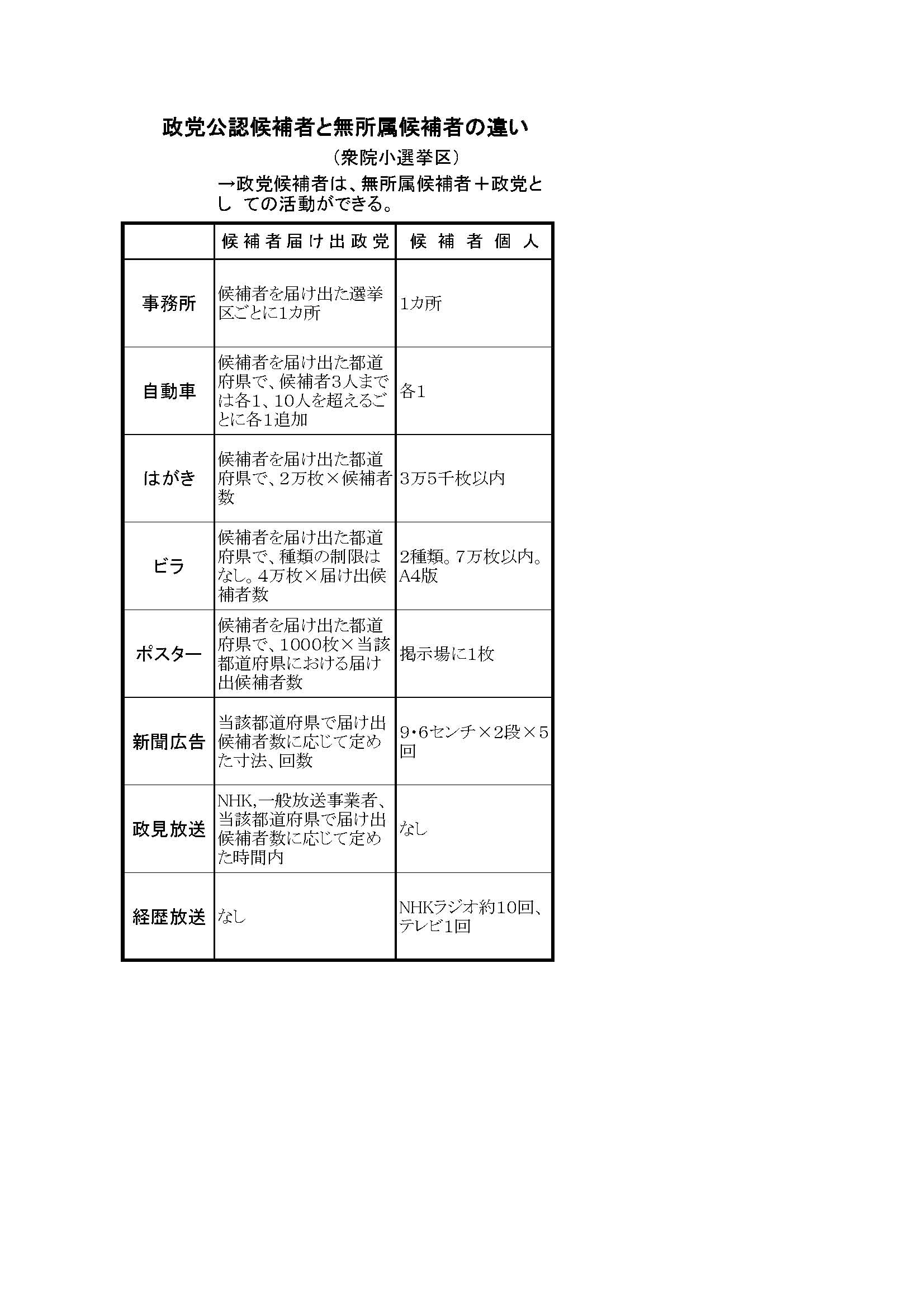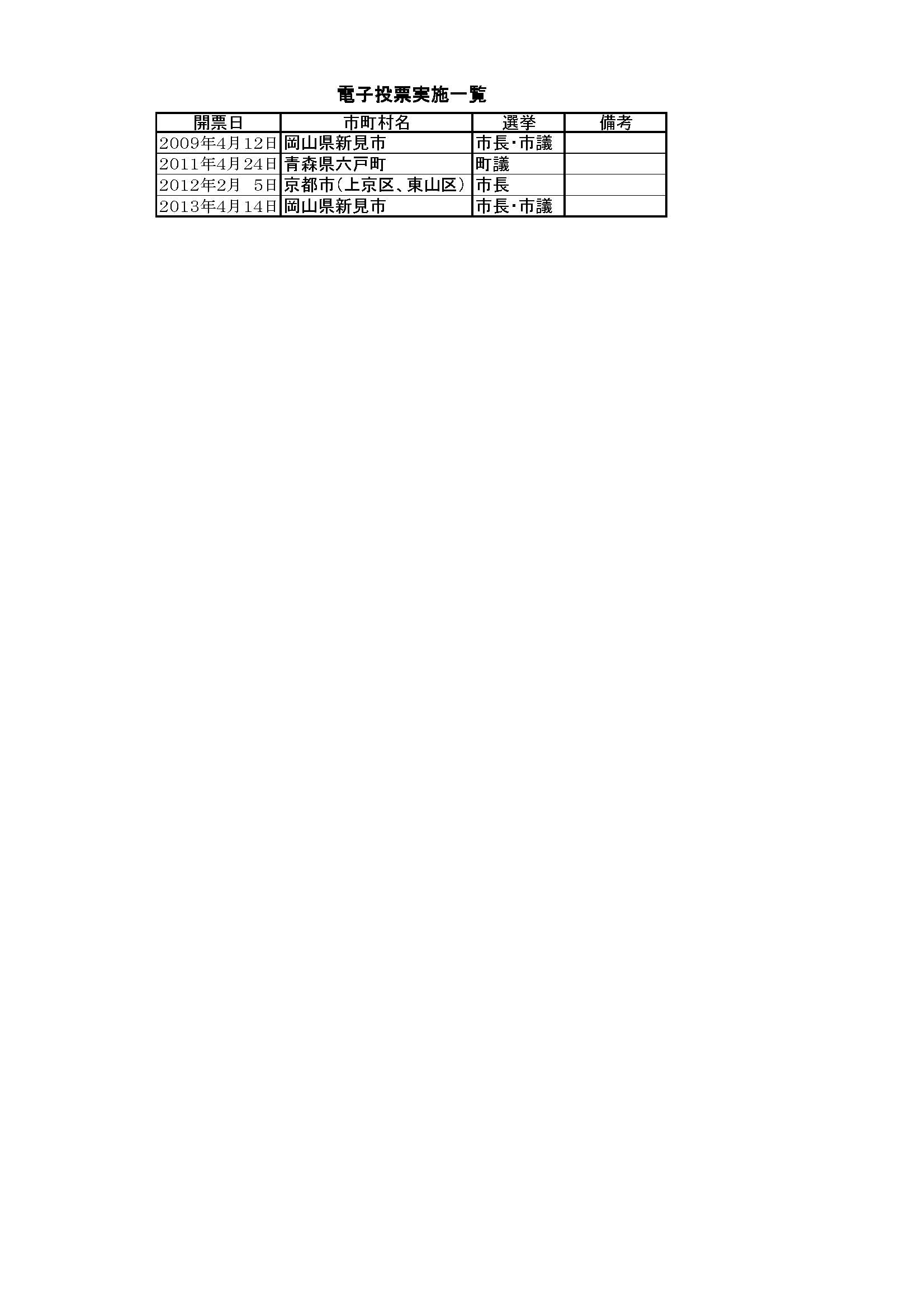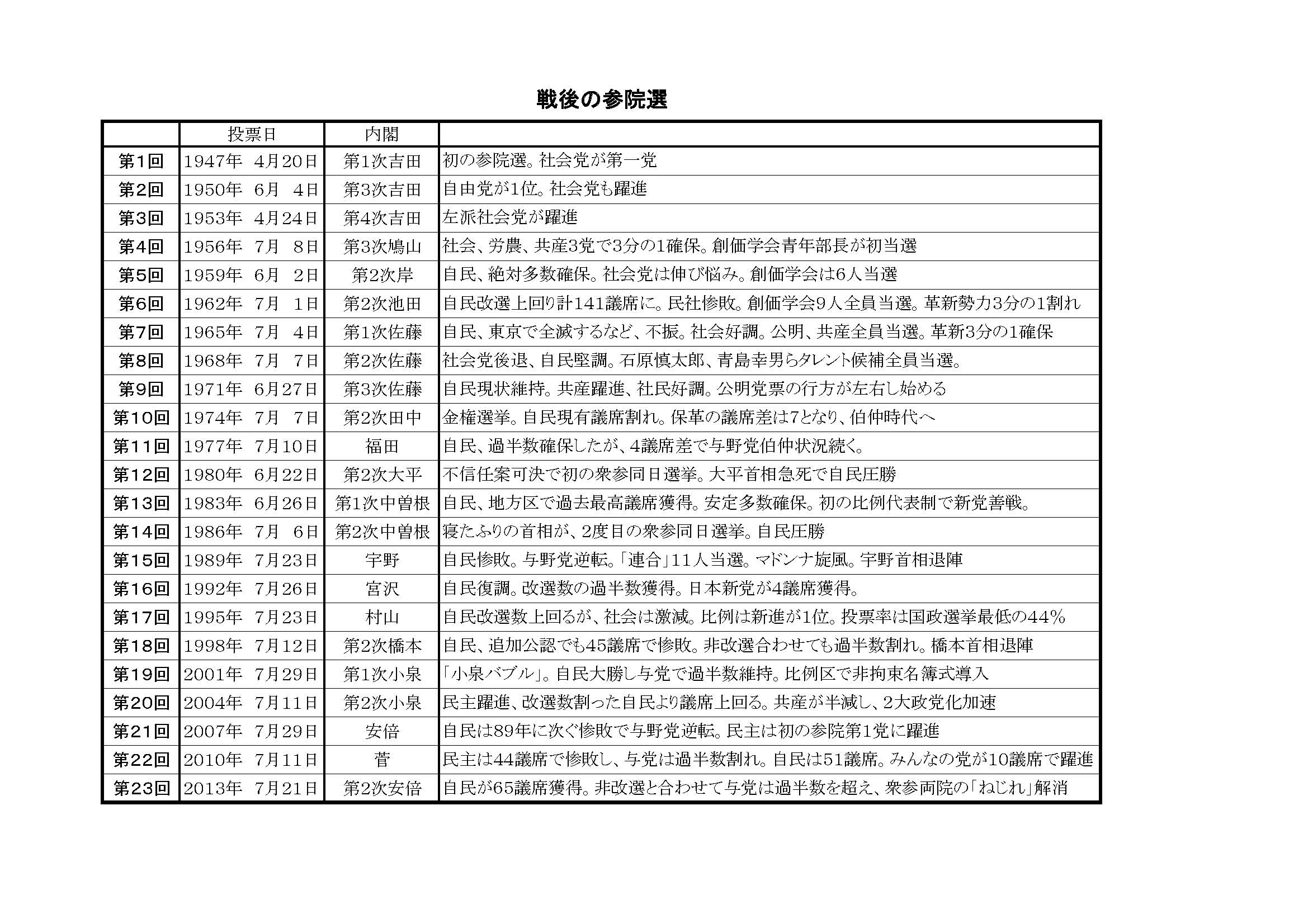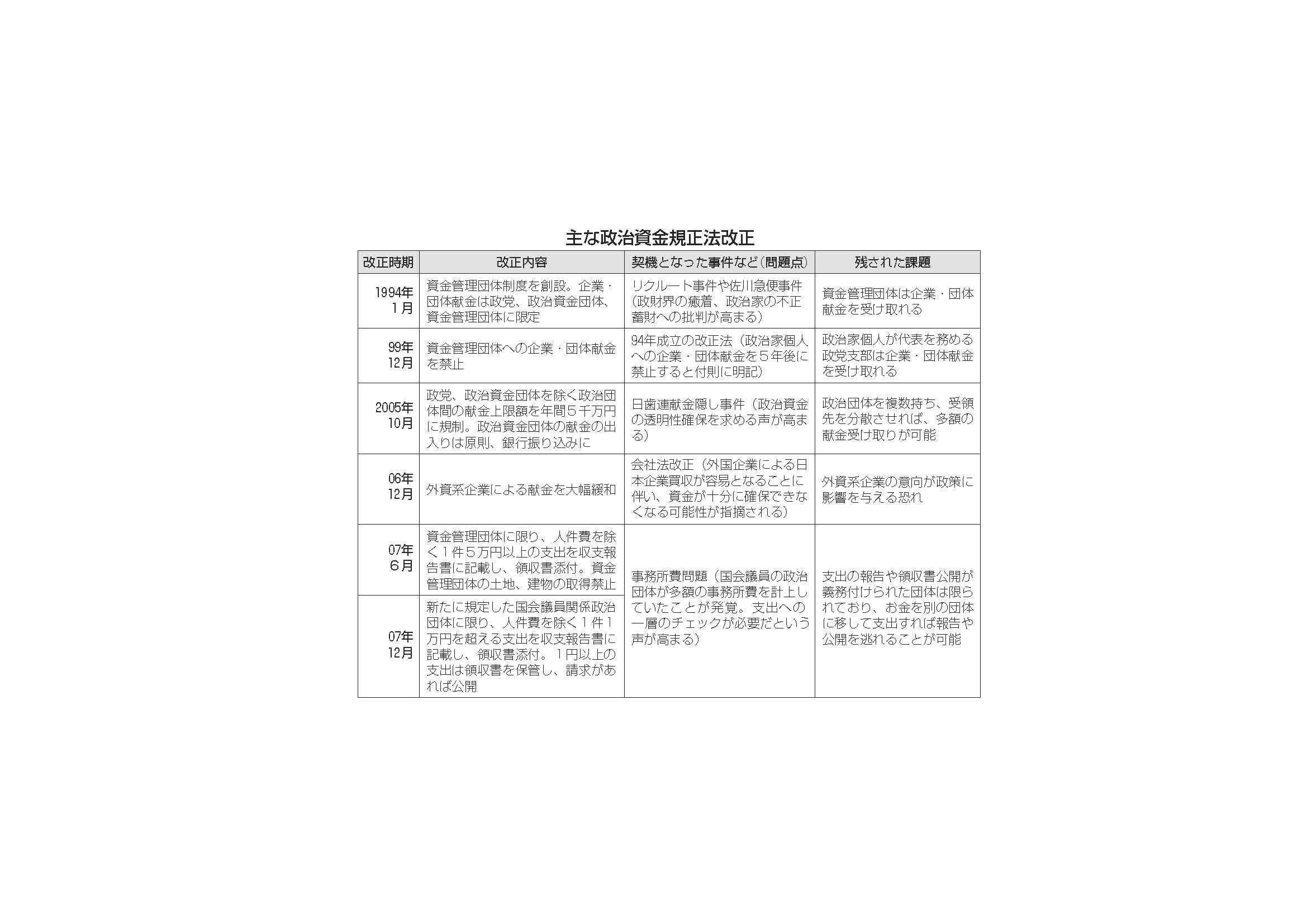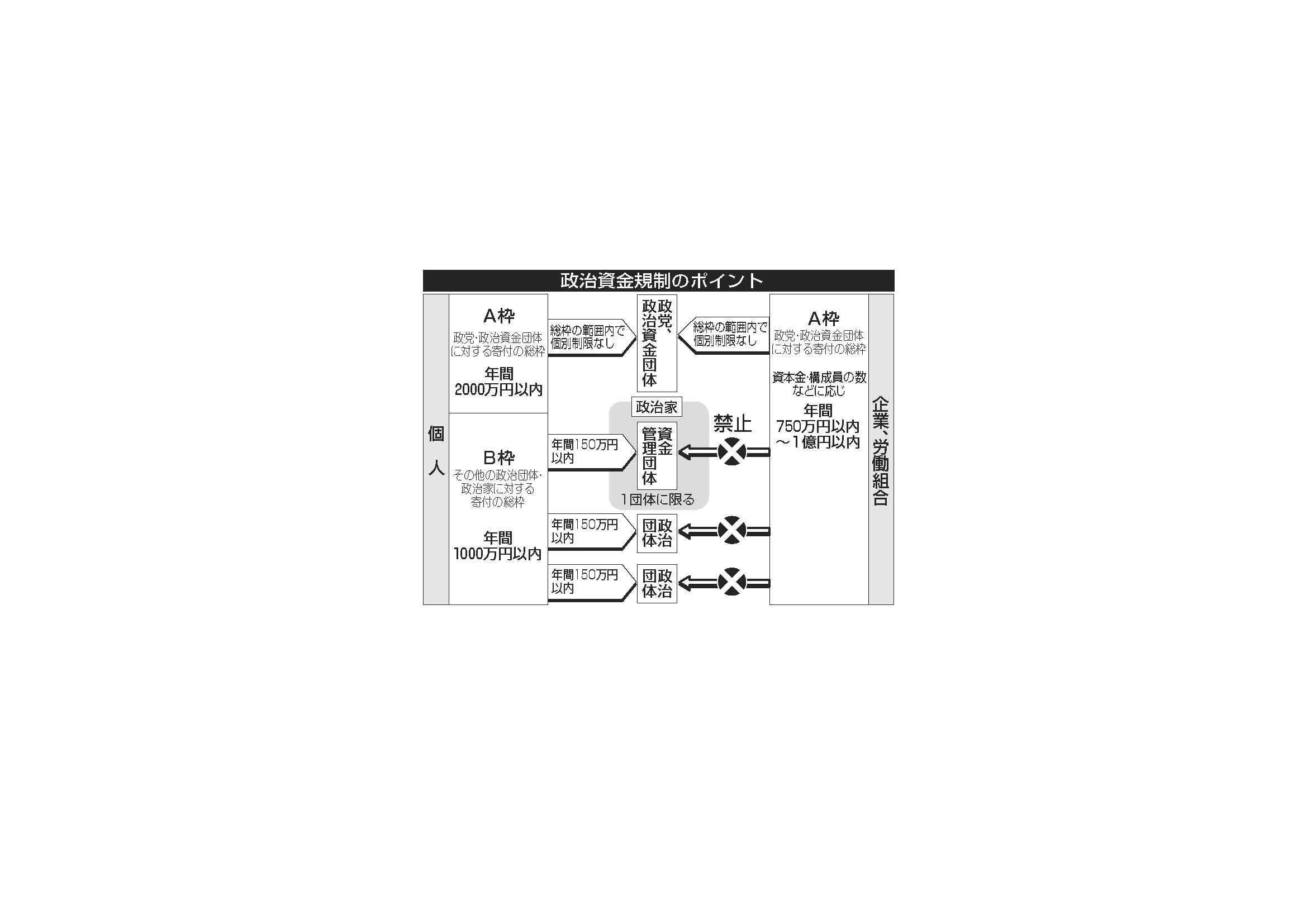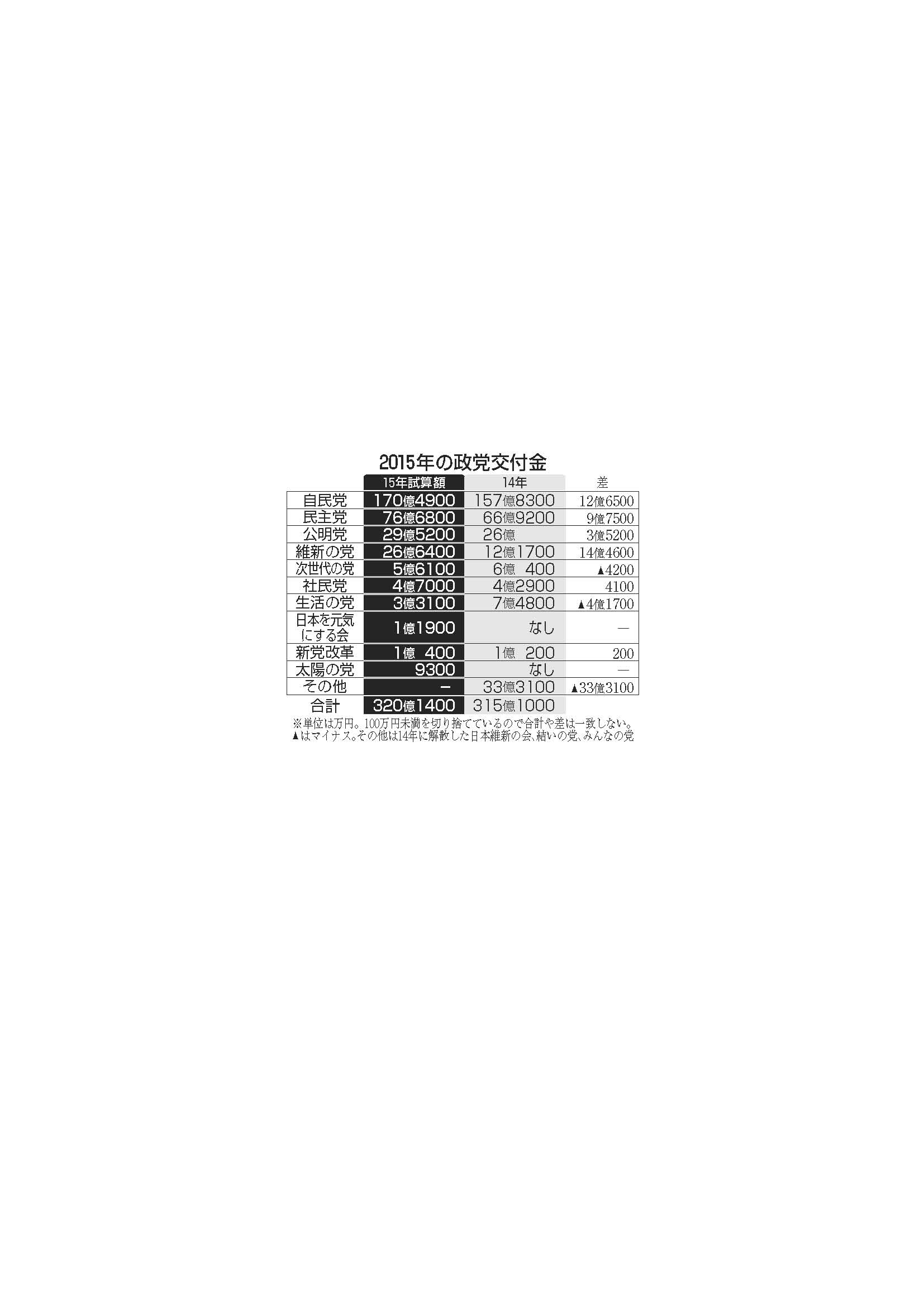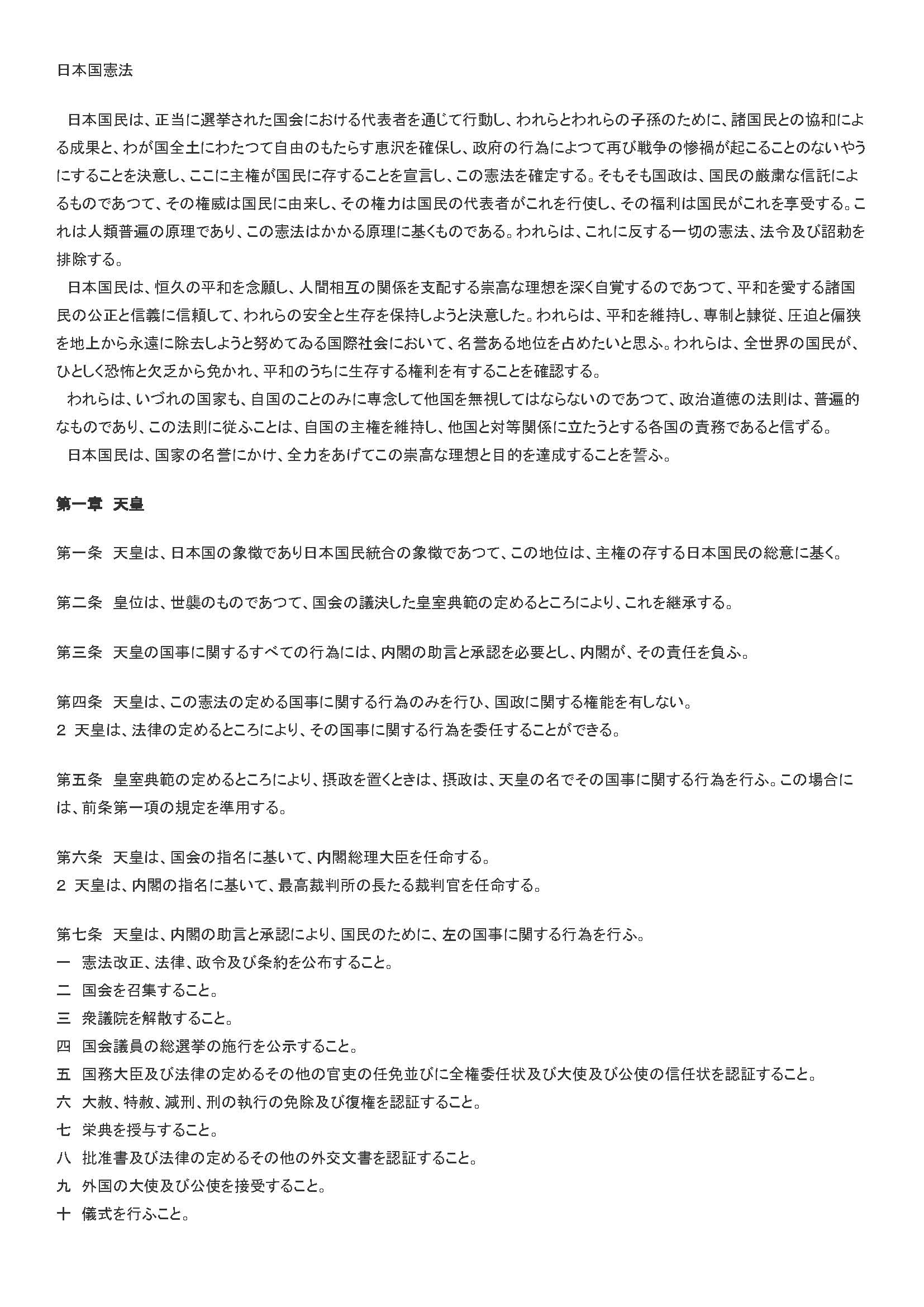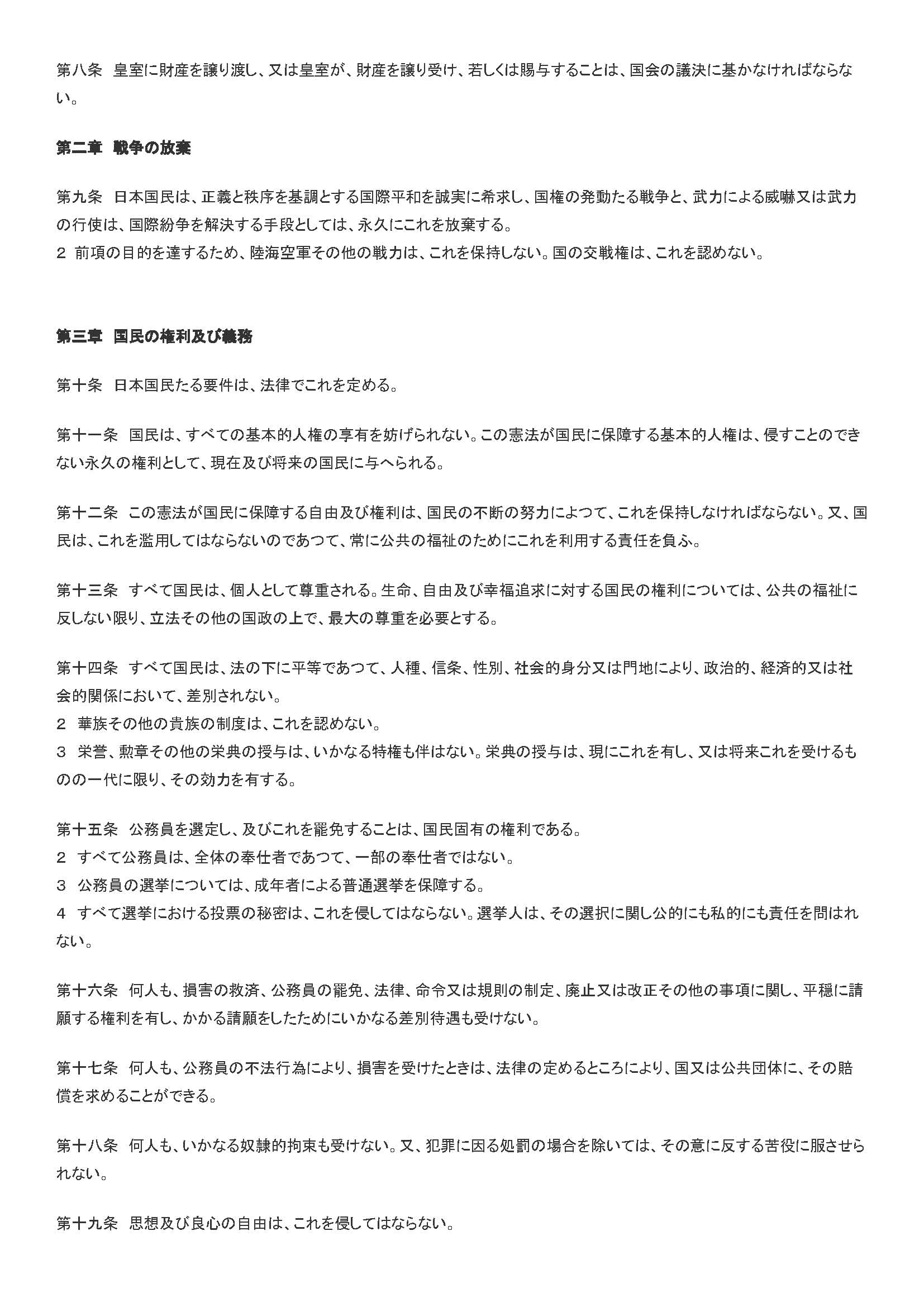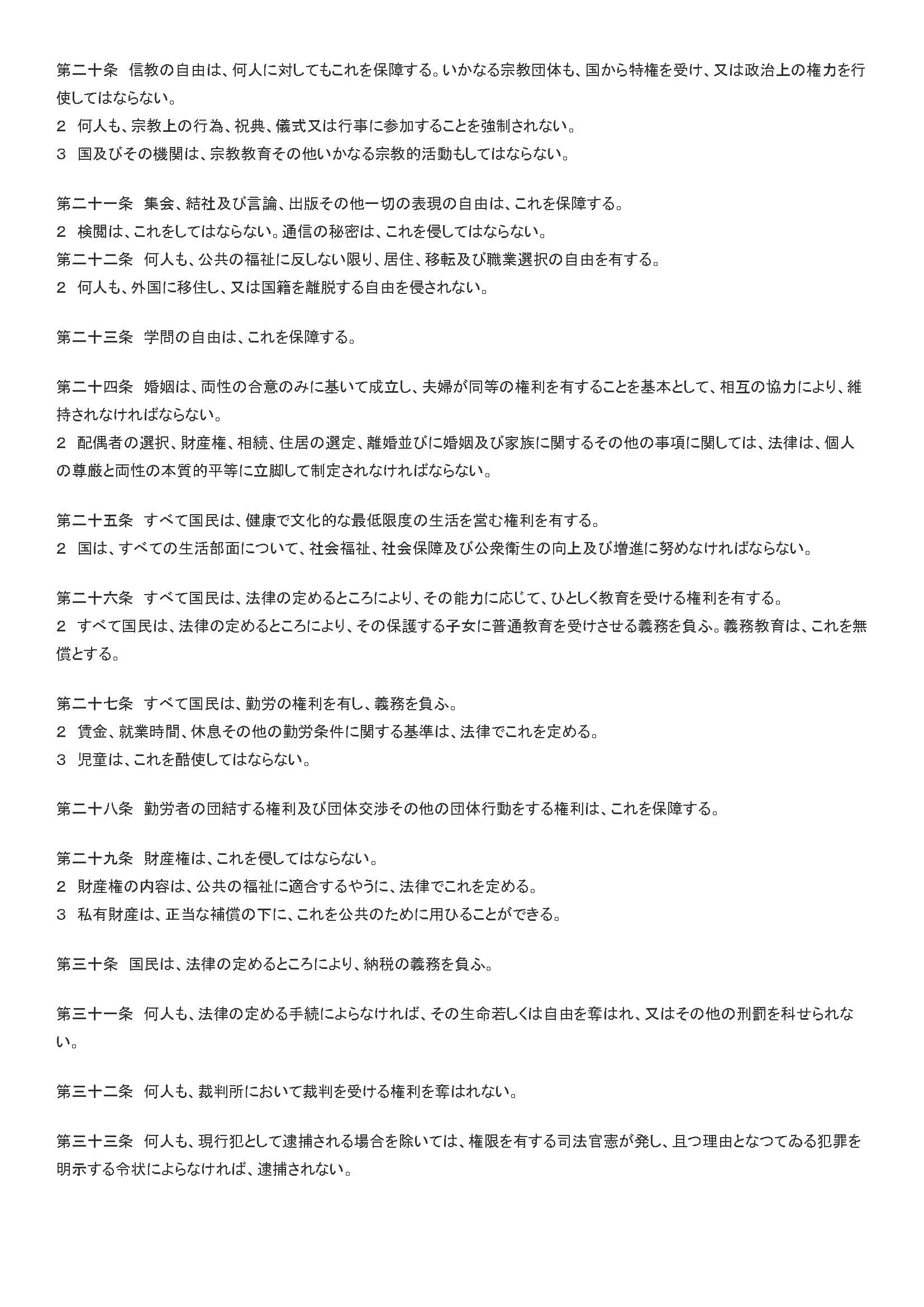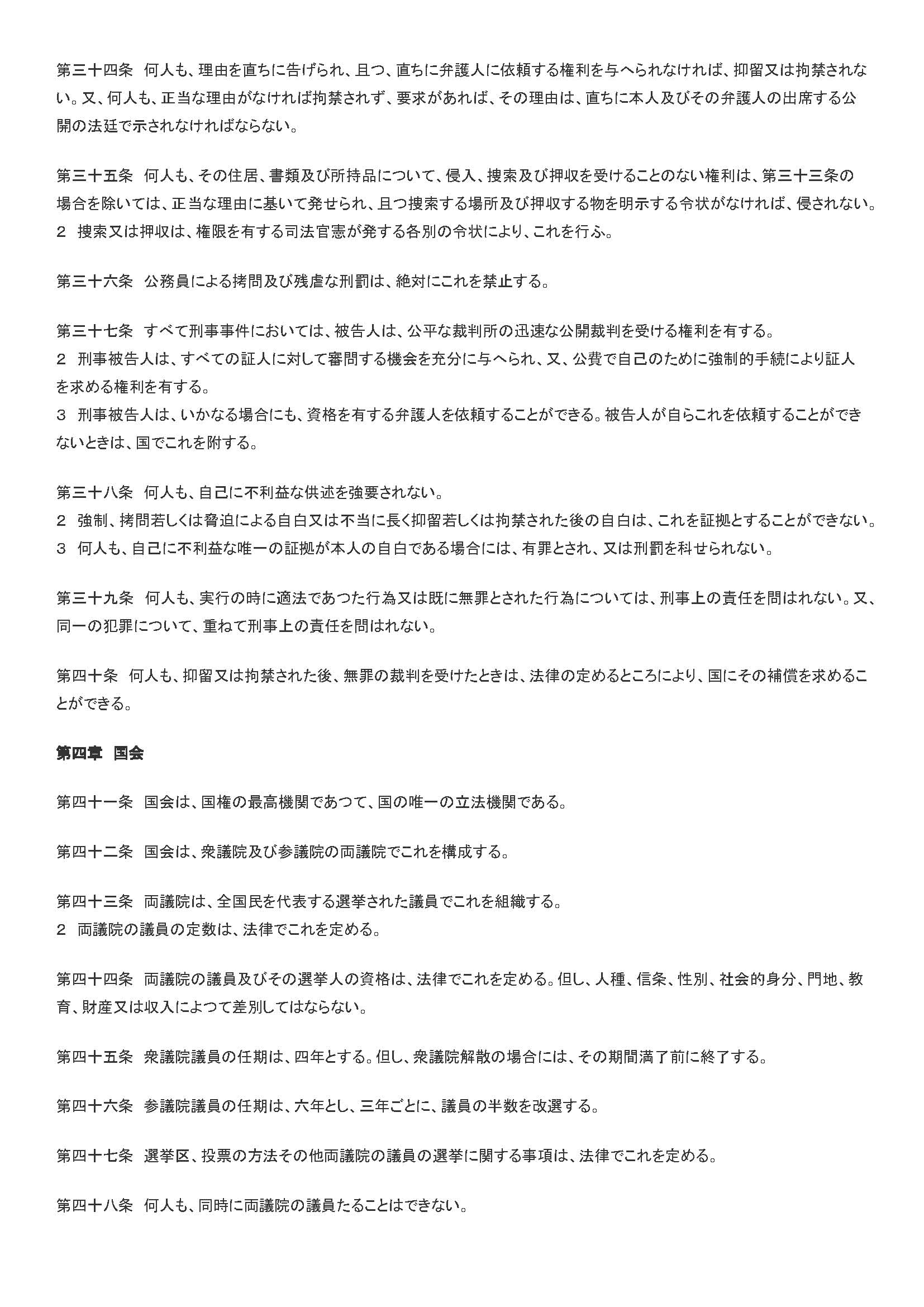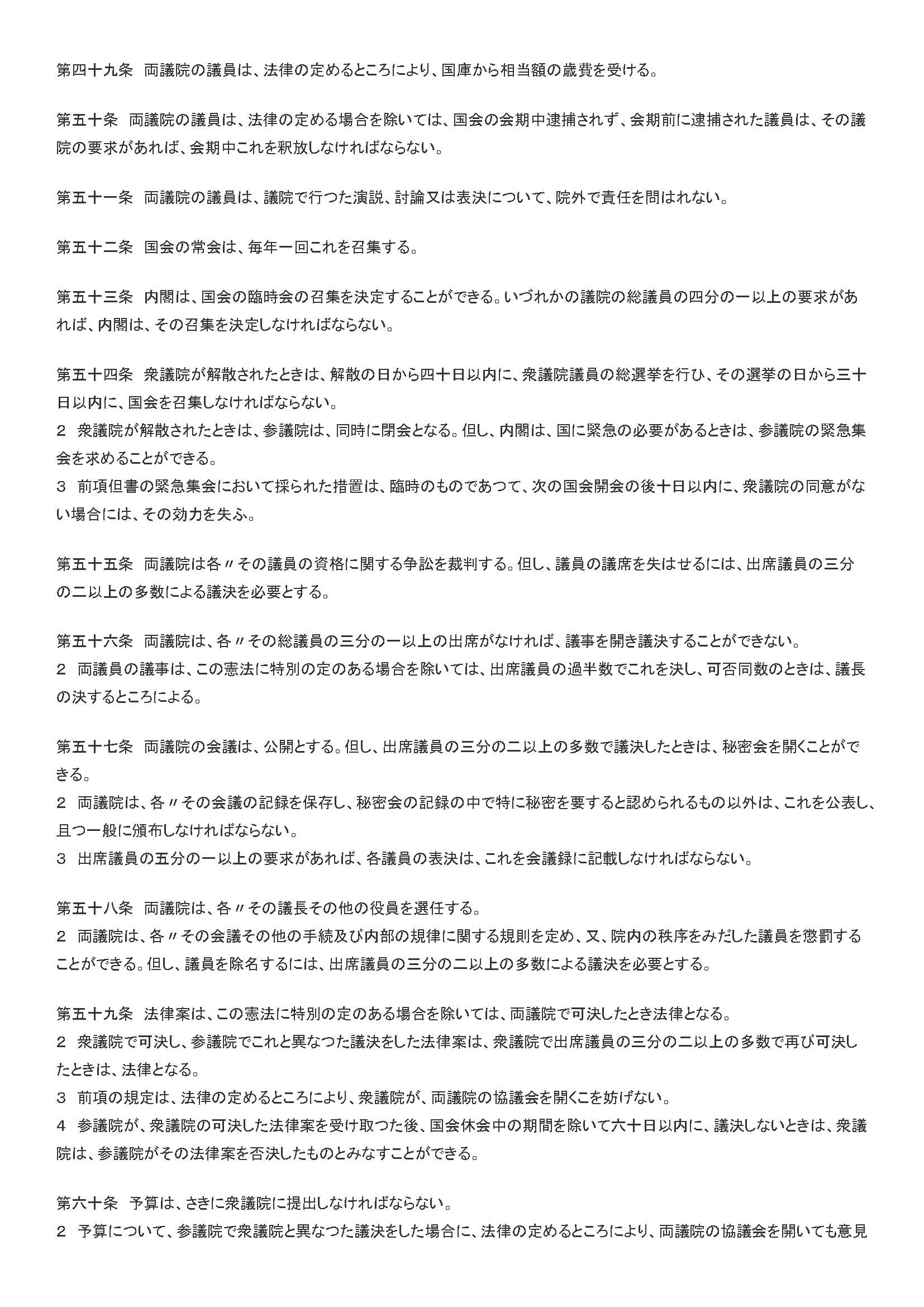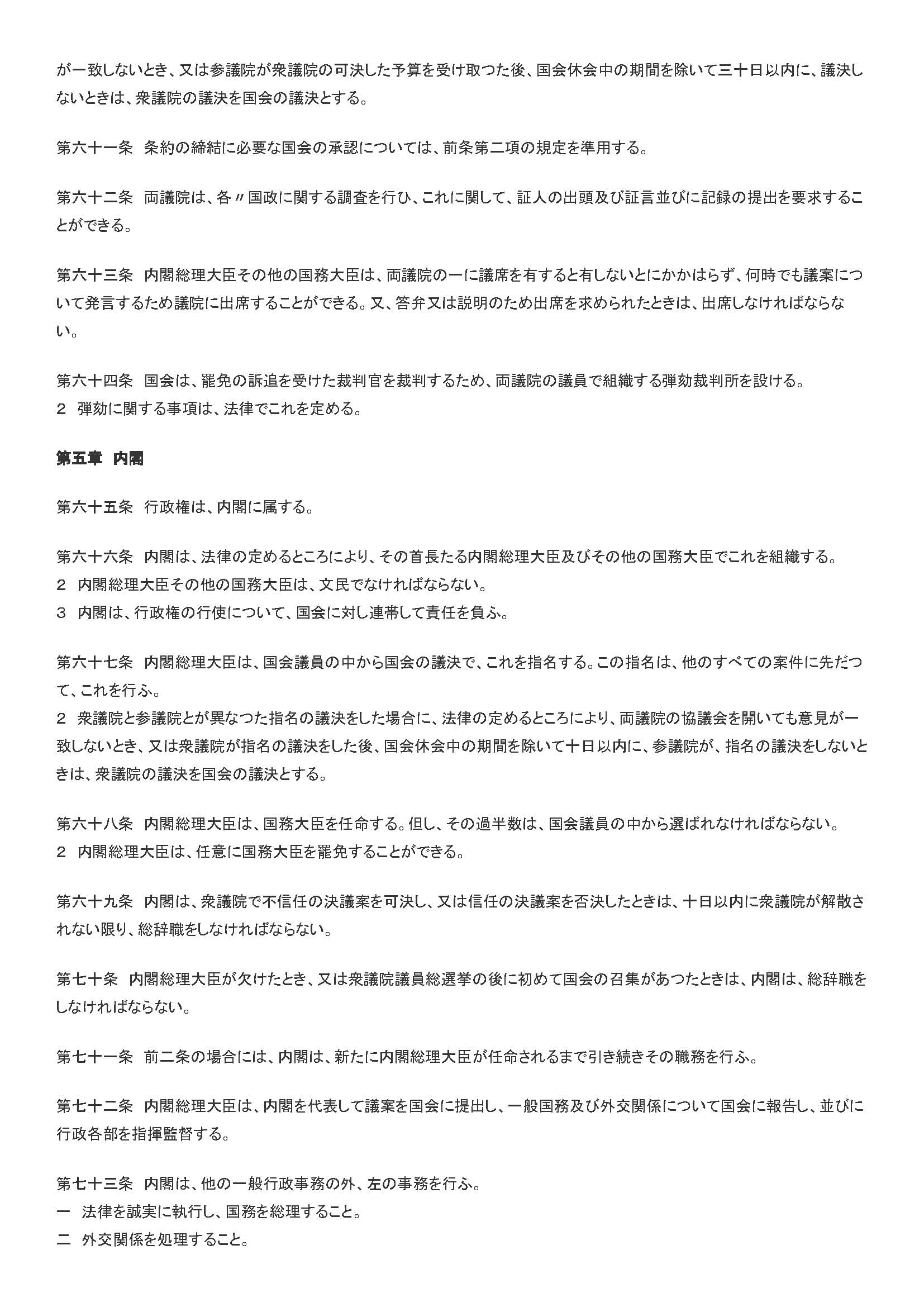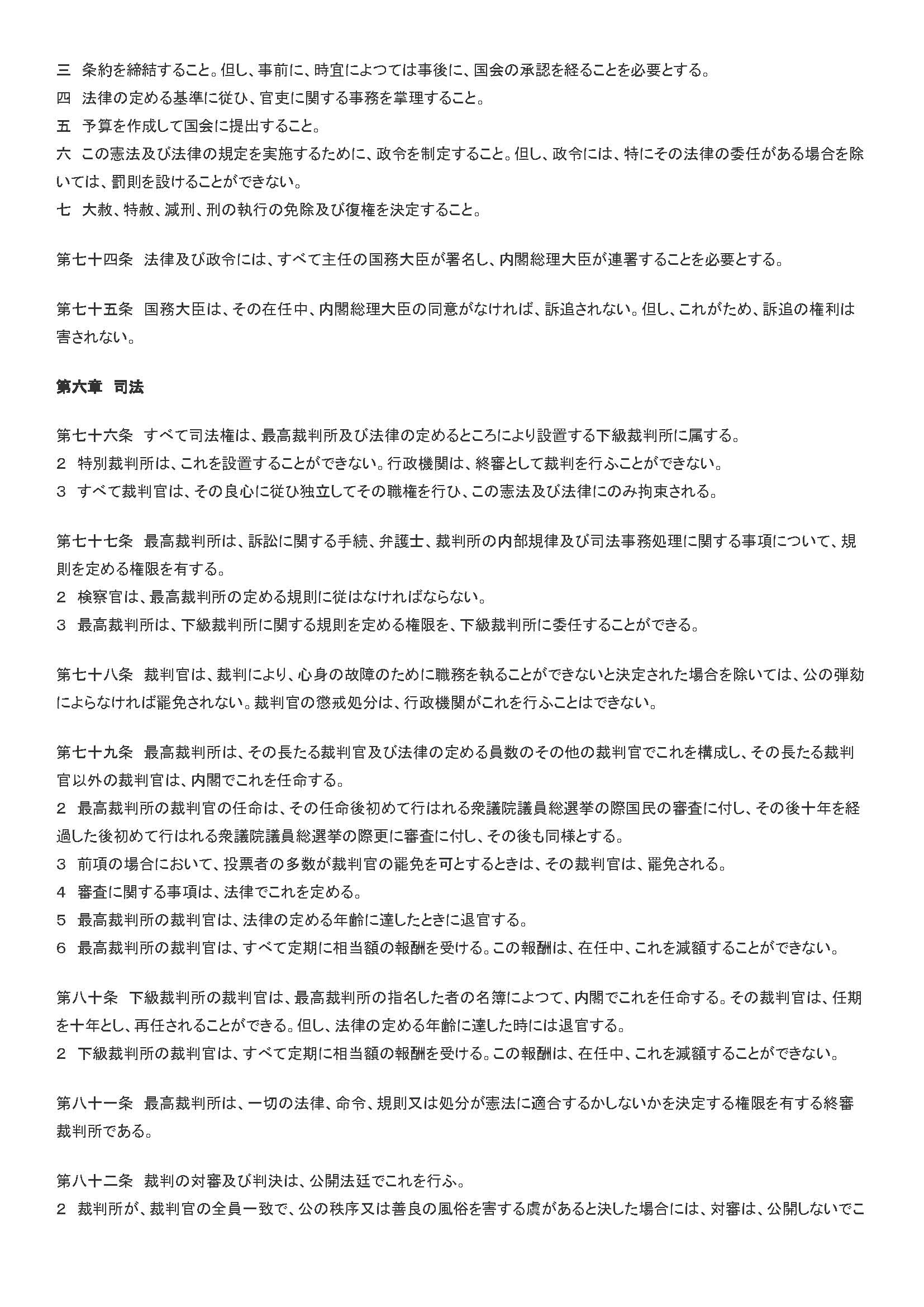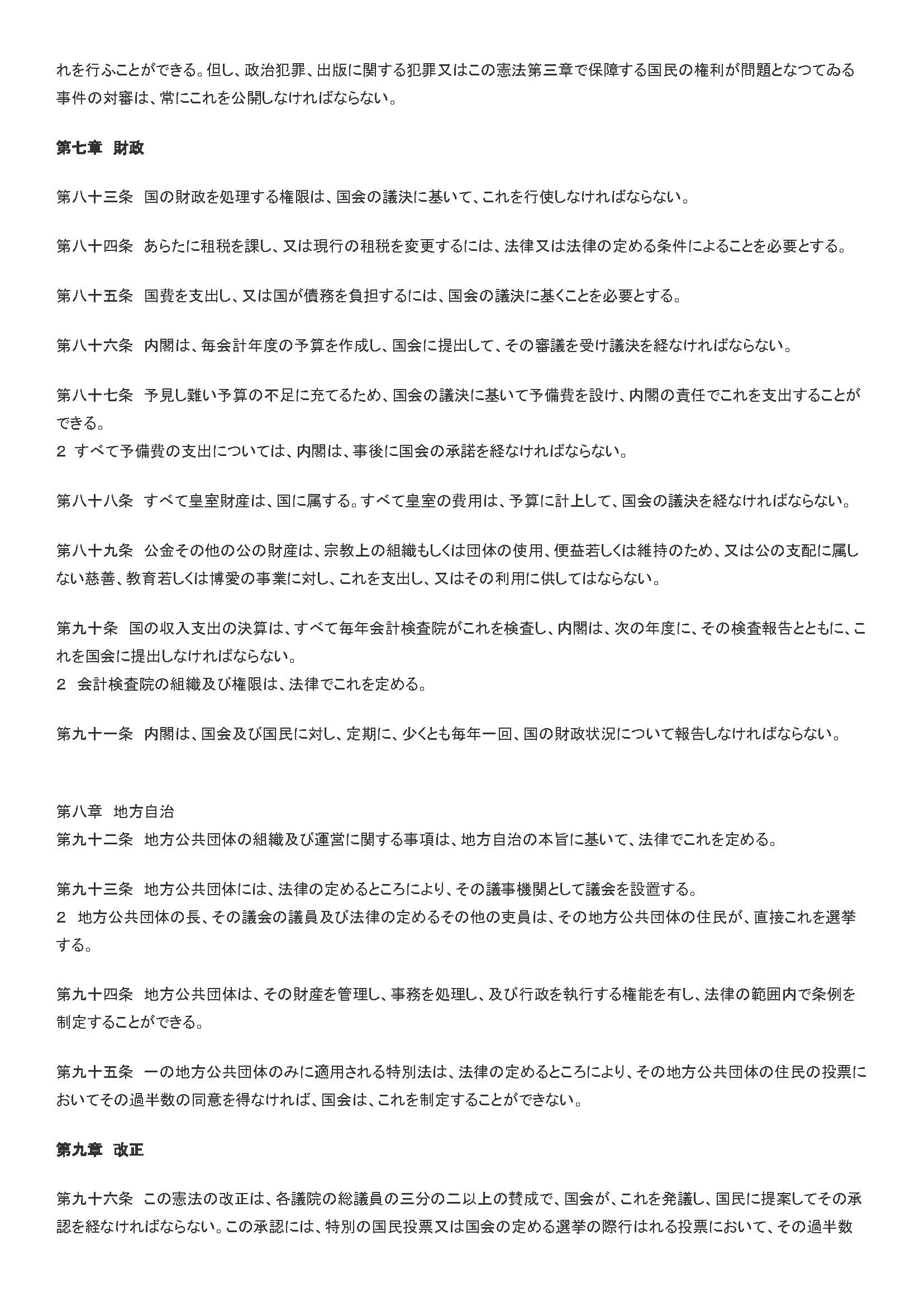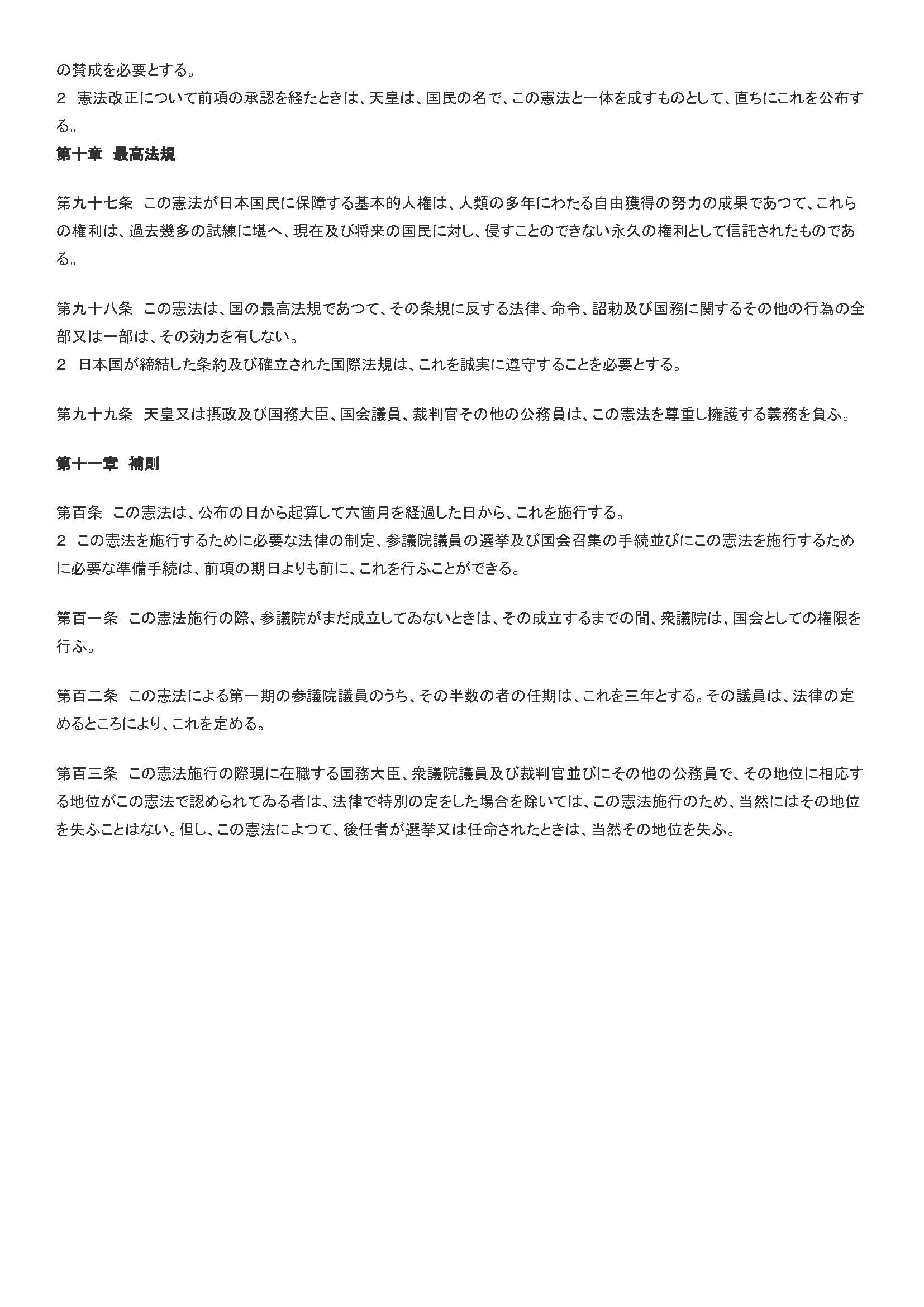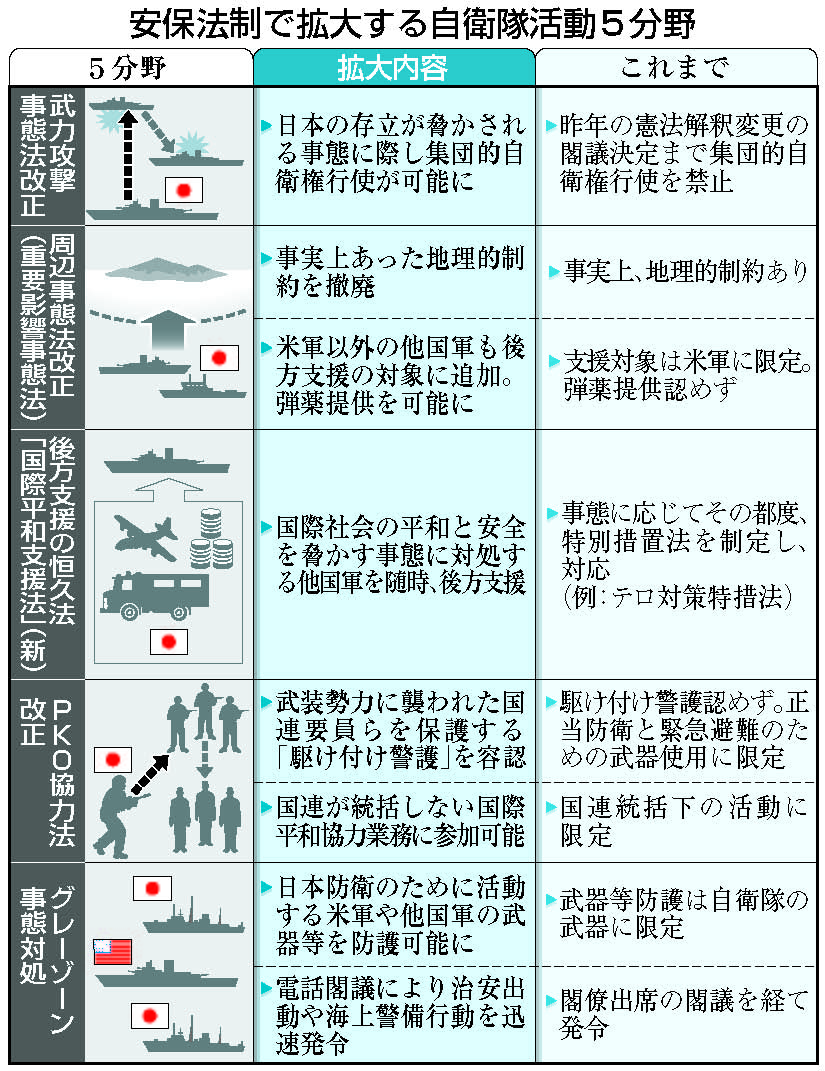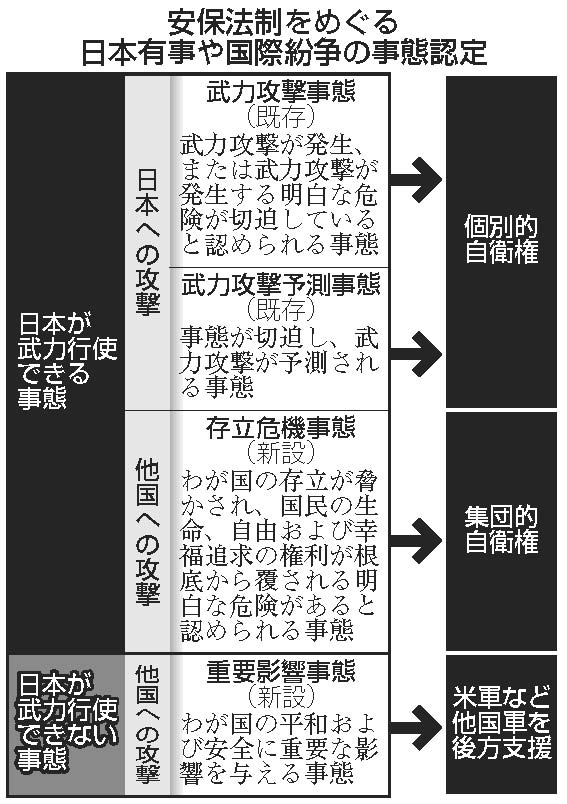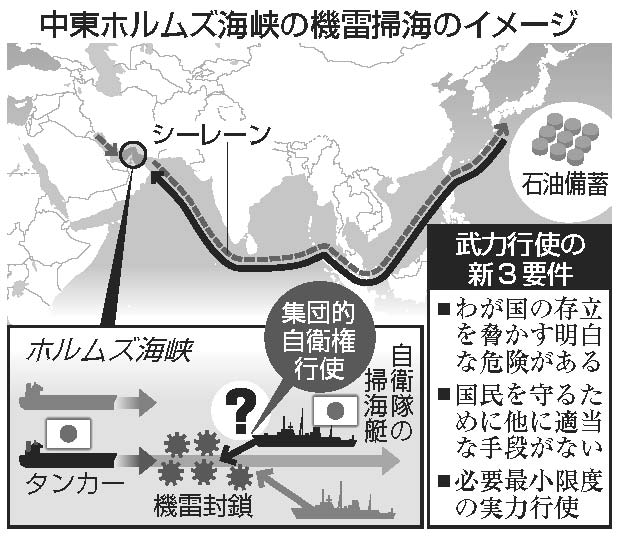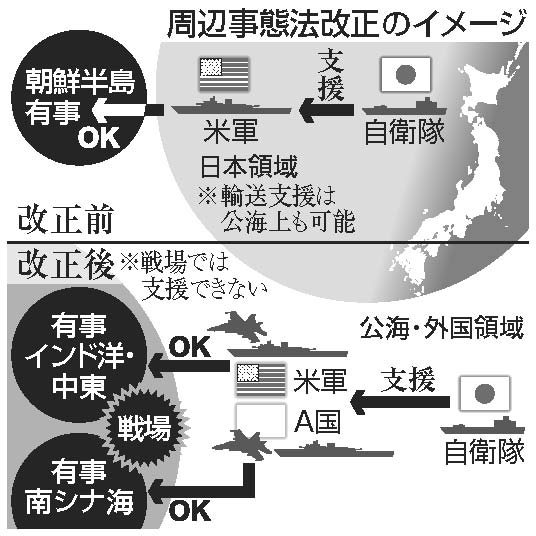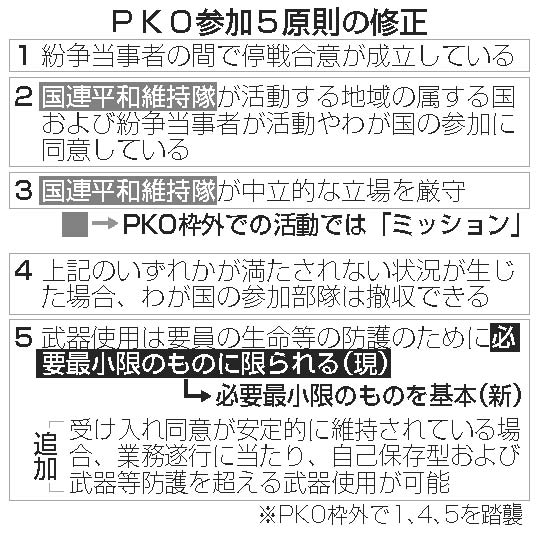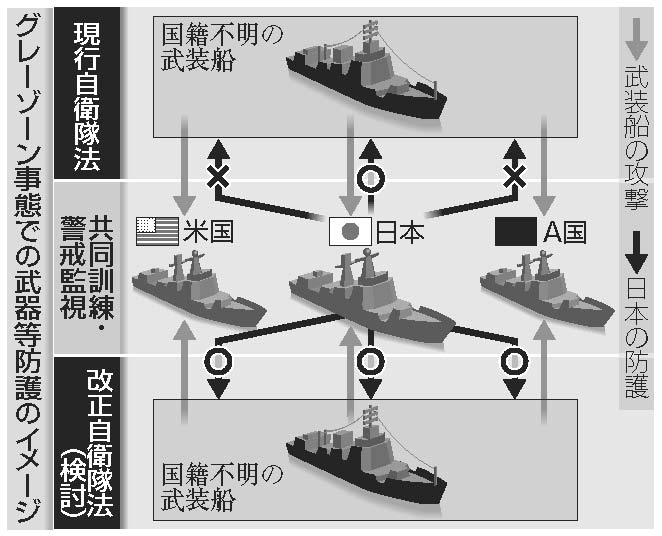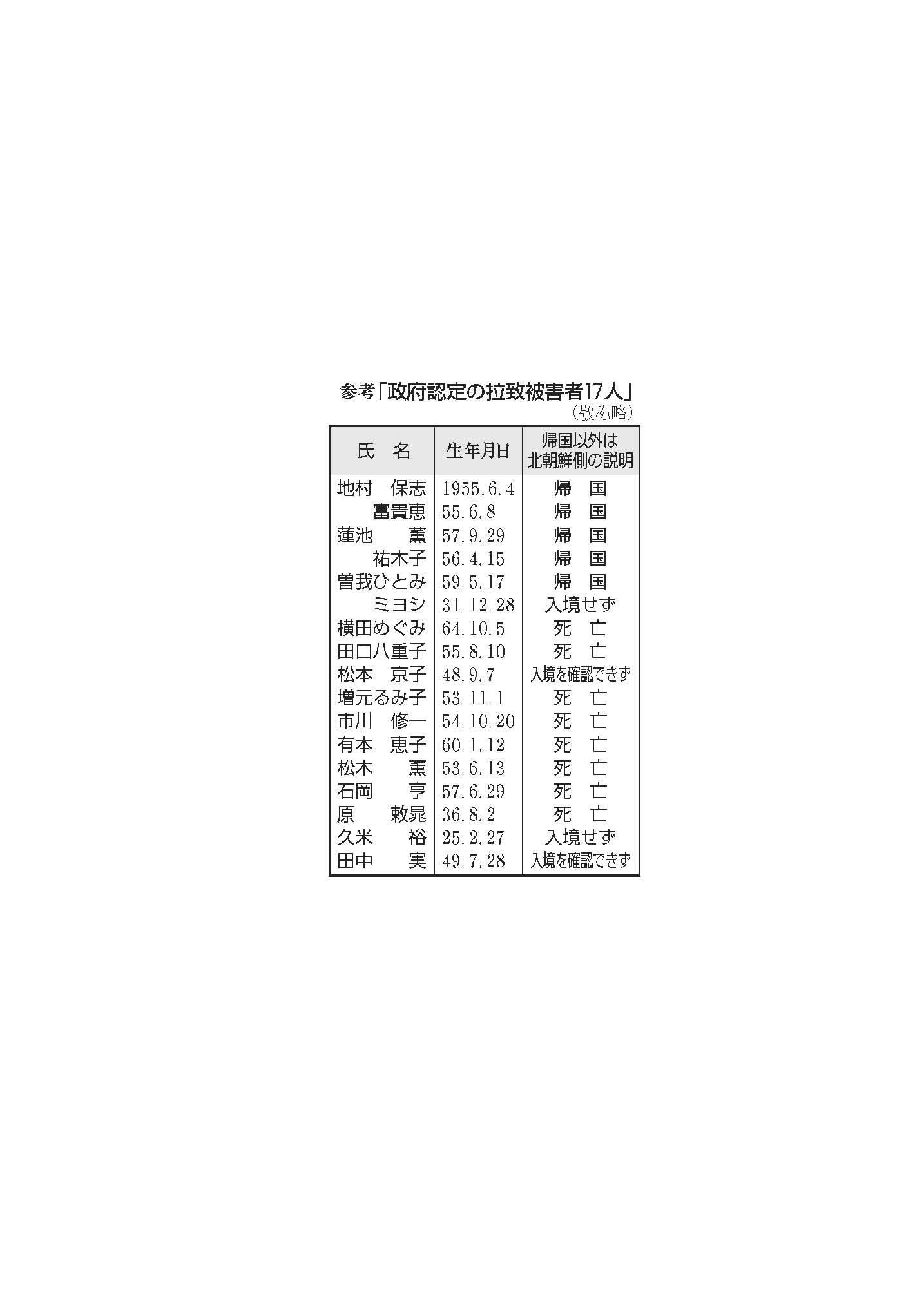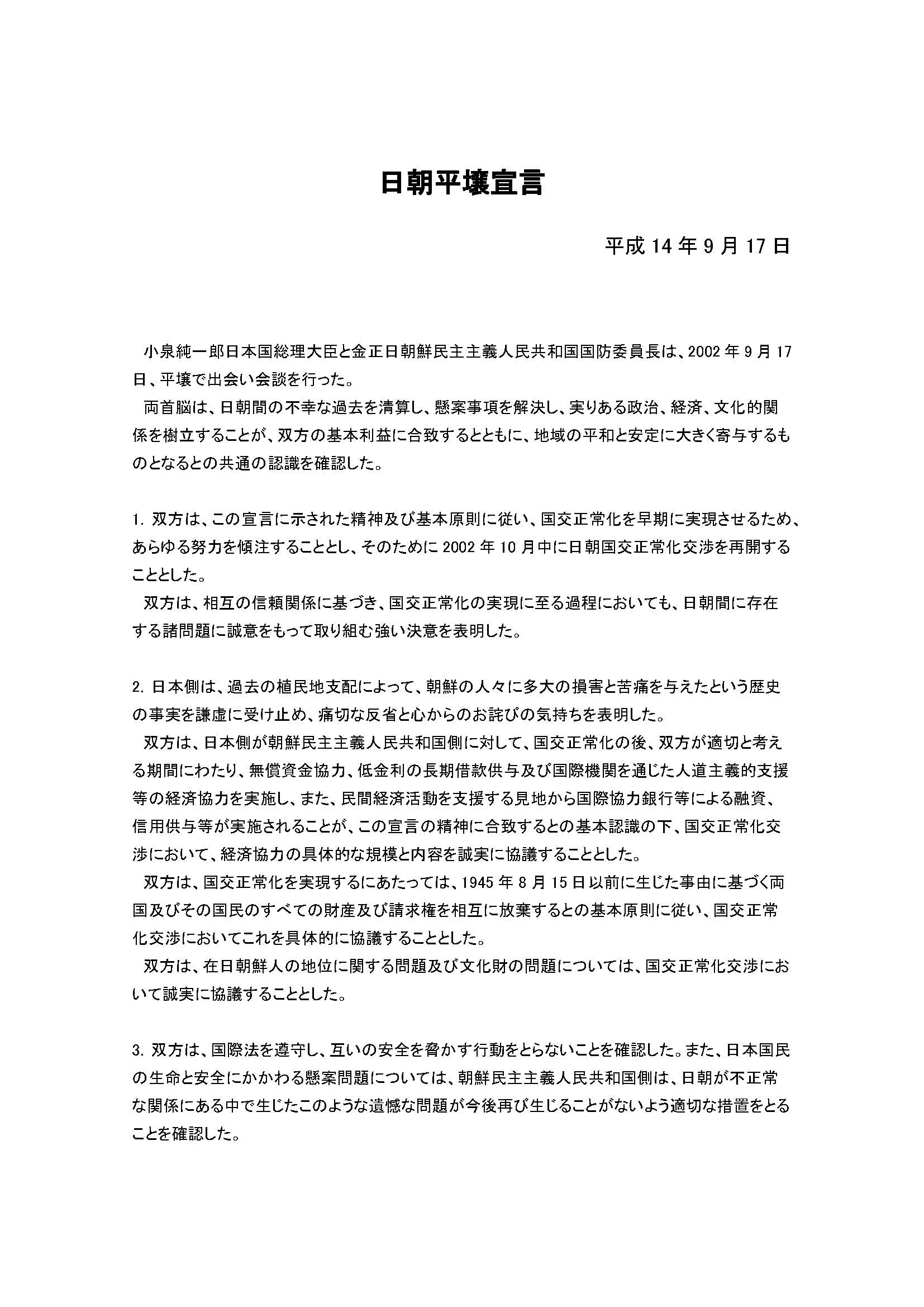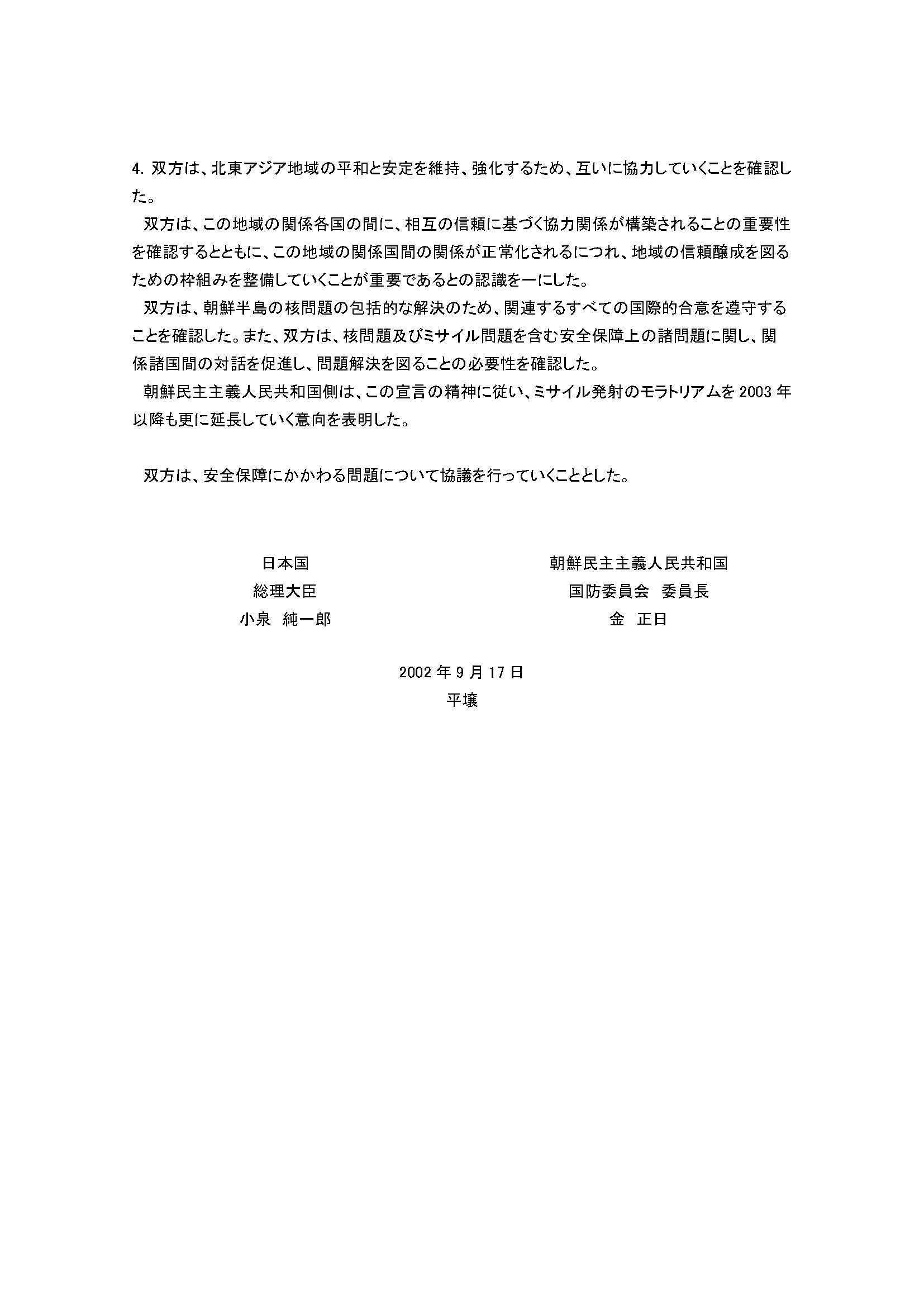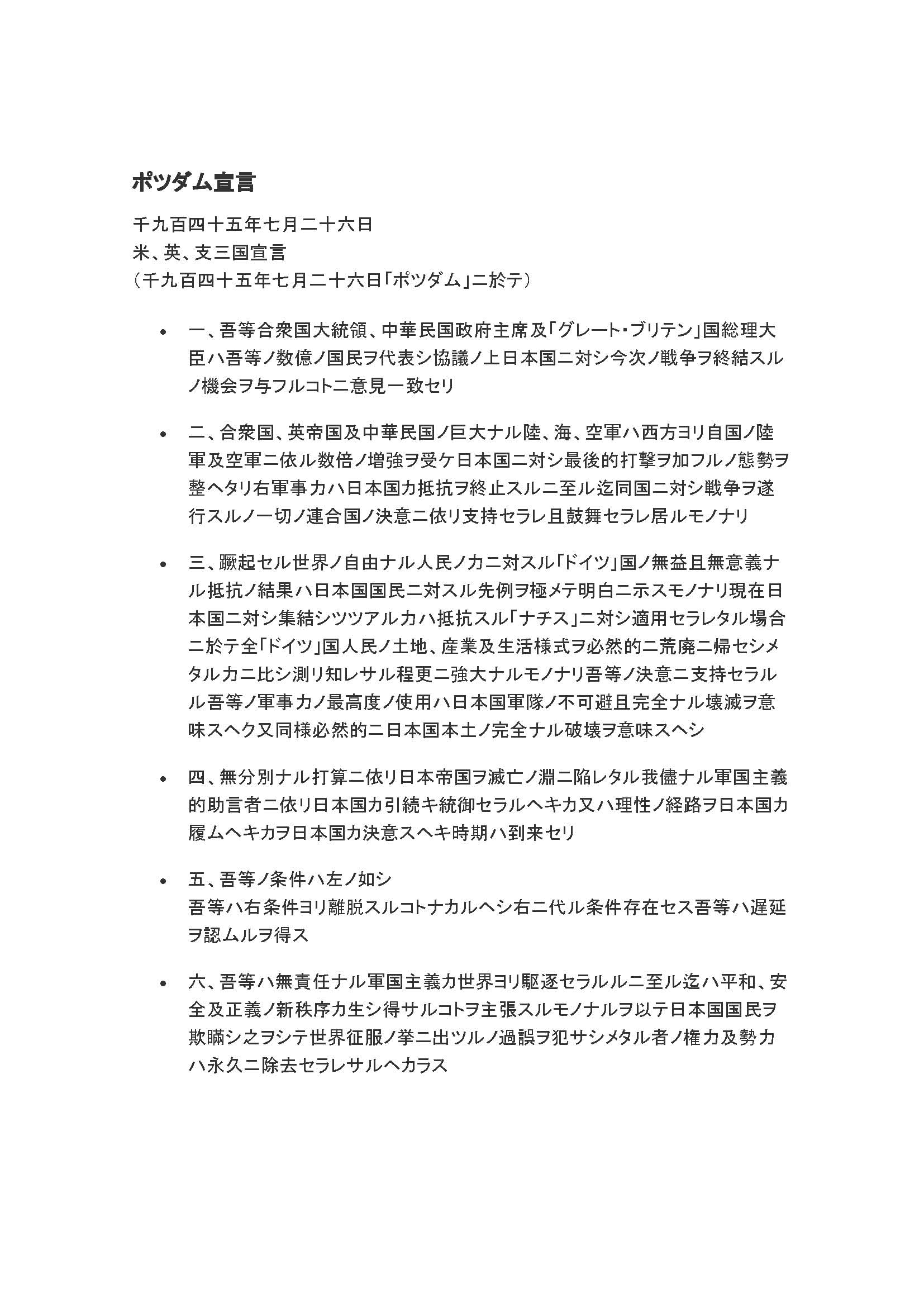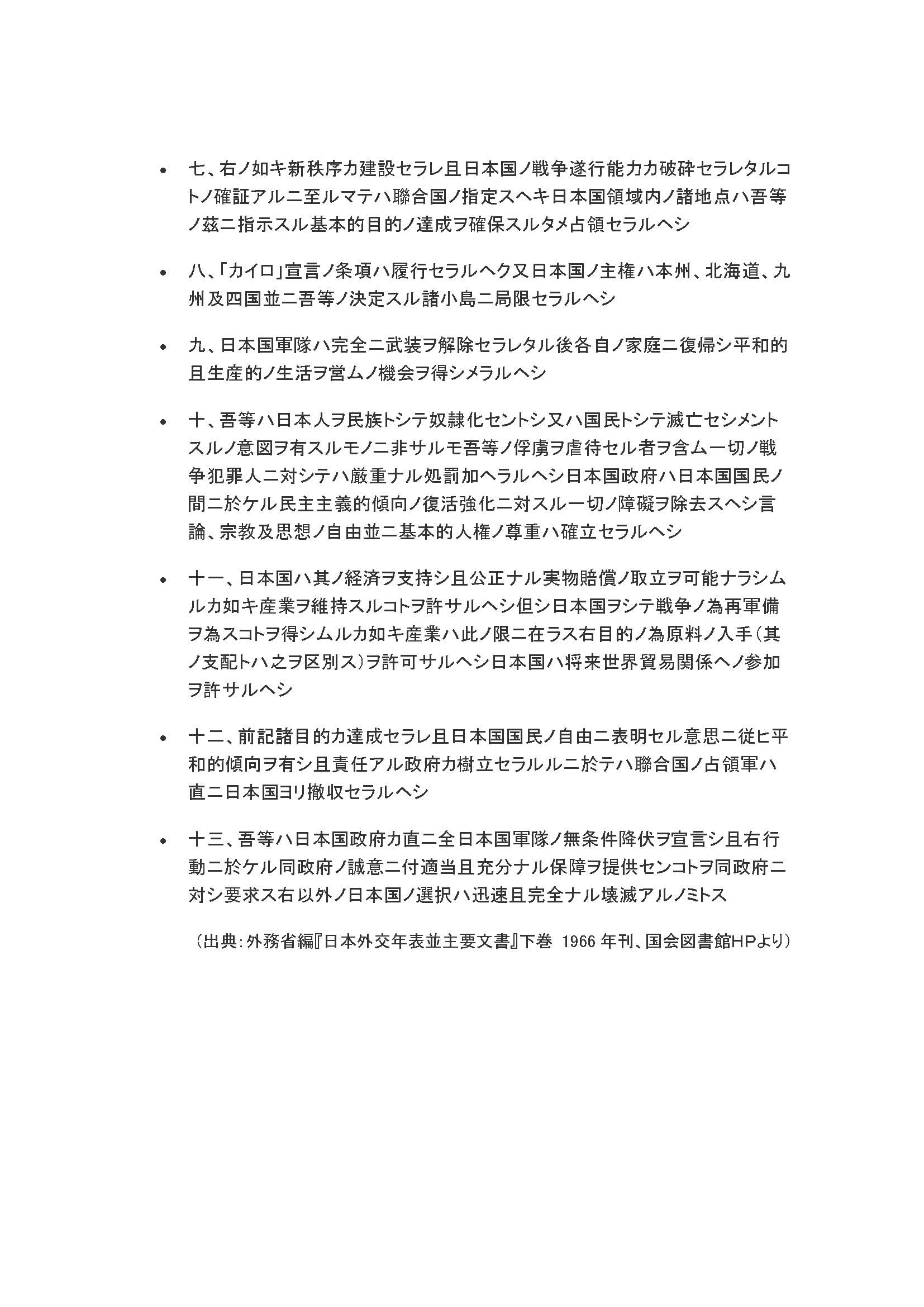巻頭言 (1)
「国のかたち」が変わろうとしている。2012年衆院選で自民、公明両党が政権を奪還し、民主党政権は3年余りで幕を下ろした。再登板した安倍晋三首相は、憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使に道を開いた。自衛隊の海外での活動が大幅に拡大し、安全保障政策は大きく転換することになる。憲法改正への取り組みも本格化させている。
11年3月11日、東日本大震災が発生した。犠牲者は2万人を超え、今も仮設住宅などで不自由な暮らしを強いられている被災者が少なくない。東京電力福島第1原発の事故を受け、「脱原発」などエネルギー政策見直しの必要性が指摘されているが、一方で発電コスト軽減を理由に原発再稼働の動きが進んでいる。
経済情勢も変化した。「デフレ脱却」の掛け声の下、大規模な金融緩和や規制緩和で株価は上昇し始めた。賃金、雇用環境も改善したと政権側は言うが、地方で暮らす人々に景気回復の実感は行きわたっていない。労働法制の改革による格差定着の懸念は残っている。
首相が毎年交代する状態が続いたため、政治の安定が求められていたのは確かだ。長期政権であれば国際社会で日本の発言権が増し、他国との交渉が有利になる場合もある。外交に限らず、内政面でも強い指導力を背景にトップダウンで方針を決定しなくてはならない局面は存在する。
しかし、戦後の日本の歩みが築いてきた国民生活に変革をもたらす政策決定であればあるほど、民意に耳を澄ます必要があるのではないか。国会審議はそのために存在している。与野党とも責任の重さを自覚しなくてはならないし、政治報道に携わるわれわれの使命はこれまで以上に大きくなっている。
「政治ハンドブック」をほぼ4年ぶりに改訂した。政権交代に伴う政治情勢の変化や新たに生じた課題について加筆し、資料を充実させた。サイズを小型化し携帯性を向上させるとともに情報量を増やした。文字がやや小さくなり、ベテランの方々には読みづらいかもしれないが、ご容赦いただきたい。
2020年、東京五輪・パラリンピックが開かれる。世界から集まる人々の目に日本の姿がどう映るか。社会のありようのかなりの部分を政治が方向付けていくだろう。それに対し有権者が審判を下す国政選挙もある。このハンドブックが、日々の政治や選挙報道の一助になれば幸いだ。
2015年5月 政治部長 鈴木博之
第1章 国会 (11)
国会は、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関である。予算の議決、条約締結の承認、首相の指名、憲法改正の発議などの機能を持つ。1947年の総選挙後に開かれた現憲法施行後初の第1回特別国会から、国会の種類に関係なく開かれた順に番号を付けている。開会目的によって次の3種類に分けられる。
(1)通常国会(常会)
憲法と国会法に基づき、毎年1回、1月中に召集される。国会法で会期は150日間となっており、延長は1回だけ可能。来年度予算(総予算)や予算関連法案を審議す
るのが主な目的だ。
(2)臨時国会(臨時会)
緊急を要する法案、条約、災害対策がある場合に召集される。会期は一定でなく、2回まで延長可能。衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば開会しなくてはならない。また、衆院議員の任期満了による総選挙が行われた場合と、参院議員の通常選挙が行われた場合は、それぞれの任期が始まる日から30日以内に召集しなければならな
い。
(3)特別国会(特別会)
衆院解散による総選挙後に召集。召集日に議長、副議長、常任委員長の選挙などいわゆる「院の構成」を決め、首相指名を行う。会期は召集の都度決め、2回延長できる。
国会議員の最終的な意思決定機関。開会には議員の3分の1以上の出席が必要。憲法では出席議員の過半数をもって議決できるが、議員の除名や、衆院と参院で違った議決をした際の衆院での再議決などは3分の2以上、憲法改正の発議は「衆参各院の総議員」(定数)の3分の2以上の賛成が必要だ。
(1)召集、政府演説、代表質問
国会が召集されると、議席の指定や会期を議決(常会を除く)した後、参院本会議場で天皇が出席して開会式を行う。召集日が必ずしも開会式の日とは限らない。国会の召集は天皇の国事行為だが、「内閣の助言と承認」に基づくため、実際は内閣が召集日を決める。通常は官房長官が衆参両院の議院運営委員会(議運委)理事会で召集日を提示、閣議決定する。
主に召集日当日か翌日、衆参両院本会議場で首相が施政方針演説(常会)、所信表明演説(臨時会、特別会)を行う。施政方針演説は国政全般に対する政府の基本姿勢を訴える内容で、内政、外交、経済運営について説明。常会では外相が外交演説、財務相が予算や税制に関する財政演説、経済財政担当相が経済に関する経済演説をする。
所信表明は臨時国会召集の理由などを説明する。補正予算案が提出された場合は財務相が財政演説をする。
これらの演説を受けて通常は1日置いて、各政党が政府演説に対する代表質問を衆参両院で計3日間行う。各会派とも党首、幹事長クラスなどの大物を投入。政府の政治姿勢や重要な政策課題を取り上げて答弁を迫る。
総選挙後の召集日当日は事務総長が議長席に着いて正副議長の選挙を実施する。選挙は無記名で、過半数で決定する。過半数が得られない時は上位2人の決選投票となる。首相の指名は記名方式で投票する。立候補制をとっているわけではないが、実際はどの政党もその党首に投票するのが普通。衆参両院の指名議決が分かれた場合は両院協議会で調整するが、意見が一致しなければ憲法67条2項により衆院の議決が国会の議決となる。選ばれた首相は直ちに組閣を行う。
(2)定例日
本会議の定例日は、衆院が毎週火、木、金、参院は月、水、金。定例日でも開会しないときがある。会期末になると連日開会もある。開会時間は衆院が午後1時、参院は午前10時が定刻だが、その都度議運委で決める。
本会議は議運委で決めた議事日程にのっとって進められるが、事前の日程になくてもその日に委員会の審議が終了した法案を本会議に諮ることができる(緊急上程)。衆院では若手の「議事進行係」が動議提出の発言をして日程に追加される。
国会法や衆参の議院規則に明確な規定はないが、衆院で20人以上、参院で10人以上の会派を慣例上「院内交渉団体」と呼ぶ。衆院では本会議場内のトラブルなどを処理する場内交渉係を出すことができ、参院では国会運営の要である議運委に正式参加できる。
(3)不信任案と問責決議案
内閣不信任決議は衆院のみができる。衆院が内閣不信任決議を可決するか内閣信任決議案を否決した時は、内閣は10日以内に衆院を解散するか総辞職しなければならない(憲法69条)。
現憲法下で内閣不信任決議が可決されたのは①第2次吉田(1948年)②第4次吉田(53年)③第2次大平(80年)④宮沢(93年)―の4例あり、いずれも衆院が解散されている。
参院は問責決議案を提出できるが、法的拘束力はない。2008年、福田康夫首相問責決議が初めて可決。09年に麻生太郎首相、12年に野田佳彦首相、13年に安倍晋三首相の問責決議がそれぞれ可決された。
また閣僚について衆院は不信任案、参院は問責決議案を提出できる。閣僚の任免権は首相にあるため法的拘束力はないが、衆院では1952年に池田勇人通産相への不信任案、参院では98年に額賀福志郎防衛庁長官、2010年に仙谷由人官房長官、馬淵澄夫国土交通相、11年に一川保夫防衛相、山岡賢次消費者行政担当相、12年に田中直紀防衛相、前田武志国土交通相への問責決議がそれぞれ可決された。
(4)代表質問
委員会審議と異なり、再質問なしの「一発勝負」が慣例。ただ持ち時間の範囲内で2回までは再質問できる。
(5)継続審議
会期末までに審議が終わらなかった法案、条約などの議案は廃案となるのが原則だが、閉会中にも審議を続行すると議決した場合は次の国会への継続審議が可能となる。継続にするかは本会議で決める。与野党の調整が必要な法案は複数の国会にまたがることが少なくない。ただし衆院が解散した場合、法案は廃案となる。
(6)国会決議
衆参両院は国民の意思を内外に表明する必要があるとき、決議を行う。第1特別国会以降、2014年の第188特別国会まで衆院で361件、参院で253件を数える。内閣不信任決議などを除き法的な拘束力はないが、国権の最高機関による決議の意味は重く、政府の活動を政治的に拘束することもある。
憲法は69条で「内閣は、衆院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と定めている。また内閣が重要な政策課題などについて国民の信を問うときも解散することができる。解散の日から40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集される。衆院が解散されると参院は閉会となる。ただし内閣は緊急時、参院に緊急集会を求めることができる。
本会議の段取りは、内閣総務官が天皇の御名御璽の入った解散詔書を皇居から衆院まで運ぶ。官房長官が議長席の後ろから「紫のふくさ」に包まれた詔書を持って議場に入る。事務総長を経由して議長に渡され、朗読する。この時、議場内でバンザイが叫ばれることが多い。
(1)委員会の種類
常任委員会は法律上の常設機関。衆参両院それぞれ17ある。委員は総選挙後に召集される国会の会期初めに議長の指名で選任されるが、実際にはあらかじめ各会派から申し出のあった人が指名される。委員会での各会派の勢力分野は本会議とほぼ同じ比率。特別委員会は会期ごとに設置する。国会法は「会期のはじめに議院において選任し、議員の任期中はその任にあるものとする」としているが、各会派とも質問などに応じ「委員の差し替え」を行うことが多く、委員名簿はめまぐるしく変わる。
常任委員長は「常任委員の中から選挙する」(国会法25条)のが基本だが、最近は議運委の理事協議で決定し、議長が指名する形を採っている。
(2)絶対安定多数と安定多数
与党が国会運営を安定的に進めるのに必要な議席数。2015年4月時点で衆院の安定多数は249、絶対安定多数は266。参院の安定多数は129、絶対安定多数は140。議員定数、委員会定数が変われば、それぞれの数字も変わる。集散両院で算定根拠が異なる。
衆院では17ある常任委員会の委員長ポストを独占した上、委員数で野党と同数以上となれば「安定多数」。全ての常任委員長を独占し、委員数で野党を上回れば「絶対安定多数」となる。
参院では「一種委員会」と呼ばれる内閣、総務、文教科学、環境など11の常任委員会の委員長を取り、委員数で野党と同数以上となれば「安定多数」。さらに委員数で野党を上回れば「絶対安定多数」となる。
可否同数の場合、委員長決裁で決められるため、安定多数があれば主導権を握れる。実際は議席数に応じ、野党にも委員長ポストを分け与えるのが慣例。
(3)委員会審議
・提案理由説明
委員会の冒頭、法案の趣旨を説明すること。重要と判断される法案は本会議で行うが、その場合は趣旨説明という。議院運営委員会で判断する。本会議では担当閣僚が説明し質疑する。予算委員会は財務相のほか、副大臣らが補足説明。ほかの委員会では当該閣僚が趣旨説明する。
・質疑
一問一答形式で、担当閣僚や副大臣、政務官が答弁。重要法案は首相も出席して答弁する。
・理事会、理事懇談会
委員会日程や質問者の順序、時間の割り振りなど委員会運営に関しては与野党理事が理事会などで協議する。理事会は公報で通知する公式な協議の場。理事懇談会は公報掲載のない非公式協議の場。
・参考人質疑
法案や案件の当事者、学識経験者に事実認識や専門的見地からの意見を聴取すること。会派が推薦した参考人が意見を陳述、議員と質疑する。参考人質疑を終えると、審議は大詰めに入る。
・討論と採決
委員会採決前に会派(党)を代表した1人が賛否を明らかにするのが討論。発言順は大会派からが慣例。採決は議運委の挙手を除き、通常は起立採決が一般的。参院は挙手の場合もある。修正案が出ていればまず、修正案から採決する。
(4)主な委員会・審査会(憲法審査会は特集1「憲法改正」を参照)
・予算委員会
全委員会の中で最大の花形委員会。定数は衆院50人、参院45人といずれも最大で、衆参両院ともに最も大きい委員室の第1委員室(参院は第1委員会室と呼ぶ)で審議する。予算案(補正予算案を含む)の審議は提案理由説明、基本的質疑、一般的質疑(約3週間)、公聴会、分科会、締めくくり総括質疑(締め総)、討論、採決の順をたどるのが通例。予算は先に衆院に提出される。憲法60条の「衆院議決優位」の規定で(1)参院が衆院と違った議決をした場合で両院協議会の協議でも意見が一致しない(2)参院が衆院から予算案を受け取った日から30日以内に議決しない―場合は、衆院での議決が国会の議決となる。条約でも同様の手続きとなる。最近では2013年度予算案が参院で否決されたため、憲法の規定が適用された。
首相以下、答弁を求められなくても全閣僚が出席する基本的質疑は、与野党各会派が幹事長や政調・政審会長らを質問者に立て、国政全般について政府の見解をただす。各党一巡の間はNHKの中継が入る。基本的質疑が終わると、首相は出席せずに財務相と要求閣僚のみが出席する質疑(一般的質疑)に移る。
公聴会は通常約2日間充てられる。国会法51条で総予算や重要な歳入法案に関しては開催が必要条件。法案に対する賛成、反対両派の公述人がそれぞれ出席して意見を述べ、議員の質疑に答える。公聴会を終えれば、委員会採決に向けた環境は整う。
一般的質疑終了後、より細目にわたった質疑が分科会で行われる。衆院は予算委メンバーが分担、参院は委嘱審査で、常任委員会、特別委員会に審議を「委嘱」する。
締めくくり総括質疑は首相と全閣僚が出席。その後討論・採決に移るが、野党からは「編成替えの動議」(組み替え動議)が出される場合がある。予算を撤回の上、再編成しろとの趣旨で、動議が出ると趣旨説明を聞いた後に予算原案と、編成替えの動議を一括して討論に入る。採決は起立で行われ、審議(審査)は終了。委員長が審議経過、結果を本会議で報告、採決する。
・議院運営委員会(議運委)
本会議の日程を含め国会運営を協議する重要な機能を持つ。委員会の理事の数、委員会の構成、国会法や議院諸規則の改定などについて協議、決定する。国会が召集されると、本会議の議席、会期、施政方針演説の日取りなどを協議する。
・国家基本政策委員会=党首討論
首相と野党党首が外交、経済、社会保障など政策課題について論戦する。申し合わせで、参加できる野党党首は衆参両院のいずれかで10人以上の議員が所属する野党会派。衆参交互に水曜午後3時からとされているが、首相が本会議や予算委に出席した週は原則開かれない。時間延長や開催回数の増加、不祥事をテーマから外して政策論議のみにする―などの見直し論議がある。
・決算行政監視委員会(衆院)、決算委員会、行政監視委員会(参院)
国の各機関が年度内に実施した予算の執行結果である決算を審議する。
・政治倫理審査会
故田中角栄元首相のロッキード事件一審有罪判決を機に1985年、国会法を改正して衆参両院に設置された。疑惑を受けた議員本人の申し出か、委員の3分の1以上の申し立てを受けて協議し、出席者の過半数が賛成した場合に審査する。弁明、質疑は原則として非公開。
2009年7月には、鳩山由紀夫民主党代表の偽装献金問題審査のため、与党の自民、公明両党だけで開催。鳩山氏は出席せず休会となった。審査会委員の申し立てにより審査会が開かれたのは初めて。
note「国会対策委員会」
通称「国対(こくたい)」。国会の機関でなく、各党が設置する国会運営に関する司令塔機関。自民党単独政権下の55年体制時代には「国対政治」といわれ、与野党の癒着の温床と指摘されてきた。国会の表舞台では審議ストップや激しいやじなどで与野党の対決姿勢を見せながら、夜は自民党国対幹部による料亭の会食やマージャンなどの接待を通じて、野党に事前の根回しが図られてきた。
法案などの議案審査、国政に関する調査(事件絡みを含む)について衆参両院は、本会議や委員会で証人喚問や参考人招致ができる。ただし本会議で行った前例はない。
証人の場合、出頭し証言する義務を負う。宣誓し、陳述を求められ、宣誓拒否、虚偽証言、証言拒否などした場合、刑罰の対象となる。ただし自分や近親者が刑事訴追を受ける恐れがある場合などは証言拒否できる。病気などで出頭できない場合は病院などで出張尋問もできる。弁護士を補佐人に付けることもできる。リクルート事件を機に証人喚問のテレビ中継は「静止画像」になっていたが、1998年10月の議院証言法改正で撮影が解禁された。
一方、参考人はあくまで意見聴取されるにすぎず、出頭も発言も任意で、刑事責任を追及されることもない。このため野党が証人喚問を求め、与党が「参考人なら応じる」と主張するパターンも多い。
国会議員の身分は憲法で保障され、強制的に除名できるのは「院内の秩序を乱した」場合に限られるため、政治倫理問題などで辞職を迫る手段として使われる。可決されても強制力はない。2010年12月までに衆参両院で計16人に対して提出されているが、可決されたのは、衆院では、2002年にあっせん収賄容疑で逮捕された鈴木宗男氏、03年に政治資金規正法違反で逮捕された坂井隆憲氏、05年弁護士法違反で逮捕された西村真悟氏の3例。参院は1997年、オレンジ共済詐欺事件で起訴された友部達夫氏。
友部氏は01年、実刑判決が確定して失職するまで自ら辞職はしなかった。鈴木、坂井、西村の3氏も可決後、議員辞職していない。これ以外は議院運営委員会段階で審議未了となるか、撤回されて終わっている。
自民党の一部議員には(1)国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反する(2)可決されても拘束力がなく、院の決議の権威を著しく損なう―など採決への反対論が根強くある。
憲法50条は、会期中の国会議員の不逮捕や、会期前逮捕にも院の要求による会期中釈放を定めている。これは政権による政治的かつ恣意(しい)的な迫害から議員の活動の自由を守るという趣旨であり、会期中に犯罪による刑事訴追を逃れる特権ではない。このため不当逮捕の危険性がないと院が判断し許諾すると、議員は会期中でも逮捕される。この場合、裁判所は犯罪容疑のある議員の逮捕令状を発する前に内閣に要求書を提出。内閣はその写しを添えて院に許諾請求する。これを受けて議運委が審査し、本会議で最終的に議決する。
戦後、逮捕許諾を経て逮捕された議員は、職業訓練会社からヤミ献金を受け取ったとして、政治資金規正法違反に問われた坂井隆憲衆院議員(2003年3月逮捕)まで衆参延べ16人(関谷勝利衆院議員は2回)。日興証券利益供与事件の新井将敬衆院議員の場合は、1998年2月の本会議開会中に自殺が判明。急きょ、議運委理事が議場で協議し、逮捕の許諾請求の緊急上程を取り下げた。
会期中でも国会外の現行犯は逮捕される。(例:05年3月 中西一善衆院議員が強制わいせつで現行犯逮捕)
与党が衆院で過半数を持つ一方、参院で過半数割れしている状態を指す。近年では1989年7月(宇野政権)、98年7月(橋本政権)、2007年7月(第1次安倍政権)、10年7月(菅政権)の参院選で与党が敗れ「ねじれ」となった。12年12月の衆院選で自民、公明両党が政権を奪還(第2次安倍政権)したが、参院では下野した民主党を加えた野党が過半数を占め、13年7月の参院選で自公両党が過半数を確保するまで「ねじれ」は続いた。
衆参両院で多数派が異なるため、政府、与党提出案件の成立が遅れたり、困難になる。予算、条約、首相指名は、憲法で衆院の優越が認められており参院の結論にかかわらず成立する(憲法60、61、67条)が、法案は、参院が否決、修正した場合、成立させるには衆院は再議決し3分の2以上の賛成多数で可決させる必要がある(再可決)。参院が送付から60日以内に議決しない場合も否決したとみなされる規程がある(憲法59条)。
ただ国会同意人事は、衆院の優越規定もなく、衆院の3分の2以上による再可決もできないため、参院の同意が必要だ。
07年夏からのねじれ国会では、自公政権は衆院で3分の2以上の議席を確保していたため、参院で否決された、インド洋での海上自衛隊の給油活動のための新テロ対策特別措置法を08年1月に57年ぶりに再可決で成立させ、揮発油税などの暫定税率を復活させる税制改正法は4月、参院が60日以内に採決しなかったため「みなし否決」を56年ぶりに適用、再可決、成立させた。一方、国会同意人事は07年11月、56年ぶりに労働保険審査会委員など3人の再任を参院が反対多数で不同意。日銀総裁に元財務事務次官の武藤敏郎副総裁を充てる人事案も08年3月に参院が否決。政府は元大蔵事務次官の田波耕治国際協力銀行総裁を起用する人事案を提案したが、これも参院で否決され、戦後初めて日銀総裁が空席となった。結局4月に副総裁に就任した白川方明氏を総裁に昇格させる人事案を参院が4月に同意した。
与党は、こうした困難な国会運営を克服するため新たな連立を組んだり、政策ごとに個々の党と協力する部分連合、部分連合にいかないまでも野党との修正協議を通じて法案成立を図る。
小渕恵三首相は、1999年1月、自由党との自自連立政権を発足させ、10月に公明党も加えた自自公政権を実現させねじれを解消。福田康夫首相は小沢一郎民主党代表と会談し、大連立を模索したが民主党が拒否した。菅直人首相はたちあがれ日本に入閣を要請したが拒否された。
・会派
会派とは国会内で活動をともにしようとする議員の団体で、院内団体とも呼ばれる。政党同士で会派をつくったり、衆院と参院で会派の構成団体が異なる場合もある。議員の離党や死去、党の合併や分割など会派の異動は結構多い。
・会派控室
国会議事堂には、本会議場や委員室(参院は「委員会室」)、衆参両院の事務室のほか、それぞれの会派に応じた「控室」(参院は「会派控室」)がある。一つ一つ広さの違う控室の総面積を会派の議員数に応じて比例配分し、割り当てる。うまく割り切れない場合は一つの部屋を間仕切りすることもある。各会派は本会議前の議員総会や各種会議、打ち合わせに使用するほか、役員室や会議室などに充てる。民主党が大勝した2009年衆院選後、自民党は結党以来使っていた、国会正面に面した衆院2階の幹事長室を民主党に明け渡し、衆参とも大幅な控室の移動が実施された。
・国立国会図書館
1948年設立された日本唯一の国立図書館で、68年、東京・永田町の国会議事堂北側に本館が完成した。所蔵図書には憲政史料、連合国軍総司令部(GHQ)文書などの重要資料も多い。設立の第一目的は国会への奉仕。衆参両院の議院運営委員会の監督下にあり、シンクタンクに当たる調査立法考査局が外国法制などを研究している。支部として2000年5月に東京・上野公園に「国際子ども図書館」が開館。国会議事堂の4階には分館がある。関西館が02年10月、京都府精華町にオープンした。
・歳費等
歳費は国会議員の給与に当たり、ほかに文書交通費などもある。2010年7月の参院選で初当選した参院議員の任期は7月26日から始まるのに、歳費がまるまる1カ月分(約130万円)支給されることに批判が集まり、8月の臨時国会で改正歳費法が成立。歳費のうち任期前の相当額を返納しても、公選法が禁じる寄付行為に当たらないとして一部自主返納を可能にした。12月に歳費を日割り支給にする関連法が成立した。
・質問主意書
国会議員は国政全般について、内閣に書面で事実関係の説明や見解を求めることができる。国会法74条に基づく制度で、主意書は議長の承認を受けて内閣に転送。内閣は原則7日以内に回答しなくてはならず、答弁書の内容は閣議で決定する。1人で提出することができる。
・衆(参)院法制局
国会議員の立法活動を補佐する「議院法制局」として、国会法に基づいて新憲法施行後の1948年に設置された。内閣提出法案の審査を行う内閣法制局とほぼ同規模の定員82人(衆院)、76人(参院)のスタッフを抱える。内閣法制局は、各省庁が作成した法案の合理性を閣議決定前に審査するのが主な役割なのに対し、議院法制局は、議員の「知恵袋」として構想段階から立法作業に参加し、議員が描く法案を条文として具体化していく総合的な役割を果たしている。
・政府参考人
1999年に成立した国会活性化法により、閣僚に代わって官僚が答弁する政府委員制度が廃止され、閣僚ら政治家が答弁することが原則となった。一方、行政に関する技術的な審議を行う際には、官僚が「政府参考人」として答弁することが認められている。人事院総裁、内閣法制局長官らは議長の許可を得た上で「政府特別補佐人」として審議に出席、答弁することができたが、法制局長官は民主党政権が2010年の通常国会から答弁を禁止した。
・中間報告
衆参両院で審議中の法案に関し、本会議で委員長に中間報告を求め、委員会採決を省略して本会議採決に持ち込む手法。国会法では「特に必要があるとき」と規定。与党が法案成立を急ぐため用いることは「議会制民主主義の否定につながる」との批判が強い。2000年の第147通常国会では、自自公の与党3党が提出した、衆院の比例定数を20削減する公選法改正案を、参院では地方行政・警察委員会の委員長が民主党だったため委員会採決を省略して中間報告を求め、本会議で採決した。一方で09年の第171通常国会での臓器移植法改正案は、個人の死生観にかかわる問題として多くの党が党議拘束を外したため、衆参ともに委員会採決を省く中間報告を実施、本会議で採決された。過去に衆院で4回、参院で18回実施している(10年12月現在)。
・追悼演説
国会議員が在職中に死亡すると、本会議で故人をしのぶ演説が行われる。演説者の人選は遺族の希望を尊重するが、衆院は中選挙区制では慣例として同じ選挙区の他党議員が行うことが多かった。小選挙区制導入で、議運委は原則として同じ都道府県や比例ブロックの議員から選ぶことを申し合わせた。
・秘書制度
国会法132条の規定で、国会議員は国が給与を支給する公設の秘書を第1秘書、第2秘書、政策秘書の計3人まで雇える。政策秘書は1994年に議員の政策立案・調査能力を高めるのを目的として新設された。第1、第2秘書には特に資格が必要とされていないが、政策秘書は資格試験に合格するか、公設秘書10年以上などの秘書経験者で研修を受けた場合や司法試験などの合格者、博士号取得者など一定の資格を満たす必要がある。政策秘書は3人の中で最も給与が高く、年収は1千万円前後に上る。
公設秘書以外が私設秘書で、活動や収入の実態などはさまざま。「金庫番」と呼ばれる秘書は私設秘書がほとんど。秘書の仕事は議員の「かばん持ち」から地元事務所での陳情処理や選挙対策、後援会の国会見学の案内まで限りない。
・付帯決議
委員会は法案や予算案などを採決する際に、努力目標や要望事項を盛り込んだ付帯決議を採決することがある。審議の過程で野党側が求めた修正事項のうち法案化されなかった部分について政府に善処を求める内容が多いが、国会法規に定められたものではなく、法的拘束力はない。
・お経読み
本会議や委員会での法案の趣旨説明、提案理由説明をいう。内閣提出法案や予算案など主管の閣僚が読み上げるが、文章の棒読みをじっと聞いていなければならないことが「お経」と呼ぶゆえん。
・押しボタン式投票 ⇔ 牛歩戦術
参院で1960年代初めから検討されていた本会議での採決方式。98年1月の通常国会から導入された。自民党政権時代に野党が用いた、ひたすらゆっくりと半歩ほども動かずに投票に時間をかける「牛歩戦術」への対抗方法。
議員が自席の名札を立てると、光センサーが出席を記録。机のボタンを押すと、30秒足らずで電光掲示板に投票総数や賛成・反対者数が表示され、議員名も記録される。議員別の投票行動は1時間程度で参院記者クラブに提出される。出席議員の5分の1以上の賛成があれば、従来通りの堂々巡りによる採決も可能。10年4月の通常国会で、自民党の若林正俊参院議員が欠席した青木幹雄元官房長官のボタンを押す「身代わり投票」が発覚、若林氏は議員辞職した。
・禁足
本会議がいつ開かれてもいいように国会周辺に議員を待機させること。与野党の議員数が接近すると、重要法案などの本会議採決が議員の欠席で左右されかねない。そのため各党国会対策委員会の幹部が所属議員を足止めする。
・3倍計算
参院が委員会の審議時間を計算する方法。衆院は質問者の持ち時間に答弁者の発言時間も含める(往復方式)のに対し、参院は審議の充実を図る目的で、質問者に与えた持ち時間をすべて質問のための時間としている。答弁には質問時間の2倍かかると想定、審議全体の予定時間を質問時間の3倍として計算する。
・質問取り
閣僚らが質問に的確に国会答弁し議事が円滑に進行するよう、各府省の国会担当の官僚が、質問予定の与野党議員から事前に質問内容を聞き取ること。これを基に事務方が答弁メモを作成して質疑に臨む。丁々発止の活発な審議を阻害する要因ともされる。民主党は政権獲得後、政務官による質問取りを目指したが、人員が足りず断念。従来通り官僚に任せている。
・つるし
野党が重要法案の成立を遅らせるために使う手段。重要法案は国会に提出されると直ちに所管の委員会に付託されるが、本会議で趣旨説明を求められれば、その法案は本会議質疑が終わるまでは委員会に付託されない。本会議での趣旨説明を要求することで法案が「つるしっ放し」になることから名付けられた。国会法56条の2にある「各議院に提出された議案について、議院運営委員会が必要と認めた場合、議院の会議でその議案の趣旨の説明を聴取することができる」との規定を利用した戦術といえる。
・党議拘束
各政党は法案などの採決に当たり、所属議員に党の決定に従うように求める。特に首相指名選挙や重要法案での党議違反は、政権の行方さえ左右しかねないだけに、各党とも除名を含む厳しい処分規定を設けている。
・堂々巡り(記名投票)
重要法案の本会議採決で白(賛成)か青(反対)の氏名入り木札を手にした議員が演壇上で順次投票すること。
・荷崩れ
法案などを先議した院で与野党が激しく対立し、強行採決などを経て衆院、または参院に送った状態を指す。「荷崩れして送られても困る」などと使う。混乱すると、後の院での審議が思うように進まなくなることが多い。
・日切れ法案
ある期日までに成立させなければならない法案。予算関連法案など年度末までに成立しないと行政に支障が生じる法案などをいう。
・法案を上げる
委員会で法案を採決すること。
・与理懇(よりこん)と野理懇(やりこん)
それぞれの委員会で与党の理事だけが集まって行う非公式な理事懇。野党の理事だけで行うと野理懇。与野党の筆頭理事同士での懇談前後などに開かれ、与党内、野党内での意見などを調整する。
第2章 官邸 (9)
首相官邸は政治、行政、外交、危機管理の中枢機能を担う。
(1)首相
行政の最高責任者であり、自衛隊の最高指揮監督権を持つ。憲法66条1項で内閣の「首長」と位置付けられている。67条に基づき「国権の最高機関」である国会の議決によって指名される。68条に基づき、閣僚の任命権、罷免権を持つ。
内閣法は、内閣総理大臣が閣議を主宰し、閣議で決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督すると規定。国会に対しては内閣を代表して法案や予算案を提出、一般国務案件、外交案件について報告する。
阪神大震災対応などで首相の指導力が発揮しにくかった反省から、2001年の中央省庁再編とともに、首相が閣議で「内閣の重要政策に関する基本的な方針」等を発議できると内閣法に明記するなど、内閣機能強化も図られた。
内閣改造、衆院解散は、首相の「専権事項」とされる。実際はその時々の政治情勢に左右され、改造、解散を希望しながら果たせなかったこともある。14年には、安倍晋三首相が消費税率10%への引き上げを1年半延期する方針について国民の判断を仰ぐとして解散した。
原稿は特別な例を除き「内閣総理大臣」「総理」を使わず、「首相」とする。
(2)首相臨時代理、副総理
首相が事故や病気、外国訪問で不在となる場合、首相臨時代理が置かれる。内閣法9条は「首相に事故のあるとき、または首相が欠けたときは、あらかじめ指定する閣僚が、臨時に首相の職務を行う」と規定している。「首相に事故のあるとき、または首相が欠けたとき」を誰が判断するのかについて、内閣総務官室は「明文の規定はなく、首相自らが判断する場合もあるし、病気などの場合は医師の診断、災害の場合は連絡ができるかどうかなどを参考にして、指定されている閣僚が他の閣僚と協議することになる。必ずしも閣議は必要ない」と説明している。
2000年4月に小渕恵三首相が脳梗塞で倒れた際、青木幹雄官房長官による首相臨時代理指定の手続きが明確さを欠いたとして国会等で問題視され、小渕首相の後の森喜朗首相以降は組閣するたびに首相が臨時代理予定者順位1〜5位の5閣僚を指名している。国政全般で首相を補佐する官房長官が1位になるのが通例だが、第2次、第3次安倍内閣では麻生太郎副総理兼財務相を1位、菅義偉官房長官を2位とした。
「副総理」は法令上の名称ではない。閣僚で首相に次ぐ実力者を名実ともに「政権ナンバー2」として処遇するため、首相が指名する。連立内閣では連立の象徴的意味合いで他党の党首を指名するケースもある。
民主党の鳩山由紀夫政権では菅直人国家戦略担当相(後に財務相)が就き、退陣を受けて後継首相に就任した。過去には宮沢内閣の渡辺美智雄副総理兼外相、細川連立内閣の羽田孜副総理兼外相、村山連立内閣の河野洋平副総理兼外相、橋本龍太郎副総理兼通産相などがある。
(3)官房長官
首相の政策遂行を補佐する内閣官房を統括すると同時に、首相の補佐や、国政の重要課題に関する閣内、与党との調整役、国会に対する窓口として政権運営の要となる。国民に対する内閣のスポークスマンを兼ね、平日の午前と午後の計2回、内閣記者会との定例会見を行う。官房長官には国務大臣を充てると規定されている。与党内で政権への不満が高まると、党首である首相を名指しで批判しにくいため「官房長官の調整能力が不足している」と批判が集中するケースもある。
(4)官房副長官
政務2人と事務1人の計3人。政務の副長官は衆参両院の国会議員から1人ずつ選ばれ、衆参両院や政党と官邸の間の連絡調整など、国会対策に当たる。官房長官の不在時には記者会見も行う。事務の副長官は官僚機構の頂点であり、省庁ににらみを利かすとともに省庁間にまたがる政策課題の調整役となる。旧内務省の流れをくむ省庁(旧厚生省、旧自治省など)の事務次官経験者が就くことが多い。
(5)首相秘書官
政務秘書官1人と財務、外務、経済産業、警察など各省庁が派遣する事務秘書官4〜6人から構成される。菅直人内閣で防衛省から初めて起用され、第2次安倍内閣では女性初の首相秘書官が誕生した。政務秘書官は党の日程や政治家との会合など首相のプライベートな日程も含めて管理し、首相の事務所から起用されるケースが多いが、まれに省庁出身者からも起用される。事務秘書官は各省庁から入省25年前後の参事官、筆頭課長クラスが起用され、将来の事務次官候補と見込まれるエース級が投入される。省庁との連絡や首相のあいさつ文、国会答弁書の作成、日程調整などに当たる。
(6)首相補佐官
首相官邸の機能を強化するため、1996年成立の改正内閣法で導入された。定数は最大5人。「首相の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策など首相の行う企画、立案について補佐する」と規定されている。首相が指名し、閣議決定により任命するが、権限が不明確との指摘もある。第2次、3次安倍内閣では、衆参両議員から3人、官僚出身者から2人の計5人が任命され、安全保障や復興、地方創生などの職務を担当した。
(7)内閣官房参与
経済や金融政策、少子化対策や震災復興など様々な分野で専門的な知見を持つ識者を首相が直接任命する。非常勤の国家公務員で人数の制限はなく、首相の諮問に対して意見を述べるブレーン的な存在。第2次、第3次安倍内閣では、浜田宏一・米エール大名誉教授や本田悦朗・静岡県立大教授ら「アベノミクス」を理論的に支える学者が多く任命された。
(8)首相官邸
約73年ぶりに建て替えられ、2002年4月から使用が開始された。地下1階、地上5階建てで、延べ床面積で旧官邸(現在の首相公邸)の約2・5倍の広さがある。正面玄関は3階にあり、5階に首相や官房長官の執務室、4階に閣議室や大会議室がある。1階は記者会見場や内閣記者会(記者クラブ)などの広報フロア、地下には危機管理センターが置かれる。記者団は会議の冒頭撮影などの場合を除き、原則として4、5階への立ち入りが禁止され、旧官邸に比べ格段に厳しい取材規制が行われるようになった。
(9)内閣官房と内閣府
いずれも「重要政策の企画立案・総合調整」の機能があり、内閣官房長官が事務を統括する。内閣官房は、首相と内閣を直接補佐する機関で、政治家や官僚が「官邸で検討する」「新組織を官邸につくる」などと言うときの「官邸」は内閣官房を意味することが多い。内閣府は2001年の中央省庁再編で、官邸機能強化の目玉として総理府、経済企画庁、沖縄開発庁などを統合して新設された。法律上は他省庁より一段高い位置付けとなっており、経済財政運営など首相が直接指揮を執るべき政策、消費者保護や沖縄振興といった省庁を横断するテーマを所管する。
参事官クラスが内閣官房と内閣府のポストを併任するケースもあるなど、人事・組織面で密接に関係している。政治家のブリーフなどで内閣官房と内閣府を混同した説明が散見されるので注意が必要だ。
・内閣官房
事務方として、次官級の官房副長官補(3人)、内閣危機管理監、内閣情報官、内閣広報官、内閣総務官が置かれている。
3副長官補は財務省出身者が内政、外務省出身者が外交、防衛省出身者が安全保障・危機管理を担当する。副長官補室には各府省から計100人以上の官僚が出向し、3人の副長官補を補佐している。
内閣危機管理監は、大規模自然災害やテロなどの安全保障関連の事件・事故などが発生した場合、直ちに官邸内の危機管理センターに官邸連絡室や官邸対策室を立ち上げ、対応に当たる。阪神大震災での対応の遅れを教訓に整備されたもので、危機管理センターは24時間態勢で突発の事件、事故に備えている。ヘリコプターからの映像を映すモニター設備や、さまざまな通信設備がそろい、首相がセンターで現地の情勢を把握することもある。
内閣情報調査室は公安情報をはじめ、内閣が必要とする情報収集が任務。活動の内容はうかがい知れない部分も多い。
内閣広報室は、国民に向けた内閣の広報、マスコミ対応が中心。官房長官が毎日の記者会見を行っているため、広報官は米国のような記者会見は通常行わない。首相官邸ホームページやソーシャルメディアを用いた、海外向けの情報発信も行う。海外メディアによる首相インタビューの対応など、海外メディアとの調整役も担っている。
内閣総務官室は、官邸の事務を取り仕切る。閣議の準備をはじめ内閣改造、総辞職など内閣に関する事務を一手に引き受ける。内閣総務官は官房副長官(事務)の手足となって、省庁との調整に当たる。内閣官房報償費(機密費)の執行管理も担当する。
・内閣府
内閣府設置法で「沖縄北方」「金融」「消費者・食品安全」の3分野で特命担当相を置く。それ以外でも特命担当相を置くことができる。
副大臣と政務官は内閣府設置法で各3人と定められているが、3人以外にも他省の副大臣を兼務させることもできる。旧省庁の「寄せ集め」的な性格が残り、人事でも地域主権に関する部局には総務省、科学技術は文部科学省といった関係省庁からの出向が多く見られる。いずれも2年程度で戻るため、官僚は「本籍地」である省庁の意向を受けた政策を推進すると指摘される。
・note「建制順」
官僚取材で時々出てくる言葉。各役所を並べて表記する際の順番となる。中央省庁の体制を定める国家行政組織法の別表が根拠。他省庁より一段高い存在とされる内閣府は、別に内閣府設置法があるため、別表には記載されていない。順番は以下の通り。
①内閣府②復興庁③総務省④法務省⑤外務省⑥財務省⑦文部科学省⑧厚生労働省⑨農林水産省⑩経済産業省⑪国土交通省⑫環境省⑬防衛省
(10)閣議
合議体である内閣の機関意思を決定する場であり、主宰者は首相。閣議にかけられた案件は、全閣僚が出席した上で、全会一致で決めるのが原則だ。閣議は秘密会で、首相や閣僚の発言については、官房長官が閣議後の記者会見で説明、各閣僚もそれぞれ記者会見する。しかし、すべてを紹介しているわけではなく、閣議の席でオフレコがかかる部分も多い。
・開催場所、曜日
定例閣議は原則として毎週2回、火曜日と金曜日の午前に開かれる。開催場所は、慣例的に国会開会中は国会内の大臣室、閉会中は官邸の閣議室となっている。ただ、2012年12月に発足した第2次安倍内閣においては、国会開会中もほとんどの閣議を官邸で実施。14年12月発足の第3次安倍内閣でも官邸で実施している。閣議の時間は案件の多さによって異なる。
定例閣議以外に、早急に政府方針を決定する場合に開かれるのが臨時閣議。内閣総辞職や首相の施政方針演説を決定する際などに開かれる。
また閣僚を集めず、出先にいる閣僚からサインだけもらう「持ち回り閣議」の形式もある。ただ、持ち回り閣議は、各閣僚の同意が間違いなく得られることが前提となる。
・閣議の流れ
進行は官房長官が仕切り役となる。内閣法制局長官も陪席しており、法令の説明などを受け持つ。閣議決定が必要な案件について説明後、閣僚は異論がなければ閣議書にサインする。サインは、各閣僚の筆跡であることを証明できるように花押が用いられる。全員分の花押がそろった時点で、案件は閣議決定したとみなされる。
(11)閣僚懇談会
閣議後、必要に応じて閣僚懇談会へと移る。閣僚懇で出された閣僚の意見は、その後の政策などに反映されるケースが多い。このため閣議後会見では、閣議や閣僚懇で誰が
何を言ったのかを聞き出すことが基本的な作業。記事化する際は「○日の閣議で」「○日の閣僚懇で」などと書くので、記者会見で閣僚発言の紹介があれば、閣議と閣僚懇のどちらかを確認する必要がある。ただ、閣僚懇は閣議と同じ場所で行われ、どの時点で閣議が終わり、閣僚懇に切り替わったのか外部からは分からない。そのため首相動静は便宜上、閣僚懇が終わった時点をもって「閣議終了」と案内している。
(12)議事録
政府は2014年4月から、首相官邸のホームページで閣議と閣僚懇談会の議事録を公開している。1885年の閣議初開催以来、公式の議事録が作られるのは初めてで、
閣議から約3週間後に官邸ホームページに掲載している。政策決定のプロセスに透明性を持たせるのが目的だが、議事録は、事前に政府内で調整した形式的な発言に終始する場合が多く、閣議の形骸化も指摘されている。
(13)閣議決定、閣議了解
いずれも全閣僚が署名し、内閣として決定する手続き。「閣議決定」は合議体である内閣が政府全体の意思を決定するもの。内閣はそれを遂行する責任が生じ、ほかの手続きとは根本的に異なる重みがある。「閣議了解」は本来は主務大臣の権限で決定できる事業や人事について、国政全体への影響が予想されるため、ほかの閣僚の同意を得て内
閣として方針を確認する。閣議決定より軽い。
なお、閣議了解、閣議報告のいずれも法律で定められた行為ではないので、事細かく段取りが決められているわけではない。
このほか「閣議報告」という、関係閣僚が審議会の答申や白書などについて「これだけは伝えておきたい」という場合に取られる手続きも存在する。要は意思の確認というよりも、「○○の件につき、各閣僚の御理解をいただきたい」などと発言すること。記事では「○○を報告し、了承された」と表現する場合も多く、「閣議了承」という便宜的な用語も使われている。武装漁民による離島の不法占拠などへの「グレーゾーン事態」への対処で、自衛隊の出動手続きを迅速化するため、電話で閣僚の了解を取り付ける閣議決定も安保法制整備の一環として導入される。
(14)首相発言
首相が国政の重要事項に関して閣議で発言する内容。「閣議決定」や「閣議了解」と違い閣僚の署名は必要ないが、官房長官が記者会見で、この発言を発表すれば「事実上の政府方針」としての重みを持つとされる。2010年5月には、米軍普天間飛行場の県内移設を明記した日米共同声明を受けた政府方針について、閣僚である福島瑞穂社民党党首が閣議決定や閣議了解への署名拒否を事前に明言したため、閣内の決定的な対立を避けようと「首相発言」での決着が一時、検討された。
(15)「首相談話」と「首相の談話」
「首相談話」は、国政の重要事項について政府が閣議決定して発表する公式見解。自衛隊イラク派遣や憲法施行60年などのほか、内閣の発足や改造、総辞職といった節目でも発表される。1995年に村山富市首相が戦後50年に当たって発表した「村山談話」は、歴史認識問題をめぐりしばしば引用される。日韓併合100年となる2010年8月に菅直人首相は痛烈な反省とおわびを表明した首相談話を発表、歴史認識は村山談話を踏襲した。
「首相の談話」は外国への祝意などを伝えるため、首相の決裁だけで発出される内外へのメッセージ。閣議決定は不要。
【国家安全保障会議(NSC)】
2012年12月、安倍晋三首相は就任記者会見で国家安全保障会議(NSC)の創設を含む外交・安全保障体制の強化に取り組む方針を表明した。13年1月の邦人10人が犠牲者になったアルジェリアでの人質事件を機に、政府はNSC創設に向けた手続きを加速。有識者会合を13年2月以来、計6回開き所掌事務や目的、組織の在り方などを検討し、NSC創設関連法案を国会に提出した。関連法は13年11月27日に成立し、同12月4日の施行と同時にNSCが発足した。
NSCの議長は首相が務める。14年1月7日にはNSCの事務局機能を担う国家安全保障局(NSS)が内閣官房に設置され、首相の外交ブレーンである谷内正太郎元外務事務次官が初代局長に起用された。
局次長は2人で、外務、防衛両省出身の官房副長官補が務める。自衛官を含む両省出身の職員らが派遣されている。
NSCは法律上「わが国の安全保障に関する重要事項を審議する機関」と位置付けられている。①4大臣会合(首相、官房長官、外相、防衛相)②9大臣会合(首相、副総理兼財務相、官房長官、総務相、外相、経済産業相、国土交通相、防衛相、国家公安委員長)③緊急事態大臣会合(首相、官房長官、事案に応じて必要な関係閣僚)―の形態で開かれる。その中で司令塔役を果たすのが定期的に開かれる4大臣会合で、外交・安保政策の基本的方向性を審議し、決めている。
NSCは創設直後の13年12月、初の外交・安保政策の包括的指針となる「国家安全保障戦略」と今後10年程度の防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」を決定した。その後は「ウクライナ情勢」「アジア情勢」「日米安保協力」「北朝鮮による弾道ミサイル発射」「特定秘密保護法」など外交・安保政策を議題に月1〜7回開催された。15年1月に表面化した過激派組織「イスラム国」による邦人人質事件でも、4大臣会合を2回開催し、対応を協議した。
【サイバーセキュリティ戦略本部と内閣サイバーセキュリティセンター】
被害が深刻化するサイバー攻撃に対し、国や自治体が安全対策を講じる責務を持つと定めた「サイバーセキュリティ基本法」が2014年11月に成立した。
これを受け15年1月、官房長官が本部長を務め、情報通信技術(IT)担当相、国家公安委員長、総務相、外相、経済産業相、防衛相と有識者で構成する閣僚会議「サイバーセキュリティ戦略本部」が発足。同時に内閣官房組織令に基づき、事務局機能を担う「内閣サイバーセキュリティセンター」が内閣官房に設置された。初代センター長は国家安全保障局次長も兼務する高見沢将林官房副長官補が就任した。
安倍晋三首相は15年2月10日の戦略本部初会合に出席し、20年東京五輪・パラリンピックの成功にはサイバーテロ対策が不可欠だとして、長期的取り組みの必要性を指摘した。
政府が初めて置いたサイバー対策部署は、00年2月の「情報セキュリティ対策推進室」。05年4月に機能を強化した「内閣官房情報セキュリティセンター」が発足し、同時期に政府のIT戦略本部の下に設けられた閣僚会議「情報セキュリティ政策会議」の事務局機能も担った。
サイバー基本法成立を受け、政策会議がサイバー戦略本部に格上げされて法律に基づく権限が付与されたのに伴い、事務局機能を果たす機関も情報セキュリティセンターからサイバーセキュリティセンターに改組され人員も増強された。
【拉致問題対策本部】
北朝鮮による日本人拉致問題解決をライフワークに掲げる安倍晋三首相の意向を受け、政府は2013年1月25日、全閣僚をメンバーにした「拉致問題対策本部」の設置を閣議決定した。政権交代前の民主党政権時代の同名本部のメンバーは首相、外相、官房長官、拉致問題担当相のみで、安倍首相は政府一丸で取り組む姿勢をアピールした。「拉致問題対策本部事務局」も併設し、専任の事務局長を置いた。
対策本部は、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの大方針を堅持。第1次安倍内閣と同様、北朝鮮に①全拉致被害者の安全確保と即時帰国②拉致に関する真相究明③実行犯の身柄引き渡し―を求めている。
【経済財政諮問会議と日本経済再生本部】
「経済財政諮問会議」は首相の諮問に応じ、経済全般の運営や財政運営、予算編成の基本方針など経済財政の重要事項を審議する。有識者の識見を活用し、首相のリーダーシップを十分に発揮することを目的に、2001年の中央省庁再編を機に内閣府に設置された。首相が議長を務め、官房長官、経済財政担当相、総務相、財務相、経済産業相、日銀総裁と民間の有識者で構成する。自民党政権で活用されたが、09年9月の政権交代で一時休眠状態となった。12年12月の衆院選で自民、公明両党が政権に返り咲くと、安倍晋三首相が復活させた。
「日本経済再生本部」は、12年12月の衆院選で自民党が政権公約に掲げ、政権奪還後に新設した。政府の成長戦略を実現するための司令塔となる。首相が本部長を務め、全閣僚で構成する。
「経済財政諮問会議」も日本経済再生本部と連携し、経済財政運営全般に関する司令塔役を担う。安倍首相は再生本部と諮問会議を自身の経済政策「アベノミクス」を実現する車の両輪と位置づける。政権の至上命題であるデフレ脱却に向けた戦略立案を託している。
内閣総辞職から新政権樹立にかけての華々しい政治ドラマは、きめ細かな段取りに従って進められている。首相指名選挙(注:「首班指名」は原稿表記上使わない)で「次期首相」に誰が選ばれようとも、宮中での任命式(注:「親任式」も原稿上使わない)など所定の手続きを経なければ「首相」は誕生しないし、内閣も発足しない。手続きの概略は次の通り。
(1)内閣総辞職
・閣議
内閣総辞職は定例閣議か臨時閣議で決まる。首相が総辞職の意向を表明。A4判数枚程度の首相談話を配布する。読み上げた上で、辞めるに当たっての心境を自分の言葉で表現する場合が多い。全閣僚が閣議書に花押を書けば閣議決定し、総辞職は成立する。内閣改造では、首相が辞職するわけではなく、首相が閣議で辞表を取りまとめるが、内閣総辞職の場合は首相と全閣僚の署名による閣議決定となる。改造の場合、閣僚として留任の場合、辞表は返還する。
・任命式までは「職務執行内閣」
閣議で内閣総辞職を決定しても、次期首相が天皇の親任を受けるまでは、前の内閣が職務を執行する。憲法71条が、総辞職した内閣でも「あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ」としているためだ。ただ通例では、総辞職から間を置かずに新内閣が発足し、前内閣による職務代行は数時間程度で済む。そのため、共同の基準では、首相指名された時点をもって「首相」と呼称することに統一している。
2010年6月の鳩山内閣退陣に伴う菅内閣発足では、4日午前の閣議で鳩山内閣が総辞職を決定し、同日午後には衆参両院本会議が菅直人氏を首相に選出した。だが任命式と組閣は8日にずれ込んだため、鳩山内閣が5日間にわたり「職務執行内閣」として執務した。このケースでは4日の首相指名から8日の任命式まで、菅直人氏の呼称は「新首相」、鳩山由紀夫氏は「首相」とし、鳩山内閣の閣僚も従来の役職名を使用した。
(2)組閣
憲法68条は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」としており、閣僚人事は首相の権力の源泉だ。それだけに、組閣をめぐる手順には首相の意思や政権を取り巻く政治状況が強く反映される。
2012年、安倍晋三氏は民主党の野田佳彦氏に代わり、第96代首相に就任した。自民、公明両党による連立政権は、09年衆院選で民主党に敗れて以来、約3年3カ月ぶり。安倍氏は06年の首相就任後、体調不良を理由に約1年で退陣しており、首相を一度辞任したのちに再登板するのは故吉田茂元首相以来64年ぶりで、戦後2人目となる。
【第2次安倍内閣(2012年12月26日発足)】
・官邸入り〜名簿発表
国会で首相指名を受け、本会議場を出た安倍晋三新首相は、国会内の民主党控室を訪れて海江田万里同党代表にあいさつした。安倍氏は官邸に入ったあと、公明党の山口那
津男代表と与党党首会談を開き、引き続いてその場を「組閣本部」とした。官房長官に就任した菅義偉氏が第2次安倍内閣の閣僚メンバーを発表。新閣僚は1人ずつ官邸に呼
び込まれ、閣僚ポストの提示を受けた。その後、安倍氏と閣僚は皇居での首相任命式、閣僚認証式に出席。安倍氏は官邸で就任後初の記者会見を開いた。
・初閣議
安倍新首相は第2次安倍内閣発足後初めての閣議に臨み、12年度補正予算の編成を指示した。経済、金融運営の司令塔として「日本経済再生本部」の新設も決定。民主党政権が設置した行政刷新会議、国家戦略会議、行政改革実行本部の廃止も決めた。内閣の基本方針では、①大胆な金融政策②機動的な財政政策③民間投資を喚起する成長戦略―を「三本の矢」として、日本経済の立て直しを目指すことを打ち出した。
【第2次安倍改造内閣(2014年9月3日発足)】
・辞表取りまとめ〜組閣
安倍首相は、第2次政権発足後初めての内閣改造を14年9月に実施した。民主党が約3年3カ月にわたり政権運営を担当していた上、第2次政権発足後も閣僚が1人も交代しない期間が戦後最長となっていたため、自民党内の「入閣待機組」の間で改造への待望論が高まっていた。臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめたあと、首相は公明党の山口代表と与党党首会談を開催。組閣本部を設置し、新閣僚らの呼び込みを行った。麻生太郎副総理兼財務相や菅義偉官房長官ら主要閣僚を留任させた一方で、新設の女性活躍担当相に有村治子氏を起用するなど、女性の活躍を前面に掲げた。女性閣僚の数は、01年の小泉政権発足時と並ぶ過去最多タイの5人となった。
・記者会見〜初閣議
安倍首相は官邸で記者会見を開き、改造内閣を「実行実現内閣」とする意向を表明。政権運営に向けた決意を強調した。初閣議では、東日本大震災からの復興加速や女性活躍、外交・安全保障の立て直しなどを盛り込んだ基本方針を決定した。
【第3次安倍内閣(2014年12月24日発足)】
・衆院解散〜組閣
第2次安倍改造内閣で、政権の「目玉」として登用した女性閣僚に相次いで「政治とカネ」の問題などが発覚した。経済産業相の小渕優子氏は、関連団体の政治資金収支報告書で収支の食い違いが判明。法相の松島みどり氏には、選挙区内でのうちわ配布問題が浮上した。野党からの追及が強まり、10月20日に小渕、松島両氏が「ダブル辞任」する異例の展開となった。
安倍首相は11月18日の記者会見で、15年10月に予定していた消費税率10%への再増税を17年4月まで1年半延期し、自身が掲げる経済政策「アベノミクス」の是非を国民に問うとして、衆院解散を明言した。
衆院は14年11月21日の本会議で解散した。これを受け、政府は臨時閣議で衆院選日程を「12月2日公示―14日投開票」と決定、選挙戦に突入した。結果は自民党が単独で290議席を得、自民、公明両党では定数の3分の2(317)を上回る計325議席を獲得。12月24日、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、第3次安倍内閣が正式に発足した。防衛相兼安全保障法制担当相は江渡聡徳氏に代わり、防衛庁長官を務めた中谷元氏を起用。一部担務の移管はあったものの、防衛相以外の17閣僚を再任する閣僚名簿を発表した。正副官房長官に加え、首相補佐官も全員を続投とした。
・記者会見〜閣議
安倍首相は初の記者会見で、憲法改正について触れ「歴史的なチャレンジと言っていいが、簡単なことではない」「どういう条文から国民投票を行うのか、またその必要性について、国民的な理解を深める努力をしたい」と改正実現に向けた意欲を示した。初閣議で決定した基本方針では、成長戦略の実行加速への意気込みを明記。また「景気回復の実感を必ずや全国津々浦々にまで届ける」として、経済政策を推進する決意を盛り込んだ。
(3)任命式と認証式
・宮中へ
官邸の組閣本部を出た新閣僚は一度、議員事務所か自宅に引き返し、礼服に着替えて再び官邸に向かう。閣僚は閣僚応接室に集合し、官房副長官が段取りを説明。この後、首相が任命式のため皇居に出発。遅れて、新閣僚が認証式出席のため、車列を組んで皇居に向かう。
・任命式
任命式は、天皇が「首相」を親任する。前首相は新首相に対し、天皇から新首相にあてた辞令書である「官記」を手渡す。任命式は、衆参両院議長が列席する。
・認証式と補職辞令
新首相が各閣僚を国務大臣に正式に任命。天皇の御名御璽が付いた官記も渡し、これで各閣僚は国務大臣に任命、認証されたことになる。なお、任命、認証行為は国務大臣に対するものであって、「外務」「財務」など所管省庁のトップとしての辞令は、官邸に戻ってから首相が各閣僚に渡す「補職辞令」。補職辞令は、首相執務室で官房長官立ち会いのもと行われる。
・記念撮影など
皇居から官邸に戻り、閣僚応接室で写真撮影。続いて初閣議が始まる。法制局長官、3人の官房副長官に交代があれば、ここで閣議決定され、新任者は直ちに閣議の席に呼び込まれる。この後、官邸の階段に首相と新閣僚がずらりと並ぶ恒例の記念撮影がある。
(4)組閣時の表記、出稿
国会で首相指名を受けて再び組閣した場合、「第2次森内閣」「第3次安倍内閣」と首相指名を受けた回数で次数を変更する。内閣改造の場合、「菅改造内閣」「第2次中曽根再改造内閣」(第2次中曽根内閣で2回目の改造)などと記述する。首相指名後の組閣で閣僚がそのポストにとどまる場合は「再任」、改造でそのポストにとどまる場合は「留任」と表記する。
組閣、改造の際には閣僚の一覧表、横顔、アラカルト(例・平均年齢、政治家以前の職業、最終学歴、世襲)などを出稿する。
(1)定例会見
官房長官が平日の午前11時と午後4時に定例記者会見を行う。閣議がある火曜と金曜の午前中は、閣議終了後の開催となる。慣例として、最前列に各社の官房長官番が陣取るが、質問者、内容とも自由で政局、政策、事件、事故、スポーツなど森羅万象に及ぶ。官房長官が国会対応に当たる際には、政務の官房副長官が代理で対応する。
(2)首相会見
官邸記者会見室での首相会見は、組閣、内閣改造、通常国会終了、予算成立、大規模な経済対策の発表、年頭など政治の大きな節目に開かれる。内閣広報官が司会を務める。冒頭の首相発言を受けて幹事社が代表質問、以後は各社が自由に質問できる。
これ以外にも、1月初頭の伊勢神宮参拝、選挙応援での地方遊説時、広島、長崎の「原爆の日」など各地訪問に際し、地元記者クラブと内閣記者会の共催で、記者会見が開かれることがある。選挙の場合は、与党記者クラブの仕切り。このほか外国の首脳来日の際は、共同記者会見などが開かれる。
民主党政権時、内閣記者会が主催する官邸での首相会見はインターネットメディアやフリーランスの記者にも開放され、自民党の政権復帰後もその対応を踏襲している。出席希望者はこれまでの発表記事などを添付し、官邸報道室へ事前に申し込む必要がある。
民主党政権までは、首相が任意のメディアとの個別インタビューに応じる慣例はなく、内閣記者会主催のグループインタビューなどで首相の意向を聞き出す形式をとっていた。
第2次安倍政権以降、安倍首相は新聞、テレビを問わず積極的に単独インタビューに応じる路線に転換した。こうした手法は政権が対応メディアを恣意的に選別しかねない危険性をはらんでいる。
(3)首相ぶら下がり
第2次安倍政権以降、外遊出発前などを除き、定例の「ぶら下がり」は設定されていない。官邸エントランスで一方的にメッセージを発信し、質問を受け付けない「ぶら下がり」が開催されることもあるが、不定期。
「ぶら下がり」取材は、小泉首相就任前は、①官邸内②国会内―で首相が歩いて移動する場合に限り、共同通信と時事通信の総理番が、随時行っていた。小泉首相は、昼夕の2回に限って、記者の質問に応じる形に変更。その後、昼夕2回が基本的に続いていたが、「国のトップが一日複数回も直接、取材に応じる国はない」(政府関係者)と、政権内部に開催への消極論が根強かった。
民主党政権の菅直人首相までは、夕方のみの開催を続けていたが、2011年3月11日の東日本大震災発生以降は「震災対応に専念したい」として、実質的に廃止され、以後の野田佳彦首相、安倍晋三首相も踏襲した。内閣記者会は「ぶら下がり」取材の再開を申し入れている。記事中では「官邸で記者団に述べた」などと書き「記者会見」とはしない。
(4)懇談
懇談と称した取材で、政務、事務の官房副長官や国家安全保障局長ら政権幹部に、政策、政局への意見や背景説明を聞く。各人につきおおよそ1週間に1回程度、日中に官邸内で定期的に開催される。メモを取れる懇談と取れないオフ懇談がある。そのほか、官房長官、首相補佐官、首相秘書官ら政府幹部を含め朝回り、夜回りで首相の意向や官邸の動きを日夜探る。
(5)内政懇
首相が外遊する際、滞在国の宿泊施設で行う懇談を「内政懇」と呼ぶ。名称は内政懇だが、テーマは外交にも及ぶ。この懇談は「オンレコ」で録音も可。ただし、テレビカメラを回すことはできない。「○○首相は○日、訪問先の△△のホテルで同行記者団と懇談し」という記事になる。これとは別に、現地プレスも出席する「内外記者会見」も行うのが通例。
首相と閣僚、副大臣、政務官は就任、辞任の際に本人と家族の保有資産を公開している。土地・建物(固定資産税の課税標準額で算出)、預貯金(普通預金は公開対象外)、株などの有価証券、借入金、貸付金、ゴルフ会員権、自動車、書画などの美術品が対象となる。原則として就任、辞任1カ月後に資料が公開される。これとは別に国会議員としての資産公開もある。国会議員の公開は本人分だけだが、閣僚らは配偶者と扶養する子も公開する。
ロッキード事件の田中角栄元首相の有罪判決を契機に1984年、首相や閣僚の不正蓄財を監視する目的で第2次中曽根内閣によって導入された。
現行制度は2001年1月に閣議決定された「大臣規範」に基づく。01年10月の商法改正で額面株式が廃止されてからは、株式は銘柄と株数だけを公開。06年以降は個人富裕層など限られた顧客から資金を集めて運用する私募ファンドも公開対象となった。ゴルフ会員権、自動車、美術品は金額を表記しない。
→第7章「政党と政治家の資金」参照
戦後停止されていた叙勲制度は1964年に再開し、毎年春と秋の2回、各界の功労者に勲章を授与している。菊花章、旭日章、瑞宝章がある。菊花章以外は勲1~8等に分かれていたが、数字によるランク付けや官民格差との批判を受け、2003年に等級区分の簡素化や、一般から候補者推薦を受け付ける制度を導入するなど大幅な制度改正を実施した。
「褒章」も春と秋の2回授与される。その道一筋に励んだ人に贈られる黄綬褒章、芸術、学問などの分野で功績のあった人を対象とした紫綬褒章、公共の利益に貢献した人に贈られる藍綬褒章などがある。
褒章は特定分野での功績を対象にしているのに対し、叙勲はそれまでの功績を総合的に勘案して贈られる。
緊急事態に備え、首相官邸地下にある内閣情報集約センターと官邸危機管理センターが24時間態勢で情報収集と初動に備えている。発生時の政府対応については、基本的に番外を打つ。
具体的には、大規模自然災害(地震、水害、火山噴火)、重大事故(航空、海上、鉄道、道路、危険物、火災、原子力)、重大事件(ハイジャック、大量殺傷型テロ、重要施設テロ、サイバーテロ、不審船)、武力攻撃事態、その他(邦人救出、大量避難民流入、核実験、新型インフルエンザ)を想定している。
(1)地震・災害発生時 ①東京23区内で震度5強以上②その他の地域で震度6弱以上③津波警報(大津波)発令④東海地震注意情報発令―の場合、内閣危機管理監は直ちに「官邸対策室」を危機管理センターに設置。「緊急参集チーム」に指定されている関係府省庁の局長級職員は呼び出しを待たずに集合し、情報集約や政府機関の初動指揮に当たる。東京23区内で震度6強以上の「首都直下地震」の場合は、首相と全閣僚も直ちに官邸対策室に集合する。多数の死者や経済被害が予想される場合、政府の対策本部を設置して対応に当たる。官邸対策室設置に至らない場合は「官邸連絡室」を設置して対応する。
(2)武力攻撃事態・テロ 「事態対処法」や「国民保護法」などの有事法制で政府や自治体の役割を規定している。外国の侵略や弾道ミサイル、航空機攻撃などが発生するか「明白な危険が迫っている」場合、首相は閣議で「武力攻撃事態」に認定。武力攻撃に準じるテロ攻撃も「緊急対処事態」に認定し、対策本部を設置する。政府は国民に警報を発令し、都道府県知事・市町村長を通じて国民に避難を指示。被害を最小限に食い止めるため発電所やダムなど重要施設の警備を強化し、必要に応じて使用停止命令を出す。放送局や運送事業者、医療機関などの「指定公共機関」には、警報などの放送、避難者の輸送、治療などへの協力義務が課せられている。
(3)共同訓練 他国からの侵攻やテロなどの有事を想定し、国と自治体による共同訓練を2005年から始めている。国民保護法に基づく実動・図上訓練を、希望した各都道府県と順次実施。訓練費用は国の負担となる。
(4)政府専用機 「空飛ぶ官邸」ともいわれる政府保有のボーイング747―400型のジャンボ機。中曽根内閣で導入を決定した。現在2機保有しており、航空自衛隊が管理・運航を受け持ち、通常は千歳基地(北海道)で待機している。初フライトは1993年2月の渡辺美智雄外相の訪米。首相としての初フライトは93年4月の宮沢喜一首相の訪米。
機内サービスを担当する客室乗務員も含めて、特別航空輸送隊に所属する自衛官が担当する。運航する際は2機の政府専用機が同時に飛び、整備担当の自衛官も同行する。
機内は、首相執務室のほか会議室、事務室、客室が設けられており、首相外遊の際は同行の秘書官や外務省スタッフ、警護官、報道陣などの座席が用意される。緊急時における在外邦人の輸送や国際緊急援助活動、国連平和協力活動にも利用される。
政府は2013年8月、機体整備を担う日本航空が747の運航を終え、今後の整備が困難になることから、後継機種の選定を開始。14年8月、後継機種をボーイング777―300ERにすると決定した。機体整備を担う企業には全日空を選んだ。19年度から導入される予定。
(5)アルジェリア人質事件 北アフリカ・アルジェリア南東部のガス田施設で2013年1月16日、プラント建設大手「日揮」の日本人駐在員を含む多数がイスラム武装勢力に拘束された事件。アルジェリア軍が犯行グループを攻撃し、少なくとも40人が死亡した。日本人は17人が人質となり、うち10人が犠牲となった。
安倍晋三首相は事件発覚時、東南アジアを訪問中だった。政府は事件発覚後の16日に官邸対策室、外務省に対策室(その後、緊急対策本部)、在アルジェリア日本大使館に現地対策本部を設置。17日に政府対策本部を設置した。首相はアルジェリアなど関係国首脳と電話会談し、協力を要請した。17日には欧州訪問中の城内実外務政務官をアルジェリアに派遣した。21日には無事が確認された日本人の帰国支援のため政府専用機の派遣を決めた。外国で騒乱などの緊急事態に巻き込まれた邦人退避のために派遣された初めてのケースとなった。同日、日本人7人の死亡が確認され、さらに23日に2人、24日に1人の死亡が確認された。1人を除く9遺体も政府専用機で搬送された。
政府は事件後、政府の対応を検証する委員会を設置。同年2月に①海外で緊急時に邦人を救出するため、車両による陸上輸送を可能とする自衛隊法改正の検討②邦人保護担当者の迅速な現地派遣に向け、外務省に「緊急展開チーム」創設の検討③官邸の司令塔機能発揮④アフリカ・サハラ砂漠南部地域を中心に軍情報を収集する防衛駐在官拡充と現地言語に通じた外交官の確保―などを明記した報告書をまとめた。
その後、有識者懇談会が政府対応について議論し、4月に自衛隊による陸上輸送を可能とする自衛隊法改正案を含め、政府は邦人退避のために必要な手段を拡充すべきなどとする報告書をまとめた。
事件は海外での邦人保護の在り方に課題を投げ掛け、緊急時に自衛隊による在外邦人の陸上輸送を可能とする改正自衛隊法が13年11月に成立した。政府は事件を教訓に、海外での邦人救出を可能とする安全保障法制を検討している。
(6)過激派組織「イスラム国」による邦人人質事件 2014年8月、千葉市の湯川遥菜さんがシリアで拘束され、過激派組織「イスラム国」を名乗るグループが犯行声明を出した。10月に仙台市出身のジャーナリスト後藤健二さんが湯川さんを捜すため、シリアのイスラム国支配地域に入り、連絡が途絶えた。同組織は安倍晋三首相が中東外遊中の15年1月20日、日本人2人の殺害を警告し、2億邸㌦の身代金を要求するビデオ声明を発表した。24日に湯川さんが殺害されたとの画像声明をインターネット上で公開し、後藤さん解放の条件としてヨルダンで収監中の死刑囚の釈放を新たに要求した。2月1日(現地時間1月31日)に後藤さんを殺害したとする声明を公表した。
政府は、湯川さんの事件について14年8月17日付、後藤さんの事件について同年11月1日付で、官邸に情報連絡室、外務省に対策室を設置。在ヨルダン日本大使館に現地対策本部を8月16日、11月1日にそれぞれ設置した。いずれも設置当初は公表せず、殺害警告後に明らかにした。殺害警告後、首相はヨルダン、トルコ、エジプトなど関係各国の首脳らとそれぞれ電話会談し、協力を要請した。首相の外遊に同行していた中山泰秀外務副大臣をヨルダンに派遣し、現地対策本部の責任者とした。
政府は2月、政府の対応を検証する委員会を設置、外部有識者も加わり、5月に政府の対応に「人質の救出を損ねるような誤りがあったとは言えない」とする有識者の総括を明記した報告書をまとめた。報告書は、海外での日本人の安全確保に向け、情報収集能力や危険地域への渡航制限を検討課題に挙げた。
(1)集団的自衛権 自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されていなくても、自国への攻撃と見なして実力で阻止する権利。国連憲章51条は、自国への侵害を排除する「個別的自衛権」とともに加盟国の権利として認めている。第2次安倍政権より前の歴代内閣は、憲法9条が許容する「必要最小限度の自衛権の範囲を超える」と解釈し、行使を禁じてきた。
第2次安倍内閣は2014年7月1日、それまでの憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を限定容認すると閣議決定した。日本の存立が脅かされるなどの要件を満たせば、必要最小限度の武力行使は許されるとの内容だ。
閣議決定までは、自衛隊による武力行使は1954年4月に吉田茂内閣が国会答弁で示した「自衛権発動3要件」を満たす場合に許されると解釈されてきた。①わが国に対する急迫不正の侵害②他に適当な手段がない③必要最小限度にとどまる―との要件だ。
自衛権発動3要件は個別的自衛権を念頭に置いており、集団的自衛権の行使は3要件を超えるとして禁じられてきた。しかし安倍内閣は憲法9条下での集団的自衛権行使を認めるため、「武力行使3要件」を閣議決定に新たに盛り込んだ。
武力行使3要件は①わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと―で政府の憲法解釈変更の根幹部分となる。
安倍晋三首相は武力行使3要件を満たすケースとして、邦人を輸送中の米艦が攻撃を受けた際の防護や、日本への原油輸送ルートである中東・ホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合を挙げている。
一方、国連を中心とした国際社会が他国を侵略した国に対して団結して制裁を科す仕組みを「集団安全保障」という。90年にクウェート侵攻したイラク軍を安保理決議に基づく米国中心の多国籍軍が攻撃した例がある。
日本政府は、集団的自衛権行使を容認した閣議決定までは、憲法9条を理由に武力行使を伴う集団安保措置への参加はできないと解釈してきた。
しかし閣議決定後、横畠裕介内閣法制局長官は、3要件に当てはまれば、武力行使を伴う集団安保措置への参加も可能との見解を表明している。安倍首相は「機雷の掃海のように受動的、限定的なものは3要件に当てはまる可能性がある」としている。
→特集「安保法制」参照
(2)主権回復の日 第2次大戦後の1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本は主権を回復した。政府はこの日が「主権回復の日」に当たるとして2013年4月28日に「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」を東京都内の憲政記念館で開催。内閣府によると、国会議員や中央官庁幹部ら約390人が参加した。
自民党は12年の衆院選公約で、政府主催の式典開催を明記した。安倍晋三首相は政権奪還後「主権を失っていた7年間の占領期間を知らない若い人が増えている。日本の独立を認識する節目の日だ」と開催の意義を強調。政府は、13年3月12日の閣議で、政府主催の式典を憲政記念館で開催すると決定した。
式典には、天皇、皇后両陛下が出席されたが、お言葉は述べなかった。両陛下が式典終了後に退場する際には「万歳」が唱和された。
一方、72年まで米施政権下に置かれた沖縄県では、4月28日は「屈辱の日」と呼ばれる。県議会の一部会派は、宜野湾市で抗議集会を式典と同時刻に開いた。翌14年の同じ日には、式典の開催は見送られた。
(3)内閣官房報償費(機密費) 「国の事務または事業を円滑に遂行するため機動的に使用する経費」と位置付けられる。取り扱い責任者の官房長官が政治的判断で国費から支払う。内閣情報調査室の経費を含めて最近の支出は年間約14 億6千万円に上る。国内外の情報収集の費用とされ「国の機密保持上、その使途を明らかにすることが適当でない性格の経費」とも言われる。国会運営で野党対策に使われていたとの証言もあるという。【支出の手続き】
政府が2002年4月に定めた内閣官房報償費に関する「基本方針」「取り扱い要領」で定められている。支払い目的は①政策推進費(高度な政策的判断で機動的に使用する経費)②調査情報対策費(必要な情報を得るための経費)③活動関係費(政策推進費、調査情報対策費の所期の目的が達成されるよう支援する経費)―に3分類。
官房長官を取り扱い責任者とし、機密費の受領、支払い時期、金額、目的類型を記載した出納簿を整備するよう規定。官房長官は機密費の使途に関連して毎年度、目的類型を明らかにした「執行の基本方針」を定め、それに基づいて支払うよう定めた。
ただ官房長官自身が引き出した機密費は「支払い目的」を明示する必要はない。会計検査院長からの申し入れがあれば官房長官自身が説明し、支払い関係書類は5年間保存する。毎年度末には、官房長官が内閣官房総務官室職員を指名し、機密費の出納が適切かどうかを確認する。
【支出額の公表】
2009年11月、民主党政権の平野博文官房長官は、内閣官房報償費の04年4月以降の月別支出額を公表した。内閣自ら支出額を明かすのは初めてだった。
04年度からの各年度の支出総額は約12億円で、いずれの年度も4月に2億円、その後は1カ月に1億円ずつ支出していた。年度末間近の2月に残額を引き出し、ほぼ満額を使い切っていた。3月の支出はなく、その分を4月に上乗せする慣例とみられる。
公表により、自民党が衆院選で惨敗し、野党転落が確実になった09年9月1日に、麻生内閣が2億5千万円を引き出し、支出していたことが判明した。過去5年半での月別支出額でみても突出していたが、使途は公表しなかった。10年2月の政府答弁書は「それまでの支出の態様とは異なるものと言わざるを得ない」と指摘した。
(4)特定秘密保護法
・概要
安全保障上、外部への漏えいにより著しい支障を与える恐れのある重要情報の保全に関する法律。2014年12月10日に施行された。外交・安保政策の司令塔の国家安全保障会議(NSC)創設に合わせ、同盟国との間で重要情報をスムーズに共有するのが狙い。政府が不都合な情報を恣意的に機密指定する恐れや、国民の知る権利や報道の自由が侵害される懸念が指摘されている。
防衛や外交、スパイ防止、テロ防止の4分野を対象に、政府が安全保障上の秘匿が必要と判断した情報を「特定秘密」に指定する。公務員らが特定秘密を漏えいした場合、10年以下の懲役。公務員以外が唆した場合も5年以下の懲役を科す。特定秘密は原則的に30年まで非公開にできる。「安保上やむを得ない」場合には内閣の承認を受けて60年まで延長できる。行政機関は特定秘密を扱う職員らの身辺を調べる「適性評価」を実施する。
・経過
沖縄県・尖閣諸島沖での中国漁船衝突の映像流出事件などを受け、政府の有識者会議は11年8月、情報保全強化の新法制定を求める報告書を提出。民主党政権は12年の通常国会への提出を目指したが、国民の知る権利を侵害する懸念から党内に異論があり、断念した。
政権交代後、安倍晋三首相は法整備の必要性を訴え、政府は13年10月25日に法案を閣議決定し、国会提出した。公明党の要求を踏まえ国民の知る権利と報道の自由への配慮を明記した内容だったが、強制力のない「努力規定」にとどまった。
国会審議と並行して行われた修正協議の結果、野党の日本維新の会とみんなの党とも修正合意した。ただ与党は13年11月26日の衆院本会議での採決を強行したため、日本維新の会は早期採決を認めないと退席し、自民、公明両党とみんなの党の賛成多数での可決となった。13年12月6日の参院本会議で自民、公明両党の賛成多数で成立したものの、日本維新の会に加え、みんなの党も退席した。
・運用
政府は14年10月14日、特定秘密の指定や解除の在り方を定めた運用基準を閣議決定した。秘密指定をチェックする機関として、官房長官をトップに府省庁の事務次官級が参加する「内閣保全監視委員会」を内閣官房に新設。内閣府には特定秘密の管理状況を検証、監察する審議官級の「独立公文書管理監」ポストと、その下に「情報保全監察室」を置くこととした。運用是正を要求できるが、政府内組織のため実効性は見通せない。
法施行から5年後に秘密保護法の運用状況を検討し、必要があれば運用基準を見直す。秘密指定権限を持つ19行政機関には内部通報の窓口を設ける内容とした。
一方、特定秘密保護法の運用をチェックする国会の監視機関が「情報監視審査会」で、改正国会法は14年6月20日に成立した。審査会は衆参両院に常設され、いずれも8議員で構成。政府から秘密保護法の運用状況について報告を受け、必要に応じて特定秘密の提出を要求できる。秘密指定が不適切と判断した場合は指定の解除を勧告できるが、法的拘束力はない。
政府が安全保障上の理由などで特定秘密の提出を拒否した場合、内閣に対して非開示理由の声明を出すよう求めることができる。政府が国会の各委員会から求められた特定秘密の提出を拒んだ場合でも審査会は提出を勧告できるが、強制力はない。情報監視審査会は盗聴などを防ぐ措置を施した特殊な部屋で、非公開の秘密会によって開かれる。担当する国会職員は機密を扱える人物かどうか身辺を調べる「適性評価」の対象となり、秘密を漏らした議員は刑罰や除名を含む懲罰を科される。
取材を大幅に制限する内容の法律だ。たとえば、邦人人質事件の検証も、当時の政府内の動きは、特定秘密にあたる可能性が高い。
・経過
現職首相による靖国神社参拝は、日本の独立回復を定めたサンフランシスコ平和条約調印直後の1951年10月、吉田茂首相が参拝し再開された。当時は春季か秋季の例大祭に合わせて参拝するケースが多かった。
一方、日本遺族会などによる靖国神社国家護持運動を受け、自民党は69年から5年連続で、靖国神社を首相管轄の特殊法人として国営化する靖国神社の国家管理法案を国会に提出した。「憲法の政教分離原則に違反する」などの反31 官 邸対や軍国主義の復活につながるとの懸念から運動は終息。首相の公式参拝を実現する運動に転換していった。
三木武夫首相は自民党内の求心力を高める狙いから75年に首相として初めて8月15日に参拝。その後、福田赳夫、鈴木善幸、中曽根康弘各首相が参拝し、首相の8月15日靖国参拝が慣例化した。公用車を使わないなど「私的参拝」としていた。
戦後政治の総決算を掲げた中曽根首相は公式参拝に意欲を見せた。85年8月9日に藤波孝生官房長官の私的諮問機関が、宗教儀礼によらなければ首相らの公式参拝も憲法の政教分離に違反しないとの報告書を提出。こうした地ならしをした上で同月15日に「二礼二拍手一礼」しないなど、神道形式をとらない形で戦後初の公式参拝を行った。
だが靖国神社が78年10月17日に東条英機元首相らA級戦犯を合祀(ごうし)していたことを共同通信がスクープ。公式参拝はA級戦犯合祀問題と相まって中国側の猛反発を招き、中曽根首相はその後、在任中の参拝を自粛した。昭和天皇は戦後、靖国神社に8回参拝したものの、75年11月を最後にA級戦犯が合祀されて以降は参拝していない。
宮沢喜一首相は自民党総裁選で日本遺族会に首相在任中の靖国参拝を約束。靖国神社にも記録はないが、退陣後の2001年7月に共同通信社のインタビューで秘密裏に参拝したことを認めた。日本遺族会の会長だった橋本龍太郎首相は96年に自分の誕生日である7月29日に参拝したが、中韓両国などの批判を浴び、在任中の参拝を見送った。
・小泉〜民主党政権
小泉純一郎首相は2001年4月の自民党総裁選で「首相に就任したら8月15日にいかなる批判があろうとも必ず参拝する」と明言。実際は中国などの反発に配慮し、01年は8月13日に現職首相として5年ぶり参拝した。その後、02年4月21日、03年1月14日、04年1月1日、05年10月17日に参拝。任期中最後となる06年は8月15日に参拝した。一方、中韓両国は反発、両国との政治関係は冷え込んだ。
その後、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎各首相に加え、民主党政権の鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦各首相は中韓両国への配慮から、首相在任中の参拝を見送った。
・第2次安倍政権以降
安倍首相は2012年9月の野党時代の自民党総裁選の際に「首相在任中に靖国参拝できなかったのは痛恨の極みだ」と表明。同年10月17 日に自民党総裁として参拝した。
首相就任後も「国のために命をささげた英霊に対し国のリーダーが尊崇の念を表すことは当然で、各国のリーダーも行っている。第1次安倍内閣で参拝できなかったのは痛恨の極みだった」(13年2月7日の衆院予算委員会)と意欲は隠さなかった。
参拝を決行したのは、第2次安倍政権発足からちょうど1年の13年12月26日。「中国、韓国の人の気持ちを傷つける考えは毛頭ない」と説明したものの、中韓両国は抗議し、米政府は「近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに米政府は失望している」との声明を発表した。
・新たな追悼施設構想
中韓両国などは東京裁判によるA級戦犯が靖国神社に合祀されている点を問題視。靖国神社はA級戦犯の分祀を拒否し、政府は政教分離の原則から強制することはできないとの立場で対応に苦慮してきた。このため新たな国立追悼施設構想が浮上したこともあったが、議論は盛り上がりを欠いている。
小泉首相が2001年8月13日の最初の参拝の際に出した談話で「内外の人々がわだかまりなく追悼の誠をささげるにはどのようにすればよいか議論する必要がある」と表明したのがきっかけだ。これを受け福田康夫官房長官の私的諮問機関が発足。02年12月に「国を挙げて追悼・平和祈念を行うための国立の無宗教の恒久的施設が必要」とする報告書をまとめた。自民党内から「靖国神社を形骸化させる」との反発が噴出し、棚上げ状態になった。公明党は新たな国立追悼施設の設置に意欲を示しているものの、安倍首相は「(靖国神社は)追悼の中心的な施設で、遺族の気持ちもそうだ」と否定的な立場を取っている。
第3章 政党 (18)
1955年11月15日、日本民主党と自由党が合流して結党。新自由クラブと連立を組んだ一時期を除き、93年8月の細川政権発足までの約38年間、長期単独政権を維持した。「非自民・非共産」の細川、羽田両連立政権の下で野党となったが、94年6月に自民、社会、新党さきがけ3党連立政権を樹立。社会党の村山富市委員長を首相に担ぎ、1年足らずで政権与党に復帰した。96年1月に村山首相退陣を受け、橋本龍太郎自民党総裁が首相に就任した。
一方で、参院では自民党単独で過半数に達しない状況が続いていたことから、小渕恵三首相は98年11月、小沢一郎党首が率いる自由党と連立政権を組むことで合意。さらに99年10月、公明党とも政権・政策合意をし、「自自公」の連立政権が誕生した。自由党とは2000年4月に連立を解消したが、「自公」連立は継続した。02年12月には、自由党と民主党の離党者で結成した保守新党とも連立、「自公保」政権となった。その後保守新党が議席を減らし、03年11月、自民党に合流して「自公」連立政権に戻った。
第1次安倍政権時代の07年7月に参院選で惨敗し、衆参両院で多数派が異なる「ねじれ国会」となった。09年8月の衆院選では119議席しか取れず野党に転落した。12年12月の衆院選で公明党と合わせて定数の3分の2を超える325議席を獲得して政権に復帰するとともに、安倍晋三総裁も首相に返り咲いた。翌13年の参院選でも勝利し、久々にねじれを解消した。
10年に綱領を大幅改定し、①世界に貢献できる新憲法の制定②日本の主権は自らの努力で守る③財政再建―などを掲げた。
憲法に関し、野党時代の12年4月、谷垣禎一総裁の下で新たな憲法改正草案を決定した。前文や自衛隊を「国防軍」に改める9条のほか、天皇を「日本国の元首」と明記するなど保守色を強めた。結党60周年となる15年の運動方針には「あらためて胸に刻まねばならないのは、憲法改正を党是として出発した保守政党の矜持(きょうじ)だ」「改憲賛同者の拡大運動を推進する」と実現に全力を挙げる姿勢を盛り込んだ。
年1回、原則として1月の通常国会召集前に大会を開く。総裁の任期は3年で、連続して2期を超えて在任できない。その他の役員の任期は1年。総裁選に出馬するには国会議員20人以上の推薦が必要で、党所属の国会議員と党員による公選で選ばれる。総裁が任期途中で辞任した場合も原則公選だが、特に緊急を要する時は両院議員総会で選任できる。この場合は全国会議員と都道府県代表各3人が投票し、新総裁の任期は前総裁の残りの任期となる。12年の総裁選後、地方の声をより反映させるため、党所属国会議員しか参加できなかった決選投票に地方票も加えるなどの規程改正を実施した。
毎週月曜の夕方に役員会、火曜と金曜(国会閉会中は火曜日だけ)の午前に役員連絡会、総務会を開く。木曜に各派閥の総会が開かれる。
党本部は東京都千代田区永田町1―11―23。電話03(3581)6211
機関紙は「自由民主」(週刊)68万部(15年2月)
12年の総裁選で投票権を持っていた党員・党友数は78万9348人で、09年時点の約108万人から減少した。
自民党総裁は首相の座に直結する。55年体制下では首相を目指す有力政治家は総裁選に向けて党所属議員の「子分」を育成し、派閥を形成した。選挙制度が定数3〜5の中選挙区制だったことも派閥を生む土壌となった。1選挙区に複数の自民党候補が出た中選挙区時代、自民党候補は激烈な選挙戦を勝ち抜くため、大方の候補は「票とカネ」の支援を求め、派閥に所属するようになった。
小選挙区制導入後はこの面での派閥機能は弱まり、政党助成金の配分権を握った党執行部の力が相対的に強くなった。小泉純一郎氏が首相に就くと、当選回数重視、派閥順送りの閣僚人事を見直し、派閥が影響力を残すのは副大臣や政務官、国会、党役員の人事ポスト配分程度になった。
結党当初の「8個師団」といわれる時代から「三角大福中」「安竹宮」の時代を経て、15年4月現在、細田派、額賀派、岸田派、麻生派、二階派、石原派、山東派の7派閥が存在する。派閥ではないが、岸田派から分裂した谷垣グループ(有隣会)や、石破茂地方創生担当相に近いグループ(無派閥連絡会)もある。一方、いずれにも属さない無派閥議員も増加している。
・細田派(正式名称・清和政策研究会、会長・細田博之)
福田赳夫氏が1972年に結成した「八日会」が前身で、福田首相退陣後の79年に「清和会」として旗揚げした。派閥会長は創始者の福田氏から安倍晋太郎元外相、三塚博元蔵相、森喜朗元首相と引き継がれた。森政権時代の1年間、小泉元首相が会長を務めたが、小泉内閣発足に伴い森氏が復帰。2006年10月には町村信孝元外相が会長に就任した。町村氏が福田康夫内閣で官房長官に就いたため、一時、町村、中川秀直、谷川秀善の3氏による「代表世話人」の集団指導体制になったが、09年2月に町村氏が会長職に戻った。14年衆院選を受けて町村氏が衆院議長就任。14年12月25日の派閥幹部会で細田会長代行を後任会長に昇格させることを決め、「細田派」へ衣替えした。細田氏は安倍晋三首相と近い関係とされ、実質「安倍派」となったとの見方が党内では有力だ。15年4月現在、約90人の最大派閥。
脳梗塞で倒れた小渕恵三首相の後を受けて森氏が派閥の「悲願」である首相の座を射止めたのは00年4月。その後、小泉氏、安倍氏、福田氏と同派閥出身の総裁を4代続けて輩出した。小泉氏は3度の総裁選への挑戦の末、01年4月、総裁の座を勝ち取った。野党時代の12年9月の総裁選では、安倍氏が決選投票で石破茂氏を下し、総裁に返り咲36政 党いた。約3カ月後の同年12月の衆院選で自民党が政権を奪還。同月に第2次安倍内閣が発足した。
結成以来40年以上の歴史で、お家芸と言われるほど内紛や分裂が多いことで知られる。1991年には加藤六月氏と三塚氏が「三六戦争」を展開した。93年には武村正義氏らが離脱し新党さきがけを旗揚げ、94年にも鹿野道彦氏らが離脱し新党みらいを旗揚げした。98年9月には亀井静香氏らが森、小泉両氏との主導権争いの末、集団離脱した。福田首相の後継を選ぶ2008年総裁選の対応をめぐっては、森、町村両氏と対立した中川氏が09年10月に派閥を退会した。10年の参院議員会長選では、森氏が支援する谷川氏が、安倍氏の応援する中曽根弘文氏に敗れ、森氏は派閥を去った。
・額賀派(正式名称・平成研究会、会長・額賀福志郎)
田中角栄氏が、1972年5月に佐藤派から分離独立して結成した「木曜クラブ」(田中派)が前身。87年7月に竹下登氏が金丸信氏らとともに独立し、経世会を結成した。92年12月に小沢一郎氏らが分離・独立し、一時は第4派閥に転落したが、96年の衆院選で新人を大量当選させ、再び最大派閥になった。竹下派以来、竹下氏、橋本龍太郎氏、小渕恵三氏と3人の首相を輩出している。
竹下派、小渕派、橋本派時代は党内主流派として君臨してきたが、2001年4月の総裁選で橋本氏を擁立して小泉純一郎氏に惨敗して以来、小泉政権下で「抵抗勢力」のレッテルを貼られて非主流派の道を歩んだ。03年9月の総裁選は小泉氏を支持する青木幹雄氏と、藤井孝男氏を推す野中広務氏で派内が分裂し、混乱を深めた。
04年には日本歯科医師連盟からの1億円献金隠し事件が発覚。政治資金規正法違反罪で派閥元事務局長が有罪判決を受けたほか、元派閥会長代理の村岡兼造氏が在宅起訴された。橋本氏(不起訴)は派閥会長を引責辞任。05年の郵政民営化関連法案の衆院採決では、反対票を投じた保利耕輔氏らが直後の衆院解散・総選挙で公認を得られず、無所属で出馬。綿貫民輔氏は国民新党を旗揚げして自民党を除名された。選挙後はメンバーが大幅に減り、森派(現・細田派)に最大派閥の座を奪われた。
橋本氏の後任会長は1年3カ月も空席だったが、05年11月にようやく津島雄二氏が就任。09年8月に津島氏が政界引退したのを受け、現体制になった。 額賀氏は求心力を保ちきれていない。石破茂氏が11年12月、自身の勉強会を設立し、派閥を離脱した。14年には脇雅史氏、田村憲久氏ら中堅以上のメンバーが相次いで脱退した。15年4月現在のメンバーは53人で、最大派閥の細田派に大きく水を空けられている。
14年10月には、党内で「女性首相」候補と目されてきた小渕優子氏が自身の「政治とカネ」の問題で経済産業相を辞任した。 一方、約20人いる参院側では、現在も青木氏が隠然たる影響力を持つとされる。
・岸田派(正式名称・宏池会、会長・岸田文雄)
1957年6月、池田勇人元首相を初代会長に結成された老舗派閥。池田氏の後、前尾繁三郎、大平正芳、鈴木善37 政 党幸、宮沢喜一、加藤紘一ら各氏が派閥を継承。前尾、加藤両氏を除く4人が首相に上り詰め「保守本流」を自負してきた。旧大蔵省を中心とする官僚出身者が多く、政策には強いが「切った張った」の権力闘争に弱い「お公家集団」とやゆされる。
98年12月、宮沢派から加藤派への代替わりに反発した河野洋平氏ら15人が河野グループとして派閥を離脱。2000年の「加藤の乱」をきっかけに堀内派(のちの岸田派)が分裂し、加藤派を引き継いだ谷垣派と三つに分かれた。
堀内派では、派閥会長だった堀内光雄元総務会長が05年7月の郵政民営化関連法案の衆院採決で反対票を投じ、「郵政解散」に伴う9月の衆院選後に離党。同年秋の内閣改造・党役員人事では、50人近い所属議員がいるにもかかわらず入閣ゼロ、党の重要ポストも獲得できなかった。後任会長には丹羽雄哉元厚相と古賀誠元幹事長の名前が挙がったが、両氏とも派内の支持をまとめきれず、06年2月に「2人代表制」とした。10月5日、古賀氏が会長に就き古賀派となった。
一方、加藤派は「加藤の乱」後、少数派閥に転落。会長だった加藤氏が02年4月、元秘書の脱税事件に絡み議員辞職した後、小里貞利氏が会長代行を経て会長を務めた。小里氏は05年9月の衆院選を機に政界を引退し、谷垣禎一氏が後を継ぎ、谷垣派となった。
古賀派、谷垣派はともに「宏池会」を名乗り本家争いを続けていたが、08年5月、ポスト福田への主導権確保と、続く清和会支配への対抗から合流。古賀氏が新会長となった。09年8月の衆院選で自民党が敗れ下野した後、谷垣氏は総裁に就任した。
古賀氏は、谷垣氏の党運営に不満を持っていたとされ、12年9月の総裁選で再選を目指した谷垣氏への支援を拒んだ。出馬に必要な推薦人20人を集められなかった谷垣氏は立候補を断念。古賀氏の協力拒否に反発した谷垣氏に近い議員は退会し、派閥は再分裂した。古賀氏は総裁選後、派閥会長を辞任する考えを表明。10月4日、岸田氏が後任会長に就いた。
宏池会は池田派以来、加藤派の一時期を除いて約56年にわたり東京・赤坂の日本自転車会館に派閥事務所を置いていたが、同会館の取り壊しに伴い13年10月に全国町村会館へ移した。
・麻生派(正式名称・為公会、会長・麻生太郎)
1998年12月、宮沢派が加藤派に代替わりする際、加藤紘一氏の派閥会長就任に反対する河野洋平元総裁を支持するグループが宮沢派を離脱。既に無派閥だった河野氏を中心として結成した。98年の総裁選では梶山静六氏を支援、2000年4月の総裁選ではグループ内から麻生氏を擁立した。河野氏が03年に衆院議長就任に伴い離脱してから会長職は空席が続いた。麻生氏が06年12 月に後継会長となり、08年9月、4度目の総裁選出馬で勝利し総裁に就任。だが、約1年後の09年衆院選で自民党が下野した責任を取って辞任した。所属議員は12年衆院選で大幅に増加し、15年4月現在、計37人。
・二階派(正式名称・志帥〈しすい〉会、会長不在、会長代行・河村建夫、中曽根弘文) 山崎拓氏らが離脱した後の旧渡辺派と、三塚派を離脱した亀井グループが1999年3月に合併して結成した。旧渡辺派出身の村上正邦氏が会長、亀井グループ出身の亀井静香氏が会長代行の態勢で発足し「村上派」と呼ばれた。2代目会長に就いたのは旧渡辺派出身の江藤隆美氏。亀井氏が引き続き会長代行を務め「江藤・亀井派」と称された。2003年10月、江藤氏の政界引退で亀井氏が念願の会長に就任、「亀井派」となった。
01年の総裁選では亀井氏を擁立。しかし、最終局面で小泉純一郎陣営と政策協定を結び亀井氏は本選を辞退した。その後、主流派として処遇されなかったことから小泉氏に批判的な立場に転じた。亀井氏は03年9月の総裁選にも立候補したが、2位に終わった。05年8月、郵政民営化関連法案が参院で否決されたことを受け、小泉氏が衆院を解散。派内を郵政民営化反対でけん引した亀井氏は「首相の強権政治を阻止できなかった」として会長を辞任した。9月の衆院選で公認を得られなかった亀井氏は離党し国民新党を設立、ポスト小泉の有力候補だった平沼赳夫氏も離党勧告を受け、離党した。
衆院選後は伊吹文明氏の「代表」就任を内定。しかし、島村宜伸氏らが「一部が勝手に決めた」と反発、12月になって伊吹氏の「会長」と島村氏の「名誉会長」を正式決定した。
自民党が下野した09年8月の衆院選では多数の落選者が出た。伊吹氏は「互助機関として助け合うには数が多い方がいい」と11月、衆参3人となっていた二階俊博氏率いる旧二階派(正式名称・新しい波)と合流。二階氏が会長代行に就いた。12年9月の総裁選は自主投票とした。
自民党が政権復帰した12年12月の衆院選後には、所属議員が約30人にまで増加。伊吹氏の衆院議長就任に伴い、二階氏が会長となった。14年12月の衆院選後、議長職を離れた伊吹氏が復帰した。
・石原派(正式名称・近未来政治研究会、会長・石原伸晃)
旧渡辺派に所属していた山崎拓氏らが1998年11月、同派の中堅・若手議員や無派閥議員を引き連れて独立した旧山崎派が前身。山崎氏は2012年12月の衆院選に出馬せず政界を引退したため、石原氏が同月に会長職を引き継いだ。石原派への衣替えに伴い、石原氏をライバル視していた甘利明氏らが退会した。山崎氏は最高顧問として今も影響力を保っている。
石原氏は行政改革担当相や幹事長など要職を歴任、12年9月の総裁選では安倍晋三氏らに敗れた。所属議員数は、旧山崎派の最盛期には約40人いたが、15年4月現在、十数人の小所帯で、入閣ゼロ。石原氏の求心力低下は否めず、勢力回復は見通せていないのが現状だ。
・山東派(正式名称・番町政策研究所、会長・山東昭子)
故三木武夫元首相が率いた三木派が起源。会長だった河本敏夫元国務相が1996年に政界を引退後、会長を置かない集団指導体制が続いた。2001年から高村正彦元外相が会長を務めていたが、12年10月、高村氏が執行部入りし派閥を離脱したため、大島理森前副総裁が会長に就任し39 政 党た。大島氏が15年4月、衆院議長に就任したのに伴い、山東昭子元参院副議長が後任会長に就いた。
15年4月現在、総勢9人。影響力拡大に向けて麻生派との合流構想もくすぶっている。
・甘利グループ(正式名称・さいこう日本) 山崎派を退会した甘利明氏を中心に約20人の議員が2011年6月に結成した。派閥とは位置付けておらず、派閥に所属したままでの重複参加を認めている。甘利氏の将来の総裁選出馬をにらんだ動きと見る向きもある。15年4月現在、30人超が所属している。
同グループは①国民の信頼を回復するための政治を「再考」②東日本大震災から「再興」し、日本経済を「再興」③世界に誇れる「最高」の日本文化、製品を世に送り出す④「最高」の日本を創る―ことを掲げている。
・谷垣グループ(正式名称・有隣会)
野党時代の2012年10月、前総裁の谷垣禎一氏が、所属していた古賀派を離脱し、側近議員ら15人とともに結成した。再選を目指した同年9月の総裁選で、古賀誠元幹事長の協力を得られなかったことなどを受け、たもとを分かった。15年4月現在、総勢31人。谷垣氏は顧問。主な所属議員は川崎二郎元厚労相、逢沢一郎前衆院議院運営委員長、中谷元・防衛相、佐藤勉国対委員長ら。谷垣氏らは派閥ではなく「政策勉強会」と位置付けており、他派閥からの参加議員もいる。
谷垣氏は12年12月に発足した第2次安倍内閣に法相として入閣。14年9月の党役員人事では幹事長に就任した。側近議員の中には、同グループを支持基盤に谷垣氏の総裁返り咲きを目指す考えもあるが、実現に向けた戦略は描けていない。
・無派閥連絡会(石破グループ)
2012年9月の総裁選で石破茂氏を推した無派閥議員を中心に、13年1月に発足した。15年4月現在、山本有二、鴨下一郎両氏ら閣僚経験者を中心に計約40人が名を連ねる。石破氏は顧問。
12年総裁選の安倍晋三首相との決選投票で国会議員票が伸び悩み敗北した経験から、将来の石破氏出馬に備えて支持議員を確保しておくのが狙い。石破氏は「派閥ではなく、情報交換の場だ」としているが、党内からは「事実上の石破派」とみなされている。他の派閥からの離脱組などが混在する「寄せ集め集団」のため、いざ決戦の時にどこまで結束を維持できるか、不安視する声もある。
14年9月の内閣改造・党役員人事では、当時幹事長だった石破氏に安倍首相が入閣を要請。同連絡会内は「応じるべきだ」「無役となり、15年総裁選に備えた方が得策だ」と意見が分かれた。結局、石破氏は地方創生担当相として入閣したが、「主戦論」を訴えた一部議員は反発。石破氏の求心力低下が指摘された。
【初の選挙】(1956・4・5)緒方竹虎の急死の結果、鳩山一郎が圧倒的多数で初代総裁の座を射止めた。
【2・3位連合】(56・12・14)第1回投票1位の岸信介に40政 党対し、2位の石橋湛山と3位の石井光次郎が「2・3位連合」を組み、決選投票は7票差で逆転して石橋総裁が実現。
【禅譲】(57・3・21)病気退陣した石橋が、外相の岸を後継者に指名。
【交代密約】(59・1・24)岸は「次期総裁に大野伴睦を推す」と「密約」、反主流派の松村謙三を抑えて再選された。
【官僚対党人】(60・7・14)60年安保騒動で辞任に追い込まれた岸の後、池田勇人、石井、藤山愛一郎、大野、松村の5人が立候補の意向を表明、乱戦の様相だったが大野、松村が立候補を取りやめ、官僚派対党人派の決戦となった。第1回投票で3位だった藤山は決選投票で、1位の池田支持に回り、官僚派勝利。
【批判票】(62・7・14)佐藤栄作の出馬断念で池田が再選されたが「池田批判票」として大量の白票、無効票が出た。
【一本釣り】(64・7・10)池田3選断念を迫る佐藤と池田との対決となり、第1回投票で池田は過半数をわずか4票上回る際どい勝利だった。2派、3派からカネをもらう「ニッカ」「サントリー」の隠語が横行した。
【総裁指名】(64・12・1)がんに倒れた池田が、次期総裁に佐藤を指名。池田の指名を期待していた河野一郎は無念の涙。
【黒い霧】(66・12・1)政界を汚職疑惑が覆い、佐藤が藤山、前尾繁三郎を抑えて再選されたものの、批判票が3分の1を上回った。
【新勢力台頭】(68・11・27)佐藤が3選されたが、批判票も200票を超えた。佐藤を支える田中角栄、福田赳夫が競い合う一方、前尾派内で大平正芳が力を持ってくるなど、ポスト佐藤をうかがう新勢力が台頭した。
【初の4選】(70・10・29)佐藤が三木武夫を抑えて4選。これを機に党内情勢は田中、福田の角福を軸にポスト佐藤に向けて一斉に走り出した。
【角福戦争】(72・7・5)第1回投票は田中、福田、大平、三木の順。決選投票で大平、三木と出馬断念した中曽根康弘の支持を受けた田中が福田を圧倒。億単位のカネが動き、史上空前の金権選挙といわれ、その後も「角福怨念の戦い」が続いた。
【椎名裁定】( 74 ・12・4)金脈批判で退陣した田中の後継選びは混迷、調整役の副総裁椎名悦三郎が「神に祈る気持ちで」三木を推す裁定を下して収拾、三木は「青天のへきれき」と驚いてみせた。
【三木降ろし】(76・12・23 )ロッキード事件の嵐の中で「三木降ろし」が吹き荒れ、戦後初の任期満了に伴う衆院選の大敗で三木は退陣を余儀なくされた。反三木派の挙党協(挙党体制確立協議会)を背景にした大平、福田の大福提携が実を結び、後継には福田がすんなり選ばれた。
【初の予備選】(78・12・1)全国150万人の党員、党友による総裁予備選を初めて実施。予想を覆して大平が福田、中曽根、河本敏夫を抑えて1位となった。福田は「天の声にも変な声がある」と未練を残しながらも本選挙を断念、総裁の椅子を明け渡した。予備選は有権者千人について1点の割合で各都道府県に持ち点を与え、各都道府県で1位と2位の候補に得票比で持ち点を配分する方式。持ち点の上位2人が国会議員による決選投票に臨むことができることになっていた。
【遺産相続】(80・7・15)自民党の内紛で内閣不信任案が可決され、大平は初の衆参同日選に打って出たが、選挙の最中急死した。自民党が圧勝、後継に大平派の大番頭だった鈴木善幸が急浮上、大平の遺産を相続し、党内融和に努めた。
【田中軍団】(82・11・25)鈴木退陣表明を受けた後継調整工作は、鈴木、福田らの徹夜協議もむなしく失敗し、2回目の予備選に突入。「田中軍団」の全面支援を受けた中曽根が過半数を獲得。河本、安倍晋太郎は本選挙を辞退した。中川一郎は4位で落選。このときの予備選は党員の得票を単純に合計して上位3人に絞り、国会議員による本選挙を行うとしていた。
【二階堂擁立】(84・10・31)野党も巻き込んで副総裁二階堂進を中曽根の対抗馬に立てようという「二階堂擁立工作」が土壇場で表面化したが、田中が強く反対し挫折。中曽根が無投票で再選された。
【任期延長】(86・9・11)2度目の衆参同日選で大勝をもたらした中曽根が、党則改正により「1年間の任期延長」を両院議員総会で認められた。
【中曽根裁定】(87・10・31)安倍、竹下登、宮沢喜一のニューリーダー3人の争いとなり「安竹」の8時間会談などを経て最終的には中曽根裁定に委ねられ、中曽根は竹下を指名した。
【緊急避難】(89・6・2)リクルート事件で退陣表明した竹下は伊東正義を担ごうとしたが失敗。若手・中堅議員が山下元利擁立に動いたが果たせず、派閥力学で宇野宗佑が選出された。
【短命総裁】(89・8・8)参院選で過半数割れし、宇野はわずか2カ月で退陣。海部俊樹、林義郎、石原慎太郎が立候補。林を支持した宮沢派以外が推した海部が当選。
【竹下派支配】(91・10・29)政治改革の挫折で海部が退陣。宮沢が渡辺美智雄、三塚博を抑えて当選した。最大勢力竹下派幹部の小沢一郎が各候補を「面接」するなど、竹下派支配が浮き彫りに。このときの公選は従来の党員による予備選と国会議員による本選挙を一本化した。各都道府県には党員数に応じて1〜4票の「持ち票」を配分、それぞれの都道府県での最多得票者にその全持ち票が与えられ、これに国会議員による投票数を合算して当選者を決めた。
【初の野党総裁】(93・7・30)自民党分裂直後の衆院選敗北の責任を取って宮沢が退陣、河野洋平が渡辺を破って当選。直後の特別国会で非自民勢力の細川政権が誕生、自民党は初めての野党に。
【勝敗度外視】(95・9・25)自民党は社会党、新党さきがけと連立を組み政権復帰したが、参院選で低迷。河野は再選を目指したが、党内基盤が弱く、足元の宮沢派も大半が橋本龍太郎支持となり出馬断念。大勢が決した中で「公選が必要」との声で小泉純一郎が勝敗を度外視して名乗りを上げた。党所属国会議員(1人1票)と、3年間党費・会費を継続して納めた党員・党友(1万人で1票)により単記無記名で投票された。
【派閥流動化】(98・7・24)参院選大敗の引責で橋本が退陣。最大派閥会長の小渕恵三のほか、小渕派を飛び出した梶山静六と、三塚派の小泉の3人が立候補、宮沢派と旧渡辺派内山崎拓グループの支持も得た小渕が後継に。
【しこり】(99・9・21)無投票で小渕再選とみられていた中、宮沢派を継承した加藤紘一、旧渡辺派から独立、派閥を結成した山崎が立候補した。下馬評通り小渕が大勝したが、しこりは消えず、小渕派は加藤を敵視。「加藤の乱」の遠因となった。
【5人組】(2000・4・5)小渕が脳梗塞による突然の入院で退陣。後継者選びは官房長官の青木幹雄と党内実力者ら5人で協議し、幹事長の森喜朗に電光石火で決定した。
【小泉旋風】(01・4・24)森退陣を受け、小泉、橋本、麻生太郎、亀井静香が立候補。返り咲きを目指す最大派閥会長の橋本が優勢とみられたが「自民党を変える、日本を変える」と訴えた小泉が党員・党友による予備選で圧勝。亀井は本選を辞退して小泉支持に回り、小泉が総裁に就任した。
【無風】(01・8・10)参院選での大勝を受け、9月だった総裁選を前倒しして実施。小泉以外に立候補者はなく、両院議員総会で無風のまま再選された。
【派閥分裂】(03・9・20)現職の小泉が過半数(329票)を大きく上回る399票を獲得し亀井、元運輸相の藤井孝男、元外相の高村正彦を大差で破った。最大派閥の橋本派が小泉支持、藤井支持に分裂。同派の動きは自民党の派閥の溶解を象徴した出来事だった。
【真夏の雪崩】(06・9・20)官房長官の安倍晋三が国会議員票、党員・党友票を合わせた過半数(352票)を大きく上回る464票を獲得し、外相の麻生、財務相の谷垣禎一を破った。元官房長官の福田康夫を擁立する動きもあったが、福田が不出馬を決めたことから、各派閥が一気に安倍支持を打ち出す雪崩現象を生んだ。
【初の親子総裁】(07・9・23)安倍の突然の退陣で「予定外」の総裁選となった。福田が国会議員票254票、地方票76票の計330票を獲得。計197票だった幹事長の麻生を破り、父親の赳夫に続く初の親子2代の総裁(首相)となった。だが麻生が「派閥談合」批判や個人的な人気から地方票を中心に予想以上に善戦。総裁選でさえ締め付けられない派閥の弱体化をあらためて印象づけた。
【漫画オタク】(08・9・22)政権運営に行き詰まった福田の辞任で、再び1年ごとの総裁選となったことに「首相たらい回し」と批判が高まった。「漫画好き」で知られ、秋葉原の若者など一部の国民から熱狂的に支持される麻生が、衆院選での集票力を見込まれ351票を集め大勝。特に地方票は95%の票を獲得、経済財政担当相の与謝野馨、元防衛相の小池百合子、元政調会長の石原伸晃、元防衛相の石破茂に圧勝した。
【2度目の野党総裁】(09・9・28)衆院選大敗で党勢立て直しが急務とされる中、ベテラン対若手の構図となった。ベテランの元財務相の谷垣が計300票を集め、元法務副大臣の河野太郎、元外務政務官の西村康稔に大差で勝ったが、党員・党友による地方票の投票率は同様の投票方法をとった06年に比べ15㌽も下回り、党員の関心の低さが浮き彫りとなった。
【逆転勝利】(12・9・26)地方票と国会議員票を合わせた第1回投票は前政調会長の石破、元首相の安倍、幹事長の石原、元外相の町村信孝、政調会長代理の林芳正の順。国会議員による決選投票で安倍が108票を獲得、石破の89票を上回り、逆転勝利した。決選投票になったのは40年ぶり4回目。2位候補による逆転勝利は56年ぶり。安倍の総裁選出は06年9月以来2度目で首相、総裁経験者の「再登板」は初めて。
・政策決定の流れ
政府提出法案への賛否や対案など議員提出法案について、まず政務調査会の部会が検討。原案通りか、修正した上で了承した後、政調審議会に諮られる。政調審議会が了承すると、総務会に報告。総務会で了承されれば自民党として正式に了承したことになる。自民党では、政府提出法案については政調審議会、総務会が了承しない限り国会への提出を認めなかったが、小泉内閣は2002年、郵政公社関連法案と5増5減の公選法改正案を党の事前承認抜きに国会に提出した。
テーマや法案によっては、部会ではなく、別に設けられている調査会や委員会で実質的に議論する場合がある。この場合はその委員会が了承した後に部会に提出され、部会は形式的に了承、その後は通常の手続きを経ていく。複数の部会が合同で議論するケースも多い。この場合も合同部会で了承後、政調審議会に諮られる。部会、政調審議会、総務会には法案をまとめた府省庁もしくは議員が出席し、法案の内容を説明する。
議論が対立して了承が得られない場合は「部会長一任、預かり」「政調会長一任、預かり」という形を取り、上部機関に持ち込むケースもあるが、総務会では必ず了承を得ることが必要とされている。
府省庁は法案をまとめる過程で、族議員の幹部クラスや部会長らと接触し、法案への感触を探る「根回し」を行う。
・部会
省庁に対応して設置。2015年4月現在、以下の13部会がある。多くの場合、自民党本部で朝、開かれる。省庁が資料を持って説明にくる。配布物は宝の山。他部が担当している案件もあるので、連絡を緊密にする。
内閣→内閣府 国防→防衛省 総務→総務省 法務→法務省 外交→外務省 財務金融→財務省 文部科学→文部科学省 厚生労働→厚生労働省 農林→農林水産省 水産→農林水産省 経済産業→経済産業省 国土交通→国土交通省 環境→環境省・政調審議会 政務調査会の最高意思決定機関。法案をめぐって激論が交わされたこともあったが、最近は提出された法案を淡々と了承する傾向が強い。政調会長、副会長らが出席する。
・調査会、委員会
部会が省庁別に縦割りになっているのに対し、調査会は税制など個別の政策課題ごとに設置されている。中堅・若手中心の部会と対照的に、会長、副会長、顧問などに族議員の実力者が名を連ね、政策決定に力を持っていたため「責任が不明確」との批判が出ている。調査会は、税制調査会、安全保障調査会、選挙制度調査会、国土強靱化総合調査会などが代表的。各課題についてはそれぞれの調査会の了承が絶対条件で、実質的な決定機関となる。 委員会は複数の省庁にまたがる中長期的な問題に関する「意見交換会」的な傾向が強く、調査会のような実質的決定権を持つケースは少ない。
時の政調会長が問題を短期的に決着させる意思をもって「特別調査会」「特別委員会」を設置することがある。2015年には、財政再建を検討する「財政再建に関する特命委員会」が設けられた。
・連立政権での政策決定
自公両党の政調会長、政調会長代理らで構成する「与党政策責任者会議」で、与党としての政策調整を行っている。個別の政策テーマに関しては、同会議の下に与党プロジェクトチームを設置し、実務者レベルでの協議を実施するケースもある。ただ、政治判断を要する重要政策課題では、自公両党の「幹事長会談」「幹事長・政調会長会談」「幹事長・政調会長・国対委員長会談」などが節目に開かれる。幹事長・国対委員長会談(通称・2幹2国)は、国会開会中は、毎週水曜日朝、ホテルオークラで開かれることが多い。
・主な族議員
族議員は関係の省庁や国会、党での役職を複数経験し、政策決定に影響力を行使する与党議員。業界と省庁とのパイプ役を果たし、利害が対立するときは調整役を務める。非公開の「インナー」で協議することも。行政では、閣僚や副大臣、政務官、国会では常任委員長、党で部会長などのポストを経験している。(敬称略)
建設=二階俊博、金子一義、山本有二
農水=大島理森、森山裕、西川公也、吉川貴盛、林芳正
商工=甘利明、二階俊博、額賀福志郎
運輸=二階俊博
税制・財務=野田毅、高村正彦、伊吹文明、額賀福志郎、林芳正、宮沢洋一
厚労=川崎二郎、丹羽雄哉、伊吹文明、鴨下一郎、田村憲久、尾辻秀久
文教=大島理森、河村建夫、渡海紀三朗、塩谷立、遠藤利明、中曽根弘文
郵政=川崎二郎、佐田玄一郎、山口俊一
自治=菅義偉
法務=保岡興治、高村正彦
外交=高村正彦、麻生太郎
防衛=石破茂、中谷元、浜田靖一、岩屋毅、今津寛、江渡聡徳
・旧民主党結成
自民党を離党して新党さきがけに参加した鳩山由紀夫代表幹事は船田元・新進党総務会長代理と「鳩船新党」を模索したが、1996年4月につぶれた。その後、弟の鳩山邦夫新進党広報企画委員長らと新党結成を進め、9月28日、社民、さきがけ両党の離党者を中心に旧「民主党」を結成した。当初は鳩山、菅直人両氏の「2人代表制」。武村正義さきがけ代表や村山富市社民党党首は合流に前向きだったが拒否し、「排除の論理」と騒がれた。97年9月に菅代表―鳩山幹事長の1人代表制に移行した。
・新民主党結成〜民由合併
最大野党だった新進党から、1996年12月に羽田孜元首相らが離党し「太陽党」を結成。97年12月には離党した細川護熙元首相らが「フロムファイブ」を旗揚げした。同月、新進党は解党。党首だった小沢一郎氏率いる「自由党」、衆院旧公明党の「新党平和」、旧民社党の「新党友愛」、鹿野道彦元総務庁長官らの「国民の声」、参院旧公明党の「黎明クラブ」、小沢辰男元厚相らの「改革クラブ」に分かれた。
98年1月、旧民主党、新党友愛、国民の声、太陽党、フロムファイブ、民主改革連合の野党6党が統一会派「民主友愛太陽国民連合(民友連)」を結成。この後、国民の声、太陽党、フロムファイブの3党が合流した新党「民政党」を経て4月27日、旧民主党、民政党、新党友愛、民主改革連合が合流した新「民主党」が誕生した。初代執行部は菅代表―羽田幹事長。衆院93人、参院38人の計131人で野党第1党。
基本理念として「『生活者』『納税者』『消費者』の立場を代表し『市場万能主義』と『福祉至上主義』の対立概念を乗り越え、自立した個人が共生する社会を目指し、政府の役割をそのためのシステムづくりに限定する『民主中道』の新しい道を創造する」と掲げた。「政権交代可能な政治勢力の結集をその中心となって進め、国民に政権選択を求めることにより、この理念を実現する政府を樹立する」と宣言した。
98年7月、初の国政選挙となった参院選は、改選議席18を27に伸ばして快勝。橋本龍太郎首相退陣を受けた参院の首相指名選挙では菅氏が指名された。同年の金融国会では金融再生法の野党案を丸のみさせたが、菅氏は「金融問題を政局に絡めるつもりはない」と発言。小沢一郎党首率いる自由党は野党共闘から離脱、翌99年1月に自自連立政権が発足した。
2002年9月、鳩山由紀夫代表は3選を果たし、立候補表明後に出馬を見送り自らの支援に回った中野寛成副代表を幹事長に起用した。しかし党内若手らが「論功行賞」などと猛反発。10月の衆参統一補欠選挙も7戦1勝と惨敗した。小沢氏と進めた新党構想も性急すぎると批判を浴び、12月に辞任した。同月、熊谷弘前副代表ら5人が離党し、保守党議員らとともに保守新党を結成した。
03年7月、鳩山氏の後任の菅代表は小沢氏とあらためて協議し両党合併に合意。9月、正式に合併が実現した。11月の衆院選では本格的な「マニフェスト選挙」を仕掛け、民由合併効果もあって、解散前の137議席を177議席に伸ばした。
04年春、国民年金未加入問題で菅氏の未納が発覚、引責辞任した(後に社会保険事務所の手続きミスと判明)。後任を受諾した小沢氏自身も未加入期間があったとして辞退。岡田克也幹事長が無投票で代表に選出された。
・郵政選挙で惨敗〜ねじれ国会へ
2005年9月の郵政民営化を争点にした衆院選で、解散時の175議席から113議席と激減。特に東京、南関東、近畿など都市部で大敗した。岡田氏は退陣し、松下政経塾出身で43歳の前原誠司代表が誕生した。
06年2月、永田寿康衆院議員がライブドア事件関連で武部勤自民党幹事長を追及したが、根拠となるメールが偽情報と判明。永田氏は議員辞職し、前原氏も代表を辞任。後任に小沢氏が就任した。
07年7月の参院選は年金、子育て、農業を3本柱に掲げ、32の改選議席を過去最高の60議席に伸ばして大勝。非改選議席を合わせ109議席の参院第1党に躍進した。参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」となり、江田五月氏が参院議長に就任したほか、議院運営、外交防衛、厚生労働、農林水産などの主要委員長ポストを獲得。10月には国民新党と統一会派を組み、過半数(122議席)目前の119人(江田議長を除く)の勢力に拡大した。
10月30日と11月2日の2回、小沢氏は福田康夫首相と会談、自民、民主両党の大連立構想が浮上した。だが役員会で反対が相次ぎ、頓挫。小沢氏は代表辞任の意向を表明したものの、2日後に辞意を撤回し、両院議員総会で続投が承認された。
この後、民主党は対決路線を強化し08年1月、インド洋での海上自衛隊の給油活動を再開させる新テロ対策特別措置法案を参院で否決。3月末には揮発油税の暫定税率維持を盛り込んだ税制改正法案を採決せず、暫定税率を期限切れに持ち込んだ。国会同意人事の日銀正副総裁人事でも政府提案をたびたび不同意にした。6月には、他の野党とともに福田首相の問責決議案を参院に提出し、現行憲法下で初めて可決。福田氏は9月に退陣した。
4月の日銀人事で政府案に賛成するなど執行部方針に反旗を翻した渡辺秀央、大江康弘両参院議員らが8月、新党「改革クラブ」を結成した(姫井由美子参院議員は離党届を提出したが、撤回)。
09年3月、準大手ゼネコン西松建設の裏金をめぐる事件を捜査していた東京地検特捜部は、違法な企業献金を受け取った疑いが強まったとして、政治資金規正法違反容疑で小沢代表の公設第1秘書で資金管理団体「陸山会」の会計責任者ら3人を逮捕。小沢氏は大型連休明けの5月に辞任した。
代表選は鳩山氏が124票を獲得し、95票の岡田氏を破り新代表に就任。7月12日投開票の東京都議選で第1党に躍進し、自民、公明両党を過半数割れに追い込んだ。
一方で鳩山氏も「政治とカネ」問題が発覚。鳩山氏は6月末に記者会見して政治資金収支報告書の虚偽記載を認め、件数は05〜08年の4年間で約90人、193件、総額2177万8千円に上ることを明らかにした。
8月30日投開票の衆院選で、民主党は選挙前の115議席から大幅に増やして308議席を獲得し、戦後初めて本格的な政権交代を実現した。
・政権交代と鳩山退陣
2009年9月16日、鳩山代表は衆参両院本会議で第93代、60人目の首相に選出され、民主、社民、国民新3党の鳩山内閣が同日夜、発足した。初閣議で、本当の国民主権実現、内容の伴った地域主権を政策の2本柱にすることを決定。鳩山首相は国家戦略局の原型となる「国家戦略室」設置を指示。行政刷新会議設置や事務次官会議廃止、国家公務員の天下りや渡りのあっせんの全面的禁止も確認した。
しかし、「政治とカネ」問題と沖縄県の米軍普天間飛行場移設問題が政権を苦しめた。鳩山氏の収支報告書虚偽記入問題で、東京地検特捜部は12月、政治資金規正法違反の罪で経理担当だった元公設第1秘書を在宅起訴、会計責任者を務めていた元政策秘書を略式起訴した。鳩山氏本人は嫌疑不十分で不起訴となった。鳩山氏が実母から巨額の資金提供を受けていたことも判明。02年からの7年間で12億円を超え、贈与に当たるとして国税当局に修正申告した。
小沢氏に関しては、資金管理団体「陸山会」の土地購入で04年の政治資金収支報告書に虚偽記入したとして、東京地検特捜部が10年1月、政治資金規正法違反容疑で元私設秘書の石川知裕衆院議員を逮捕。小沢氏は事情聴取を受け不起訴となったが、検察審査会は4月に「起訴相当」と議決した。検察が再度不起訴としたのに対し、検察審査会は9月にあらためて起訴相当の議決をした。
普天間問題は迷走の揚げ句、名護市辺野古地区のキャンプ・シュワブ沿岸部に先祖返り。日米両政府は10年5月に合意、鳩山氏は社民党党首の福島瑞穂消費者行政担当相を罷免して閣議決定した。社民党は連立政権を離脱した。
「政治とカネ」、普天間問題で内閣支持率が低下した鳩山首相は6月に退陣。「脱小沢」路線を掲げた菅氏が両院議員総会で291票を獲得、129票の樽床伸二衆院議員を破って代表に就任、6月8日に菅内閣が発足した。
・参院選惨敗と菅再選
菅首相は「元気な日本を復活させる」をキャッチフレーズに「強い経済、強い財政、強い社会保障」を一体として実現する方針を表明。参院選マニフェスト発表記者会見で「消費税10%」に言及した。しかし、これが唐突な消費税増税論と国民に受け止められ、2010年7月の参院選は改選前の54から44議席へと激減。参院は再び野党が多数を握る「ねじれ国会」となった。
9月の代表選は菅、小沢の両氏が対決。党員・サポーター参加の02年代表選以来の本格的選挙となった。党員・サポーター票で圧倒した菅氏が計721ポイントを獲得し、再選された。小沢氏は国会議員票で激しく迫ったが、計491ポイントにとどまった。
菅氏は新幹事長に岡田外相を起用。後任外相に前原国土党交通相、総務相に片山善博前鳥取県知事などを起用する第1次改造内閣を17日発足させた。しかし、9月の沖縄県・尖閣諸島付近の中国漁船衝突事件の対応などで批判を受け、支持率が急落。11月、参院で仙谷由人官房長官、馬淵澄夫国交相の問責決議が可決された。11年1月14日、事態打開のため仙谷氏らを交代させた上で、たちあがれ日本を離党した与謝野馨氏を経済財政担当相に起用する再改造を行った。
一方、小沢氏ら反執行部勢力は、3月11日の東日本大震災と東京電力福島第1原発事故への菅政権の対応を批判。自民党など野党が提出した内閣不信任決議案に同調する動きを見せた。菅氏は震災復興などに「一定のめど」が付けば退陣する意向を表明し、決議案の可決を回避。8月26日、正式に退陣表明した。
・野田内閣発足と衆院選敗北
菅内閣退陣に伴う民主党代表選は2011年8月29日に投開票が行われ、決選投票の末、社会保障財源のための消費税増税に積極的な野田佳彦財務相が、海江田万里経済産業相を破って新代表に選ばれた。9月2日、野田内閣が発足した。幹事長には小沢氏に近い輿石東参院議員会長が起用され、挙党態勢の構築を目指した。ただ一川保夫防衛相や山岡賢次消費者行政担当相が参院で問責決議を受けたほか、11年末には増税反対派議員が集団で離党届を提出するなど混乱が続いた。12年1月、岡田氏を副総理として入閣させる内閣改造を行い、3月には消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案を閣議決定した。6月に一体改革関連法案は衆院を通過したが、小沢氏や支持グループは大量造反し、新党「国民の生活が第一」を結成した。
野田氏は8月8日、同法案を成立させるため自公両党党首と会談し「近いうちに信を問う」と約束、同10日に同法は参院で可決、成立した。10月19日の民自公3党首会談で、解散の環境整備として公債発行特例法案の早期成立などを挙げ協力を要請したが、解散時期の明示をめぐり決裂した。自民が公債法案への協力姿勢に転じると、野田氏は11月14日の党首討論で、13年の通常国会で衆院定数削減の実現を確約することを条件に「11月16日解散」を表明した。解散前後も離党者は相次ぎ、09年衆院選で獲得した308議席は選挙前に230議席まで減った。12月16日投開票の衆院選では、逆風をはね返せず57議席にとどまり、計325議席を獲得した自公両党が3年3カ月ぶりに政権を奪還した。
・野党転落
2012年12月25日の両院議員総会で、海江田氏が馬淵氏を破って新代表に選出された。幹事長には細野豪志氏を起用し党の立て直しを急いだが、13年7月の参院選では結党以来最低の17議席で惨敗。細野氏は辞任した。海江田氏は続投したものの、党勢回復が見込めない中で党内に不満がくすぶり「海江田降ろし」の動きが活発化。14年9月、大畠章宏氏を交代させ、枝野幸男氏を幹事長に起用する役員人事を行い、沈静化を図った。同12月の衆院選は73 議席の微増にとどまった。海江田氏は野党第1党の党首として65年ぶりに落選、代表を辞任した。これに伴う代表選が15年1月に行われ、岡田、細野、長妻昭の3氏が出馬。決選投票で岡田氏が細野氏を破り、新代表に選出された。 党本部は東京都千代田区永田町1―11―1。03(3595)9988 党員約3万160人、サポーター約20万830人。地方議員は約1650人(14年6月末)。機関誌は月2回発行する「プレス民主」で、4万5千部(15年2月)
最高議決機関は党大会。大会代議員は所属国会議員および各県連の代表ら。代表が少なくとも年1回招集し、通常は1月に開催する。年間活動計画、予算・決算、規約の改正などを決定する。党大会に次ぐ議決機関は両院議員総会。 代表選は党大会、もしくは両院議員総会を開いて実施する。
党の最高責任者である代表には、これまでに菅直人、鳩山由紀夫、岡田克也、前原誠司、小沢一郎、野田佳彦、海江田万里の7氏が就任した(再登板も含む)が、任期途中で引責辞任するケースが多く「党内で代表の足を引っ張り合う」という党のイメージにつながっているとされる。
党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。代表は、両院議員総会が議決で開会を要請した場合は大会を招集しなければならない。
通常の党運営は常任幹事会、役員会で方針を決める。役員会メンバーは代表、代表代行、幹事長、政調会長、国会対策委員長、参院役員、男女共同参画推進本部長、総務委員長、選挙対策委員長、財務委員長、組織委員長、広報委員長、企業団体対策委員長、青年委員長、国民運動委員長。常任幹事会メンバーは役員会メンバーに常任幹事会議長、最高顧問、副代表、ブロック代表常任幹事らが加わる。役員会は通常、隔週月曜日、常任幹事会は隔週火曜日に開かれる。
このほか、国会対策の方針などを幹部が議論する会合が金曜朝にある。代表、代表代行、幹事長、参院幹部による「5者会」と、これに国対委員長、選対委員長、政調会長が加わる「8者会」で隔週ごとに行われる。
2006年に小沢氏が代表に就任して以降、「トロイカ」と称される小沢代表、菅代表代行、鳩山幹事長による「三役懇」が開かれ、党運営の方向性を決定した。07年参院選後は輿石東参院議員会長を代表代行兼任とし、三役懇メンバーに加わった。脱小沢路線を掲げる菅政権で、トロイカ体制は崩壊した。
党の政策や法案対応は原則、省庁に対応した部門会議で議論した上で、毎週火曜夕の「次の内閣」(ネクストキャビネット=NC)閣議で取りまとめる。 現在の主要政策は、2012年に政権から転落した衆院選で掲げたマニフェスト(政権公約)が基礎となっている。
12年マニフェストで民主党は「生活者」「働く者」「納税者」「消費者」のための政党と明記。「分厚い中間層」を取り戻すため、誰もに「居場所」と「出番」のある共生社会を目指すとした。09年の政権交代後に打ち出した「新しい公共」も引き継いだ。
主要政策では、民主党政権で決めた消費税の10 %への引き上げ、農業者戸別所得補償制度、2030年代原発稼働ゼロ方針は堅持。政権交代選挙での公約だった年金制度一元化・最低保障年金創設も掲げ続けている。
安倍政権発足以降は「アベノミクス」で格差が拡大したとして、女性や子どもの貧困対策など格差是正、雇用対策に力を入れている。
15年4月には、安全保障法制に関する党見解を取りまとめた。「専守防衛に徹する観点から、安倍政権が進める集団自衛権の行使は容認しない」とする一方、将来的に行使を容認する可能性は残した。
代表選は、国会議員のほか党員・サポーターらが参加できるケースがある。ポイント数の総計で争い、①各国会議員に2ポイント②地方自治体議員は全国集計し、計141ポイントをドント方式で候補者に配分③党員・サポーター票は都道府県単位で集計し、総支部数に応じ与えられたポイントにドント方式で配分―としている。国政選挙の公認予定者が決まっている場合、公認予定者にも投票資格が与えられる。過半数を獲得した候補がいない場合は上位2人による決選投票になり、国会議員が2ポイント、国政選挙の党公認予定候補者が1ポイントを持つ。
党員・サポーターが参加した代表選は2002、10、12、15年の4回。代表の任期は3年で、これまで代表が任期途中で欠けた場合は両院議員総会で代表を選出し、党員・サポーターの投票は任期満了時に限られていた。しかし党内で要望があり、14年9月に途中で欠けた場合も両院議員総会の承認があれば参加が可能になるよう党規約などを改正。15年1月の代表選で初適用となった。立候補できるのは原則として国会議員のみで、20人以上の国会議員の推薦人が必要。新代表の任期は就任3年目の9月末までとなる。
民主党のグループは細野グループを除いて重複入会が可能で、勉強会的な要素が強い。時流に合わせて軸足を動かす議員が多い。2012年衆院選、13年参院選、14年衆院選を経て国会議員数が約130人となったことで、各グループとも小規模化している。すべて政治資金規正法上の「政治団体」として届けている。( )内が届け出名称。
・前原グループ(凌雲会)
代表経験者の前原誠司氏が率いるグループ。枝野幸男、古川元久、福山哲郎、渡辺周、田嶋要、小川淳也の各氏ら。10年10月から会合を定例化した。15年1月の代表選では、出馬を模索した前原氏にメンバーの支持が集まらず、前原氏の求心力維持が課題となっている。約25人。
・野田グループ(花斉会)
野田佳彦前首相を中心に保守系の中堅、若手議員が集まる。花斉会とは「百花斉放」を略した名称。代表選などで一致結束することが多い。2008年の代表選では野田氏の出馬をめぐって亀裂が生じ、松本剛明、馬淵澄夫の両氏が退会した。武正公一、蓮舫、長浜博行、近藤洋介の各氏ら約10人。
・細野グループ(自誓会)
細野豪志氏を代表に、中堅・若手議員でつくる。原則として他の党内グループとの掛け持ちを禁止し、落選組に財政支援するなど派閥的な色彩が強い。2014年1月に政治団体として東京都選挙管理委員会に登録した。メンバーは黄川田徹、笠浩史、後藤祐一、榛葉賀津也の各氏ら14人。
・赤松グループ(新政治文化フォーラム)*通称「サンクチュアリ」
赤松広隆前衆院副議長を中心に、旧社会党出身者や自治労、情報労連などの労働組合を支持母体とする党内のリベラル系議員20人が集まる。横路孝弘、近藤昭一、輿石東の各氏ら。支持基盤の弱かった海江田万里前代表を支えた。2015年1月の代表選では政策などが近いとしてグループ外の長妻昭氏を支援。決選投票では岡田克也氏に投票し、岡田氏勝利に重要な役割を果たした。岡田新体制では近藤氏が幹事長代理として執行部入りするなど、存在感を示すことに成功した。
・民社協会
自動車総連、ゼンセンなど旧同盟系の連合組織の支援を受ける議員のグループで、党内では保守系に分類される。かつてはグループで代表選に候補者を出したが、近年は自主投票が増えている。選挙に比較的強いベテラン議員が多いのが特徴。川端達夫、高木義明、古本伸一郎、直嶋正行、小林正夫、柳沢光美の各氏ら。約15人。
・大畠グループ(素交会)
大畠章宏氏を中心としたグループ。2011年代表選で鹿野道彦氏を支持したグループが母体で、12年衆院選で鹿野氏が落選後、大畠氏が引き継いだ。政治理念はさまざまで結束は弱く、親睦会、勉強会的な色彩が濃い。篠原孝、生方幸夫、大島敦、松原仁、前田武志、増子輝彦、白真勲の各氏ら。約15人。
・菅グループ(国のかたち研究会)
菅直人元首相を支持するグループ。脱原発を志向し、左派系の議員が多い。江田五月、石橋通宏、荒井聡の各氏ら。約10人。
2014年9月、橋下徹大阪市長率いる「日本維新の会」と、江田憲司氏が代表を務める「結いの党」の合流により衆院42人、参院11人の計53人で結成された。結いの党は、野党再編を志向する江田氏が、渡辺喜美氏とともに創設したみんなの党を割る形で13年12 月に旗揚げした。日本維新内では、合流協議の過程で石原慎太郎氏ら旧太陽の党系メンバーを中心に江田氏に対する反発が強まり、橋下氏と石原氏が14年5月に会談して日本維新の分党を決定。石原氏らは「次世代の党」として独立した経緯がある。
中央集権・官僚主導からの転換を訴え、首相公選制や道州制導入など「憲法改正による統治機構改革」や、「既得権益を打破する徹底した規制改革」を通じた民間の自由競争促進を基本政策に掲げる。安全保障政策をめぐっては、集団的自衛権行使に前向きな旧日本維新と慎重な旧結いの党の不一致が指摘されたが、「自衛権の再定義」により行使を事実上限定的に容認する方針で折り合った。原発については、再生可能エネルギーの普及などを通じて依存を減らし、最終的に「フェードアウト」を目指す立場を取っている。
14年12月の衆院選は、国会議員定数や公務員人件費削減などの「身を切る改革」を公約の柱に位置付けて戦い、公示前に比べ1議席減の41議席を獲得。民主党に次ぐ野党第2党の座を守った。直後の特別国会に、国会議員歳費と衆院議員定数をそれぞれ3割削減し、国会議員に支給される文書通信交通滞在費の使途公開を義務付けるための関連法案を提出。15年1月からは、文書通信費の所属国会議員による使途の自主公開を始めた。
結党時には、橋下氏と江田氏がそろって共同代表に就任した。しかし、衆院選直後に橋下氏が「大阪都構想実現のため統一地方選に集中する」として共同代表を辞任。江田氏が単独の代表となった。橋下氏の右腕とされる松井一郎大阪府知事も幹事長を辞し、松野頼久国会議員団会長が後任に就いた。橋下氏と松井氏は15年5月現在、最高顧問と顧問をそれぞれ担っている。
自民党に代わり得る「政権担当可能な改革勢力の結集」を綱領に明記し、民主党を巻き込んだ野党再編の実現を目指している。ただ、江田氏は15年1月、「党の足元を見つめ直して基盤を強化する」として、5月の住民投票までは再編に向けた動きを封印する考えを表明した。
大阪都構想は、15年5月17日の住民投票で否決された。橋下氏は市長を任期いっぱい務めた後、政界を引退すると表明。江田氏も責任を取り辞任した。
党の旗印である大阪都構想と、「橋本」「江田」の二枚看板を失った党は、5月19日の両院議員総会で、幹事長だった松野氏を新代表に選出。松野氏は柿沢未途政調会長を幹事長に据えた。松野氏は野党再編に意欲を示しつつも、当面は党の再生を優先させる考えを表明。安倍政権とも「是々非々」で対応していく考えを示した。
届け出上の党本部を大阪に置く一方、東京にも本部を設けている。 大阪本部 大阪市中央区島之内1―17―16 三栄長堀ビル。06(4963)8800 東京本部 東京都千代田区永田町2―9―6 十全ビル101。03(3595)7801
創価学会を支持母体として1961年11月に発足した公明政治連盟が前身。64年11月、参院議員15人と地方議員で公明党を結成した。67年衆院選で25議席を獲得して衆院に進出し、55年体制下で保守でも革新でもない「中道政治」を目指した。
93年に細川連立政権の一翼として初めて政権に参加。羽田政権崩壊後は「公明」を結成した一部の参院議員と地方議員を除き、新進党結党に加わった。新進党解党後、旧公明党系衆院議員は新党平和を結成、98年11月に新党平和と公明が合流し、新「公明党」が誕生した。
99年10月に自民、自由両党の連立政権に参加。2003年11月に自民党と保守新党が合併し、自民党と公明党の自公連立時代に入った。しかし09年8月の衆院選で、太田昭宏代表ら小選挙区に立候補した8人全員が落選し野党に転落した。
12年衆院選で自民党とともに政権を奪還。14年衆院選では、小選挙区比例代表並立制で初の衆院選が行われた96年以降、過去最多の35議席を獲得した。
12年12月発足の第2次安倍内閣で、集団的自衛権行使について断固反対を主張していたが、自民党との激論の末、受け入れた。行使を容認した閣議決定が行われた14年7月1日、山口那津男代表は記者会見で「平和主義という憲法の柱を堅持し、憲法9条の下で許される自衛の措置の限界を示した。専守防衛は全く変わらず今後も貫かれる。従来の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性を確保した」と説明した。ただ支持者からは不満も少なくなかった。
結党50年を迎えた14年の全国大会で山口代表は「公明党は草創期以来、生命、生活、生存の人間主義を政治理念とする中道主義を貫いた」と強調。「時代の要請に柔軟に対応し、調和のとれた合意形成の軸となる」と宣言した。
党の最高議決機関は通例2年に1回開かれる全国大会。代表は選挙で選出され、任期は2年。山口代表は09年9月、衆院選敗北の責任を取って辞任した太田前代表の任期を引き継いで就任し、10年、12年、14年の代表選で再任された。代表は幹事長、政務調査会長、中央幹事会会長らを指名するほか、必要と認めるときは代表代行、副代表を指名する。大会から次の大会までの議決機関は中央幹事会。最高執行機関は代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長らで構成する常任役員会で、毎週木曜日の午前中に常任役員会、中央幹事会を開催している。
党本部は東京都新宿区南元町17。03(3353)0111 機関紙は公明新聞(日刊)約80万部。党員数は約41万人(14年)
1922年7月、非合法政党として創立。終戦後の45年12月、第4回党大会で再建した。2000年11月の第22回党大会で規約を全面改定し、理念として掲げていた「労働者階級の前衛政党」を削除、有事の際の「自衛隊活用容認論」を盛り込んだ大会決議を採択した。「21世紀の早い時期に民主連合政府を樹立する」との方針も打ち出し「現実・柔軟路線」への転換を印象づけた。
07年7月、党内に絶対的な権力を確立してきた宮本顕治元議長が死去した。1958年に書記長就任以来、旧ソ連、中国両共産党と一線を画す「自主独立路線」を明確化させ、半世紀にわたって指導的地位にあった宮本氏の死は一つの時代の区切りを象徴した。
09年8月の衆院選は、全小選挙区に候補者を擁立することは避け、民主党中心の新政権が誕生した場合は政策ごとに是々非々で対応する「建設的野党」路線を表明したが、新政権の「対米従属」などを理由に対決姿勢に回帰。国政選挙の獲得議席は12年12月の衆院選まで後退が続いた。
その後、「第三極」勢力の失速などを背景に政権批判票を取り込み、13年7月の参院選は改選3議席から8議席へ、14年12月の衆院選は8議席から21議席へ躍進した。20議席以上の獲得は00年以来で、沖縄1区では96年以来となる小選挙区勝利も果たした。「ゆるキャラ」を活用した広報戦略を展開するなど、「ソフト化」を印象づける取り組みも話題を呼んだ。
最高機関は党大会で、2〜3年に1回開かれる。規約では、中央委員会総会を1年に2回以上開くことが義務付けられている。14年1月の第26回大会で、約13年にわたり志位和夫委員長を支えた市田忠義氏が書記局長を退任し、山下芳生氏に交代した。15年1月の中央委総会では、次期国政選挙で「比例代表で850万票、得票率15%以上」の獲得を目指すとする新たな目標を決めた。
機関紙「しんぶん赤旗」の発行部数と党員数は、党大会ごとに公表される。26回大会時点での発行部数は約124万部、党員約30万5千人。党財政を支える「赤旗」の部数減や党員の高齢化などが課題となっている。 党本部は東京都渋谷区千駄ケ谷4―26―7。03(3403)6111
日本維新の会の分党に伴い、共同代表だった石原慎太郎元東京都知事を中心に2014年9月に結党大会を開いた。結党時のメンバーは平沼赳夫元経済産業相ら「たちあがれ日本」のベテラン議員と、山田宏元杉並区長や中田宏元横浜市長など「改革派」の衆参計23人。党首は平沼氏で、石原氏は最高顧問に就いた。「自立」「新保守」「次世代」の理念を掲げ、自主憲法の制定が党是。しかし、知名度不足もあり同年12月の衆院選では2議席しか獲得できず惨敗した。所属国会議員は衆院2人と参院6人の計8人にとどまる。現在は、新保守などの基本路線を堅持する一方で改革志向を色濃く打ち出すなど、みんなの党出身の松沢成文幹事長の下で路線を微修正している。 党本部は東京都千代田区永田町1―11―28 クリムゾン永田町ビル6階。03(3595)3555
1955年10月、左右両社会党が統一し社会党を結成。労働者勢力を糾合する「革新政党」として宮沢政権まで野党第1党のポジションにあり、自民党政権と対峙(たいじ)してきた。93年8月発足の細川連立政権に与党第1党として参画し、羽田政権では野党に転じたが、94年6月、自民党、新党さきがけとともに村山富市委員長を首相とする自社さ連立政権を発足させた。この時、「非武装中立」から「自衛隊合憲」に歴史的転換をした。96年1月、村山内閣総辞職後、党名を社会民主党に変更、土井たか子氏が党首に就いたが、多くの議員が民主党結成に加わり分裂。多くの労組も民主党支持に回り、10月の衆院選で惨敗し勢力が激減した。
野党に転じた98年以降、「市民勢力との連携」を掲げ、2000年6月の衆院選は議席を増やし一時、党勢を回復させたが、北朝鮮による拉致事件、辻元清美衆院議員の秘書給与詐取事件でダメージを受け、03年11月の衆院選で再度惨敗した。引責辞任した土井氏の後任の福島瑞穂党首は小泉政権に対抗する形で護憲路線を強化。06年2月の第10回党大会で「社会民主党宣言」を採択。「憲法の枠内」とした自衛隊を「明らかに違憲状態」として改編・解消を提唱、日米安保条約の平和友好条約への転換、「北東アジア非核化構想」も打ち出し、かつての非武装中立路線に事実上回帰した。
09年9月、民主党、国民新党との連立政権に参加したが、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題をめぐって「県外・国外移設」を強く主張。10年5月の日米共同声明を受けた政府方針への署名を拒否した消費者行政担当相の福島氏は鳩山由紀夫首相から罷免され、連立から離脱した。その後辻元氏が離党して民主党入りした。
任期満了に伴う12年の代表選は反福島派が候補者を擁立できず、無投票で福島氏の5選となった。ただ、国政選挙の連敗で党勢衰退にブレーキはかからず、新陳代謝も進まなかったため、14年の代表選には地方の不満を代弁する形で東京都豊島区議の石川大我氏が出馬。吉田忠智政審会長も出馬し、1996年に旧社会党から、社民党に党名変更して初めての選挙戦となった、自治労出身で国会議員である吉田氏が大差をつけて勝利した。吉田氏は石川氏ら地方議員や有識者もメンバーとした党改革推進本部を新設するなど党再建に注力したが、2014年の衆院選では現有2議席をかろうじて維持するにとどまった。16年の参院選では吉田氏と副党首の福島氏が改選を迎える。党員の減少や高齢化の中、党勢回復の打開策は見いだせていないのが実情だ。
党本部は東京都千代田区永田町2―4―3。03(3580)1171 機関紙は「社会新報」(週間)6万部(15年1月末)。党員数は約1万7千人(14年10月末)
消費税増税法案の衆院採決で反対し、民主党を除名された小沢一郎氏と支持グループの計49 人が2012年7月に結成した「国民の生活が第一」が前身。同12月の衆院選を前に、嘉田由紀子滋賀県知事(当時)が脱原発を掲げて結党した「日本未来の党」に合流した。しかし小沢氏と嘉田氏は党運営をめぐって対立、衆院選後に結党からわずか1カ月で分党した。小沢系議員が旧日本未来を存続させる形で、党名を「生活の党」に変更。13年1月の結党大会で、小沢氏の代表就任が決まった。
基本政策として、消費税増税法を廃止し増税を凍結、原発の再稼働・新設は認めないことなどを掲げた。14年12月の衆院選前には、小沢氏の側近で幹事長の鈴木克昌、国対委員長の小宮山泰子の両氏が離党、民主党に復党した。衆院選では議席を減らし、所属国会議員は衆参両院で4人となり、政党要件を失った。同月、無所属の山本太郎氏が入党、政党要件を再び満たし、政党名を「生活の党と山本太郎となかまたち」に変更した。15年1月、小沢、山本両氏の共同代表制となることを発表した。
党本部は東京都千代田区永田町2―12―8。03(5501)2200
2014年11月解党のみんなの党に所属していた無所属の松田公太氏ら参院議員4人と、次世代の党に離党届を提出していたアントニオ猪木参院議員の計5人が15年1月1日付で結成した。松田氏が代表と幹事長を兼任し、山田太郎氏が政調会長。猪木氏は最高顧問となった。他は井上義行氏が国対委員長、山口和之氏が広報委員長。15年1月20日には「日本初の、政策を国民と共に決定する政党である」と明記した党の綱領を発表した。党員は会員と呼ばれる。
「直接民主型政治」の実現を掲げたのが最大の特徴。国論を二分するような政策や、法案の賛否については、会員のインターネット投票を行い、所属議員は賛否の比率に応じた「割合投票」を行う。年に3〜4本を想定しており、仮に会員投票の結果が賛成60%、反対40%なら、5人の参院議員は国会で賛成に3票、反対に2票を投じる。その理由を「原発事故など政権公約で想定していない問題が生じた時に、国会議員だけで対応を決めていいのか」と説明している。
党員投票を行わない法案などの賛否に関しては党議拘束を設けないため、所属議員の賛否が割れることも頻発する。政策面ではみんなの党の政策を多く引き継いだ。小さな政府、自由経済、規制改革の実現を目指している。
3月17日に開催した初の党大会は東京・新宿駅東口の街頭で行った。初の会員投票は「日本を元気にする会は党名を変えるべきか」をテーマに実施し、党名変更賛成が48・2%、変更反対が51 ・8%だった。変更賛成が上回れば、15年通常国会閉会後に党名変更に踏み切る姿勢を見せていた。
党本部は東京都北区上十条2―25―14。
政党としての電話は登録されていない。
2010年4月、自民党を離党した舛添要一前厚生労働相を中心に参院議員6人で結成した。民主党を離党した渡辺秀央氏や無所属の荒井広幸氏らが08年に設立した改革クラブに舛添氏らが移籍した上で、名称を変更した。10 年7月の参院選では比例代表1議席しか確保できず、所属国会議員は代表の舛添、幹事長の荒井両氏となった。比例の得票率で政党助成法の政党要件は満たしている。14年1月、舛添氏が東京都知事選出馬にともない離党したため、荒井氏1人となった。同年の衆院選で比例東京ブロックに4人の新人候補を擁立したが、得票率は0・29%にとどまり幸福実現党を下回った。
党本部は東京都港区赤坂2―8―15 オリエントニュー赤坂202。03(6277)
第4章 法律の成立過程 (4)
国会に提出される法案は、各省庁が立案した内閣提出法案と議員立法に大別される。成立するのは圧倒的に内閣提出法案が多い。議員立法には、公選法改正案など議員の身分に関する法案のほか、超党派でつくる議連で起草される法案(カジノ法案など)、政党が自らの政策をアピールする法案などがある。
1 内閣提出法案
(1)作成
内閣提出法案は、担当各省庁の主幹担当課で作成する。①政府の政策決定②行政執行上の必要性が生じた③法解釈の明確化④審議会の答申―などが法案化の動機として挙げられる。閣議決定を経て国会に提出する。
(2)内閣法制局 法案作成段階から、緊密に連絡を取り合うのが内閣法制局だ。①憲法や他の法律との整合性、合法性②立法内容の社会的、法的妥当性③立法の意図が明確か④語句、用語の誤り―などに詳細な検討を加える。
(3)自民党政権の法案決定過程 自民党政権は「事前審査」により、党側が政府提出法案に対する事実上の拒否権を握る。根拠となるのは1962年2月に赤城宗徳自民党総務会長が「各法案提出の場合は閣議決定に先立って自民党総務会に連絡をすることを願う」と官房長官に要望した文書。閣議決定前に与党の審査、了承を得る段取りが盛り込まれた。各省庁は法案の骨子が出来上がると、与党でその分野に詳しい関係議員(かつては族議員とも呼ばれた)に説明し、意見を聴取する。法案作成後は自民党の部会、政策審議会、総務会の了承を得る。公明党でもほぼ同様の手続きがある。最終的に与党政策責任者会議での了承を経て、閣議決定に至る。
一方、2009年からの民主党政権では「政治主導」の考え方に基づき、閣僚ら政務三役(大臣、副大臣、政務官)が法案の起草段階から主導するとした。政策決定の内閣への一元化を掲げたことから当初、議員は担当の副大臣が主催する「政策会議」で意見を述べることしかできなかった。しかし、政策に関与できないことに議員から不満が相次ぎ、菅政権になって政策調査会が復活。総務や国土交通など政策分野ごとに「部門会議」が発足した。座長には各委員会の筆頭理事が就任、関係する副大臣も共同座長として会議に参加し、政府と党が一体となって議論する仕組みとなった。
(1)提出理由 議員立法は、以下のケースで検討される。
①国民の祝日など、国民生活に直結するもの
②地域振興
③災害対策
④議員や政党に関係する業界や団体の意向を反映するもの
⑤行政庁の所管の整理
⑥国会や議員の身分に関する法律の改廃
⑦政党がその政策をアピールするためのもの
⑧議員個人の問題意識
⑨内閣提出法案としてはなじまないもの
(2)法案作成 議員や政党は、各常任委員会にある調査室(各省庁からの出向者が多い)、国会図書館、または関係省庁の協力を得ながら、法案の原案を作成する。議員が作成するのは骨子や概要までで、衆参両院の法制局が法文化するケースも少なくない。
(3)各党内での手続き 法案は、各党内で定められた手続きを踏む。了承を得られれば国会に提出される。
(4)提出要件 法案提出先はその提出者が所属する院となる。衆院議員なら衆院、参院議員であれば参院となり、提出先を選ぶことはできない。 一般法案の場合、衆院は、提出者(1人以上)に20人以上の衆院議員、参院は提出者(1人以上)に10人以上の参院議員の賛同者が必要。予算を伴う法案になると賛同者が衆院では50人、参院では20人必要となる。
(1)付託 閣法、議員立法ともに、提出先となった院では、議長が委員会に付託することとなっている。提出先ではない院には「予備送付」する。ただし、野党が対決法案と位置付けるなどの重要法案は本会議で趣旨説明を行った後、委員会に付託することが多い。
(2)委員会審議 内閣提出法案は、担当省庁の閣僚や副大臣らが答弁に立つ。議員立法は趣旨説明も含めて議員が行い、議員同士の討論が展開される。野党側が提出した内閣提出法案への対案に、与党議員が問題点などを追及するという予算委員会などとは全く逆の光景もみられる
。(3)本会議 衆院は火、木、金、参院は月、水、金が定例日。付託された委員会の委員長が質疑の概要や委員会の採決結果などを報告。討論ののち、採決が行われる。予算案など本会議開催日に委員会採決が行われる場合、本会議直前に緊急上程されるケースもある。
(1)閣議決定 法律は、国会で議決があった時に成立するが、効力は公布によってはじめて生じる。成立した法は、内閣に送付され、閣議決定される。担当閣僚と首相が連署する。
(2)裁可・公布 内閣は天皇に奏上し、裁可を受ける。天皇は国事行為として、法律を公布する。官報には、奏上から30日以内に掲載される。
第5章 省庁 (3)
(1)日米関係 2012年12月に就任した安倍晋三首相は、民主党政権時代に「揺らいだ」と批判してきた日米関係の立て直しに着手。近年、米国の力の低下が指摘されているが、北朝鮮による核・ミサイル開発や中国による軍備拡張など、東アジアをめぐる安全保障環境を踏まえると、日米安保条約を基盤とした日米同盟が日本外交の基軸であることは間違いない。
安倍首相は13年2月、ワシントンのホワイトハウスでオバマ米大統領と初の首脳会談に臨んだ。首相は会談後の記者会見で「日米同盟の信頼、強い絆は完全に復活した」と強調した。民主党政権時代に迷走した米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題では、普天間飛行場は返還し、基地機能の一部を同県名護市辺野古に移設するとの日米合意に沿って作業を早期に進めることや、北朝鮮問題に断固として対処する方針で一致した。環太平洋連携協定(TPP)交渉については米国が強く主張する関税撤廃に例外があり得ることを確認した。これを踏まえ首相は3月、TPP交渉への参加を正式表明した。
10月には東京都内で外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)を開き、自衛隊と米軍の役割を定めた防衛協力指針(ガイドライン)を再改定することで一致した。14年10月に中間報告を決定し、安倍政権が閣議決定した集団的自衛権の行使容認を踏まえた協力を新指針に「適切に反映」させると明記。自衛隊の対米支援では地理的制約を外し、活動範囲や任務を飛躍的に拡大させる方針も打ち出した。日米両政府は14年末までに改定の完了を目指したが、15年春に先送り。日米両政府は4月27日、ニューヨークで2プラス2を開き、新たなガイドラインを決定。自衛隊と米軍の協力を地球規模に広げ、平時から有事まで「切れ目のない」連携を打ち出した。
オバマ氏は14 年4月、米大統領として18年ぶりに国賓待遇で来日した。安倍首相との首脳会談では、中国が領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島に関し、日米安保条約に基づく米側の防衛義務を会談に伴う成果文書に明記した。安倍首相は15年4月28日、オバマ氏とワシントンで会談。ガイドライン再改定を踏まえ、国際秩序の構築に向け日米同盟を強化することで一致した。TPP交渉の早期妥結を日米が主導する方針も確認した。安倍首相は日本の首相としての9年ぶりの公式訪問。翌29日には、同じく日本の首相として初めて、米連邦議会の上下両院合同会議で演説した。
(2)日中関係
東アジアの安定に向け、中国とどう向き合うかは日本外交にとって最重要課題の一つだ。中国は近年、海洋権益の確保を狙い、南シナ海と東シナ海で軍事的プレゼンスを強めている。東シナ海では沖縄県・尖閣諸島の領有権を主65 省 庁張。2012年9月の野田内閣による尖閣国有化以降、公船による尖閣周辺の日本領海への侵犯を繰り返しており、緊張状態が続いている。偶発的衝突の回避に向けた取り組みが急務となる中、中国が14年11月、北京でアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を主催したのに合わせ、安倍首相と中国の習近平国家主席は、関係改善に向けて会談した。会談以降、安全保障について意見交換する「日中安保対話」をはじめ、さまざまなレベルでの対話や協議が開かれるようになった。15年3月にはソウルで3年ぶりとなる日中韓外相会談が開催され、岸田文雄外相と王毅外相による日中外相会談も開かれた。4月22日には、インドネシアで開催された国際会議に合わせて安倍首相と習国家主席が会談。関係改善に向け、戦略的互恵関係を推進することで一致した。本格的な緊張緩和に向かうかどうかが注目される。中国は、南シナ海の南沙(英語名スプラトリー)諸島で岩礁埋め立てを進めており、周辺国との緊張が高まっている。
【尖閣情勢】
日本は1895年、無人島だった尖閣諸島を領土に編入し、第2次大戦後の米国統治を経て、実行支配を確立した。1968年に周辺での豊富な石油資源の埋蔵が学術調査で明らかになった後、中国が領有権を主張し始めた。中国は92年には国内法で尖閣諸島を「自国の領土」と明記。小泉内閣時代の2004年3月、中国人活動家7人が上陸したが、強制送還された。 12年9月の尖閣国有化に中国は激しく反発し、中国全土で反日デモが激化。緊迫感が増す中、東シナ海の公海上で13年1月、中国海軍フリゲート艦が海上自衛隊の護衛艦に射撃管制用レーダーを照射し、日本は厳重抗議した。
安倍首相は14年4月、オバマ米大統領との会談で尖閣諸島について日米安保条約に基づく米側の防衛義務があることを確認した。一方、5月、東シナ海の公海上空で自衛隊機が中国軍戦闘機の異常接近を受けた。中国の戦闘機が自衛隊機にこうした行動を起こしたのは初めてで、日本側に衝撃を与えた。6月にも同様の異常接近が発生した。
日中両政府は9月に双方の関係当局が東シナ海での危機管理や協力の在り方について話し合う「日中高級事務レベル海洋協議」を中国・青島市で開催。対話を継続する方針で一致した。11月の日中首脳会談では、防衛当局間の「海上連絡メカニズム」の早期運用開始に向け、実務者協議を進める方針を確認した。両政府は首脳会談に先立ち、尖閣情勢をめぐる見解の相違を認め、対話と協議を通じて不測の事態を避けることで一致したとの文書をまとめた。
【歴史認識】
安倍首相は13年12月、靖国神社を参拝した。現職の首相としては、06年に当時の小泉純一郎首相が参拝して以来7年ぶりだった。首相の参拝を求める保守層に配慮したとみられる。中国は東京裁判のA級戦犯が合祀されている靖国への首相や閣僚の参拝に反対しており、強く反発した。 尖閣情勢とともに、靖国神社参拝をはじめとする歴史認識の問題は両国間の最大の懸案となっている。14年11 月の首脳会談に先立ち両政府で合意した文書では、歴史認識に関し「両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた」と表現した。中国側は首相が靖国参拝をしないとの確約を求めたが、文書には盛り込まれなかった。
安倍首相が15年夏に発表する戦後70年談話についても、戦後50年の村山富市首相談話が明記し、戦後60年の小泉純一郎首相談話も引き継いだ「植民地支配と侵略への反省」をどこまで継承するかが課題となっており、内容によっては中国側の反発も予想される.
(3)日韓・日朝関係
韓国も日本外交における「最も重要な隣国」(外務省)だ。だが、2013〜14年に日中韓首脳会談は実施されず、日韓首脳が年に1回相互に訪問する「日韓シャトル外交」も12〜14年には行われなかった。日韓両国の対立が続いている。
従軍慰安婦問題をめぐる旧日本軍の強制性を認めた1993年の河野洋平官房長官談話について、作成にかかわった石原信雄元官房副長官は2014年2月、元慰安婦の証言を基に作成し、裏付け調査は行わなかったと証言した。政府は、談話作成過程の検証チームを設置する考えを表明し、韓国の反発を招いた。
日本政府は2014年6月、河野談話の検証結果を国会に報告。「談話の信頼性を傷つけるものではない」(岸田外相)と説明したが、韓国政府は理解を示さなかった。
10月には、ソウル中央地検が朴槿恵韓国大統領の名誉を毀損する記事をウェブサイトに掲載したとして加藤達也・産経新聞前ソウル支局長を在宅起訴し、対立が拡大した。
安倍晋三首相と中国の習国家主席が11月、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて北京で会談したこともあり、この日の夕食会で朴大統領が安倍首相と言葉を交わした。その後、朴大統領はミャンマーで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)プラス3首脳会議で、12年を最後に開かれていない日中韓首脳会談開催を提案。韓国側は、首脳会談の環境整備のため3カ国外相会談の年内開催に向けて調整したが、今度は中国側が難色を示した(実現したのは15年3月)。慰安婦問題では、14年12月に斎木昭隆外務事務次官がソウルを訪問し、韓国の趙太庸外務第1次官と協議したが、進展しなかった。
対北朝鮮関係では、日本人拉致問題の再調査について2014年5月に日本と北朝鮮が合意し、7月から金正恩第1書記直轄とされる特別調査委員会が再調査を実施している。北朝鮮の核をめぐる6カ国協議は08年12月に首席代表会合が開かれたが、北朝鮮の核実験を受けて長期中断が続いている。(詳細は拉致問題の特集を参照)
(4)日ロ関係
日ロ関係が改善すれば日本と極東地域の平和と安定が進み、日本海側地域とロシア沿海州を中核とした新たな経済圏が育まれる可能性がある。しかし日ロ平和条約の締結には北方領土問題の解決が不可欠だ。歴代内閣が北方領土返還を求める一方、ロシアは実効支配を進めてきた。
2012年12月にスタートした第2次安倍政権では、安倍首相がプーチン・ロシア大統領と会談を重ねており、首脳同士の信頼関係醸成で打開の糸口を探っている。しかし、ロシアによるクリミア編入を受けたウクライナ情勢の緊迫化で、容易に協議進展を見通せる状況ではない。
【対ロ制裁】
日ロ両政府は13年11月2日、初の外務・防衛閣僚協議(2プラス2)を東京都内で開き、海上自衛隊とロシア海軍の間でのテロや海賊対処の共同訓練実施など安全保障分野の協力拡充で合意した。安倍首相は14年2月8日、ロシアでのソチ冬季五輪開会式に出席し、プーチン大統領と会談。プーチン氏の同年秋の来日や、北方領土問題を早期に解決し、平和条約締結交渉を加速することなどで合意した。
しかし、ロシアがウクライナからの独立を宣言したクリミアを国家承認したため、日本政府は3月18日、渡航の際の査証(ビザ)発給緩和に向けた協議停止などの対ロ制裁を発表。ロシアは同日、クリミア編入を発表した。
日本政府は4月17日、同月下旬に予定していた岸田文雄外相の訪ロ延期を発表。4月29日、7月28日には対ロ追加制裁を相次いで発表した。これに対し、ロシアは8月5日、同月末に予定していた日ロ外務次官級協議の延期を公表した。
森喜朗元首相は9月11日、モスクワでプーチン大統領と会談し、安倍首相からの親書を手渡した。プーチン、安倍両氏とも対話継続に意欲を表明した。ただ日本政府は24日、ロシア金融機関の日本での証券発行制限を柱とする追加制裁を明らかにした。
【首脳会談】
安倍首相とプーチン大統領は14年、それぞれの誕生日の9月21日と10月7日に相次ぎ電話会談し、個人的な信頼関係の維持に努めた。同月17日には、イタリア・ミラノでのアジア欧州会議(ASEM)首脳会議の場で首脳会談を開催し、11月の中国・北京でのAPEC首脳会議に合わせて首脳会談を行うことでも合意した。
11月9日に北京で会談した両首脳は、15年に大統領来日を目指すことで合意。北方領土問題を含む平和条約締結交渉については、日ロ首脳会談の声明に基づき、双方が受け入れ可能な解決策に向け議論を進める方針を確認した。岸田外相の訪ロは引き続き検討することとした。15年2月12日、杉山晋輔外務審議官とモルグロフ外務次官が、14年8月から延期となっていた日ロ次官級協議をモスクワで開催し、平和条約締結交渉などについて意見交換した。
(5)対国連関係
国連安全保障理事会の常任理事国入り問題は、2005年3月にアナン事務総長が国連改革に関する勧告を発表したことを受けて機運が高まった。安保理は国連創設の1945年に常任理事国5カ国、非常任理事国6カ国の計11カ国でスタートし、63年に非常任理事国だけを4カ国増やす憲章改正が行われて以来、15カ国が定着している。
日本とドイツ、インド、ブラジルの4カ国グループ(G4)は2005年、常任理事国を6カ国、非常任理事国を4カ国増やし、計25カ国とする枠組み決議案を国連総会に68省 庁提出したが、廃案となった。
G4は14年9月、ニューヨークで外相会合を開催し、国連創設70周年の15年に向け、結束して安保理改革に取り組む方針で一致した。アフリカを含む発展途上国の常任理事国入りに理解を示した。G4は15年5月、05年に廃案となった案を微修正した案を国連に提出した。非常任理事国を「14または15カ国」とし、アフリカの拡大幅を「1または2カ国」とした。
(6)人事の出稿基準
【本省】参事官以上の幹部。課長は、大臣官房=総務、人事、会計各課▽外務報道官、組織=報道課▽総合外交政策局=総務課▽アジア大洋州局=北東アジア、中国・モンゴル1、中国・モンゴル2各課▽北米局=北米1、北米2、日米安全保障条約各課▽欧州局=ロシア課▽経済局=国際貿易、経済連携両課▽国際協力局=政策課▽国際法局=国際法、条約両課―を出稿。
【在外】大使、公使、総領事を出稿。米国、英国、フランス、ロシア、中国、ドイツ、韓国、国連の各大使についてだけ「政府は○○に▽▽氏の起用を内定した(固めた)」などの前打ちができる。それ以外の大使は、過去の大使人事取材の激化、相手国のアグレマン(事前の同意)などの関係から、外務省側との申し合わせで正式発表までは出稿しないことになっている。
*略歴、顔写真が必要なのは本省が部局長以上、在外は大使と特命全権公使。
*大使などの「免」(退職を伴わない場合)と「帰朝」(帰国)は出稿しない。
(1)沿革
1950年に勃発した朝鮮戦争への米軍投入による日本の治安悪化を懸念したマッカーサー米元帥の指示で同年、警察予備隊が発足した。52年には警察予備隊と海上保安庁の海上警備隊が統合され、新設された保安隊と警備隊を保安庁が管理した。保安隊は陸上自衛隊、警備隊は海上自衛隊の前身となった。
保安庁の任務は「わが国の平和と秩序を維持するため、特別の必要がある場合において行動する部隊の管理および海上警備救難の事務」とされ、防衛組織と位置付けられていなかった。だが、米ソ冷戦が激化する中、53年に朝鮮戦争の休戦協定が結ばれ、日本に駐留する米軍が終戦当時の約100万人から4分の1に削減されたことを受け、米国が日本に再軍備を要求。吉田茂首相は戦力不保持を規定する憲法9条を根拠に抵抗したが最終的に受け入れ、54年に自衛隊と防衛庁が設置された。
防衛庁は総理府(現内閣府)の外局として設置されたため、独自に法律制定や予算要求ができなかった。90年代以降、国連平和維持活動(PKO)への参加や災害活動への取り組みなどを通じ、自衛隊の役割を強化する観点から、自民党を中心に「省」昇格を求める声が強まった。第1次安倍内閣時の2006年12月に改正防衛庁設置法が成立。07年1月に防衛省が発足した。
(2)防衛省改革
守屋武昌元防衛事務次官の汚職事件や海上自衛隊の給油量訂正問題、航海日誌誤破棄問題などの不祥事を踏まえ、08年7月に政府の有識者会議が福田康夫首相に報告書を提出した。防衛省を指揮する大臣の補佐体制強化のため、内部部局(背広組=文官)と幕僚監部(制服組=自衛官)の混合化を打ち出した。具体的には①内局幹部が兼ねる防衛参事官制度の廃止と大臣補佐官の設置②背広組と制服組の幹部でつくる防衛会議について法的位置付けを付与③内局の運用企画局を廃止し部隊運用を統合幕僚監部に一元化④防衛力整備部門の一元化―などが示された。報告書を踏まえた防衛省設置法改正案が2009年5月に成立し、8月から防衛参事官制度の廃止や防衛会議の新設、大臣補佐官の新設などが進められた。
政権交代により9月に発足した民主党の鳩山政権は、新たな省改革の検討を開始。内部部局と幕僚監部の混合化や運用部門、防衛整備力部門の一元化については、さらに検討を進めることになった。12年12 月の自民、公明両党による政権奪還で発足した第2次安倍政権は、省改革加速のため13年2月に防衛副大臣を委員長とする省改革検討委員会を設置。8月に改革の方向性をまとめた。文官と自衛官の垣根をなくすため、内局と幕僚監部にそれぞれ自衛官と文官を定員として配置するほか、陸海空各自衛隊が個別に行っていた防衛力整備を全体で実施することが盛り込まれた。部隊運用の統合幕僚監部への一元化も、あらためて明記された。
これらの内容を踏まえ政府は15年3月、「防衛装備庁」(仮称)の新設、文官が自衛官より優位に立つと解釈される「文官統制」規定の廃止などを含めた防衛省設置法改正案を閣議決定し、国会に提出した。
(3)防衛計画の大綱
日本の安全保障の基本方針や日本を取り巻く安保環境などに基づき、自衛隊の体制や主要装備品の整備目標といった防衛力整備の基本方針を示したもの。1976年、95年、2004年、10年に閣議決定された。第2次安倍政権は13年1月、「安保環境の厳しさは一層増している」として民主党政権が策定した10年大綱の見直しを表明。13年12月に新たに決定した大綱は、安保環境の変化を踏まえ、あらゆる事態に「シームレス(切れ目なく)」かつ臨機応変に対応するため、陸海空の各自衛隊を機動的に運用する「統合機動防衛力」を基本理念として打ち出した。離島奪還作戦を担う「水陸機動団」と「機動旅団」の新設も明記。北朝鮮のミサイル開発をにらんだ、敵基地攻撃能力の保持については「米軍との役割分担に基づき対処能力の強化を図る」との表現にとどめた。
(4)中期防衛力整備計画(中期防)
中期的見通しに立ち継続的に行う防衛力の整備計画。1986年からは5年間を対象期間として策定されている。2010年には大綱に併せて中期防が策定されたが、大綱見直しに伴い廃止され、13年12月に新たな中期防が新大綱とともに閣議決定された。新中期防は、14〜18年度に新型輸送機オスプレイ17機や無人偵察機グローバルホーク3機を導入することを明記。離島奪還作戦のための水陸両用車52両、大砲を備えた機動戦闘車両99両の配備が盛り込まれた。予算総額は中期防として3期ぶりに増え、24兆6700億円程度を上限とした。
(5)防衛装備移転三原則
東西冷戦を背景に1967年、佐藤栄作内閣が①共産圏②国連決議で武器輸出が禁じられている国③国際紛争の当事国―への武器輸出を認めないと表明した。76年に三木内閣が全面禁輸へと拡大。「武器輸出三原則」として歴代政権が踏襲した。案件に応じて官房長官談話などで例外を設けるなど、禁輸措置の緩和も進み、2011年に野田内閣が兵器の国際共同開発は例外とする新たな基準を導入した。
この流れを受け、第2次安倍政権は13年12月に策定した「国家安全保障戦略」で武器輸出三原則の見直しを打ち出し、14年4月に新たな輸出ルールとして「防衛装備移転三原則」を閣議決定した。国際協力を積極的に推進する場合や、日本の安全保障に資する案件では輸出を認めた。7月には国家安全保障会議(NSC)で、米企業へのミサイル部品の輸出、ミサイル技術をめぐる英国との共同研究実施を承認した。
(6)日米防衛協力指針(ガイドライン)の再改定
指針は、日本に対する武力攻撃の際に、自衛隊と米軍の役割と協力のあり方を定めた文書で、冷戦時代の1978年、旧ソ連の上陸侵攻を想定して策定された。冷戦終結後の97年、北朝鮮の核開発に伴う朝鮮半島危機をきっかけに「半島有事」を重視した内容に改定。これを具体化する形73 省 庁で、日本周辺地域で日本の平和と安全に重要な影響を与える「周辺事態」発生を想定した周辺事態法が99年に成立した。
その後、中国の軍備拡張や北朝鮮の核・ミサイル開発の進展などを念頭に、2012年8月、野田内閣の森本敏防衛相が、パネッタ国防長官との会談で再改定を打診し、協議開始で一致した。第2次安倍政権下の13年10月、外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)で、14年末までの再改定で合意。14年10月には、集団的自衛権の行使容認を受け、自衛隊による対米支援を地球規模に拡大するほか、宇宙・サイバー空間での協力も盛り込んだ中間報告を発表した。しかし、日本政府が進めている新たな安全保障法制の内容と整合性を図るため、再改定時期は15年に先送り。15年4月27日、ニューヨークでの2プラス2で新たなガイドラインを決定した。
(7)自衛隊の海外派遣・PKO
1990年の湾岸戦争で日本は計130億㌦を多国籍軍に資金援助したが、国際社会から評価が得られなかった。停戦後の91年、ペルシャ湾での機雷掃海のため自衛隊が初めて海外に派遣された。さらに政府は92年、国連平和維持活動(PKO)協力法を制定。同年のカンボジアPKOへの自衛隊派遣を皮切りに2015年4月までにモザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、スーダン、ハイチなど、計9回の部隊派遣を行った。継続中なのは、11年11月からの南スーダン派遣のみ。
・海賊対処
アフリカ東部ソマリア沖アデン湾で海賊行為に対処するため、政府は09年3月、日本関連船舶を警護するため海上自衛隊の護衛艦2隻を派遣。7月施行の海賊対処法で、日本に関係のない外国船も警護対象とした。13年12月から多国籍軍にも参加し、15年5月には多国籍部隊の司令官に、海自の海将補を派遣。自衛官が多国籍部隊の司令官を務める初めてのケースとなる。
・対テロ
01年9月11日の米中枢同時テロを受け、テロ対策が喫緊の課題として浮上。日本政府は同年中にテロ対策特別措置法を制定し、海上自衛隊をインド洋に派遣。米海軍など各国艦艇への後方支援に従事させた。だが、与野党の「ねじれ」の下で07年11月に特措法が期限を迎えて失効し、部隊は撤収。08年1月に新テロ特措法の成立で活動を再開させたが、撤退方針を掲げた民主党政権下の10年1月に同法が失効。再び撤収した。一方、03年3月のイラク戦争を受け、同年7月にイラク復興支援特別措置法を制定。自衛隊部隊がイラク・サマワで復興支援活動を06年7月まで行った。
(8)人事の出稿基準
防衛省には政治部と社会部が乗り入れているが、人事原稿は政治部案件となっている。出稿基準は以下の通り。2015年の通常国会に提出した先述の防衛省改革に伴う防衛省設置法改正案が成立すれば、技術研究本部長、装備施設本部長、経理装備局長、運用企画局長などのポストは廃74省 庁止される一方、防衛装備庁長官(仮称、以下同)、防衛技監、運用政策官などのポストが新設されるので注意が必要。
・防衛省 一般出稿は審議官以上の指定職と、大臣官房の秘書課長、文書課長、広報課長、防衛政策局防衛施策課長、運用企画局事態対処課長、人事教育局人事計画・補任課長、経理装備局会計課長、装備政策課長。 経歴・顔写真付き出稿は、事務次官、防衛大学校長、防衛監察監、官房長、防衛政策局長、防衛医科大学校長、技術研究本部長、装備施設本部長、運用企画局長、人事教育局長、経理装備局長、防衛研究所長、地方協力局長。
・統幕、陸海空、情報本部 一般出稿は陸将、海将、空将。 経歴・顔写真付き出稿は①統幕=統合幕僚長②陸自=陸幕長、北部、東北、中部、西部各方面総監、中央即応集団司令官③海自=海幕長、自衛艦隊司令官、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊各地方総監、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官④空自=空幕長、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、北部、中部、西部各航空方面隊司令官、南西航空混成団司令⑤情報本部=情報本部長。
(1)法務省
前身は戦前の司法省。戦後、裁判所が分離され、裁判所関係の事務は最高裁に移管された。1952年に法務省と改称。2001年1月の中央省庁再編で大臣官房のほか、民事局、刑事局、矯正局、保護局、人権擁護局、入国管理局の6局制に。15年4月、訟務局を設置した。外局として公安調査庁、公安審査委員会がある。また法務総合研究所が置かれ、国連の協力の下に国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)が運営されている。 法務省の特徴は、課長以上の主要幹部ポストの多くを検事(判事は発令時に検事に任官)が占めていること。検察庁が法務省の本体となっていることが分かる(裁判所からは約100人の判事が法務省に来ている)。
(2)検察庁
検察庁は法務省に置かれた「特別の機関」との位置付けで「法務・検察」と称される。法務行政は法相を最高責任者とする法務省、個々の事件処理は検事総長をトップとする検察庁が担当する。
組織としての統一性も求められることから、検事総長、検事長、検事正などには部下検察官を指揮監督できる「検察官同一体の原則」が認められている。検事総長をトップにピラミッド型の機構を形成している。
検察権の行使は、内閣が国会に対し連帯して責任を負うとされ、法相が指揮監督権を持つ。しかし、検察庁法第14条ただし書きは、法相は検察官を一般的に指揮監督できるが、個々の事件については、検事総長のみを指揮することができるとして制限している。1954年の造船疑獄では、犬養健法相が指揮権を発動し佐藤栄作自由党幹事長の逮捕許諾請求を阻止し、直後に辞任した。
2007年から検察審査会法改正に伴い、検察審査会が2回続けて起訴すべきだと議決すれば、強制起訴できることになった。検察による起訴権限の独占が崩れた。 10年9月、厚生労働省の文書偽造事件をめぐる、大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽事件が発覚し、担当検事や前特捜部長らが逮捕された。大林宏検事総長は最高検が検証結果をまとめた10年12月に引責辞任した。検察は国民の信頼回復のため、取り調べの可視化などを進めている。
(3)人事の特徴
検察官は全国で約2730人(2014年7月時点、副検事を含む)。検察の序列は検事総長、東京高検検事長、大阪高検検事長、次長検事、次いで名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の各高検検事長の順。すべて内閣が任命権を持ち、天皇が認証する認証官。事務次官は認証官ではない。次官に就任するといったん検事の身分を離れる。各省では事実上トップにある次官が、法務・検察ではトップではない。
検事総長、東京高検検事長、次長検事などの検察首脳になるのは、本省の官房3課長(秘書課長、人事課長、会計課長)、官房長、刑事局長、法務事務次官経験者が圧倒的に多かったが、異なるケースも増えている。
(4)人事の出稿基準
政治部の扱う人事は次の通り。(○印は経歴、顔写真付き)
【本省】○事務次官、○官房長、○局長、○法務総合研究所長、訟務総括審議官、司法法制部長、秘書課長、人事課長、会計課長、民事、刑事、矯正、保護、人権擁護、入国管理各局の総務課長
【最高検】○検事総長、○次長検事、部長、検事
【高検】○検事長、○次席検事、部長、支部長
【地検】○検事正、○次席検事(東京、大阪、名古屋、横浜、京都、神戸、福岡)、○支部長(立川、川崎、沼津、浜松、岡崎、堺、姫路、小倉)
【法務局】局長
【地方入国管理局】局長
【矯正管区】管区長、研修所長
【中央更生保護審査会】委員長、委員
【地方更生保護委員会】委員長
【公安審査委員会】事務局長(委員長、委員は内閣府人事)
【公安調査庁】○長官、○次長、公安調査局長
【国税不服審判所】所長
【最高裁】○長官、○判事
【高裁】○長官
【法制審議会】委員
【検察官適格審査会】委員、予備委員(政治家以外)
(5)政策課題
【取り調べ可視化】
検察は2006年、警察は08年から、一部の事件に限り取り調べの録音・録画の試行を始めた。検察や警察による容疑者の取り調べで、自白の強要がないかを検証し、裁判で供述の任意性を立証するのが目的。10年9月、厚生労働省文書偽造事件で村木厚子元局長に無罪判決が出され、強76省 庁引な取り調べが発覚すると、供述に頼った捜査の在り方への批判が一層強まった。 法制審議会(法相の諮問機関)は11年6月、可視化の法制化を含む刑事司法制度改革の議論に着手し、14年9月に刑事訴訟法などの法改正要綱を松島みどり法相に答申。取り調べの全過程の可視化を義務付けるよう求めた。だが、対象は殺人や強盗致死などの裁判員裁判対象事件と、検察の特捜部や特別刑事部が扱う独自事件で、全事件の2〜3%でしかない。 取調官が容疑者から十分な供述を得られないと判断した場合や暴力団事件などは含まれず、対象が限定されていることに批判もある。要綱を踏まえ、政府は15年の通常国会に刑訴法などの改正案を提出した。
【死刑制度】
法務省は07年12月に死刑を執行した際、初めて対象者の氏名と執行場所を公表した。鳩山邦夫法相は2カ月に1回の頻度で計13人の執行を命令し、一時中断した執行が再開された1993年以降の歴代法相で最多となった。民主党政権では2009〜12年に延べ9人が法相を務め、千葉景子氏ら3人が計9人の執行を命令した。第2次安倍内閣以降では谷垣禎一法相が計11人の執行を命令。松島法相は任期が短く、執行を命じなかった。 内閣府が15年1月に発表した世論調査では、死刑制度を容認する人が約8割に上った。今回調査で終身刑を導入した場合の死刑廃止の是非について初めて質問したところ「廃止しない方がよい」51・5%、「廃止する方がよい」37・7%となった。終身刑について法務省は「人格が破壊され死刑より残酷」との立場で慎重論が強い。上川陽子法相は調査結果に「現行制度に肯定的な結果が示された」と評価し「直ちに見直すことにはならない」としている。
【共謀罪】
殺人などの重大犯罪の謀議に加わっただけで処罰対象とするもので、法務省は組織犯罪処罰法を改正して新たな刑罰として盛り込む方向で検討中。国連は00年11月に「国際組織犯罪防止条約」を採択。政府は翌12月に署名したが、条約加入には法定刑4年以上の重大犯罪への共謀罪規定が必要との立場で、法務省は国際協調の観点から規定が不可欠としている。
これまで同法改正案は3回、国会に提出されたが全て廃案になった。野党や日弁連は「国民監視につながる」などと批判している。20年東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策強化もにらみ、法務省は法案提出を検討している。
【民法改正】
企業や消費者との契約ルールを定めた債権分野に関し、インターネットの普及など時代の変化に対応するため、千葉法相が09年、法制審議会に見直しを諮問。法制審は15年2月、改正要綱を上川法相に答申した。要綱は買い物の際に売り手側が契約内容を提示する「約款」の規定新設が柱。アパートなどの部屋を借りる際、大家に支払う敷金の定義や返還規定を明文化し、飲食料や弁護士報酬など業種ごとに異なる未払い金の時効を原則5年に統一することなどを盛り込んだ。1896年に民法が制定されて以来の大幅改77 省 庁正で、政府は2015年の通常国会に改正案を提出した。
夫婦が希望すれば、それぞれの姓を結婚後も名乗れる選択的夫婦別姓に関し、法制審議会が1996年に制度導入を盛り込んだ民法改正案を答申したが、賛否両論があり改正は実現していない。2015年2月、最高裁大法廷で、夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法違反かどうか争われている訴訟が審理されることが決まった。判決で初の憲法判断を示すとみられ、注目される。
【相続法制】
法務省は15年2月、高齢化社会の進展や法律婚尊重の観点から、法制審に民法の相続法制の見直しを諮問した。法務省が設置した有識者の「相続法制検討ワーキングチーム」が同年1月に論点をまとめた報告書に基づき、法制審が議論を進める。報告書は①配偶者の貢献に応じた遺産分割②加算される「寄与分」への介護負担の反映③最低限保障される相続割合に当たる遺留分制度の見直し④配偶者の居住権保護―に論点を整理し、課題を指摘した。
【裁判員制度】
刑事裁判に一般市民の感覚を反映させる目的で09年5月に始まった。最高刑が死刑または無期懲役か、故意に被害者を死亡させた事件が対象。原則として有権者から無作為に選ばれた裁判員6人と裁判官3人が共に審理し、有罪・無罪と量刑を決める。裁判員は被告や証人に質問できる。また守秘義務を課される。 現行法は裁判員らに危害が及ぶ恐れのある暴力団事件などに限り除外を認めている。法務省の有識者検討会は長期間の審理について「裁判員の負担が重すぎる」として法改正を要請。政府は15年の通常国会で、審理が著しく長期間に及ぶ事件を除外できる規定を盛り込んだ裁判員法の改正を目指す。初公判から判決まで1年を超える事件が想定されている。
【再犯防止】
刑務所の出所者が再び罪を犯さないよう、政府は14年12月、取り組み強化のための新たな数値目標を掲げた「犯罪に戻らない・戻さない」宣言を決定した。13年の再犯者率は46・7%で過去最高となり、刑務所に入った人の約6割が再入所。うち約7割が無職だった。政府は刑務所や少年院を出た人を雇う「協力雇用主」登録者のうち、実際に雇用する企業を20年までに3倍の約1500社にする目標も決めた。一般刑法犯の半分近くを占める再犯者を減らし、20年東京五輪に向け安全な社会づくりを目指す。
【性犯罪の罰則強化】
現行刑法では、強姦致死傷罪の罰則は無期または5年以上の懲役に対し、強盗致傷罪は無期または6年以上の懲役、強盗致死罪は死刑または無期となっている。この量刑に対し、松島法相が「強盗より強姦の方が軽いのはおかしい」と見直しの検討を指示。後任の上川法相は性犯罪の厳罰化を議論する法務省の有識者検討会を設置し、14年10月に初会合を開いた。法務省が示した検討項目は①強姦罪の法定刑引き上げ②起訴に被害者の告訴が必要となる「親告罪」規定の見直し③暴行や脅迫がなくても強姦罪が成立する「性交同意年齢」(13歳未満)の引き上げ―など。被害78省 庁者団体や有識者からヒアリングし、意見を取りまとめる。
【法曹養成制度改革】
政府は司法試験合格者数を「年間3千人程度」とする計画を02年に閣議決定したが、一度も実現しないまま13年7月に撤回した。これを受け同年9月に適正な法曹人口や法科大学院の改革案を検討する「法曹養成制度改革推進会議」を設置。法務省などでつくる事務局の「法曹養成制度改革推進室」が、3千人に代わる適正な法曹人口の数や予備試験の見直しの是非を検討している。合格率の低い法科大学院に対し、修了しても司法試験の受験資格を与えないなどの法的措置を含め、法科大学院の充実策も盛り込み、15年7月までに改革案を取りまとめる。
【成人年齢引き下げ】
民法に規定する成人年齢を現在の20歳から18歳へ引き下げるかが今後の課題となる。法制審は09年、成人年齢を18歳に引き下げるのが適当と答申したが、法改正は実現していない。14年6月施行の改正国民投票法は憲法改正に必要な国民投票の投票年齢を4年後に「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げると規定した。これを受け、自民、民主、公明、維新など与野党6党は15年3月、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案を通常国会に提出。今国会成立は確実な情勢で、16年夏の参院選から適用される見込みだ。
第6章 選挙 (6)
衆院選は議員全員を一度に選ぶことから一般に「総選挙」と呼ばれる。任期(4年)満了と解散による二つのケースがある。参院選は議員の任期が6年で、3年ごとに半数改選され「通常選挙」という。いずれも内閣の助言と承認により、天皇の「公示」で実施される。 国政選挙でも再選挙や補欠選挙は、選挙管理委員会による「告示」となる。再選挙は立候補者が定数より少なかったり、法定得票を獲得した候補がいなかったり、選挙違反の裁判で当選無効となるなど「当選人の不足」が理由。補欠選挙は、議員の死亡、辞職など「議員の欠員」を補う。
(1)選挙期日
任期満了による選挙の投開票日は満了日前30日以内。満了日前53日以内に国会の会期がかかる場合は閉会の日から24日以後30日以内。衆院解散は40日以内。公示日(補選は告示日)は、衆院が12日前、参院が17日前(投開票日が日曜日ならば、衆院は火曜日、参院は木曜日)。
2000年5月の公職選挙法改正で、議員の死亡や辞職などの選挙事由が生じた場合の補選は、年2回に集約して行うことにした。「統一補選」と呼ばれる。政党が選挙に追われるのを防ぎ、有権者の関心を高めるのが狙い。9月16日から翌年3月15日の間は4月の第4日曜、3月16日から9月15日の間は10月の第4日曜が投開票日となる。
(2)衆院(定数475)の選挙制度 小選挙区(定数295)と比例代表(11ブロック、定数180)並立制。1996年の第41回衆院選から導入された。有権者は小選挙区の候補者名と比例代表の政党名を書く。
・小選挙区
小選挙区は定数1で「1票でも多い票」を集めた候補者が勝つ。 「1票の格差」が最大2・30倍だった2009年衆院選を「違憲状態」とした11年最高裁判決を受け、小選挙区定数を「0増5減」する衆院選挙制度改革関連法が12年11月に成立し、小選挙区定数は山梨、福井、徳島、高知、佐賀各県で1減の295となった。だが、格差是正には衆院選挙区画定審議会による新たな区割り策定や一定の周知期間が必要なため、12年12月の衆院選は従来の定数、区割りで実施された。
・比例代表
比例代表は全国を11ブロックに分け、ブロックごとの定数をドント式で各党に配分する。最大は近畿ブロックの29、最小は四国ブロックの6。 比例代表の候補者となりうるのは、次のいずれかの要件を満たす政党、政治団体に限られる。①国会議員が5人以上②直近の衆院選の小選挙区か比例代表、参院選の比例代表か選挙区のいずれかで、得票率が全国の有効投票総数の2%以上③比例代表名簿の登載者数がそれぞれのブロックの議員定数の2割以上。
各党の得票をそれぞれ1から順に整数で割り、その商の多い順に、定数まで議席数を各党に配分する。その上で、各党が届け出時に提出した候補者に順位をつけた比例代表名簿に基づいて、名簿上位から順に当選となる。 政党は小選挙区の候補者を比例代表の名簿にも登載できる(重複立候補)。比例代表名簿は複数の重複立候補者を同一の順位に登載可能なため、同一順位の候補者が多数おり、獲得議席数が足りない場合、当選者は惜敗率により決まる。比例単独立候補者の順位は他の候補者と同一にはできない。
小選挙区の得票が有効投票数の10分の1に達せず「供託金没収」となった候補は、名簿順位に関係なく当選できない。2000年6月の42回衆院選で自由党候補が初めて適用された。05年9月の44回衆院選でも、東京ブロックの共産党候補が、名簿登載順位1位にもかかわらず、小選挙区での得票が9・8%しかないため、比例当選できなかった。09年8月の45回衆院選でもみんなの党が、東海、近畿の両ブロックの計2議席、当選できなかった。
比例代表の当選対象は名簿に登載された候補者に限られる。獲得議席が名簿登載者数を上回れば、その党のさらなる比例当選者はなくなり、ドント式で配分された次の政党が議席を獲得する。05年衆院選では比例東京ブロックで自民党が8議席を獲得したが、小選挙区当選者を除いた名簿登載者は7人にとどまり、1議席を社民党に譲った。(保坂展人・現世田谷区長)09年の衆院選は民主党が比例近畿ブロックで2議席を譲った。
(3)参院(定数242)の選挙制度
選挙区(定数146、各都道府県の定数は2〜10)と比例代表(定数96)からなり、3年ごとに半数を改選する。定数「4増4減」により、改選数1の「1人区」は31県となり、神奈川県と大阪府が改選数4の「4人区」となった。
有権者は選挙区では候補者名を書き、比例代表では政党名か比例候補者名を書く。比例代表の名簿は名簿登載者の順位がない「非拘束名簿式」。比例代表は、政党名と比例候補者名を合わせた得票数を基に、ドント式で議席数を配分。非拘束名簿式のため、候補者名票が多い順に当選する。
(4)補欠選挙が実施されるケース、されないケース
・衆院議員、参院議員で、当該議員の任期が終わる日の6カ月前の日が属する9月16日〜3月15日(第1期間)、または3月16日〜9月15日(第2期間)の初日以後に欠員が生じた場合には補欠選挙は行わない。
例①2010年に選出された参院議員の任期は16年7月25日。この6カ月前は16年1月25日になり、この1月25日が属する第1期間の初日(15年9月16日)以降に、欠員が生じても補選は行われない。12年12月衆院選には、参院議員9人がくら替え出馬し、公示日の12月4日に自動失職した。うち5人は07年参院選の選挙区当選者で、任期日は1382選 挙年7月28日で、この6カ月前は13年1月28日。失職した12月4日は、1月28日が属する第1期間の初日(12年9月16日)以降だったため、補欠選挙は行われなかった。
例②2014年12月14日に当選した衆院議員の任期は18年12月13日。この6カ月前は18年6月13日。この6月13日が属する第2期間の初日(18年3月16日)以降に、欠員が生じても補選は行わない。
・参院議員選挙区は、東京選挙区(定数10)では2人以上欠員がでないと補選にならないが、他の選挙区では1人欠ければ補選が行われる。
・参院選の通常選挙がある年で、3月16日から通常選挙の期日が公示されるまでに改選時期の異なる議員の欠員が出た場合には、通常選挙の期日に前倒しして行う。
・衆院議員の補欠選挙は、参院議員の任期が終わる年では、3月16日から参院議員の任期が終わる日の54日前までに欠員が生じた場合は、通常選挙の期日に前倒しして行う。
(1)「1票の格差」訴訟
衆院の小選挙区や参院の選挙区は、行政区画に加え、地域や交通の事情などに配慮して区割りが決められており、人口に完全比例していない。選挙区間での議員1人当たりの有権者数の差により生じる「1票の格差」について、憲法14条が規定する「法の下の平等」に反するとして、選挙のやり直しなどを求める訴訟が繰り返されている。2014年1月1日現在の住民基本台帳人口を基に、共同通信社が「1票の格差」を試算したところ、衆院小選挙区の最大格差は2・109倍、参院選挙区の最大格差は4・767倍だった。
かつて、衆院は中選挙区当時で3倍、参院は6倍が違憲の目安とする判例が定着していたが、司法判断は厳しくなっている。最高裁は、最大格差が小選挙区で2・30倍だった09 年衆院選、2・43倍だった12年衆院選を「違憲状態」と判断。選挙区で5・00倍の10年参院選、4・77倍の13年参院選をめぐる判決でも「違憲状態」と断じた。14年12月の衆院選について15年に入り、各高裁が判決を出しているが、「違憲」「違憲状態」「合憲」と判断が分かれている。
(2)0増5減
衆院小選挙区の区割りは「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」に基づき、有識者からなる衆院選挙区画定審議会(区割り審)が10年ごとの大規模国勢調査結果を基に区割り案を首相に勧告し、政府が関連法案を国会に提出して成立する手順で行われる。2010年の国勢調査は11年2月25日に公表され、区割り審は3月1日に区割り改定作業を始めた。しかし、最高裁は3月23日、09年衆院選の「1票の格差」をめぐる判決で、作業の前提となる「1人別枠方式」の廃止を要求したため、改定作業は中断された。判決は、09年衆院選を「違憲状態」と判断し、1人別枠方式について「格差を生む主要な原因となっており、速やかに廃止し立法的措置を講じる必要がある」と指摘した。同方式83 選 挙は区割り審設置法で定められており、小選挙区議席を47都道府県にまず一つずつ配分する方式だ。
最高裁判決を受け、与野党は選挙制度改革をめぐる協議を始めた。民主党は小選挙区定数の「5増9減」または「6増6減」と比例代表定数を80削減する案を掲げる一方、自民党は小選挙区定数を「0増5減」し、比例代表定数を30削減する案をまとめた。協議は難航したが、民主党は12年1月、「1票の格差」の是正について、自民党の「0増5減」案を採用することを決めた。その後も、格差是正と併せて定数削減を主張する民主党に対し、自民党は格差是正を先行させるよう訴え、改革をめぐる両党の見解は対立した。
12年11月、野田佳彦首相は党首討論で、次期通常国会での衆院議員定数削減の確約を条件に「解散してもいい」と表明した。この提案を自民党は受け入れ、衆院は解散されることになり、「0増5減」を盛り込んだ選挙制度改革関連法は11月16日に成立した。山梨、福井、徳島、高知、佐賀各県の小選挙区定数は各1減となり、区割り審設置法にある1人別枠方式の規定は削除された。
(3)区割り改定
選挙制度改革関連法の成立を受け、区割り審は2012年11月、「0増5減」を実現するための新たな区割り案の策定作業を1年8カ月ぶりに再開した。作業は数カ月かかるため、12年12月の衆院選は従来の定数、区割りで行われた。衆院選では自民、公明両党が政権復帰した。新たな改定案は13年3月、安倍晋三首相に勧告された。17都県42選挙区の区割りを見直す内容で、人口最多は東京新16区で、最少の鳥取新2区との格差は、10年の国勢調査基準で1・998倍となった。
政府・与党は4月、区割り改定を盛り込んだ公選法改正案を閣議決定し、衆院に提出した。野党は、区割り改定を選挙制度の抜本改革に先だって処理することに反発。法案は衆院を通過したが、野党多数の参院では採決されず、参院送付から60日以内に議決されない場合に法案否決とみなす憲法59条の規定が適用され、6月24日、衆院本会議で自民、公明両党と日本維新の会による3分の2以上の賛成多数で再可決され、成立した。
(4)衆院選挙制度改革
2012年11 月の衆院解散に伴い、自民、公明、民主の3党は議員定数削減を含む衆院選挙制度改革について、13年1月召集の通常国会中に結論を得ることで合意した。自公両党は比例代表定数を180から30減らし、残り150のうち60を中小政党に優遇して配分する案を決める一方、民主党は議員定数を小選挙区で30、比例代表で50の計80削減する案をまとめた。与野党は4月、実務者協議に入ったが、結論は出ないまま通常国会は閉会した。安倍晋三首相は閉会に合わせた記者会見で、有識者による第三者機関を国会に設けるよう提案した。
最高裁は2013年11月、「1票の格差」が最大2・43倍だった12年衆院選を「違憲状態」と判断した。「0増5減」の定数是正は評価したが、1人別枠方式について「構造的問題は残る」と指摘し、国会に対し格差是正に向けた一層の取り組みを要求した。
14年2月、民主、維新、みんな、結い、生活の野党5党は、小選挙区「5増30減」と「3増18減」の2案をまとめ、自公両党に提示した。だが、小選挙区定数は変えないとする与党案との隔たりは大きく、両者が歩み寄ることはできなかった。結局、与野党7党(自民、公明、民主、維新、みんな、結い、生活)は3月、衆院議長の下に有識者による第三者機関を設置することで大筋合意した。
第三者機関は、新党改革も加えた与野党8党による衆院議長への設置要請をへて6月、議院運営委員会で設置が決まった。名称は「衆院選挙制度に関する調査会」で、議長の諮問機関と位置付けられた。座長は佐々木毅元東大学長が務め、①格差是正②現行の小選挙区比例代表並立制の評価③定数削減④選挙制度の抜本改革―をテーマとすることとなった。
初会合は9月に開催され、「1票の格差」是正を議題に11月まで4回の会合が開かれたが、衆院解散により、議論は一時中断。15年2月に再開された。
有識者調査会は2月9日、小選挙区議席の都道府県への配分方法に関し、現行に比べて人口比をより反映する「アダムズ方式」と呼ばれる方法を軸に検討を進める方針を決めた。
・note「アダムズ方式」 衆院事務局は都道府県の人口を「470259」で割って得られた試算を15年2月に公開。その商に、小数点以下を切り上げて1議席を加えたのを、その県の議席数とした。「470259」は、都道府県の議席数を合計すると295となるように調整。米国の第6代大統領を務めたアダムズ氏が提唱したとされる。
(5)参院選挙制度改革
最高裁は2012年10月、選挙区の「1票の格差」が最大5・00倍だった10年参院選を「違憲状態」と判断。「都道府県単位の選挙区設定を改めるなどの立法的措置を講じ、できるだけ速やかに不平等を解消する必要がある」と指摘し、国会に抜本改革を強く求めた。
参院には13年9月、山崎正昭議長と与野党の代表が選挙制度改革について協議する「選挙制度の改革に関する検討会」と、各党実務者による「選挙制度協議会」が設置され、改革に向けた議論が始まった。
協議会は有識者からの意見聴取などを終え、14年4月、座長を務める脇雅史自民党参院幹事長から、有権者数が少ない選挙区を隣接選挙区と統合する「合区」を柱とする座長私案が提示された。22府県の選挙区を11合区に再編し、6合区では改選議席を1ずつ減らし、議員1人当たり人口が多い6選挙区に割り振る内容だった。
各党からは異論が相次ぎ、自民党内からも「都道府県単位の選挙区を維持すべきだ」「現職同士の候補者調整は容易ではない」との反対意見が噴出した。脇氏は対象府県を縮小した修正案を提示したものの、党内の反対論はやまず、案に反対する溝手顕正参院議員会長との対立が深まり9月、参院幹事長を更迭され、座長からも退いた。
各党は脇氏の案への対案をまとめ、協議会に提示した。民主党は22府県を11選挙区に統合する案、公明党は全国を85 選 挙11ブロックに分ける大選挙区制案など。維新の党、次世代の党、社民党は大選挙区制に全国比例代表制を組み合わせた案、共産党は9ブロックの比例代表制とした。
自民党も改革案を一つにまとめようと議論したが、意見集約できず、10月の協議会には選挙区定数「6増6減」など4案を提示した。しかし、複数案となったことに各党は反発し、再検討の末、3案に絞って再提出した。3案は①改選2人区の宮城、新潟、長野を1人区とし、北海道、東京、兵庫の改選議席を1増とする6増6減②鳥取、島根の「合区」により定数を2減など③6増6減した上で鳥取、島根を合区し、定数を2減など―。
14年11月、最高裁は「1票の格差」が最大4・77倍だった13年参院選を「違憲状態」と判断し、あらためて抜本的な制度改正を求めた。だが、協議会は、各党の考え方に隔たりが大きいことから、改革案の一本化を断念した。脇氏の後任として座長に就任した伊達忠一自民党参院幹事長は12月、各党案を列挙した報告書をまとめ、議長に提出した。
1994年の一連の公選法改正で、連座制の対象が組織的選挙運動管理者に広げられたことにより(拡大連座制)、訴訟を経て候補者の当選無効だけでなく、立候補禁止の措置が取られることになった。
(1)拡大連座制
買収などの選挙違反で候補者の当選無効の対象となる範囲は、選挙の総括責任者、親族から秘書に広がり、1994年の公選法改正で組織的選挙運動管理者まで広げられた。組織的選挙運動管理者とは「候補者と意思を通じて」「組織により行われる選挙運動において」①計画の立案、調整を行う者②選挙運動従事者を指揮、監督する者③その他選挙運動の管理を行う者―をいう。この場合、組織とは後援会などの選挙用の組織だけでなく、候補者を支援する企業、労組、町内会なども含まれる。
(2)立候補禁止訴訟
連座制が適用されると、当選が無効になるだけでなく、当該選挙に5年間立候補できなくなる。これを確認する立候補禁止訴訟には2種類ある。
選挙総括責任者などの有罪が確定した場合には、当該当選者(候補者)が一定期間内に検察官を相手取って高裁に「当選有効」確認訴訟を起こさないか、確認訴訟を起こしても敗訴が決定すれば、当選無効と立候補禁止が確定する。
組織的選挙運動管理者、秘書、親族の有罪が確定した場合には、検察官が当該当選者(候補者)を相手取って「当選無効」確認訴訟を起こし、検察官の勝訴が確定すれば、当選無効と立候補禁止が確定する。
衆院比例代表選挙は「政党中心の選挙」という理由から連座制が適用されない。ただし、重複立候補者の場合、小選挙区で違反があれば比例代表での復活当選は無効になる。 参院比例代表選挙は、候補者名でも投票できる非拘束名簿式の導入に伴い、政党ではなく候補者のために行う選挙運動は適用対象になった。
現職国会議員で初めて拡大連座制が適用されたのは、1996年10月の衆院選で地元事務所職員が選挙違反に問われた野田実氏(自民、衆院比例近畿ブロックと和歌山3区に重複立候補し比例で当選)。98年11月17日の最高裁判決で、比例での当選無効と和歌山3区からの立候補禁止が即日確定した。その後も連座制に問われた国会議員は多い。
・ネット選挙解禁
2013年4月、インターネットを使った選挙運動を解禁する改正公選法が成立し、同年7月の参院選から、交流サイト「フェイスブック(FB)」や短文投稿サイト「ツイッター」を含むウェブサイトの利用が可能になった。解禁されたのはホームページ(HP)や掲示板、ブログ、無料通信アプリ「LINE(ライン)」、動画投稿サイトなど。公示日から投票日前日まで、投票の呼びかけや特定の候補者に関する演説会の告知ができる。ネット広告は、政党がHPに誘導するバナー広告に限って認められた。
13年参院選では、若年層を中心とした投票率アップが期待されたが、投票率は52・61%と過去3番目の低さだった。政党や候補者が訴えたい情報は盛んに発信されたものの、当初期待されていた有権者との双方向の議論には結びつかなかったとみられている。一方、懸念されていた候補者を装う「成りすまし」や誹謗(ひぼう)中傷による大きな混乱は表面化しなかった。今後は、政党と候補者に限って認められている電子メールと携帯電話のショートメールの送信について、有権者を含めて全面解禁するかどうかが論点となりそうだ。
・無所属候補と政党候補
公選法では、無所属候補と政党候補では、認められている選挙運動の範囲が大きく異なる。政党候補は、「候補者個人」としての活動と「政党の候補」としての活動の両者が可能だが、無所属は「候補者個人」としてしか活動範囲が認められていない。
・惜敗率
同一順位に登載された重複立候補者の各小選挙区での当選者の得票に対する得票割合(惜敗率)のことで、割合が大きい順に当選となる。例えば当選者の得票数が10万票で、落選者Aが9万票なら惜敗率は90%、別の選挙区での当選者の得票数が15万票で、落選者Bが12万票となると惜敗率は80%。AとBが同一政党で比例名簿でも同一順位、かつ議席数が1しかなければ、当選者は惜敗率の高いAとなる。
・法定得票
候補者が当該選挙の当選者となるために必要な票数。これ以上、得票がなければ再選挙となる。2003年の札幌市長選、07年の宮城県加美町長選などがこれにあたる。 落選者であっても、法定得票に達していれば、参院の選挙区であれば、当選者が選挙日から3カ月以内に死亡、辞職などで欠員となった場合、繰り上げ当選となる。なお、衆院の小選挙区には繰り上げ当選はない。
法定得票の定義は以下の通り。
【衆院小選挙区】有効投票の6分の1以上
【参院選挙区】有効投票数を選挙区定数で割り、その6分の1以上
【都道府県知事選、市町村長選】有効投票の4分の1以上
【衆参の比例代表】規定なし
・供託金とその没収
供託金は、遊び半分での立候補を防ぐために設けられているとみなされている。現金か同額の国債証書を供託する。いずれも1人当たり、衆院の小選挙区、参院の選挙区、都道府県知事選が300万円。衆院の比例代表に重複立候補しようとするとさらに300万円。衆院の比例単独、参院の比例代表は600万円。候補者または政党が以下の要件に達しなければ、供託金没収となる。
【衆院小選挙区】有効投票数の10分の1
【参院選挙区】有効投票数を選挙区定数(改選数ではない)で割り、さらにその8分の1
【衆の比例代表】(納めた供託金)-(重複立候補者のうち小選挙区の当選人数×300万+比例代表の当選人数×600万×2倍)
【参の比例代表】{名簿登載者数-(当選者数×2)}×600万円
・くら替え出馬
連座制に伴い、ある選挙区、選挙に立候補できなくなった政治家が別の選挙区や別の選挙に立候補することが問題視されている。2002年10月の統一補選で、民主党・古賀一成衆院議員(比例代表)が辞職して福岡6区補選に立候補(結果は落選)したことで、現職議員が補選に立候補することも問題化した。
・在外投票
2006年の公選法改正で、衆院小選挙区、参院選挙区でも在外邦人が投票できるようになった。これで有権者数は、選挙区、比例代表とも同数となる。(投票率は持ち帰りなどがあるため、同じになるとは限らない)。
海外に在住する有権者がその地の在外公館に出向いて「在外選挙人名簿」への登録申請をする。その有権者が日本で最終居住していた市町村の選挙人名簿に登録される。実際の投票は、在外公館に出向くか、登録されている市町村選管から投票用紙を送付してもらい郵便で投票するか、帰国して投票するかのいずれか。
・電子投票
2001年11月に地方選挙電子投票特例法が成立、02年2月に施行された。これを受けて02年6月23日、岡山県新見市の市長選・市議選で日本初の電子投票が実施された。総務省によると、15年2月までに電子投票が実施された例は23回あるが、国政選挙に導入の見通しは立っていない。経費もかさむことなどから撤退する自治体が相次いでおり、政令指定都市で唯一導入していた京都市は廃止する見通しだ。
開票時間の短縮などの効果は実証されているが、トラブルもある。03年7月に行われた岐阜県可児市議選では、機器の故障などで29カ所の全投票所で最大1時間以上も投票ができないなどの事態が発生。05年7月、最高裁が選挙を無効とした高裁判決を支持する決定をしたことから、しばらく、電子投票は実施されなかった。
・比例代表の繰り上げ当選
拡大連座制に伴って当選無効が決まった議員や、選挙違反を認めて辞職した議員の補充など、スキャンダルが原因で辞職したのに、同じ党の名簿から繰り上げ当選者が出ることについて、制度上の欠陥ではないか、との指摘がある。ライブドア事件に絡む送金指示メール問題では、南関東ブロックから選出された民主党の永田寿康議員が辞職し、次点の池田元久氏が繰り上げ当選した。
・比例選出議員の政党移動
政党名で投じられた票を基に議席を得た衆議院の重複立候補者や参議院の比例代表選出議員が当選後、新たに結成した党に移ったり、無所属のまま活動したりすることは「候補者ではなく党へ投票した有権者への裏切り」「党の名前で当選した候補者であるのに...」などとして、たびたび問題視されている。公選法は比例代表選出議員について、同じ選挙で争った他党に移ると失職すると定めているが、新党への移動や無所属となることに制限はない。
2012年7月、民主党を離れた小沢一郎氏らによる新党「国民の生活が第一」の結成や、13年12月、みんなの党を離れた江田憲司氏らが「結いの党」を旗揚げしたケースでは、離党者に比例選出議員も含まれていた。江田氏に同調した離党者の大半は、比例選出だったため、みんなの党の渡辺喜美代表(当時)は、公選法の規定を見直すべきとの考えを示した。直近では、15年4月、維新の党の上西小百合衆院議員(比例近畿ブロック選出・重複立候補)が体90選 挙調不良を理由に本会議を欠席した直後に旅行していたことが発覚。党は除籍(除名)としたが、上西氏は議員辞職せず、無所属で活動すると表明した例がある。
・有効投票
投票総数のうち、無効票や白紙持ち帰りなどを引き、各候補者・政党の得票として数えられた投票のこと。
1955年に保守合同、社会党統一による「55年体制」が発足して以来、2014年12月まで、衆院選は20回、参院選が20回、それぞれ実施された。
▽自社二大政党が対決(1956年7月8日の第4回参院選、58年5月22日の第28回衆院選、59年6月2日の第5回参院選)
自民、社会二大政党下で初の国政選挙となった56年の第4回参院選。自民党は非改選を含め122議席を得て、過半数にあと一歩の勢い。社会党など革新側も憲法改正阻止に必要な3分の1を確保した。創価学会役員3人が無所属で初めて出馬、全員当選を果たした。
一方、衆院でも保守合同、社会党統一を受けて解散機運が高まり、岸信介首相は鈴木茂三郎社会党委員長との話し合いで、58年4月に衆院を解散。自民党が287議席、社会党が166議席を獲得した。59年の参院選では、自民党が初めて過半数を占め、社会党も84議席と単独で3分の1を超えた。
▽安保解散、参院の政党化進む(1960年11月20日の第29回衆院選、62年7月1日の第6回参院選、63年11月21日の第30回衆院選、65年7月4日の第7回参院選)
安保闘争後に登場した池田勇人首相は60年10月に「人心一新」を理由に解散。自民党は296議席と大勝、社会党から分かれて初登場の民社党は17議席にとどまった。 62年の参院選で、自民党は非改選を含め141議席と過去最高。公明党の前身である公明政治連盟は、創価学会出身の9人が全員当選した。同政治連盟は64年に公明党に衣替えした。民社党が参院でも候補を擁立。二院クラブも登場し、多党化の様相を呈した。
第2次池田勇人内閣の下で実施された63年11月の第30回衆院選は、特段の対決案件もなく「争点なき選挙」と呼ばれた。参院での政党化が進み、65年の参院選では公明党の進出が目立った。戦後、参院の主導権を握っていた無所属議員らの緑風会は解散、この選挙から姿を消した。
▽黒い霧解散(1967年1月29日の第31回衆院選、68年7月7日の第8回参院選)
佐藤栄作首相は田中彰治事件、共和製糖事件など不祥事が相次いだため与野党の話し合いを経て、66年12月に解散。年明けの選挙で、自民党は277議席とほぼ現状維持。公明党が衆院に初進出し、25議席を獲得した。68年の参院選では、タレント候補が進出。石原慎太郎氏が全国区で301万票を取り、トップ当選した。
▽沖縄解散(1969年12月27日の第32回衆院選、71 年6月27日の第9回参院選)
米国から沖縄返還の約束を取り付けた佐藤首相が解散、「師走選挙」を断行した。自民党は保守系無所属を加え300議席を獲得。社会党は90議席に転落した。佐藤首相は自民党総裁4選を果たした。沖縄返還を受け、70年11月には沖縄選出衆参議員選挙が実施された。71年の参院選で自民党は現状維持、多党化傾向がさらに進んだ。選挙後、実力者の重宗雄三議長を中心とする体制が自民党の一部と野党の協力で崩れ、河野謙三議長が誕生。
▽保革伯仲(1972年12月10日の第33回衆院選、74年7月7日の第10回参院選)
田中角栄首相は日中国交正常化の余勢を駆って72年11月に解散したが、自民党は選挙前勢力を割り込み271議席。社会党は3桁を回復。74年の参院選で、自民党は「企業ぐるみ選挙」の批判を受け、辛うじて過半数を確保、与野党伯仲時代に入った。候補者の選挙運動に過重な労力と資金がかかる全国区制度への批判も強まり、この選挙で「銭酷区」の異名をとった。
▽自民初の過半数割れ(1976年12月5日の第34回衆院選、77年7月10日の第11回参院選)
三木武夫首相は自民党内の反発で解散権を行使できず、76年12月に戦後初の任期満了選挙となった。ロッキード事件で、自民党は249議席と初めて、過半数割れし保革伯仲に。新自由クラブ・ブームが起きた。翌77年の参院選でも多党化現象が定着し、伯仲状況が続いた。
▽自民惨敗、40日抗争へ(1979年10月7日、第35回衆院選)
79年9月、予算関連法案不成立の事態に直面した大平正芳首相は、安定多数を目指して解散。一般消費税導入問題が争点となり、自民党は248議席で再び過半数割れ。「40日抗争」へ発展した。共産党は39議席と過去最高。
▽初の衆参同日選(1980年6月22日の第36回衆院選、第12回参院選)
80年5月、社会党が提出した内閣不信任決議案が自民党非主流派の本会議欠席で可決されたのを受け、大平首相は衆院を解散、史上初の衆参同日選挙になった。大平首相の急死もあり、自民党は衆院で284議席を獲得、参院でも圧勝した。社会党は現状維持で、公明、共産両党が後退。伯仲時代に終止符。
▽初の比例代表選(1983年6月26日、第13回参院選)
全国区制に代わり比例代表制を導入。各党は名簿上位に著名人を登載。身近な政策を掲げたミニ政党も比例選挙で4人当選。自民は選挙区で過去最高議席獲得。
▽田中判決(1983年12 月18日、第37回衆院選)
83年秋は、ロッキード事件で一審有罪判決を受けた田中角栄元首相の議員辞職問題をめぐり、国会が空転。中曽根康弘首相は田中派に押し切られ衆院を解散したが、自民党は250議席と三度、過半数割れし、新自由クラブと連立を組んだ。公明党は58議席で過去最高。
▽2度目の同日選(1986年7月6日の第38回衆院選、第14回参院選)
解散を否定していた中曽根首相が衆院定数是正を受けて86年6月、臨時国会を召集し、冒頭で解散、2回目の衆参同日選挙となった。自民党は、追加公認を含め304議席と過去最高の大勝。社会党は結党以来最低の85議席。参院でも、自民党が圧勝。ミニ政党も健闘した。
▽マドンナ旋風(1989年7月23日、第15回参院選)
89年の参院選で、自民党はリクルート、消費税、農政の3点セット批判で36議席と保守合同以来の惨敗、宇野宗佑首相が引責辞任した。社会党は土井たか子氏を先頭とするマドンナブームで大勝した。
▽自民復調(1990年2月18日の第39回衆院選、92年7月26日の第16回参院選)
海部俊樹首相は90年1月の通常国会冒頭で、施政方針演説もしないまま解散。消費税導入が焦点で、自民党は275議席と安定多数を確保。社会党は136議席で3桁を回復。92年の参院選は、自民党が68議席で復調、初の国政選挙に挑戦した細川護熙氏を担いだ日本新党が4議席を獲得した。
▽55年体制が崩壊、連立時代へ(1993年7月18日の第40回衆院選、95年7月23日の第17回参院選)
93年6月、宮沢内閣不信任案は自民党の一部が賛成し可決。自民党が分裂し、55年体制は崩壊した。選挙の結果、自民党は223議席で比較第1党だったが、日本新党の細川代表を首相とする非自民連立政権が誕生、38年間続いた自民党政権に終止符を打った。その後、政権の担い手が自民、社民、さきがけ3党に移り、95年の参院選は連立政権下で初の本格的国政選挙となった。社会党は16議席で敗北。自民党も伸び悩んだが、与党全体で参院過半数を維持し、村山富市首相が続投した。野党の新進党は比例代表で自民を上回るなど躍進。投票率は44・5%と過去最低。無党派層が拡大した。
▽初の小選挙区制選挙(1996年10月20日、第41回衆院選)
小選挙区比例代表並立制による初の選挙。自民党は239議席で半数に届かなかったが、連立を組む自民、社民、さきがけ3党が過半数を確保し、政権を維持。新進党は156議席と振るわず、その後、党内抗争が激化、翌97年12月に解党した。
▽自民惨敗(1998年7月12日、第18回参院選)
自民党は44議席の惨敗を喫し、橋本龍太郎首相が退陣した。民主党が躍進し、共産党は倍増、無所属が20議席を獲得した。投票率は不在者投票の緩和、投票時間延長などで回復した。
▽自公保が連立維持(2000年6月25日、第42回衆院選)
小渕恵三首相が00年4月1日に自由党との連立解消を表明。2日未明、脳梗塞で倒れ、緊急入院。4日に小渕内閣は総辞職した。後継の森喜朗首相は公明党に加え、自由党から分裂した保守党との3党連立政権を発足。自公保連立が問われた衆院選で自民党は233議席と38 減、公明、保守両党も後退したが、与党3党で絶対安定多数を上回る271議席を確保した。野党は民主党が127議席と躍進、自由、社民両党も議席増、共産党は後退。
▽小泉ブームで自民大勝(2001年7月29日、第19回参院選)
財団法人「ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団」(KSD)汚職や外務省機密費事件、ハワイ沖の実習船事故の対応のまずさから森首相が公明党だけでなく自民党内からも退陣を求められ、01年4月に内閣総辞職。4候補で争った自民党総裁選に圧勝した小泉純一郎首相は「聖域なき構造改革」を掲げて選挙戦に臨み、自民64議席で大勝。与党3党が過半数を確保した。民主党は26議席と伸び悩んだ。
▽二大政党制(2003年11月9日の第43回衆院選、04年7月11日の第20回参院選)
各党が景気対策や社会保障政策などマニフェスト(政権公約)を掲げ、「政権選択」が問われた。自民党は解散時勢力を維持できず、過半数も下回る237議席だったが、公明、保守新両党を加えた与党三党では275議席と、絶対安定多数を確保。小泉首相は続投することになった。民主党も比例代表で第1党となるなど躍進。一方で共産、社民は伸び悩み、二大政党制の到来を感じさせた。 年金未納問題などが相次いで発覚し、イラク多国籍軍への自衛隊参加問題が争点となった04年の参院選は、自民党は選挙区、比例代表合わせても49議席にとどまり、公明党の議席を加えても、改選過半数に届かない敗北を喫した。 民主党は比例第1党となり、自民党を上回る50議席を獲得。共産は大幅に減り、社民も改選2議席維持にとどまり、二大政党制の流れはさらに加速した。
▽与党が3分の2議席(2005年9月11日、第44回衆院選)
郵政民営化法案が、参院で自民党議員の造反で否決されたことから、小泉首相は05年8月8日、「郵政民営化の是非を問う」として衆院を解散した。自民党執行部は、衆院で同法案に賛成しなかった議員を非公認とする一方、「刺客」と呼ばれた対立候補を擁立。「小泉劇場」とやゆされた。自民党は296議席を獲得。公明党の31議席と合わせ、与党は憲法改正の発議に必要な衆院の3分の2以上を占めた。衆院選での自民党単独過半数獲得は1990年2月の選挙以来で、96年に小選挙区制が導入されてからは初めて。
共産、社民両党は現有議席を上回るか、維持したのに対し、民主党は113議席と大惨敗。岡田克也代表は責任を取って辞任した。
自民党に公認されず、無所属となった亀井静香氏らが結党した国民新党や田中康夫長野県知事が代表となった新党日本も議席を獲得。新党大地を結成した鈴木宗男氏も当選を果たした。
▽ねじれ国会誕生(2007年7月29日、第21回参院選)
「政治とカネ」「年金記録不備問題」や「格差問題」など与党に強い逆風が吹き荒れた。「1人区」で民主党と野党系無所属候補は23勝6敗、「3人区」でも民主党が複数擁立した4県でいずれも2人の当選を決めるなど、民主党は公認候補で60議席、無所属の推薦候補を入れると65議席を獲得。「55年体制」が確立して以来、衆参両院で初めて自民党以外の政党が第1党となった。
一方、自民党は保守系無所属候補(後に追加公認)を含めても38議席にとどまり、1989年の宇野内閣での大敗に次ぐ惨敗を喫した。また与党の公明党も9議席、比例代表でも700万票台と厳しい結果となり、参院で与野党勢力は逆転。「ねじれ国会」が誕生した。
共産は1議席を減らし3議席、社民は現状維持の2議席にとどまり、二大政党の間に埋没した格好となった。国民新党は選挙区、比例代表で各1議席、新党日本も比例代表で1議席を獲得した。
▽政権交代(2009年8月30日、第45回衆院選)
政権を投げ出す形で辞任した安倍晋三、福田康夫両首相の後を継いだ麻生太郎首相は、当初検討していた就任直後の衆院解散を見送り、追加経済対策の実施に取り組んだ。しかし定額給付金など政策をめぐる発言のぶれ、漢字の誤読や失言が重なって内閣支持率は急落。任期満了を前に、09年7月21日、衆院解散に踏み切った。
民主党は政権交代を訴え、308議席を獲得し圧勝。戦後初めて野党第1党が選挙で過半数を取り政権を奪取した。9月中旬の特別国会で鳩山由紀夫代表が首相に選出され、社民、国民新両党との連立内閣が発足した。自民党は選挙前の300議席から119議席に落ち込む歴史的惨敗。1955年の結党後、初めて、衆院第1党から転落した。麻生首相は退陣と党総裁辞任を表明。
▽再びねじれ(2010年7月11日、第22回参院選)
米軍普天間飛行場移設問題や「政治とカネ」問題で引責辞任した鳩山由紀夫首相の後を受けて就任した菅直人首相は支持率回復を受けて通常国会延長を見送り、早期選挙の日程を組んだ。しかし自らの消費税増税発言で支持率は急低下。民主党は改選議席54を44に減らす惨敗で、29ある1人区のうち勝ったのは8選挙区だけ。非改選合わせて与党系は参院過半数(122)を12議席割り込み、再びねじれ国会を招いた。ただ菅首相は続投。自民党は改選38から51と改選第1党。消費税率引き上げに反対したみんなの党が改選獲得議席10で公明党を上回る伸びを見せた。
▽自民政権奪還(2012年12月16日、第46回衆院選)
菅直人首相の後を継いだ野田佳彦首相は12年8月8日、自民党の谷垣禎一総裁、公明党の山口那津男代表と、消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革法を成立させた上で「近いうちに信を問う」ことで合意。首相は11月14日、党首討論で次期通常国会での衆院議員定数削減の確約を条件に「解散してもいい」と表明。この提案を自民党は受け入れ、衆院は16日に解散された。
自民、公明両党は計325議席を獲得し、約3年3カ月ぶりに政権を奪還した。参院で否決された法案を衆院で再可決できる3分の2を確保する圧勝。民主党は選挙前の230議席を57議席に減らす壊滅的惨敗となった。12月26日の特別国会で自民党の安倍晋三総裁が首相に選出され、第2次安倍内閣が発足した。
▽ねじれ解消(2013年7月21日、第23 回参院選)
第2次安倍内閣発足後、初の大型選挙。安倍首相の経済政策「アベノミクス」の是非に争点を絞り込み、圧勝につなげた自民党は、現行制度で過去最多となる65議席を獲得。非改選議席を合わせると、自民、公明両党は過半数122議席を超え、衆参両院の「ねじれ」が解消された。民主党は結党以来最低の17議席で惨敗。共産党は現行制度で過去最多の8議席を得た。
▽自公圧勝(2014年12月14日、第47回衆院選)
安倍首相は14年11月18日、消費税率10%への引き上げに関し、予定していた15年10月から1年半延期すると決め、この方針について国民の信を問うため、衆院を解散すると表明。衆院は21日に解散された。 自民、公明両党は定数の3分の2を上回る325議席を獲得し、圧勝した。民主党は公示前の62議席から73議席に上積みしたが、海江田万里代表は落選し、代表を辞任した。共産党は公示前の倍以上の21議席となった。「1票の格差」是正のため、小選挙区は前回から定数が5減り、定数295となった。
第7章 政党と政治家の資金 (4)
(1)国会議員の収入と政治資金
正副議長を除く衆参両院議員は歳費法の規定により、サラリーマンの給料に当たる歳費を月129万4千円受け取っている。ボーナスに相当する年2回の期末手当も含めると、年間で計約2106万円になる。ほかに年1200万円の文書通信交通滞在費も支払われる。文書通信交通滞在費は事実上の政治資金との指摘があるが、使途の報告義務はない。首相や閣僚らは、特別職の国家公務員としての給与のうち、歳費を引いた差額分が、歳費に上乗せされて支給される。ほかに、常任委員長など国会の役職に就いていれば、国会開会中に日額6千円の議会雑費がでる。国会会派ごとに立法事務費として議員1人当たり月65万円が支給される。
政治資金は、これらと別に支援者などからの献金やパーティー収入として集めるお金のこと。
(2)政治団体
政治団体とは政治的な活動を行う団体のことを一般に指す。政治資金規正法は政治上の主義や施策の推進、特定の政治家を支持するために設立された団体などと定義している。議員らの活動に関し、収支を明らかにすることで「国民の不断の監視と批判の下に」置くことを目的として、毎年、政治資金収支報告書を提出することが義務付けられている。
政治団体は①政党(「政党支部」を含む)②政治資金団体③その他の政治団体の3種類に分類される。政党助成法でも政党は定義されているが、要件は政治資金規正法とは異なる。
このうち②の政治資金団体は、政党がお金を集める受け皿として設置した団体のことで、自民党の「国民政治協会」などがある。全ての党が設けているわけではない。
③については、その他の政治団体は幅広い。主なものには国会議員が代表を務め、個人からの献金を受けるために一つだけ指定できる「資金管理団体」や、特定の議員の活動を支援するための後援会がある。日本医師会の政治活動を担う「日本医師連盟」を含む各業界がつくる政治団体、労働組合がつくる政治団体のほか、自民党のいわゆる派閥も該当する。
・政治家の三つの財布
政治団体のうち国会議員に関する団体は特別なくくりがあり、議員の政党支部、資金管理団体、後援会などを「国会議員関係政治団体」と位置付ける。ほかの政治団体よりも厳しいルールが設けられている。これらは俗に「政治家の三つの財布」と呼ばれることもある。政党支部で企業・団体献金を受け取り、資金管理団体で政治家が個人の寄付を受ける。後援会は議員本人や秘書が代表者である必要はないが、パーティー券収入など実質的に議員の資金を管理97 政治資金している場合がある。企業・団体献金をめぐり、1999年12月の規正法改正で、政治家の資金管理団体への企業・団体献金が禁止された。このため、資金管理団体は主に個人の寄付の受け皿に、政治家が代表を務める政党支部が企業・団体献金の受け皿になった。
・届け出義務
政治団体は政治資金規正法により、二つ以上の都道府県にまたがって活動する場合は総務相に、主として一つの都道府県の中だけで活動する場合は都道府県選挙管理委員会に、団体の目的、名称、主たる事務所の所在地、代表者、会計責任者を届けなければならない。
・収支報告書
政治資金規正法により、政治団体は政治活動に関する収支を明らかにしなければならない。暦年(1月〜12月)の政治資金収支報告書を原則として、翌年3月末までに複数の都道府県で活動する政治団体は中央分として総務相に提出する。一つの都道府県で活動する団体は地方分として都道府県選挙管理委員会に提出する。
このうち「国会議員関係政治団体」については、原則、翌年5月末を期限としている。総務省や都道府県選管は、官報や都道府県公報で提出期限に当たる年の11月末までに報告書の要旨を公表する。公表日から3年間は総務省や選管で閲覧や写しの交付を請求できるほか、総務省などはホームページ上でも公開する。報告書に不記載、虚偽記載の違法行為があった場合、5年以下の禁錮や100万円以下の罰金が科せられる。
報告書には①年間5万円を超える献金をした人の氏名等②一つの政治資金パーティーで20万円を超える支払者の氏名等③政治活動費のうち1件5万円以上の支出を受けた者の氏名等④土地、建物などの不動産や100万円を超える貸し付け、借入金など―を記載しなければならない。
政治家が寄付の受け皿とする「資金管理団体」と「国会議員関係政治団体」は、収支報告書に明細を記載すべき支出の範囲が拡大されている。資金管理団体は人件費を除く1件5万円以上の支出、国会議員関係政治団体は人件費を除く1件1万円超の支出を記載し、領収書を添付しなければならない。国会議員関係政治団体に限り、1円以上の全ての支出の領収書を保管する必要がある。報告書提出の際には登録された弁護士、公認会計士などの監査を受けることも義務付けられている。
(3)疑惑と改正
事件や疑惑が起きるたびに、規制を新たに設ける政治資金規正法改正が繰り返されてきた。リクルート事件や佐川急便事件をきっかけに政財界の癒着や政治家の不正蓄財への批判が高まったことを受け、企業・団体献金を受け取れる政治団体の範囲は縮小された。2004年に発覚した日本歯科医師連盟(日歯連)献金隠し事件では、政治資金の透明性確保を求める声が高まり、政治団体間の献金上限額に制限が設けられた。
(4)現在の制限と課題
国会議員の政治団体が多額の事務所費を計上していた問題を受け、2007年6月と12月に政治資金規正法が改正された。このうち6月の改正では、資金管理団体が収支報告書に記載すべき支出の範囲が拡大された。12月の改正では、国会議員関係政治団体の規定が新たに設けられ、該当する団体は1万円超の支出を収支報告書に記載し、「1円以上の支出」の領収書を保管することが義務付けられた。ただ、いずれも、別の団体にお金を移して支出すれば、報告書への記載や領収書の保管を逃れることもできるといった抜け道もある。
15年2〜3月、国の補助金交付が決まった会社・団体側から議員の政党支部への献金を受けたというケースが相次いで発覚した。企業側は、国の補助金交付決定通知から1年以内に献金すれば、認識の有無を問わず「違法」となる。
一方、受け取る議員側は、補助金交付決定の企業だと知りながら受け取れば「違法」だが、「知らなかった」場合は「違法」にならないなど「法の不備」も浮き彫りになった。議員を支援する任意団体が政治団体の届け出をせず、議員の政党支部に献金された閣僚の疑惑も浮上した。仮に、任意団体の実態が特定の議員を支援する政治団体であれば、政治資金規正法で定める政治団体届け出の義務が生じ、収支報告書を提出する必要がある。
(1)量的制限
・政党、政治資金団体への献金
個人は年間総額2千万円以内、企業・労組・団体は資本金・構成員数などに応じて年間総額で750万円以内から1億円以内までの献金が政党、政治資金団体に対してできる。この範囲内なら同一の相手方に対する個別制限はない。
・資金管理団体、その他の政治団体への献金
資金管理団体、その他の政治団体に対する企業・団体献金は禁止されている。個人は年間計1千万円以内(1団体への限度額は年150万円以内)の献金が資金管理団体、その他の政治団体に対してできる。
・政治団体間の献金
2006年1月1日から政党・政治資金団体以外の政治団体間の献金について年間計5千万円以内に制限された。
(2)質的制限
・補助金等を受けている企業・団体
国から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金を受けている企業、法人は交付決定の通知を受けた日から1年間は献金できない。地方公共団体から補助金などを受けている企業、法人は交付決定の通知を受けてから1年間は、その地方公共団体の長、議員、それらの候補者には献金できない。試験研究、調査、災害復旧など利益を伴わない補助金は制限の対象外で、独立行政法人からの補助金は国や地方公共団体からの直接の交付に当たらず対象外。
・赤字会社
3事業年度以上継続して赤字の会社は、欠損が埋められるまで献金できない。・外国人 ・外国法人
外国人や外国人が主たる構成員の企業・団体も献金ができない。しかし、2006年12月の改正で、日本の法人で国内の証券取引所に5年以上継続して上場していれば、外資の株保有比率が50%を超えていても、献金ができるよう緩和された。
・政治資金パーティー
政治資金パーティーは原則として、政治団体によって開催されなければならない。また収入が1千万円以上(と見込まれるものも含む)のものを特定パーティーと呼ぶ。誰であっても一つのパーティーに150万円を超えて支払いをしてはならない。
・企業・団体献金
企業や労働組合などが政治家の資金管理団体に対して行う献金は2000年1月から禁止された。これを受け、政治資金団体に加えて、政党支部が企業・団体献金の新たな受け皿になっている。
・政治資金の違反例
政治資金収支報告書への記載漏れや寄付制限違反など、明らかに違法な事例を除く(ただし、明らかに違法でも収支報告書の概要はそのまま公表される)と、次のような問題となる事例がある。
①回し献金 複数の政治家がそれぞれ同一金額を寄付し合う。悪質な場合、収支報告の記載だけで、実際に金が動かないケースもある。
②迂回(うかい)献金 政治団体への寄付の制限を超えて寄付を受けるため、いったん個別制限の緩い政党に寄付し、そこから政治団体へ寄付する。また、政治家が所得税の優遇措置を受けるため、一度政党へ寄付し、その後、その党から自分の政治団体に回す(政治家が自身の団体へ寄付しても優遇措置が受けられないため)
細川内閣の下での政治改革の一環として、政党に国が交付金を支給する「政党助成法」と政党に法人格を与える「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」(法人格付与法)が1995年1月1日施行され、同年から交付が始まった。①監査制度が形骸化している②交付金の使途に制限がない③領収書添付に抜け道があり、流用が容易にできる④支部長となる国会議員が自己の政治資金と混同しがち―などの問題点が指摘されている。
(1)政党助成法上、交付の対象となる政党の要件
①国会議員が5人以上②直近の衆院選の小選挙区・比例代表、参院選の比例代表・選挙区、前々回の参院選の比例代表・選挙区のいずれかで、得票率が全国の有効投票総数の2%以上かつ1人以上の国会議員を有する―のいずれかを満たす政治団体
(2)交付金の計算方法
最新の国勢調査による人口に1人当たり250円を掛けた額が年間の交付金総額となっている(2010年国勢調査で約320億円)。総額の2分の1を得票数に応じて配分(得票数割)し、残りの2分の1は議員数に応じて配分(議員数割)する。
(3)交付の原則
その年の1月1日現在で政党助成法上の政党要件を満たし、1月16日までに総務省に届け出ていれば、党が解散するか(ただし、合併、分割する場合は別)所属国会議員がゼロになるなどしない限り、原則として1年間交付を受けることができる。国政選挙があった場合には、その時点で交付要件を満たし、総務省に届け出ている政党に対し、その年の残りの交付金を国政選挙の結果を反映させて再計算し、交付する。 交付は、4、7、10、12月の4回に分けて行われる。
(4)使途の公表
国は政治活動の自由を尊重し、交付に条件を付したり使途を制限したりしてはならない。一方、政党は政党交付金の適切な使用が求められている。このため使途報告を通じて国民の批判と監視の下に置き適正化を図る。 政党本部は12月31日現在での収支を記した使途等報告書を翌年3月末までに総務相に提出、総務省は9月末までに要旨を官報で公表する。使途等報告書は5年間閲覧できる。
(5)政党の合併、分割、分派
次のような異動があった場合、特例としての計算をする(総務省への届け出が必要)
・合併
二つ以上の政党が合併した場合、合併によって解散する政党(合併解散政党)のその年の交付金残額を、吸収合併して存続する政党(存続政党)や合併によって新たに生まれる政党(新設政党)が受け取ることができる。翌年からは、合併解散政党の得票を自らの得票とすることができる。
・分割
分割協議が調った上で分割、解散した場合、分割によって解散する政党(分割解散政党)が受け取るはずだった交付金年額の残額を、分割によって設立された政党(分割政党)が議員数に応じて受け取ることができる。 翌年から交付金の「得票数割」を計算する際、分割解散政党の得票を分割政党の議員数に応じて配分したもの(国会議員の割合による)を各分割政党の得票とみなす。(議員数は選挙の際、分割解散政党で当選した議員に限られ、無所属で当選してその後その党に移った議員は配分の頭数に含まれない)
・分派
分割協議が調わない場合、「得票数割」は継承できない。「分派」した党はその年の政党交付金を受け取れず、その翌年以降も既に済んだ選挙の得票数はゼロのまま。・特定交付金 政党が交付対象とならない政治団体となった場合、要件を満たさなくなった日の属する月までの分を月割りで算出し、交付を受けられる。
・返還
政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付決定を受けた場合、総務相は交付を停止し、すでに交付された交付金の返還を命じることができる。政党交付金を受けた政党が、その年の交付金を支出に回さず、基金として積み立てない場合も、総務相は残額の返還を命じることができる。
(6)過去の交付例
・日本維新の会は2014年7月、橋下徹共同代表グループと石原慎太郎共同代表グループに分かれる形で解散し、橋下氏のグループは党名を引き継いだ新党「日本維新の会」に、石原氏のグループは新党「次世代の党」に分割された。新党の日本維新の会は同年9月、結いの党と合併し、「維新の党」となった。政党の分割には、新進党が国民の声、新党平和、自由党、新党友愛、黎明クラブ、改革クラブの6党に分かれた例もある。
国会議員はリクルート事件や佐川急便事件が契機となって1993年に施行された「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に基づき、資産や所得を公開している。閲覧開始日は、提出期限の61日後。保存期間は7年間。都道府県ならびに政令指定都市の議会、知事、市町村長も条例を制定し、資産公開するよう求めている。 ただし、閣僚の資産公開が配偶者や家族分まで含むのに対し、この法律による公開は、本人分だけ。しかも、衆参両院の議員会館で閲覧できるだけで、インターネットなどによる公開はしていない。虚偽記載の罰則規定もなく、実態を映し出しているのかは、政治家のモラルに頼らざるを得なくなっている。
(1)資産等報告書
任期開始日から100日を経過するまで、所属する院の議長に提出する。衆院選後は衆院議員全議員、参院選後改選された参院議員。
報告の内容は
①土地=所在、面積、固定資産税の課税標準額、相続取得ならその旨
②建物所有を目的とする地上権、または土地の賃借権=土地の所在、面積、相続取得ならその旨
③建物=所在、床面積、固定資産税の課税標準額、相続取得ならその旨
④預金(普通、当座預金を除く)、貯金(普通貯金を除く)、郵便貯金(通常郵便貯金を除く)
⑤有価証券=種類、種類ごとの額面金額の総額。株券は株式の銘柄、株数。金銭信託は元本の額
⑥100万円を超える自動車、船舶、航空機、美術工芸品
⑦ゴルフ会員権
⑧生計を同じくする親族に対するものを除く貸付金
⑨生計を同じくする親族に対するものを除く借入金
(2)資産等補充報告書
新たに有した資産で、12月31日現在所有する資産について、翌年4月1日から30日までの間、所属する院の議長に提出する。
(3)所得公開
前年に1年間、国会議員であった者は、4月1日から30104政治資金日までの間、前年分の所得として、所属する院の議長に提出する。
①総所得金額および山林所得金額
②他の所得と区分して計算された所得
③贈与により取得した財産で、当該財産に係る贈与税の課税価格
(4)関連会社等報告書
毎年4月1日現在、報酬を得て会社その他の法人の役職等に就いている場合に、当該会社、その他の法人の名称、住所、職名を記入する。肩書がなくても、「社員」などと記入し提出する。
特集 憲法改正 (5)
衆参両院に憲法調査会が設置された2000年以降、国会を舞台とした憲法論議は政局に翻弄されながらも少しずつ進んできた。憲法改正手続きを確定させる改正国民投票法は14年に施行された。自民党は15年の通常国会から改正項目の絞り込みへ向け、大災害などに備える緊急事態条項、環境権、財政規律条項の3項目を軸に議論を進める考え。最速の日程として16年秋の臨時国会での改憲原案発議を掲げる。憲法に新たな理念を書き込む「加憲」を掲げる公明党は、自民党ペースでの議論を警戒する。一方、民主党は安倍政権下での改憲論議に慎重姿勢を崩さない。維新の党は自民党への協力に前向きだ。共産、社民両党は改憲そのものに反対している。
*過去の憲法論議については、国会図書館がホームページで「日本国憲法の誕生」を特集しており、基本的な資料が次のアドレスに示されている。 http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/keisai.html
(1)2009年の政権交代まで(政党名は当時のものも含む)
2000年1月、衆参両院に憲法調査会が設置された。05年4月、それぞれ最終報告書をまとめ、各院議長に提出した。衆院はA4判で約700ページ。調査会での発言者(議員)全体の3分の2以上を占めた意見を「多数意見」と位置付けた。9条に関しては「自衛権および自衛隊について何らかの憲法上の措置を否定しない意見が多く述べられた」との遠回しな表現で、9条改正の方向を多数意見とした。その他、国連の集団安全保障活動への参加、非常事態の規定、前文への「日本の歴史、伝統、文化」の盛り込み―などを多数意見とした。参院はA4判で約550ページ。環境権などの新たな人権規定を憲法に設けるべきだとの意見を「趨勢(すうせい)」意見だと位置付けることで、憲法改正の方向性を出した。「趨勢」意見は自公民3党がおおむね一致した意見。9条については1項維持が共通認識、2項改正では賛否が分かれた、とした。二院制維持と参院改革の必要性は「共通認識」。
衆院側は国民投票法案を審議する場として05年9月、新たに憲法調査特別委員会を設置。憲法96条は国民投票を改正の要件としているが、国会発議までの手続きや国民投票の実施方法を定めた法律がなく、改憲にはこうした法整備を完了する必要があった。
自民党は立党50年となる05年に初めて条文形式の「新憲法草案」を発表し、民主党も05年に「憲法提言」をまとめた。自民、公明両党と民主党は国民投票法案の共同提出に向けた協議を進めたが、与党との対決姿勢を鮮明にした民主党の小沢一郎代表は06年5月、共同提案に参加しないと表明。協議は不調に終わり、与党と民主党は国民投票法案を別々に提出した。
その後、法案の一本化に向けた議論も合意に至らず、07 年5月には民主党案を取り込んだ与党の修正案が成立した。自民党が参院選の争点に改憲を掲げるため採決を強行したとして、民主党は批判。07年の臨時国会では、改憲論議の舞台となる憲法審査会が衆参両院に設置された。09年6月の通常国会で、衆院憲法審査会の委員数や手続きを定める審査会規程が与党の賛成多数により可決、制定された。
(2)民主党政権時代
2009年8月の衆院選を経て誕生した民主党を中心とする政権には、護憲を掲げて憲法審査会の凍結を求める社民党が参加した。国民投票法の採決強行による民主党と自公両党とのしこりもあり、憲法審査会は両院とも開かれない状態が続いた。11年5月に参院の規程整備を経て、11年11月にそれぞれ初めて開かれた。
投票年齢を「18歳以上」と定めた国民投票法は10年5月に施行された。民法の成人年齢と公選法の選挙権年齢も法施行までに18歳に引き下げることが付則に盛り込まれていたが、改正は期限までに実現しなかった。公務員の政治的行為の制限に関する「宿題」も積み残された。
ほぼ1年ごとに首相が交代する不安定な政治状況が続いたほか、東日本大震災への対応もあり、憲法論議は停滞した。自民党は10年の国民投票法施行に合わせて改憲案の国会提出を目指したが、党内に慎重論が強く断念した。
自民党はサンフランシスコ講和条約の発効から60年に当たる12年4月に新たな改憲草案を策定した。「国防軍」を創設する9条改正や、天皇を元首とする改正を盛り込んで保守色を強めたほか、96条で定める改憲発議要件の緩和も打ち出した。橋下徹大阪市長率いる大阪維新の会も96条改正や首相公選制の導入を訴えた。
憲法審査会は12年に入り、衆院では憲法各章の検証、参院では有識者ヒアリングなどをそれぞれ実施したものの、衆院解散をにらんだ与野党の激しい攻防のあおりで、議論は深まらなかった。
(3)第2次安倍政権以降
2012年12月の衆院選では自民、公明両党が圧勝し、日本維新の会も躍進した。安倍晋三首相は13年1月の衆院本会議で「まずは多くの党派が主張している96条の改正に取り組む」と明言し、その後、13年参院選での争点化にも意欲を示した。最終的には、96条を先行改正する首相方針に慎重姿勢を示した公明党に配慮し、自民党は参院選公約には明記しなかった。
衆参両院の憲法審査会は政権交代後、3月に再始動した。衆院では各章を検証する作業を13年5月に終えた。国民投票法で積み残された課題を解消する同法改正案は、与野党協議を踏まえて14年4月、自公両党と民主、日本維新の会、みんなの党、結いの党、生活の党の計7党が共同で提出し、6月に成立、施行された。①投票年齢は施行から4年間は「20歳以上」で、その後自動的に「18歳以上」に引き下げ②警察官や裁判官を除き、改憲の賛否を働き掛ける「勧誘運動」を公務員に認める③国民投票の憲法改正以外への拡大は施行後速やかに検討―が主な内容。
手つかずとなっていた選挙権年齢の引き下げについては、国民投票法の施行から2年以内に国民投票年齢と同時に引き下げる法整備を目指すことで、7党に新党改革を加108憲法改正えた8党が合意した。8党はプロジェクトチーム(PT)を設置し、18、19歳の未成年者による重大な選挙違反は原則、検察官送致(逆送)とする付則を盛り込んだ公選法改正案を15年3月に提出した(提出政党は衆院に会派のある6党)。通常国会中に成立させ、16年参院選での初適用を目指している。
自民党は14年4月から党員らを対象に、憲法改正に関する対話集会を各地で始めた。安倍首相は14年12月の衆院選を経て「憲法改正の必要性について、国民的な理解を深める努力をしたい」と改憲に強い意欲を示している。自民党は16年参院選までに、衆院憲法審査会の議論を中心として憲法改正項目を絞り込んだ上で、最速で16年秋の臨時国会で改憲を発議し、17年春に初の国民投票を実施したい考えだ。改憲には、衆参両院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要で、与党だけでは確保できない。そのため、民主党との協力が不可欠との立場だ。
だが、民主党は安倍政権下での憲法論議に消極的。公明党内には拙速を警戒する声が根強く、自民党の狙い通りに進展するかどうかは見通せていない。同党では改憲に前向きな与野党だけでPTをつくり、改正項目をまとめる案も浮上したが、憲法審査会が形骸化するとの懸念から当面は見送られた。
1946年11月3日 日本国憲法公布
47年5月3日 日本国憲法施行
97年5月 超党派の憲法調査委員会設置推進議員連盟が発足。会長は自民党の中山太郎元外相(後に憲法調査推進議員連盟に改称)
2000年1月 衆参両院に憲法調査会設置
04年12月 自民党が新憲法制定推進本部を設置
05年4月衆参両院の憲法調査会がそれぞれの議長に最終報告書を提出
9月 衆院が憲法調査特別委員会を新設 10月 民主党が「憲法提言」をまとめる 11月 自民党が新憲法草案を正式に発表
06年5月 自民、公明両党と民主党がそれぞれ国民投票法案を国会に提出
07年5月 自民、公明両党提出の民主党案を取り入れた国民投票法が成立
8月 衆参両院に「憲法審査会」設置
09年6月 衆院で憲法審査会規程を制定
10年5月 国民投票法が施行
11年5月 参院で憲法審査会規程を制定
11月 衆参両院の憲法審査会がそれぞれ初開催
12年4月 自民党が憲法改正草案を決定
14年4月 与野党7党(自民、民主、維新、公明、みんな、結い、生活)が国民投票法改正案を提出。自民党が憲法改正に向けた対話集会を初開催
6月 改正国民投票法が成立、施行
11月 衆院憲法審査会で共産党を除く7党が緊急事態条項の新設に言及
同 与野党7党(自民、民主、維新、公明、次世代、みんな、生活)が選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案を提出。衆院解散で廃案に
12月 第3次安倍内閣発足。安倍晋三首相は憲法改正に関し「必要性について国民的な理解を深める努力をしたい」と表明
15年2月 自民党が憲法改正推進本部の会合で、党改憲草案のうち9条、96条の改正などを「特に重要な項目」と位置付ける方針を示す
3月 与野党6党(自民、民主、維新、公明、生活、次世代と無所属議員)が公選法改正案を再提出
同 自民党大会。改憲実現に向けて「賛同者の拡大運動を推進する」と明記した運動方針を採択
(1)憲法審査会
国民投票法の成立に伴い、2007年8月の臨時国会で衆参両院に設置された。憲法改正原案の提出を受け、審議する。議員が原案を提出する場合、衆院で100人以上、参院で50人以上の賛同者を必要とする。審議の後、過半数の賛成で本会議に上程され、総議員の3分の2以上の賛成でもう一方の院に送られ、審査会と本会議で同様に賛成が得られれば「発議」されることになる。衆院の場合、現行制度では総議員は475人で、辞職や死亡で欠員が出ていたとしても3分の2である317人の賛成が必要となる。
改憲原案は、関連項目ごとに明確に区分けする必要があり、例えば9条改正と環境権の創設を一つの原案としてまとめることはできない。なお改憲原案を憲法審査会に提出することも「発議」と呼ばれるため、両院の3分の2以上の賛成を得た段階の発議は「国会発議」と表記し、原稿上区別する場合がある。15年4月現在、審査会長は衆院が保岡興治氏、参院が柳本卓治氏(いずれも自民党)。
(2)国民投票
国会発議の日から起算して60日から180日の間に行われる。賛成が投票総数の2分の1を超えた場合、改正案が承認される。投票用紙の「賛成」「反対」の欄に○印を記入する方式となる。
投票年齢は、2014年の改正国民投票法施行から4年間は「20歳以上」。各党は公選法の選挙権年齢を18歳以上110憲法改正に引き下げる法改正の後、国民投票法をさらに改正して投票年齢も4年後を待たずに「18歳以上」に下げる方針だ。
国民投票法に伴う課題には選挙権年齢のほか、民法の成人年齢と少年法の適用対象年齢もある。各党は公選法改正を先行させ、検討事項の多い民法・少年法は中長期的課題と位置付けている。自民党は成人年齢などに関し、15年4月から特命委員会で検討を開始した。
【自民党】
1955年の結党時の「政綱」に、「現行憲法の自主的改正」を掲げた。だが、池田勇人内閣以降、改憲は政権の課題としては事実上封印され、党側も結党20年、30年、40年の節目で綱領や付属文書の政綱の見直しの動きが出るたびに、「憲法改正」や「自主憲法」の文言を残すかどうかで攻防が繰り返された。自社さ政権下の95年の「新綱領」は改憲に触れず、同時に決定された「自民党新宣言」で「新時代にふさわしい憲法の在り方について、国民とともに論議を進める」などと言及するにとどまった。
2004年12月に小泉純一郎首相を本部長とする新憲法制定推進本部を設置。下部組織として新憲法起草委員会が置かれた。05年11月の立党50年記念党大会で新憲法草案を正式発表。自民党が初めて条文形式でまとめた前文も含む全面改正案で、9条は1項を残すものの2項を削除した。「9条の2」を設け、首相を最高指揮権者とする「自衛軍」の保持を明記した。軍事裁判所の設置も盛り込んだ。野党時代の12年4月には全11章からなる新たな憲法改正草案をまとめた。自衛隊を「国防軍」に改め、自衛権の保持も明記した。天皇を「日本国の元首」、国旗は日章旗、国歌は君が代と位置付けた。
最速で17年春の国民投票実施を目指し、憲法改正原案の取りまとめに向けて各党と積極的に議論を進める方針。緊急事態条項、環境権、財政規律条項を軸に絞り込みを目指す。9条など難しい項目は2回目以降の発議に先送りする方向だが、党内には「初回の発議で9条改正を問うべきだ」との意見も根強い。15年4月現在、党憲法改正推進本部長は船田元氏。
【公明党】
基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義は、憲法の骨格をなす人類普遍の原理だとして、3原則を堅持しつつ、新たに必要とされる理念・条文を現行憲法に加える「加憲」がもっとも現実的で妥当な手段だとの立場。2002年11月の党大会で打ち出した。14 年の衆院選公約にも明記された。
加憲の対象としては、環境権やプライバシー権といった「新しい人権」、地方自治の拡充などがなり得るとしている。ただ、環境権については公共工事など必要な開発の妨げになるとして、慎重意見もある。
憲法9条については戦争放棄と戦力の不保持等を定める第1項、2項は堅持した上で、自衛のための必要最小限度の実力組織として自衛隊の存在の明記や、国際貢献の在り111 憲法改正方についても加憲の論議の対象として慎重に検討するとの姿勢だ。
【民主党】
民主党は、綱領で「国民とともに未来志向の憲法を構想していく」としており、改正自体は否定していない。04年1月、菅直人代表が党大会で改正に向けた党内論議を提起し、05年10月に憲法改正案に盛り込む要素をまとめた「憲法提言」を発表した。
提言は、憲法に新たに自衛権を明記するが、「先の戦争が『自衛権』の名の下で遂行されたという反省に立って、『制約された自衛権』を明確にする」と強調。「『専守防衛』の考えに徹し、必要最小限の武力行使にとどめる」とした。武力行使を含む国連平和維持活動への関与の程度は日本が自主的に選択するとしたほか、首相のリーダーシップ強化のため首相への執政権付与を提言。「国民の義務」に代わる概念として「共同の責務」を提起し、「知る権利」や知的財産権など「新しい人権」も明記するとした。
しかし、与党が国民投票法を強行採決したことなどから、党憲法調査会を07年の参院選後に廃止し、11年5月の再開まで党内議論は停滞した。
15年1月に就任した岡田克也代表は、安倍晋三首相が「現憲法は米国がつくった」と批判してきたことを踏まえ「現憲法への嫌悪を感じる。首相の下での議論はリスクがある」と安倍政権下での議論を警戒している。
【維新の党】
綱領には「より効率的で自律分散型の統治機構を確立する」とうたい、「統治機構改革」のための憲法改正を訴えている。具体的には、道州制(92条関連)や一院制国会(42条関連)、首相公選制(67条関連)の導入を掲げる。行政の無駄遣い抑止に向けて米国並みに強力な会計検査機関を国会に設置することや、「憲法裁判所」を新設して時の政権による恣意(しい)的な憲法解釈を防ぐ案も主張している。松野頼久代表は『首相公選制や一院制など統治機構改革が1丁目1番地の政党だ。憲法改正は胸襟を開いて話し合おう』と安倍晋三首相に求めている。
【共産党】
綱領に「現行憲法の前文を含む全条項を守り、特に平和的民主的諸条項の完全実施を目指す」と明記している。14年衆院選公約では「憲法9条の精神に立った外交戦略で平和と安定を築く」と訴えた。
【社民党】
護憲の社民党は、14年の衆院選公約で、憲法の「平和主義」「国民主権」「基本的人権の尊重」の3原則を順守し、憲法の保障する権利を実現する法整備や政策を打ち出すと掲げた。平和憲法の理念に基づく安全保障政策の実現に向け、集団的自衛権の行使は認めず、平和創造基本法を制定して自衛隊を必要最小限に改編し、専守防衛を徹底すると主張している。
【生活の党】
15年の憲法記念日に出した小沢一郎共同代表談話は「何が何でも憲法を改正してはならぬというのもおかしな話」と主張。14年の衆院選公約は「集団的自衛権の行使容認112憲法改正は、憲法9条にのっとり断固反対する」とした。
【次世代の党】
綱領に「国民の手による新しい憲法、すなわち自主憲法を創り上げる」と規定した。基本政策では自衛権や自衛隊(国防軍)に関する規定の新設のほか、国家緊急権に関する規定を整備すると打ち出した。憲法改正の発議要件の緩和も盛り込んだ。
【日本を元気にする会】
憲法に関する統一的な見解はなく、今後、議論を深める考えだ。
【新党改革】
14年の衆院選公約で、新時代にふさわしい憲法改正の国民的議論を起こしていくとした。
特集 安保法制 (10)
政府は2015年5月14日の臨時閣議で、自衛隊の海外活動拡大を図る新たな安全保障関連法案を決定した。歴代政権が憲法9条下で禁じてきた集団的自衛権行使を可能とするなど、戦後の安保政策の歴史的転換に踏み切る内容となった。「専守防衛」の基本方針が根本から変容する。法案は自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動(PKO)協力法などの改正10法案を一括した「平和安全法制整備法案」と、国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能とする新法「国際平和支援法案」の2本。閣議決定に先立つ4月27日、18年ぶりに改定した日米防衛協力指針(ガイドライン)に盛り込んだ対米協力の拡大を裏付ける性格が色濃い。海洋進出を続ける中国を強く意識した。政府、与党は厳格な派遣要件を設け、歯止めをかけたと強調する。だが政府の裁量は依然広範で、なし崩し的に海外派遣が行われる懸念はぬぐえない。紛争に巻き込まれるリスクは、これまでになく高まる。
安倍晋三首相は12年12月の就任会見で、自国が攻撃を受けていなくても密接な関係にある他国への攻撃に共同で反撃する集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の検討を始める意向を表明。13年2月、第1次政権時代の07年に設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二元駐米大使)を再開した。14年5月、有識者会議が行使容認を提言すると、首相は政府、与党に憲法解釈変更の具体的検討を指示した。 自民、公明両党は、安全保障法制整備に関する与党協議会を開始。政府は検討対象として、米国に向かうミサイルの迎撃など自衛隊の任務拡大へ15事例を提示した。11回の会合を経て、与党は7月1日に行使の一部容認で合意したが、事例の可否の結論は棚上げした。 政府は7月1日の臨時閣議で「集団的自衛権の権利はあるが行使できない」としてきた従来の憲法解釈を変更。①日本や密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある②日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない③必要最小限度の実力行使にとどまる―とする新たな「武力行使3要件」を満たせば、集団的自衛権の行使は現行憲法下でも許されるとした。 これを受け自民、公明両党は具体的な安全保障法制の整備に向けて、15年2月13日から与党協議会を再開。7回の会合を経て3月20日に「具体的な方向性」と題した安保法制の骨格を公表し、関連法制の大枠を固めた。政府は個別の法案作成を本格化し、与党協議を経て5月14日に閣議決定、15日に国会提出した。6月24日に会期末を迎える通常国会を95日延長し、成立を図る。
集団的自衛権の行使容認を閣議決定した14年7月の憲法解釈変更を具体化するため、武力攻撃事態法改正などで対応。他国への攻撃であっても「日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態」を「存立危機事態」と定義し、武力行使を容認。政府、与党は、この定義に①国民を守るために他に適当な手段がない②必要最小限度の実力行使にとどまる―の2項目を加えた「武力行使の新3要件」を歯止めと主張。中東・ホルムズ海峡が機雷封鎖され、停戦前に機雷掃海する事例について、集団的自衛権行使が可能かどうか自民、公明両党間で認識に違いが残ったまま閣議決定に至った。
周辺事態法を「重要影響事態法」に改称し、事実上あった地理的制約を撤廃。日本周辺に限らず後方支援を可能とし、支援対象を米軍以外の他国軍にも拡大。重要影響事態を「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」と定義した。国際貿易やエネルギー輸送の要路の中でも、海洋進出を加速する中国と周辺諸国との対立が激化する南シナ海での活動を想定している。弾薬提供や戦闘作戦行動のため発進準備中の航空機への給油・整備などもできる。派遣は国連決議の有無を要件とせず、緊急時は事後の国会承認も認める。政府が重要影響事態と認定すれば派遣できる。政府は他国軍への後方支援を検討する場合、国際平和支援法でなく、まず重要影響事態に該当するかどうかを判断する考えだ。重要影響事態は、要件が緩いため安易に多用される恐れがある。
国際紛争に対処する他国軍を後方支援できる恒久法「国際平和支援法」が成立すれば、事態が起きるたびに時限立法の特別措置法を制定してきた従来と異なり、自衛隊の海外派遣がいつでも可能となる。活動範囲も「非戦闘地域」から「現に戦闘行為を行っている現場(戦場)以外」に広げた。重要影響事態法と同様に、弾薬提供なども可能。関連法案で唯一、「国会の例外なき事前承認」を派遣要件とした。国連決議も要件としたが、武力行使容認決議だけではなく、米中枢同時テロ非難決議のような決議も含めており、有志国連合への後方支援もできる。
国連平和維持活動(PKO)に似ているが、国連が統括していない活動を「国際連携平和安全活動」と位置付け、治安維持任務や人道復興支援のため、随時派遣できる態勢を敷く。治安維持と停戦監視任務のみ事前承認の対象で、国会閉会中や衆院解散時は事後承認も認める。既存のPKOとともに武器使用基準を緩和し、襲われた国連要員や他国部隊員を助ける「駆け付け警護」を容認。危険な任務への参加で、自衛隊員がトラブルに巻き込まれる可能性は高まる。
武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」に対処するため、電話による閣議で自衛隊に海上警備行動や治安出動を発令できる仕組みを導入する。適用するのは①武装集団による離島への不法上陸②国際法上の無害通航に該当しない外国軍艦対処③公海での民間船舶への侵害行為―の3類型。沖縄県・尖閣諸島を含む東シナ海や、南シナ海で海洋進出を活発化させる中国の存在が念頭にある。海上保安庁や警察が手に負えない場合に自衛隊が迅速に対応できる半面、武力衝突が生じかねず、事態をより深刻化させる危険も伴う。平時から日本防衛のために活動する米軍や他国軍の艦船などを防護できるよう自衛隊法を改正。
政府が憲法9条の下で禁じてきた集団的自衛権の行使を認めるため、従来の「自衛権発動3要件」に替わり、昨年7月に閣議決定した。憲法解釈変更の根幹に当たる。具体的には①日本や密接な関係の他国へ武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある②存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない③必要最小限度の実力行使にとどまる―場合に武力行使できるとし、武力攻撃事態法改正案に手続きを明記した。
1991年4月 湾岸戦争停戦後、政府が機雷除去のため自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣
92年6月 国連平和維持活動(PKO)協力法が成立
2001年10月 米中枢同時テロを受け、米艦船への補給などを可能にするテロ対策特別措置法が成立
03年6月 武力攻撃事態法など有事関連法成立
7月 自衛隊をイラクに派遣するイラク復興支援特措法が成立
12年12月 第2次安倍内閣発足
13年11月 国家安全保障会議(NSC)創設関連法が成立
14年4月 武器輸出禁止の政策を転換。輸出に関する「防衛装備移転三原則」を閣議決定
7月 政府が集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更を閣議決定
10月 日米両政府が防衛協力指針(ガイドライン)の再改定に向けて中間報告公表
12月 特定秘密保護法施行。衆院選で与党が3分の2を超える議席獲得
15年4月 日米両政府が防衛協力指針を再改定
5月 与党が安保法制で正式合意。政府が関連法案を閣議決定
(1)国際平和支援法案(新規)
(2)平和安全法制整備法案(一部改正10法案を一本化)
・自衛隊法
・国連平和維持活動(PKO)協力法
・周辺事態法
・船舶検査活動法
・武力攻撃事態法
・米軍行動円滑化法
・特定公共施設利用法
・外国軍用品海上輸送規制法
・捕虜取り扱い法
・国家安全保障会議(NSC)設置法
特集 日本人拉致問題 (4)
1970〜80年代を中心に、日本人が行方不明になる事案が相次ぎ、警察の捜査や北朝鮮を脱出するなどした元工作員らの証言によって、北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになった。日本政府は91年以降、北朝鮮に対し拉致問題について提起。北朝鮮は否定し続けたが、2002年の日朝首脳会談で初めて認めた。政府はこれまでに、17人を拉致被害者として認定し、帰国していない12人について、全員の帰国と真相究明を要求。実行犯の身柄引き渡しも求めている。
2002年9月17日、小泉純一郎首相が初めて訪朝し、金正日(キム・ジョンイル)総書記と首脳会談し、国交正常化に向けた日朝平壌宣言に署名した。金総書記は拉致を認めて謝罪し、5人が生存、8人が死亡、1人は入国の確認ができないと伝達。再発防止を約束した。日本政府は、生存者の本人確認や、北朝鮮が「死亡した」とした被害者の情報収集のため、調査団を同9月28日〜10月1日の4日間の日程で派遣した。
生存が確認された地村保志さんら5人は本人と確認されたが、死亡者については、交通事故や自殺など検証しようがない情報に限られ、松木薫さんのものと思われるとして示された「遺骨」は、その後の鑑定で別人のものと確認された。地村さんら5人は、10月15日に帰国した。曽我さんは政府に拉致被害者として認定されていなかったため、母のミヨシさんとともに追加認定された。
04年5月22日、小泉首相が再訪朝して金総書記と会談。金総書記は拉致再調査を約束した。地村保志さんと富貴恵さんの家族、蓮池薫さんと祐木子さんの家族の計5人が日本への帰国に同意。曽我ひとみさん家族3人も同7月18日に帰国した。
11月9〜14日、政府代表団が平壌を訪問し、北朝鮮当局者らと協議。北朝鮮側からは、横田めぐみさんの「遺骨」や被害者の所持品などの物証や情報の提供を受けたが、日本で「遺骨」の鑑定をしたところ、横田さんとは異なるDNAが検出された。
07年3月と9月に開かれた北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議の「日朝国交正常化のための作業部会」では、北朝鮮は「拉致問題は解決済み」との立場を繰り返した。08年6月に北京で開かれた実務者協議では立場を変更して拉致再調査を約束した。8月に瀋陽で行われた実務者協議で、北朝鮮は調査委員会を設置し、全面的な調査を行うことで合意。日本は、人的往来とチャーター機の規制解除を実施することを表明したが、北朝鮮は1か月後の9月4日、福田康夫首相の辞任を理由に調査を行わないことを表明した。
2012年12月に第2次安倍内閣が発足すると、安倍晋三首相は任期中に拉致問題の解決を目指す考えを表明。首相、外相、官房長官、拉致問題担当相で構成していた拉致121 拉致問題問題対策本部のメンバーに全閣僚を加え、組織を強化した。
日朝間の交渉は、しばらく表に出ることはなかったが、14年3月、小野啓一外務省北東アジア課長と、北朝鮮外務省の劉成日課長が中国・瀋陽で非公式に協議し、拉致被害者の横田めぐみさんの両親と娘キム・ウンギョンさんの初めての面会に合意した。面会は、3月10〜14日にモンゴル・ウランバートルで実現し、対話ムードが一気に高まった。
拉致問題解決に意欲を示す安倍政権と、経済の立て直しを目指す北朝鮮の思惑が一致した形とみられたが、北朝鮮は直後、事前の予告なしに弾道ミサイルを相次いで発射した。それでも、日本政府は対話の継続を決め、北京で3月30、31日、外務省局長級による公式協議を約1年4カ月ぶりに開いた。
5月26〜28日にはスウェーデンのストックホルムで局長級協議を再度開催。日朝両政府は29日、北朝鮮が「特別調査委員会」を設置して拉致被害者の再調査を始めることで合意したと発表した。同時に発表された合意文書では、特別調査委は、日本政府認定の拉致被害者のほか、拉致濃厚の行方不明者、戦後の混乱で現地に残った残留日本人、戦後に北朝鮮に渡った日本人妻、日本人遺骨問題について「同時並行的に」調査するとした。
7月1日、北朝鮮は北京での局長級協議で、特別調査委の権限や陣容を説明。北朝鮮の全ての機関を調査できる権限を付与し、委員長には金正恩(キム・ジョンウン)第1書記直属の秘密警察組織「国家安全保衛部」で副部長を務める徐大河(ソ・デハ)氏を任命した。拉致被害者のほかに、行方不明者、残留日本人と日本人妻、日本人遺骨をそれぞれ調査する4つの分科会を設置することになった。
菅義偉官房長官は3日の記者会見で、北朝鮮の対応を評価。初回報告の時期について「今夏の終わりから秋の初め」との見通しを示した。北朝鮮は4日に特別調査委を設置し、日本は同日、独自に科す経済制裁のうち人的往来や送金報告義務に関する制裁を解除した。
この後、日本政府認定の拉致被害者12人の安否情報を初回報告に盛り込むよう求める日本と、成果の出た分野から順次回答することで経済的な見返りを期待する北朝鮮と立場の違いが生じた。
外務省幹部は2014年8月下旬から9月上旬にかけ、少なくとも3回、中国などで北朝鮮当局と極秘接触し、初回報告では拉致被害者の安否情報の提示を求めたが、北朝鮮側は応じなかった。結局、北朝鮮は9月18日に北京の大使館ルートを通じて「調査は初期段階にある」と伝達。菅官房長官が「夏の終わりから秋の初め」とした初回報告の時期は先送りとなった。
政府は、調査の現状確認のため9月29日、中国・瀋陽で局長級協議を開催。宋日昊(ソン・イルホ)朝日国交正常化交渉担当大使は、平壌で特別調査委から直接調査状況を聞くよう提案した。
政府は、派遣の方針を早々に決定したが被害者家族や支援団体から、今後の交渉が北朝鮮ペースで進むことへの懸122拉致問題念の声が上がった。政府は訪朝の目的を金第1書記につながる特別調査委幹部に拉致の優先解決を直接要請することで、事態の打開を図るとして理解を求め、10月22日、外務省の伊原純一アジア大洋州局長をトップとした政府代表団の派遣を発表した。
同28、29両日に平壌で行われた協議では、平壌中心部の特別調査委庁舎で行われた。伊原局長は、徐委員長に対して「拉致問題が最優先」であることを繰り返し伝達し、調査の現状を聴取。北朝鮮側も、過去の調査について「時間的な制約がある中、特殊機関から出てきた一面的なものだった」と釈明し、「過去の調査結果にこだわらず、新しい角度からくまなく調査を深める」として調査に前向きな姿勢を示した。
菅官房長官は31日の記者会見で、初回報告の時期について常識的には年内になるとの見通しを表明。政府は、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に早期の調査報告を求めたが、北朝鮮から連絡はなかった。
15年1月末、中国・上海で伊原局長が、国家安全保衛部幹部と極秘に接触。早期の報告を求めたが、安否情報を示す時期は示されなかった。主張は平行線のままで、交渉は膠着状態に陥った。こうした状況を受け、安倍内閣は3月31日、期限を4月13日に迎える輸出入の全面禁止と、人道目的以外の北朝鮮籍船舶の日本入港禁止の制裁措置を2年間延長することを閣議で決定。チャーター航空便の日本乗り入れの禁止措置の継続も確認した。入港を禁止する北朝鮮籍船舶には貨客船「万景峰(マンギョンボン)92」が含まれる。
北朝鮮は4月2日、国連人権理事会で日本が拉致問題を取り上げたことや、日本の警察当局が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の議長宅を家宅捜索したことを非難し、日朝協議の中断を示唆する通知文を日本側に送付。これに対し、日本政府は「全く受け入れることはできない」と大使館ルートで抗議した。
政治年表 (2)
政治年表 *肩書は当時
【1945年】(昭和20年)
2・19硫黄島の戦い始まる
3・10東京大空襲、11日まで
3・26硫黄島の戦い終わる
3・26沖縄戦始まる
6・23沖縄戦での日本軍の組織的戦闘終わる
7・26米英と中国(当時の中華民国)が日本に無条件降伏を求めるポツダム宣言発表
8・6 広島に原爆投下
8・9 長崎に原爆投下
8・15ポツダム宣言を受諾し敗戦。鈴木貫太郎内閣総辞職
8・17東久邇稔彦内閣発足
10・9 幣原喜重郎内閣発足
11・2 日本社会党結成
11・9 日本自由党結成
11・16日本進歩党結成
12・18衆院解散。日本協同党結成
【1946年】(昭和21年)
4・10第22回衆院選
4・22幣原内閣総辞職
5・22第1次吉田茂内閣発足
5・24協同民主党結成
11・3 日本国憲法公布
【1947年】(昭和22年)
3・8 国民協同党結成
3・31衆院解散。民主党結成
4・5 第1回統一地方選挙
4・20第1回参院選。社会党が第1党に
4・25第23回衆院選。社会党は衆院でも第1党
5・3 日本国憲法施行
5・20第1回特別国会召集
5・24片山哲内閣発足
11・4 片山首相が平野力三農相を罷免(初の閣僚罷免)
【1948年】(昭和23 年)
2・10片山内閣総辞職
2・21首相指名選挙で衆院は芦田均氏、参院は吉田茂氏を指名
3・10芦田内閣発足
3・15民主自由党結成
10・15第2次吉田内閣発足(首相指名は14日)
11・12極東国際軍事裁判所がA級戦犯25被告に有罪判決
12・2 労働者農民党結成
12・7 昭電疑獄事件で芦田前首相を逮捕
12・23衆院が吉田内閣不信任決議を可決。衆院解散「なれ合い解散」。東条英機元首相らA級戦犯7人絞首刑
【1949年】(昭和24年)
1・23第24回衆院選
2・16第3次吉田内閣発足
3・7 金融引き締めで「ドッジ・ライン」実施
8・26シャウプ税制勧告概要公表。
9月15日に連合国軍総司令部(GHQ)が政府に全文を伝達
【1950年】(昭和25年)
3・1 自由党結成
4・28国民民主党結成
6・4 第2回参院選
6・25朝鮮戦争が勃発
7・11総評結成
8・10警察予備隊令公布、施行
【1951年】(昭和26年)
9・8 サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約に調印
10・24社会党が左右両派に分裂
【1952年】(昭和27年)
2・8 改進党結成
4・28サンフランシスコ講和条約、日米安保条約発効
8・28吉田首相が「抜き打ち解散」
10・1 第25回衆院選
10・15保安隊発足
10・30第4次吉田内閣発足
11・27池田勇人通産相が「中小企業の倒産・自殺やむなし」と発言、 28日通産相不信任決議を可決、29日辞任
【1953年】(昭和28年)
3・14衆院が吉田内閣不信任決議を可決、衆院解散「バカヤロー解散」
4・19第26回衆院選
4・24第3回参院選
5・21第5次吉田内閣発足
7・27朝鮮戦争休戦協定
【1954年】(昭和29年)
3・1 米がビキニ環礁で水爆実験
4・21犬養健法相が指揮権を発動し、佐藤栄作自由党幹事長逮捕許諾請求を阻止。22日法相辞任
7・1 防衛庁、自衛隊が発足
11・24日本民主党結成
12・7 吉田内閣総辞職
12・10第1次鳩山一郎内閣発足
【1955年】(昭和30年)
2・27第27回衆院選
3・19第2次鳩山内閣発足
10・13左右社会党が統一
11・15自由民主党結成(保守合同)
11・22第3次鳩山内閣発足
12・16自民、社会両党提出の原子力基本法成立
【1956年】(昭和31年)
5・14日ソ漁業条約に調印
7・8 第4回参院選
10・19日ソ共同宣言発表(国交回復)
12・18国連総会が日本の加盟を承認
12・23石橋湛山内閣発足
【1957年】(昭和32年)
2・23石橋内閣総辞職
2・25第1次岸信介内閣発足
【1958年】(昭和33年)
4・25岸首相が衆院解散「話し合い解散」
5・22第28回衆院選
6・12第2次岸内閣発足
【1959年】(昭和34年)
6・2 第5回参院選
12・14在日朝鮮人の北朝鮮への帰還事業始まる
【1960年】(昭和35年)
1・19日米新安保条約、地位協定に調印。朝鮮有事の際の日本の基地からの出撃、核搭載船などの領海通過、寄港を容認する日米密約
1・24民主社会党結成
5・19議長が衆院に警官隊を導入、自民党が会期50日延長を強行採決。20日、新安保条約を強行採決
6・15全学連主流派が国会に突入、女子東大生が死亡
6・19午前0時に新安保条約、関連協定自然承認
6・23新安保条約が発効、岸首相が退陣表明
7・19第1次池田勇人内閣発足
10・12浅沼稲次郎社会党委員長刺殺
11・20第29回衆院選
12・8 第2次池田内閣発足
【1961年】(昭和36年)
7・15国民協会(自民党の資金調達機関)設立
【1962年】(昭和37年)
2・15臨時行政調査会発足
7・1 第6回参院選
【1963年】(昭和38年)
11 ・21第30回衆院選
12・9 第3次池田内閣発足
【1964年】(昭和39年)
4・28日本が経済協力開発機構(OECD)加盟
10・10東京五輪開会式
10・25池田首相が病気のため辞意表明
11・9 第1次佐藤栄作内閣発足
11・17公明党結成
【1965年】(昭和40年)
6・22日韓基本条約に調印。後の戦後補償問題につながる請求権について「完全かつ最終的に解決した」とする日韓請求権協定も締結
7・4 第7回参院選
8・19佐藤首相が首相として初の沖縄訪問
11・19戦後初の赤字国債発行を決定
【1966年】(昭和41年)
1・15椎名悦三郎外相が外相として初の訪ソ
7・25日本初の商業用原発、日本原子力発電の東海原発が営業運転開始
12・27佐藤首相が衆院解散「黒い霧解散」
【1967年】(昭和42年)
1・29第31回衆院選
2・17第2次佐藤内閣発足
10・31吉田元首相、戦後初の国葬
12・11佐藤首相が衆院予算委で非核三原則を表明
【1968年】(昭和43年)
4・5 日米政府が小笠原返還協定に調印。6月26日、日本に復帰
7・7 第8回参院選
【1969年】(昭和44年)
12・27第32回衆院選
【1970年】(昭和45年)
1・14第3次佐藤内閣発足
6月 日米安保条約が自動継続
11・15沖縄で戦後初の国会議員選挙
【1971年】(昭和46年)
3・26東京電力福島第1原発1号機が営業運転開始
6・17佐藤首相とニクソン米大統領が沖縄返還協定に調印。米軍用地原状回復費400万㌦の肩代わりを密約
6・27第9回参院選
7・1 環境庁発足
【1972年】(昭和47年)
2・3 札幌冬季五輪開幕
3・27社会党の横路孝弘議員が衆院で、肩代わりの日米密約を暴露
5・15沖縄返還
6・17佐藤首相が退陣表明
7・7 第1次田中角栄内閣発足
9・25田中首相が訪中
9・29日中共同声明を発表、日中国交回復
12・10第33回衆院選12 ・22第2次田中内閣発足
【1973年】(昭和48年)
8・8 金大中拉致事件
10・6 第4次中東戦争。オイルショックへ
10・10日ソ共同声明(田中・ブレジネフ会談)
【1974年】(昭和49年)
6・26国土庁発足
7・7 第10回参院選
10・8 非核三原則で佐藤前首相にノーベル平和賞
10・22田中首相が外国人記者クラブで金脈問題について弁明
11・26田中首相が退陣表明
12・9 三木武夫内閣発足12月 創価学会と共産党が「創共協定」。75年7月に発表され無効化
【1975年】(昭和50年)
8・15三木首相が現職首相として初めて終戦記念日に靖国神社参拝
9・30天皇初訪米
11・15第1回先進国首脳会議(ランブイエ)
11・26公労協がスト権スト。12月3日に中止
【1976年】(昭和51年)
2・4 米上院外交委多国籍企業小委員会でロッキード献金事件が表面化
6・25新自由クラブ結成
7・27東京地検が田中前首相を逮捕
12・5 戦後初の任期満了で第34回衆院選。自民党大敗
12・17三木首相が退陣表明
12・24福田赳夫内閣発足
【1977年】(昭和52年)
7・10第11回参院選
11・15新潟市で下校途中の横田めぐみさんが行方不明に
【1978年】(昭和53年)
5・20成田空港開港
8・12日中平和友好条約に調印
10・17靖国神社が東条元首相らA級戦犯を合祀
11・26自民党総裁予備選で大平正芳幹事長が1位
12・7 第1次大平内閣発足
【1979年】(昭和54年)
3・28米スリーマイルアイランド原発事故
6・28第5回先進国首脳会議(日本初の東京サミット)
10・7 第35回衆院選。自民党単独過半数割れ
11・6 首相指名選挙決選投票で大平首相が、非主流派が推す福田前首相を破る
11・9 第2次大平内閣発足
【1980年】(昭和55年)
5・16衆院本会議で社会党提出の内閣不信任決議案が、自民党非主流派の欠席で可決
5・19衆院解散
6・12大平首相死去
6・22第36回衆院選、第12回参院選の衆参同日選挙。自民党圧勝
7・17 鈴木善幸内閣発足
【1981年】(昭和56年)
3・16臨時行政調査会(第2次臨調)が発足
【1982年】(昭和57年)
5・31中国の趙紫陽首相が来日
10・12鈴木首相が退陣表明
11・27第1次中曽根康弘内閣発足
【1983年】(昭和58年)
1・11中曽根首相が初の正式訪韓
1・18訪米した中曽根首相が、日米首脳会談で「日米運命共同体」と言明。これに先立つ米・ワシントンポスト幹部との朝食会での発言が「不沈空母発言」として報道される
3・14臨時行政調査会が増税なき財政再建の最終答申を提出
6・26第13回参院選。初の比例代表選挙を実施
10・12東京地裁、ロッキード事件で田中元首相に懲役4年、追徴金5億円の実刑判決
12・18第37回衆院選。自民党大敗
12・27第2次中曽根内閣発足。新自由クラブと連立
【1984年】(昭和59年)
8・21臨時教育審議会発足
9・6 全斗煥韓国大統領来日
【1985年】(昭和60年)
2・7 自民党田中派内に竹下登氏が「創政会」発足
2・27田中元首相が脳梗塞で入院
7・26国鉄再建監理委員会が分割・民営化の最終答申提出
8・15中曽根首相が靖国神社を公式参拝。その後、中国が反発
9・22「円高ドル安」を誘導するプラザ合意。その後の不動産バブルの発端
【1986年】(昭和61年)
4・26ソ連のチェルノブイリ原発4号機が爆発
5・4 第12回先進国首脳会議(東京サミット)
6・2 衆院解散「寝たふり解散」
7・6 第38回衆院選、第14回参院選の同日選挙。自民党圧勝
7・22第3次中曽根内閣発足
8・15新自由クラブ解党
9・6 社会党委員長公選で土井たか子氏当選
【1987年】(昭和62年)
4・1 国鉄分割民営化でJR6社開業
7・4 自民党竹下派結成
10・20中曽根首相が自民党後継総裁に竹下氏を指名
11・6 竹下内閣発足
【1988年】(昭和63年)
7・6 政界有力者、周辺へのリクルートコスモス未公開株譲渡が判明
7・23潜水艦なだしお事故
12・9 宮沢喜一蔵相がリ社株譲渡で辞任
12 ・24消費税関連法成立
【1989年】(昭和64年、平成元年)
1・7 昭和天皇逝去
1・8 新元号「平成」が施行
2・24大喪の礼
4・1 3%の消費税実施
4・25竹下首相がリクルート事件の責任などで予算成立後の退陣を表明
5・22東京地検が藤波孝生元官房長官と池田克也衆院議員を受託収賄罪で在宅起訴
5・25衆院予算委がリクルート関連疑惑で中曽根前首相を証人喚問
6・3 宇野宗佑内閣発足
7・23第15回参院選。自民党惨敗、与野党逆転
7・24宇野首相が退陣表明
8・9 首相指名選挙で衆院は自民党の海部俊樹氏、参院は社会党の土井氏を指名
8・10第1次海部内閣発足
11・21新「連合」が発足
【1990年】(平成2年)
2・18第39回衆院選
2・28第2次海部内閣発足
9・24金丸信元副総理、田辺誠社会党副委員長らの自社両党代表団が北朝鮮を訪問
9・28自社両党と朝鮮労働党の3党共同宣言を発表
11・12天皇即位の礼
【1991年】(平成3年)
1・17湾岸戦争始まる
1・24政府、自民党が湾岸戦争支援策として多国籍軍への90億㌦援助を決定
4・16ゴルバチョフ大統領がソ連元首として初来日
4・26自衛隊掃海艇がペルシャ湾に出航
11・5 宮沢喜一内閣発足
【1992年】(平成4年)
1・13加藤紘一官房長官が従軍慰安婦問題で旧日本軍の関与を認め、謝罪東京地検が共和リゾート汚職で阿部文男元北海道沖縄開発庁長官を逮捕
5・7 細川護熙前熊本県知事が新党結成発表。22日、日本新党と命名
6・9 参院本会議が自民、公明、民社3党賛成で国連平和維持活動(PKO)協力法案を可決
6・15衆院本会議でPKO協力法成立
7・26第16回参院選
8・27金丸氏が東京佐川急便からの5億円献金で自民党副総裁辞任を表明
9・17PKOによる自衛隊のカンボジア派遣部隊第1陣が出発
10・23天皇・皇后、初の訪中
11・26東京佐川急便事件で衆院予算委が竹下元首相を証人喚問、27日に金丸氏を臨床尋問
12・18自民党竹下派が分裂。小沢一郎、羽田孜両氏らが羽田派を結成
【1993年】(平成5年)
2・17衆院予算委が佐川急便事件で小沢元自民党幹事長、竹下元首相を証人喚問
3・6 東京地検が金丸前自民党副総裁を所得税法違反容疑で逮捕
4・6 渡辺美智雄副総理兼外相が健康上の理由で辞任
5・29北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイル「ノドン」発射実験
6・14衆参両院議員が初の資産公開
6・18衆院本会議で羽田派などが賛成に回り宮沢内閣不信任決議案を可決、衆院解散。自民党分裂
6・21新党さきがけ結成
6・23新生党結成
7・7 第19回主要国首脳会議(東京サミット)
7・18第40回衆院選。自民党過半数割れ
7・22宮沢首相が退陣表明
7・30自民党両院議員総会で河野洋平氏が渡辺元外相を破り党総裁に
8・4 政府が従軍慰安婦問題に関する河野洋平官房長官談話を発表
8・6 政権交代。首相指名選挙で細川護熙日本新党代表を指名。衆院議長に社会党の土井氏、初の女性議長
8・9 細川内閣発足。8党派連立
10・11ロシアのエリツィン大統領来日
12・14政府がコメの部分開放を決定
12・16田中元首相死去
【1994年】(平成6年)
1・29政治改革関連4法が成立。3月4日、改正政治改革法成立
2・3 細川首相が突然「国民福祉税」を提案、4日撤回
3・11東京地検が中村喜四郎前建設相をあっせん収賄容疑で逮捕
4・8 細川首相が退陣表明
4・25首相指名選挙で羽田孜氏を首相に指名。連立与党が社会党抜きで新会派「改新」を結成
4・26社会党が連立離脱
4・28羽田内閣が39年ぶりの少数与党政権として発足
5・7 永野茂門法相が「南京大虐殺でっちあげ発言」で辞任
6・21衆院予算委が細川前首相を証人喚問
6・25羽田内閣総辞職。政権交代
6・30村山富市内閣発足。自民、社会、新党さきがけ3党連立
7・20村山首相が国会で自衛隊合憲と発言
8・4 萱野茂氏が参院議員繰り上げ当選で、アイヌ民族初の国会議員
8・14侵略戦争発言で桜井新環境庁長官更迭
12・9 被爆者援護法が成立
12・10新進党が発足。新生党、日本新党、民社党などが参加
【1995年】(平成7年)
1・17 阪神大震災
3・20地下鉄サリン事件
7・23第17 回参院選。新進党40議席獲得し参院第2党に。投票率44・52%は戦後最低
8・15戦後50年の村山首相談話発表。「植民地支配と侵略への反省」をうたう
9・4 沖縄で3米兵が女子小学生を集団暴行
9・22自民党総裁選で、橋本龍太郎通産相が小泉純一郎元郵政相を破り当選
12・27新進党党首に小沢一郎氏
【1996年】(平成8年)
1・5 村山首相が退陣表明
1・11第1次橋本内閣発足。自民、社会、さきがけの3党連立
1・19社会党が「社会民主党」に党名変更
4・12日米両政府が沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場全面返還を発表
7・29橋本首相が靖国神社参拝
9・28旧「民主党」結成
10・20第41回衆院選。初の小選挙区比例代表並立制
11・7 第2次橋本内閣発足。社民、さきがけは閣外協力に
12・17ペルー日本大使公邸人質事件発生
12・26太陽党結成
【1997年】(平成9年)
4・1 消費税率5%にアップ
4・17改正米軍用地特別措置法が成立4・22ペルーの日本大使公邸に特殊部隊が突入、人質解放
9・23日米両政府が新たな防衛協力指針(ガイドライン)決定
9・25共産党の宮本顕治議長が引退
11・22山一証券経営破綻
12・3 行政改革会議が中央省庁再編の最終報告
12・27新進党が解党決定
【1998年】(平成10年)
1・4 新進党を自由党、国民の声、新党友愛、新党平和、黎明クラブ、改革クラブに分ける「分裂協議書」に署名
2・7 長野冬季五輪開幕・開会式
4・27民主党結成。菅直人氏が代表
6・1 社民党が与党離脱
6・9 中央省庁改革基本法が成立
6・22金融監督庁発足
7・12第18回参院選。自民党惨敗で13日、橋本首相が退陣表明
7・24自民党、総裁選で小渕恵三外相を第18代総裁に選出
7・30小渕内閣発足
8・31北朝鮮が三陸東方沖に弾道ミサイル「テポドン」を発射
10・20 新党さきがけ解党
11・7 新「公明党」結成
11・19自民、自由両党首会談で連立合意
【1999年】(平成11年)
1・14自民、自由連立の小渕改造内閣発足
3・11茨城県東海村でジェー・シー・オーのウラン加工工場臨界事故
3・23北朝鮮の工作船が領海侵犯。自衛隊発足以来の海上警備行動を発動
5・7 情報公開法成立
5・24日米防衛協力のための新指針(ガイドライン)関連法が成立
7・29改正国会法成立。衆参両院に憲法調査会を設置
8・5 野中広務官房長官がA級戦犯分祀と靖国特殊法人化を提唱
8・9 日の丸を国旗、君が代を国歌とする国旗国歌法成立
8・12組織的犯罪対策3法と改正住民基本台帳法が成立
9・21小渕首相が加藤紘一前幹事長らを破り、自民党総裁選で再選
9・25民主党代表選で鳩山由紀夫氏が代表に就任
10・5 自民、自由、公明の3党連立による小渕再改造内閣発足
12・28米軍普天間飛行場の移設先を沖縄県名護市辺野古沖と閣議決定
【2000年】(平成12年)
4・1 小渕首相が自由党との連立解消表明介護保険制度がスタート
4・2 小渕首相が脳梗塞で緊急入院。首相臨時代理に青木幹雄官房長官
4・3 自由党が分裂し保守党発足
4・4 小渕内閣が総辞職
4・5 自民党両院議員総会で森喜朗幹事長を第19代総裁に選出。第1次森内閣が自民、公明、保守の3党連立で発足
5・14小渕氏死去
6・25第42回衆院選。与党3党で絶対安定多数上回る271議席獲得
7・4 第2次森内閣発足
7・21主要国首脳会議(沖縄サミット)が名護市で開催
9・19共産党が第7回中央委員会総会で「前衛政党」を削除する党規約改正案提案。11月24日の党大会で正式決定
11・17加藤紘一元自民党幹事長が内閣不信任決議案賛成を明言する「加藤の乱」。21日の衆院本会議で加藤氏、山崎拓元自民党政調会長ら欠席
12・5 省庁再編対応の第2次森改造内閣発足
【2001年】(平成13年)
1・6 中央省庁再編。1府12省庁体制に
3・10森首相が自民党総裁選前倒しを提案。事実上の辞意表明
4・24 自民党総裁選で、第20代総裁に小泉純一郎元厚相を選出
4・26第1次小泉内閣発足。田中真紀子外相など女性閣僚5人、民間人3人。派閥均衡、派閥推薦の慣例崩す
7・29第19回参院選。自民党64議席獲得し大勝
8・13小泉首相が現職首相として5年ぶりに靖国神社参拝
9・11米中枢同時テロ
10・29テロ対策特別措置法成立。自衛隊は米中枢同時テロに対する米軍などの軍事行動の後方支援可能に
12・22国籍不明の不審船を海上保安庁の巡視船が銃撃、沈没
【2002年】(平成14年)
1・29小泉首相がアフガニスタン復興支援会議への非政府組織(NGO)参加拒否問題などで、田中外相更迭(辞任は1月30日)
4・21小泉首相が靖国神社参拝
5・7 新首相官邸で初閣議
5・31日韓共催のサッカー・ワールドカップ(W杯)開幕
7・26サラリーマンらの医療費自己負担率を3割にする改正健康保険法成立
9・17小泉首相が北朝鮮訪問。金正日総書記と国交正常化交渉再開に向けた「日朝平壌宣言」署名
9・30小泉改造内閣発足。柳沢伯夫金融担当相を更迭し、竹中平蔵経済財政担当相が兼務
10・15拉致被害者5人が北朝鮮から帰国
12・10民主党代表選で、菅直人前幹事長を新代表に選任。幹事長は岡田克也氏
12・24福田康夫官房長官の私的諮問機関が、無宗教の国立追悼施設が必要との報告書提出
12・25保守新党結成。代表は民主党を離党した熊谷弘前副代表
【2003年】(平成15年)
1・14小泉首相が靖国神社参拝。中国、韓国など強く反発
3・19ブッシュ米大統領がイラク攻撃開始と発表。小泉首相は20日、米支持表明
4・1 日本郵政公社発足
4・25国と都道府県負担で高速道を整備する新直轄方式を導入する改正高速自動車国道法成立
4・27衆参両院統一4選挙区補選。与党の3勝1敗
5・23個人情報保護関連5法成立
6・6 武力攻撃事態法など有事関連法成立
7・23「民由合併」。民主党の菅代表と自由党の小沢一郎党首が両党合併に合意。9月24日、正式合併
7・26イラク復興支援特別措置法成立
9・20自民党総裁選で小泉首相が亀井静香前政調会長らに大差をつけ再選
9・22 小泉再改造内閣発足。竹中平蔵金融・経財相は留任
10・5 民主党、自由党合併大会10・23小泉首相が宮沢喜一、中曽根康弘両元首相に引退求める。宮沢氏は同日、中曽根氏は27日、次期衆院選立候補断念を表明
10・26参院埼玉選挙区補選で、公募の自民新人勝利
11・9 第43回衆院選。与党3党で安定多数確保。民主党は177議席に躍進。
11・10保守新党が解党し、自民党へ合流決定
11・15社民党、辞任した土井党首の後任に福島瑞穂幹事長選出
11・19全閣僚再任で第2次小泉内閣発足
11・29イラクで日本大使館員2人殺害
12・9 イラク特措法に基づく自衛隊のイラク派遣基本計画を閣議決定。重火器携帯で「戦時」下の外国領土に出動するのは初めて
【2004年】(平成16年)
1・1 小泉首相が靖国神社参拝。就任以来4回目
1・17共産党大会で、天皇制と自衛隊を事実上容認する新綱領採択
1・26小泉首相がイラク南部サマワへの陸上自衛隊本隊の派遣決定
2・9 イラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊派遣承認案件が参院本会議で承認。日本単独で北朝鮮への経済制裁を可能にする改正外為法成立
4・8 日本人3人がイラク武装グループに拉致される。15日に無事解放
4・14日本人フリージャーナリスト2人がイラク武装グループに拉致される。17日に解放
4・25衆院統一補選3選挙区で自民全勝
5・7 年金保険料未払いで福田康夫官房長官辞任。10日、菅民主党代表辞任
5・18民主党両院議員総会で岡田克也幹事長を代表に選出。幹事長は藤井裕久元蔵相
5・21裁判員制度法成立5・22小泉首相が北朝鮮を再訪問し金正日総書記と会談。拉致被害者家族帰国。北朝鮮は安否不明者10人の再調査を約束、日本は25万㌧の食糧支援表明
6・2 道路4公団民営化関連法成立
6・5 徹夜国会で年金改革法成立
6・14有事関連7法成立。武力攻撃事態法などと合わせ、有事法制体系が整う。北朝鮮船舶を想定した特定船舶入港禁止特別措置法成立
6・18イラク主権移譲後に編成される多国籍軍への参加を閣議決定
7・11第20回参院選。自民党49議席に対し、民主党は50議席獲得。野党の「改選第1党」は1989年参院選の旧社会党以来
7・30参院議長に扇千景氏。初の女性参院議長。日本歯科医師連盟の1億円献金隠し事件で橋本元首相が派閥会長辞任
8・13沖縄県宜野湾市の沖縄国際大に米軍ヘリコプター墜落
8・30民主党代表選で、岡田代表無投票再選
9・10臨時閣議で郵政民営化の基本方針決定。純粋持ち株会社設立し、分社化する4事業を傘下に
9・27第2次小泉改造内閣発足。郵政民営化担当相を竹中平蔵経財相が兼務
10・23新潟県中越地震
10・31イラクで武装組織に拉致されていた日本人香田証生さんの遺体がバグダッドで発見される
12・9 イラクへの自衛隊派遣の1年間延長を閣議決定
【2005年】(平成17年)
1・7 大野功統防衛庁長官、04年12月26日発生のスマトラ沖地震で、陸海自衛隊に派遣命令
3・16島根県議会が2月22日を「竹島の日」とする条例可決
4・15衆院憲法調査会が最終報告書。9条含む憲法改正の必要性明示
4・20参院憲法調査会が最終報告書。新しい人権の明記について改正の必要性示す。9条改正は賛否両論併記
4・24衆院統一補選2選挙区で自民連勝
5・13改正祝日法成立。4月29日は「昭和の日」、5月4日が「みどりの日」に
7・5 郵政民営化関連法案が衆院本会議で5票差で可決。自民党の37人反対、14人が欠席、棄権
7・7 主要国首脳会議開催中に、ロンドンで同時多発テロ
8・8 郵政民営化関連法案が参院本会議で否決。小泉首相は衆院解散
8・15戦後60年の小泉首相談話発表
8・17綿貫民輔元衆院議長や亀井静香元自民党政調会長らが「国民新党」結成
8・20橋本元首相が政界引退
8・21自民党を離れた小林興起氏らが「新党日本」結成。代表は田中康夫長野県知事
9・11第44回衆院選。自民党は296議席で歴史的圧勝、公明党と合わせ全議席の3分の2以上に。民主党は113議席と惨敗、岡田代表は辞任表明
9・17民主党代表選で、43歳の前原誠司氏が菅前代表を2票差で破る
9・21第3次小泉内閣発足
10・14郵政民営化関連法成立。通常国会で反対した参院自民党議員20人のうち19人が賛成
10・31第3次小泉改造内閣発足。官房長官に安倍晋三幹事長代理
11・22自民党立党50年記念大会、新憲法草案を公表
11・24首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が皇位継承で女系容認、長子優先の報告書
【2006年】(平成18年)
1・14共産党の第24回大会で、不破哲三議長が退任
2・6 約3年3カ月ぶりに日朝国交正常化交渉
2・11社民党大会で自衛隊を「違憲状態」とする綱領的文書「社会民主党宣言」を採択
2・16民主党の永田寿康衆院議員が予算委で、ライブドア事件に絡んだ送金指示メールを取り上げる。28日、民主党が偽メールと謝罪
3・31民主党の前原代表が送金指示メール問題で引責辞任
4・7 民主党の新代表に小沢一郎氏就任
5・26参院本会議で行政改革推進法成立
6・16拉致問題で政府に経済制裁を促す北朝鮮人権法成立
8・15小泉首相が靖国神社参拝。終戦記念日は初めて。現職首相では1985年の中曽根氏以来、21年ぶり
9・12民主党代表選で、小沢代表が無投票再選
9・19国連安保理決議に基づき、政府が北朝鮮への金融制裁発動
9・20自民党総裁選で安倍晋三官房長官が第21代総裁に就任
9・26国会で安倍自民党総裁を第90代、57人目の首相に選出。初の戦後生まれ。第1次安倍内閣発足
10・9 北朝鮮が地下核実験を実施し、成功したと発表
10・22衆院統一補選、与党2勝
11・8 菅義偉総務相が電波監理審議会にNHK短波ラジオ国際放送での拉致問題の放送命令を諮問、同審議会は「適当」と答申。10日にNHKに放送命令
12・4 郵政造反組で自民党を離党した衆院の無所属議員12人のうち、平沼赳夫元経済産業相を除き復党
12・15改正教育基本法、防衛庁の省昇格関連法成立。海外派遣が自衛隊の本来任務に
12・27佐田玄一郎行政改革担当相が虚偽の政治資金収支報告書を提出していたとして辞任
【2007年】(平成19年)
1・9 防衛省発足
1・27柳沢伯夫厚生労働相が講演で女性を「産む機械」と発言
4・17長崎市の伊藤一長市長が暴力団員に銃撃され死亡
5・14自民、公明両党提出の憲法改正手続きを定める国民投票法成立
5・25公的年金記録不備問題で、安倍首相が衆院厚生労働委で時効撤廃し特別立法による救済を表明
5・28松岡利勝農相が議員宿舎で自殺、現職閣僚では戦後初
6・20教育改革関連3法、空自イラク派遣延長の改正イラク特措法成立
6・30久間章生防衛相が講演で、米国の日本への原爆投下を「しょうがない」と発言。7月3日辞任。
7・29第21回参院選。自民党は37議席と歴史的惨敗、60議席の民主党が第1党に躍進、与党過半数割れ。「ねじれ国会」に
8・1 事務所費問題で赤城徳彦農相を更迭
8・7 臨時国会で参院議長に民主党の江田五月氏を選出。野党議長は初
8・27安倍改造内閣発足
9・3 遠藤武彦農相が組合長理事を務める農業共済組合の補助金不正受給で引責辞任
9・12安倍首相が退陣意向表明
9・23自民党が福田康夫元官房長官を総裁に選出
9・25自民党の福田総裁を国会で第91代、58人目の首相に選出。初の親子2代の首相。首相指名選挙で参院は小沢民主党代表を選出。福田内閣発足
10・1 郵政民営化スタート
10・30福田首相と小沢民主党代表が党首会談
11・2 福田首相が、小沢民主党代表と断続的に2回会談し、連立政権協議を提案。小沢氏は党に持ち帰り後、拒否
11・4 小沢民主党代表が辞任表明。6日に撤回
11・14参院本会議で政府提示の人事案件28人のうち3人の再任を56年ぶりに不同意
11・28防衛装備品納入をめぐる収賄容疑で東京地検が守屋武昌前防衛事務次官と妻を逮捕
【2008年】(平成20年)
1・11参院本会議が新テロ対策特別措置法案否決。衆院本会議が再可決、成立。参院否決法案が衆院再可決で成立したのは57年ぶり
2・6 参院本会議、07年度補正予算案を否決。憲法60条に基づき政府原案通り成立
2・19千葉県・野島崎沖で、海自イージス艦「あたご」が勝浦市漁協の漁船と衝突、漁船沈没。父子2人不明。5月20日に死亡認定
2・21新テロ特措法に基づき、インド洋での洋上給油を約4カ月ぶりに再開
3・12参院が日銀総裁に武藤敏郎副総裁を昇格させる人事案を否決、不同意。19日に元大蔵次官の田波耕治国際協力銀行総裁を起用する案も不同意。日銀総裁が戦後初めて空席に
4・9 衆参両院が白川方明日銀副総裁の総裁昇格に同意
4・27衆院山口2区補欠選挙で民主党前衆院議員が大差で自民党新人を下す
4・30ガソリンの暫定税率を復活させる税制改正法が衆院で再可決、成立。みなし否決を経た衆院再可決による成立は56年ぶり2例目
5・13道路特定財源制度の08年度廃止と09年度からの一般財源化の基本方針を閣議決定。衆院で道路特定財源を08年度以降も10年間維持する改正道路整備費財源特例法が与党の3分の2以上の多数で再可決、成立
6・6 アイヌ民族を先住民族と認める決議を衆参両院が全会一致で採択、初の国会決議。省庁幹部人事の一元管理を盛り込んだ国家公務員制度改革基本法成立
6・11民主、社民、国民新3党提出の福田首相に対する問責決議が参院で史上初めて可決。12日に衆院が、内閣信任決議可決
6・13北朝鮮が日朝実務者協議で拉致被害者の再調査を約束し、「よど号」乗っ取り犯引き渡しも協力と町村信孝官房長官発表。政府は対北朝鮮経済制裁の一部解除方針決定
7・7 第34回主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミット)
7・14島根県・竹島について文部科学省は中学校の新学習指導要領社会科解説書に初めて記述と公表。李明博韓国大統領は遺憾表明、駐日大使の事実上召喚決定
8・2 福田改造内閣発足
8・28民主党の渡辺秀央、姫井由美子両氏ら参院議員3人が離党届提出、無所属の参院議員2人と新党「改革クラブ」結成。29日、姫井氏は離党届撤回
9・1 福田首相が辞任表明
9・15リーマン・ブラザーズ経営破綻。世界金融危機に
9・18標準報酬月額改ざん問題で、舛添要一厚生労働相が疑わしい記録を6万9千件と公表、社会保険庁の組織的関与をほぼ認める
9・19汚染米不正転売問題で「あんまりじたばた騒いでいない」と発言した太田誠一農相が引責辞任、白須敏朗事務次官は更迭
9・22自民党総裁選で第23代総裁に麻生太郎幹事長選出
9・24衆院本会議で第92代首相に自民党の麻生太郎総裁を選出、麻生内閣発足
9・25自民党の小泉元首相が今期限りでの政界引退表明
9・25中山成彬国土交通相が、成田反対闘争は「ごね得」、日本は単一民族などと発言、数時間後に撤回。28日、辞任
10・31防衛省の田母神俊雄航空幕僚長が植民地支配を正当化し「侵略はぬれぎぬ」との論文を発表、更迭される
【2009年】(平成21年)
2・17中川昭一財務相兼金融担当相が辞任。先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)閉幕後、もうろうとした状態で記者会見した責任を取った
3・3 西松建設の巨額献金事件で東京地検が政治資金規正法違反容疑で小沢民主党代表の公設第1秘書ら3人逮捕
4・5 北朝鮮が「光明2号」を打ち上げ、軌道進入に成功と発表。オバマ米大統領がミサイル「テポドン2号」と断定の声明
5・11民主党の小沢代表が辞任表明
5・16民主党代表選で鳩山由紀夫幹事長が岡田克也副代表を破り当選
5・25北朝鮮が地下核実験実施と発表、06年に続き2回目
6・12鳩山邦夫総務相が日本郵政社長の進退問題をめぐり辞任。事実上の更迭
6・30民主党の鳩山代表が05年から4年間で総額2177万円の虚偽記載を認め陳謝
8・8 渡辺喜美元行政改革担当相が新党「みんなの党」の結成を発表
8・30第45回衆院選で民主大勝308議席獲得。自民歴史的大敗119議席で初の第2党転落、麻生首相は党総裁辞任を表明。政権交代
9・1 消費者庁発足
9・16民主党の鳩山代表が衆参両院本会議で第93代首相に選出。民主、社民、国民新3党の連立内閣発足
9・28自民党総裁選で、谷垣禎一元財務相を総裁に選出
11・27行政刷新会議の「事業仕分け」第1弾終了、10年度概算要求の圧縮額は約7500億円、財政効果は1兆8千億円程度
12・4 参院本会議で日本郵政株式売却凍結法可決、成立
12・24鳩山首相の資金管理団体などの収支報告書虚偽記載で、東京地検が政治資金規正法違反罪で元公設秘書を在宅起訴、元政策秘書を略式起訴、首相は不起訴
【2010年】(平成22年)
1・1 社会保険庁を廃止し、非公務員型の特殊法人「日本年金機構」発足
1・13小沢民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入問題で、東京地検が小沢氏の個人事務所や陸山会事務所などを一斉に家宅捜索。15日、政治資金規正法違反容疑(虚偽記載)で元私設秘書の石川知裕衆院議員を逮捕
1・15北沢俊美防衛相がインド洋で給油活動する海自に撤収命令、約8年間の任務終了
1・24普天間飛行場移設問題が争点の沖縄県名護市長選で、反対派の稲嶺進氏初当選
2・4 収支報告書虚偽記入事件で東京地検特捜部は、小沢氏を嫌疑不十分で不起訴
3・9 日米密約を調査する外務省有識者委が日米安保条約改定時の核持ち込み容認など3密約を認定した報告書を提出。岡田克也外相は核持ち込みの可能性を指摘し政府見解を変更
3・26子ども手当法成立
4・10与謝野馨元財務相や平沼赳夫元経済産業相ら5議員が新党「たちあがれ日本」の結成発表4・19大阪府の橋下徹知事らが地域政党「大阪維新の会」設立
4・23舛添要一前厚労相ら参院議員6人が「新党改革」旗揚げ
4・27収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴相当」と議決。5月21日、東京地検は再度不起訴
5・18憲法改正手続きを定めた国民投票法施行
5・28日米両政府が普天間飛行場の移設先を沖縄県名護市辺野古周辺とする共同声明発表。署名拒否した社民党党首の福島瑞穂消費者行政担当相を罷免。30日、社民党が連立離脱決定
6・2 鳩山首相が民主党両院議員総会で退陣表明、小沢幹事長も辞任
6・4 菅直人副総理が民主党両院議員総会で新代表に選出、衆参両院本会議で第94代首相に指名
6・8 菅内閣発足
6・11国民新党の亀井静香郵政改革担当相が郵政改革法案処理をめぐり辞任
6・17菅首相が10年度中に消費税増税を含む税制改革案をまとめる考え表明、消費税率は自民党提案の10%を一つの参考とすると言及
7・11第22回参院選。民主党が44議席と大敗、非改選を含め与党は過半数割れ。再び「ねじれ国会」に
8・10日韓併合100年に際しての菅首相談話を発表、植民地支配を謝罪、文化財「朝鮮王室儀軌」の引き渡しを表明
8・151980年代以降初めて菅首相と全閣僚が靖国神社参拝を見送る
9・7 沖縄県・尖閣諸島周辺の日本領海内で中国漁船が海保巡視船に衝突
9・8 海保が公務執行妨害容疑で中国人船長ら逮捕
9・14民主党代表選で菅首相が、小沢前幹事長を大差で破り再選9・17菅改造内閣発足
9・24中国漁船衝突事件で、那覇地検が船長を処分保留で釈放を決定
10・4 東京第5検察審査会が2回目の議決公表。民主党の小沢元代表を強制起訴へ
11・1 ロシアのメドベージェフ大統領がロシア国家元首として初めて北方領土の国後島を訪問
11・5 中国漁船衝突事件の状況を撮影したビデオ映像のインターネット上の流出判明。10日、神戸海上保安部の海上保安官が関与認める
11・14柳田稔法相が地元の広島市での会合で国会答弁を軽視する発言。22日に辞任
11・26参院本会議で、中国漁船衝突事件の対応が不適切として仙谷由人官房長官と馬淵澄夫国土交通相の問責決議案可決
11・28沖縄県知事選で仲井真弘多氏再選、米軍普天間飛行場の県外移設をあらためて要求
12・15 菅首相が国営諫早湾干拓事業の開門調査や5年間の排水門常時開放を命じた福岡高裁判決の上告断念表明
【2011年】(平成23年)
1・14菅再改造内閣発足。経済財政担当相に「たちあがれ日本」を離党した与謝野馨氏。「脱小沢」路線を堅持
1・31収支報告書虚偽記入事件で、検察官役の指定弁護士が小沢民主党元代表を強制起訴
2・22民主党が小沢氏の判決確定までの党員資格停止処分を決定
3・6 前原誠司外相が外国人から献金を受けていた責任を取り辞任
3・11三陸沖を震源とする観測史上最大のM9・0の大地震発生、太平洋沿岸に大津波が到来(東日本大震災)。東京電力福島第1原発で全電源喪失。炉心冷却に異常、政府、初の原子力緊急事214年 表態宣言。12日夜までに半径20㌔圏の住民に避難指示
3・12福島第1原発1号機で燃料の一部が溶ける国内初の炉心溶融。原子炉建屋で水素爆発
3・143号機で水素爆発。東電が地域ごと順番に送電を止める「計画停電」を茨城など4県の一部地域で初実施
3・19菅首相が自民党の谷垣総裁に大連立を提案し入閣を要請、谷垣氏は拒否
3・23最高裁大法廷が、09年衆院選の「1票の格差」最大2・3倍は「違憲状態」と判断。「1人別枠方式」廃止を要求3・31菅首相が、30年までに原発を14基以上増やすとした政府のエネルギー基本計画の白紙化を表明
4・10統一地方選前半戦で、民主党が与野党対決型の東京、北海道、三重3知事選全敗。24日の後半戦も民主不振
5・6 菅首相が中部電力に静岡県の浜岡原発の停止を要請。9日、中部電が全面停止を決定
5・21菅首相と中国の温家宝首相、韓国の李明博大統領が福島市を訪問、原発事故の避難住民激励
5・22東京・迎賓館で日中韓3カ国首脳会談
6・2 菅首相が大震災と原発事故の対応に一定のめどがついた段階で退陣する意向を表明。衆院本会議で内閣不信任決議案否決
6・20東日本大震災復興基本法成立
6・27菅首相が新設の原発事故担当相に細野豪志首相補佐官、復興対策担当相に松本龍防災担当相を任命。自民党の浜田和幸参院議員を総務政務官に起用。7月5日、自民党は浜田氏を除名
7・1 政府が東京電力と東北電力管内の大口需要家を対象とする電力使用制限令を発動。第1次石油危機以来、約37年ぶり
7・5 松本復興担当相が被災地を訪問した際「知恵を出さないやつは助けない」と発言した問題で辞任
8・26菅首相が退陣を正式表明
8・29民主党代表選で野田佳彦財務相が新代表に決定。30日、野田氏を衆参両院本会議で第95代首相に選出
9・2 野田内閣発足。挙党態勢に配慮
9・10鉢呂吉雄経済産業相が福島第1原発周辺地域を「死の町」と表現した問題で辞任
9・26小沢民主党元代表の資金管理団体をめぐる事件で、東京地裁は衆院議員石川知裕被告ら元秘書3人に有罪判決
10・26総務省が10年国勢調査の確定値発表。総人口は1億2805万7352人。外国人を除く日本人は05年調査から0・3%減で、国籍別集計を始めた1970年以降で初の減少
11・11野田首相が環太平洋連携協定(TPP)交渉参加に向けた関係国との協議入り表明
11・19インドネシア・バリ島で日中韓3カ国首脳会談
12・9 参院が一川保夫防衛相と山岡賢次消費者行政担当相の問責決議可決
12・18野田首相と李韓国大統領が京都市で会談。従軍慰安婦問題で応酬
12・19北朝鮮が金正日総書記の17日死去を発表。後継者は三男の金正恩氏
12・26野田首相と中国の胡錦濤国家主席が北京で会談
12・29民主党会合で消費税率を14年4月に8%、15年10月に10%へ引き上げる税制改革案を了承
【2012年】(平成24年)
1・13野田改造内閣発足。一川防衛相、山岡担当相らを退任させ、岡田克也元外相を副総理兼社会保障と税の一体改革担当相に起用
2・10復興庁発足
4・8 日中韓3カ国外相が中国・寧波で会談
4・11北朝鮮の金正恩氏が朝鮮労働党第1書記に就任
4・16東京都の石原慎太郎知事が沖縄県・尖閣諸島を購入する方針表明
4・20参院が田中直紀防衛相と前田武志国土交通相の問責決議可決
4・26東京地裁が小沢民主党元代表に無罪判決。11月12日、東京高裁判決も無罪。その後、確定
5・13野田首相が温中国首相と北京で会談、尖閣諸島をめぐり激論。李韓国大統領を交え日中韓3カ国首脳会談
6・4 野田再改造内閣発足。防衛相に初の民間となる森本敏拓殖大大学院教授
6・15民主、自民、公明3党が社会保障と税の一体改革関連法案の修正に合意
6・16政府が定期検査中の関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の再稼働決定
6・26衆院本会議で消費税増税を柱とした社会保障と税の一体改革関連法案可決。民主党は小沢元代表ら57人が反対し造反。7月2日、小沢氏らが離党届提出。11日、衆参の49人で新党「国民の生活が第一」旗揚げ
7・3 ロシアのメドベージェフ首相が北方領土・国後島を訪問
8・8 野田首相が自民、公明両党首と会談し、衆院解散時期について「近いうちに信を問う」と表明
8・10一体改革関連法成立。李明博氏が竹島を韓国の現職大統領として初訪問
8・15羽田雄一郎国土交通相と松原仁国家公安委員長が靖国神社を参拝。閣僚の参拝は民主党政権で初
8・29日朝政府間協議を4年ぶりに北京で開催
9・11政府が尖閣諸島の3島を地権者から購入する契約を交わし、国有化。中国政府は撤回を要求9・12大阪市の橋下徹市長が新党「日本維新の会」結成を宣言
9・21野田首相が民主党代表選で再選
9・26自民党総裁選で安倍晋三元首相を第25 代総裁に選出。1回目の投票で1位だった石破茂前政調会長を決選投票で56年ぶりに逆転
10・1 野田第3次改造内閣発足。文部科学相に田中真紀子元外相
10・23田中慶秋法相が暴力団関係者との交際問題で辞任
11・14野田首相が自民党の安倍総裁との党首討論で、衆院定数削減を条件に16日の衆院解散を表明
11・15日朝外務省局長級協議をモンゴルで開催
11・16衆院解散
11・17日本維新の会に石原前都知事ら「太陽の党」が合流。28日、滋賀県の嘉田由紀子知事を代表とする新党「日本未来の党」が結成され、国民の生活が第一の小沢代表らが参加
12・12北朝鮮が長距離弾道ミサイル発射。「人工衛星発射に成功」と発表
12・16第46回衆院選。自民、公明両党が計325議席を獲得、約3年3カ月ぶりに政権奪還
12・25衆院選で惨敗した民主党の新代表に海江田万里元経済産業相
12・26自民党の安倍総裁を衆参両院本会議で第96代首相に選出。再登板は戦後2人目。自民、公明両党連立の第2次安倍内閣発足
12・27衆院選惨敗の日本未来の党が分裂。小沢元民主党代表らは「生活の党」に
【2013年】(平成25年)
1・16アルジェリアでイスラム武装勢力による人質事件。19日、アルジェリア軍の掃討終了。日本人10人を含む多数の人質が死亡
1・22政府と日銀が前年比2%の物価上昇率を目指すとの共同声明
2・12北朝鮮が地下核実験。06年、09年に続き3回目
2・22島根県主催の「竹島の日」式典に内閣府政務官が政府を代表し初出席
2・25麻生太郎副総理が韓国の朴槿恵大統領就任式に出席し、朴氏と会談
3・15安倍首相がTPP交渉参加を正式表明
3・20日銀総裁に黒田東彦前アジア開発銀行総裁が就任
3・22政府が米軍普天間飛行場の移設先とする沖縄県名護市辺野古沿岸部の埋め立てを県に申請
4・4 日銀が大規模な金融緩和
4・21麻生副総理が春季例大祭に合わせ靖国神社参拝。安倍首相は同日までに真榊奉納。23日、超党派国会議員168人が集団参拝。記録がある1989年以降で最多
4・28政府がサンフランシスコ講和条約発効から61年を迎え主権回復式典。米施政下に置かれた沖縄県は反発
5・15 13年度予算成立。5月の成立は1996年度以来17年ぶり
7・1 ブルネイで第2次安倍内閣発足後初の日韓外相会談
7・21第23回参院選で自民党が65議席獲得の圧勝。公明党と合わせて参院過半数を占め、「ねじれ国会」解消
8・8 内閣法制局長官に外務省出身の小松一郎駐フランス大使就任。集団的自衛権の行使容認に向けた異例の人事
8・15新藤義孝総務相と古屋圭司国家公安委員長、稲田朋美行政改革担当相の3閣僚が靖国神社を参拝。安倍首相は私費で玉串料を奉納9・5 安倍首相がロシアでの20カ国・地域(G20)首脳会合の場で中国の習近平国家主席、韓国の朴大統領とそれぞれ立ち話をし、初接触
9・7 国際オリンピック委員会(IOC)総会で20年夏季五輪の東京開催決定=現地時間
10・3 日米の外交・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)を東京で開催。日米防衛協力指針の再改定で一致
11・23中国が尖閣諸島を含む東シナ海上空に防空識別圏を設定
11・27「国家安全保障会議(NSC)」創設関連法が成立
12・6 機密漏えいに罰則を科す特定秘密保護法成立
12・17政府が初の「国家安全保障戦略」と新たな防衛計画大綱を閣議決定
12・26安倍首相が靖国神社参拝。06年の小泉首相以来7年ぶり。中韓両国が猛反発し、米政府も「失望した」と異例の声明
12・27沖縄県の仲井真知事が辺野古沿岸部の埋め立て承認
【2014年】(平成26年)
1・19沖縄県名護市長選で普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する現職の稲嶺進氏が再選
2・9 猪瀬直樹前知事の辞職に伴う東京都知事選で、自民、公明両党が支援した舛添要一元厚生労働相が初当選
2・28医療法人「徳洲会グループ」の選挙違反事件を受け、徳田毅衆院議員が議員辞職 3・20 14年度予算が戦後3番目の速さで成立
3・25安倍首相がオランダで朴韓国大統領と初会談。仲介したオバマ米大統領を交えた日米韓3カ国首脳会談の形式=現地時間
4・1 消費税率8%に。政府が武器輸出三原則に代わる輸出ルール「防衛装備移転三原則」を閣議決定
4・7 みんなの党の渡辺喜美代表が8億円借り入れ問題で引責辞任
4・20靖国神社の春季例大祭に合わせ、古屋国家公安委員長が靖国神社参拝。新藤総務相も22日に参拝。安倍首相は21日に真榊を奉納
4・23オバマ米大統領が国賓として来日。米大統領の国賓招待は1996年のクリントン氏以来18年ぶり
5・15安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が集団的自衛権の行使容認を提言
5・29日朝両政府が拉致被害者の再調査実施と制裁の一部解除で合意と発表
6・13改正国民投票法成立。憲法改正手続きが確定
6・20政府が従軍慰安婦問題をめぐる河野談話の検証結果を国会に報告
7・1 政府が憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定
7・4 北朝鮮が拉致被害者の再調査などに関する特別調査委員会を設置。日本政府は人的往来の規制など独自制裁の一部を解除
8・1 日本維新の会が解党。平沼赳夫元経済産業相らは「次世代の党」結成
8・9 岸田文雄外相がミャンマーで中国の王毅外相と初会談=現地時間
8・15新藤総務相、古屋国家公安委員長、稲田行政改革担当相の3閣僚が13年に続き靖国神社を参拝。安倍首相は私費で玉串料を奉納
9・3 第2次安倍改造内閣発足。女性閣僚は小渕優子経済産業相ら過去最多に並ぶ5人
9・11衆院議長の下で選挙制度改革を検討する有識者調査会が初会合
9・21橋下大阪市長ら日本維新の会が結いの党と合流し「維新の党」発足
10・18高市早苗総務相と山谷えり子国家公安委員長、有村治子女性活躍担当相の3閣僚が秋季例大祭に合わせ靖国神社を参拝。安倍首相は17日に真榊を奉納
10・20小渕経産相と松島みどり法相辞任。小渕氏は政治資金問題、松島氏は選挙区内でのうちわ配布が問題視された
11・10安倍首相と中国の習主席がアジア太平洋経済協力会議に合わせ北京で初会談
11・16沖縄県知事選で普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する翁長雄志氏が、移設手続きを進めた仲井真知事らを破り初当選
11・18安倍首相が消費税率10%への再増税を15年10月から17年4月に延期し、国民の信を問うと表明。21日、衆院解散
11・28みんなの党解党
12・10特定秘密保護法施行。行政機関は特定秘密の指定作業に着手
12・14第47回衆院選で自民、公明両党が計325議席を獲得し政権を継続。自民党単独では公示前から5減の290議席。民主党は微増したが、海江田代表が落選。沖縄の4小選挙区は辺野古移設反対派が勝利
12・24衆参両院本会議で安倍氏を第97代首相に選出。第3次安倍内閣発足
【2015年】(平成27年)
1・8 旧みんなの党所属の参院議員らが新党「日本を元気にする会」設立
1・11保守分裂の佐賀県知事選で自民、公明両党推薦候補敗北
1・18民主党臨時党大会で岡田克也代表代行を新代表に選出
1・20中東の過激派「イスラム国」とみられる組織が拘束した日本人2人の殺害を予告する映像公開
1・22日中両政府が海洋問題を話し合う「日中高級事務レベル海洋協議」を開催
1・24「イスラム国」による邦人人質事件で湯川遥菜さんが殺害されたとする画像がインターネット上に公開
2・1 「イスラム国」を名乗る組織が後藤健二さんを殺害したとする映像声明をインターネット上に公開=現地時間1月31日
2・2 安倍首相が中東地域の防衛駐在官の増員を検討する考えを表明
2・9 政府、与党が全国農業協同組合中央会(JA全中)の組織を抜本的に見直す農協改革案決定
2・10政府が新たな「開発協力大綱」を閣議決定。非軍事目的に限って他国軍への支援を容認
2・23西川公也農相が政治資金問題の責任を取って辞任
3・5 与野党6党が選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案を衆院に再提出
3・6 政府が、防衛官僚(文官)と制服組自衛官が対等な立場で防衛大臣を補佐することを盛り込んだ防衛省設置法改正案閣議決定
3・8 自民党が結党60年の節目の党大会で、憲法改正を前面に打ち出した運動方針採択
3・12沖縄防衛局が米軍普天間飛行場の移設先、沖縄県名護市辺野古沿岸部の埋め立てに向けた海底ボーリング調査再開
3・13日仏両政府が外務・防衛閣僚協議(2プラス2)で防衛装備品の共同開発に関する協定に署名
3・17関西電力が美浜原発1、2号機(福井県)、日本原子力発電が敦賀原発1号機(同)の廃炉をそれぞれ決定
3・18九州電力が玄海原発1号機(佐賀県)、中国電力が島根原発1号機の廃炉をそれぞれ決定チュニジアで武装勢力が観光客らを襲撃、日本人3人死亡、3人負傷
3・20自民、公明両党が新たな安全保障法制の骨格について正式合意
3・21日中韓外相会談が3年ぶりに開催。3カ国首脳会談開催へ努力する方針で一致
3・23沖縄県の翁長知事が名護市辺野古沿岸部の海底ボーリング調査の停止を沖縄防衛局に指示
3・24沖縄防衛局が翁長知事の指示取り消しを求める220年 表審査請求書と、指示の執行停止を求める申立書を農相に提出
3・26京都府警などの合同捜査本部が外為法違反容疑で在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)議長宅などを家宅捜索
3・30林芳正農相が沖縄県の翁長知事の出した作業停止指示の効力を一時的に停止すると決定
3・31政府が北朝鮮への独自経済制裁を2年間延長すると閣議決定
4・2 北朝鮮が日朝協議の中断を示唆する通知文を日本側へ送付
4・3 政府が、JA全中を一般社団法人に転換し、地域農協への監査権限をなくす農協法など農業関連法改正案を閣議決定
4・5 菅義偉官房長官が沖縄県の翁長知事と那覇市で初会談。普天間飛行場の名護市辺野古移設について平行線
4・8 天皇、皇后両陛下が太平洋戦争の激戦地パラオ初訪問
4・10日経平均株価が00年4月以来、約15年ぶりに一時2万円台
4・12統一地方選前半戦で、与党と民主党などとの対決となった北海道、大分県の知事選は与党系が勝利。41道府県議選で自民党が総定数の過半数を獲得
4・14福井地裁が関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を認めないとの仮処分決定。原発運転禁止の仮処分は全国初
4・17安倍首相と沖縄県の翁長知事が官邸で初会談。翁長氏は普天間飛行場の名護市辺野古移設作業中止を要求
4・20町村信孝衆院議長が脳梗塞のため入院するとして辞表を提出。後任は大島理森氏に
4・22 首相官邸屋上に小型無人機「ドローン」があるのを官邸職員が発見
安倍首相がジャカルタで開催されたアジア・アフリカ会議(バンドン会議)の60周年記念首脳会議で演説し、先の大戦への「深い反省」を表明
安倍首相が中国の習近平国家主席と約5カ月ぶりに会談。戦略的互恵関係の推進で一致 4・23高市総務相、山谷国家公安委員長、有村女性活躍担当相が靖国神社を参拝。安倍首相は真榊を私費で奉納
4・26統一地方選後半戦で、自民、民主両党対決型の5市区長選は自民、民主系ともに2勝。平均投票率は市長選、市議選、町村長選などいずれも過去最低
4・27日米両政府がニューヨークで外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)、新たな日米防衛協力指針(ガイドライン)決定
4・28安倍首相がオバマ米大統領とワシントンで会談し、日米同盟強化で一致。日本の首相による公式訪問は9年ぶり
4・29安倍首相が日本の首相として初めて米連邦議会の上下両院合同会議で演説。歴史認識をめぐり「先の大戦に対する痛切な反省」を表明。「侵略」と「植民地支配」への謝罪には触れず
5・12米空軍が新型輸送機CV22オスプレイ10機を17年から横田基地に配備すると日米両政府発表京都府警などが外為法違反容疑で朝鮮総連議長の次男らを逮捕
5・14政府、自衛隊の海外活動拡大を図る安全保障関連法案を閣議決定
5・17大阪都構想への賛否を問う住民投票が否決。大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長は政界引退の意向表明
5・19維新の党が、代表を辞任した江田憲司氏の後任に幹事長の松野頼久氏を選出
5・23中国の習近平国家主席が日中観光交流イベントで「歴史を歪曲することは許されない」とあいさつ。一方で日中関係改善への意欲を強調
5・26安全保障関連法案が衆院本会議で審議入り
コラム (6)
内閣の最高責任者である首相の毎日を追いかける総理番は、地方支社局から政治部に配属された記者が最初に担当する。共同通信の原稿上の表記は「首相」で統一されているが、この仕事だけはなぜか「総理」を使う。自宅や公邸からの出発、帰着を始め、会議や会合への出席、要人との面会を分単位で記録。「首相動静」として各加盟紙に掲載される。
総理番の一日は、朝、首相が出発する1時間以上前に自宅前に集合することから始まる。新聞、テレビ各社も数人の総理番記者を置くが、各社に動静を配信する共同通信と時事通信は特に責任が大きい。「番車」と呼ばれる車で首相の車列とともに移動し、夜は毎日24時まで自宅前で突然の来客などに備える。
首相の執務室がある官邸5階には記者は立ち入れないため、来客がエントランスを出入りする際に、首相との面会時間や会話内容、所属、氏名を矢継ぎ早に確認する。ぶら下がり取材に頻繁に応じた過去の首相と比べ、現在では直接首相と会話を交わす機会は減っているが、靖国神社参拝や閣僚の辞任など、フラッシュ級のニュースを目の当たりにするダイナミズムは変わらない。
一挙手一投足を記載する日本の首相動静は、世界各国と比べても格段に詳しい。過去には「知る権利の範囲を超えている」と国会で取り上げられたこともあるが、報道の大きな役割である「権力の監視」という点からも欠かせない仕事だ。
原則として毎週月曜日午後2時に国会記者会館2階で開かれる。政治部長や副部長、その週の前半関門と、官邸、平河(与党)、野党、霞(外務省)、国会長ら各クラブのキャップが相対す。ほかに、選挙センターの世論調査担当者、KKの政治部OBも参加する。
司会は前半関門が務める。まず、その週の主な予定を各キャップが報告し、参加者が共有。続けて、司会者が短期・中長期の取材テーマをいくつか取り上げ、当該のキャップを中心に、意見交換する。デスク側はその週の出稿メニューをおおむね想定し、キャップ側はどういう出稿が必要になるか判断する。
想定外の話題が出た場合や、政局の見立てでまごつくなど、準備不足でキャップが答弁に窮すると、部幹部のいらだちが募る。キャップが取材や病気などで欠席する場合、サブキャップが代理として出席する。これを多用するとサブから恨まれる。会議の最後は、部長が締める。事務連絡もあるが、部内人事の話が出ることも。
キャップ会で出た話は、前半関門が差し支えない範囲でまとめ、A4一枚の報告書となる。政治部出身の地方デスク、編集委員、社幹部がこれを楽しみにしているとか。
記者クラブのキャップを2つ、3つやり、40代も半ばとなると、汐留の政治部に上がり、デスクをやることになる政治部員は多い。デスクトップと長時間にらめっこしているので、視力は一層衰え、腰も悪くなる。老眼も出始める。現場の記者と比べると、圧倒的に体を動かさないのに、飯は食べ、酒も飲むので、腹が出る。
日々の出稿で、政治部長をのぞくと、最も責任が重いのが関門デスクだ。月、火、水の前半関門、木、金、土、日の後半関門は、道路を隔てた薄暗いホテルに泊まり込む。バイキング方式の朝飯を「うまい」という人種と「まずい」という人種に分かれる。
朝7時から出る早出、午前10時から出る日勤、午後5時から午前2時までの夜勤というシフトがある。ただ、何かあると、朝から晩までになりがちだ。
ニュースセンター、あるいは部長と、現場の間に立ち、中間管理職の悲哀を感じる時があったり、あるいは、現場に圧力を掛ける「悪代官」になったりと、鵺(ぬえ)的な存在でもある。ただ、判断が奏功し、大きく加盟紙の紙面を飾ると、執筆者とはまた違う、独特の喜びがある。そんな瞬間があるから、今日も、いい原稿にしようとジタバタしている。
「金帰火来」をご存じだろうか。日々、東京・永田町で過ごす国会議員が金曜夜に選挙区に戻り、地元で有権者の声に耳を傾け、火曜に東京に戻るさまを言う。
もし、本当にそうならば、政治部記者にとって、金曜夜から月曜朝までは「取材対象」がいなくなる、心と体を開放する絶好のチャンスのはずだ。
だが、忙しい日曜日も少なくない。早朝から政治家が出演するテレビ番組が続くからだ。午前7時半からのフジテレビ「新・報道2001」。午前9時からはNHKの「日曜討論」。自宅でテレビ観戦する場合もあるが、ほとんどがテレビ局に出向いて、ロビーや控え室でモニターを見ながら、政治家の発言を記録する。番組が終われば、テレビ局から出てきた政治家を捕まえ、発言の真意を尋ねることも多い。与党は今、自民、公明の2党だが、野党は数が多いので、掛け持ちするケースもある。
日曜討論などは、各党幹部が一堂に会して、その時々の重要テーマについて議論することもある。番組終了後は、スタジオや、控え室で政党の垣根を越えて会談する場面もある。テレビ局の幹部が、出演した有力政治家と、局内の応接室で、番記者を交え懇談している気配もある。気が抜けない、なんだかせわしい気分のまま原稿を処理していると、すっかり午後になっている。
国会論戦の詳細をメモに取り、やりとり要旨の記事を作る仕事。語源は不明。衆参両院の本会議の「代表質問の詳報」、予算委員会の「論戦の焦点」が代表例。トリテキ隊は「隊長」と「ヒラトリ」の計3〜4人で、政治部各クラブから国会記者会館に派遣されて作業する。部隊編成は本来、関門デスクの仕事だが、国会長が代行することも多い。本来業務で多忙を極める各クラブの協力を得るのは、国会長の最も気が重い仕事だ。
従来はNHKが中継する代表質問と首相出席の予算委質疑、党首討論に限られていた。近年は大型法案の質疑など、首相が出席しない審議でも出稿を求められている。
記事の基本は、質疑の「本記」で使用した答弁をそっくり取り上げ、対応する質問を付ける。本記に使わなかった議員の質疑も、主な質問と答弁で短いやりとりを作る。
行数調整はトリテキ隊長の任務。汐留では午後5時から勤務が始まる夜勤デスクが、250行から300行の詳報の作業を行う。本記、表層深層、最前線などのサイド記事と、齟齬がでないようにしながら、できるだけ早く送信する〝体育会〟的な仕事でもある。
メモが手書きの時代は「詳報」などの記事作成が主な役割だったが、パソコン作業が主流になり、他の記事執筆に便利な質疑の「全起こしメモ」も期待されるようになっている。
原則午前11時と午後4時の1日2回、首相官邸1階の会見室で行われる。内閣の要として多忙を極める重要閣僚がこれだけの頻度で会見に応じるのは世界的にも珍しい。
会見室の最前列には、各社の官房長官番が座る。質問テーマや時間の制限はない。国内政治にとどまらず、国際情勢や社会問題まで森羅万象に及ぶ。重要案件が重なった場合は30分を超えることも。政府の公式見解を問う貴重な機会だ。2009年からの民主党政権時代、毎日行われていた首相ぶら下がり取材が廃止されたため、その後、重要度は増している。
ただ政権側にとって相当な負担なのは間違いない。ゴールデンウィークや年末年始などは1日1回となるのが慣例だ。2014年衆院選では、菅義偉官房長官は全国遊説を優先したため、参院議員の世耕弘成官房副長官が代行した。
日本最大級の記者クラブである内閣記者会に所属する新聞、通信、テレビ、ラジオ各社や、外国プレスのほか、ネットメディアやフリー記者も参加する。インターネット動画配信サイトで同時中継され、記者の質問に対しても容赦なくコメントが書き込まれる。なれ合いや不勉強な質問は禁物だ。
編集後記 (1)
政治ハンドブックを4年ぶりに改訂した。前回2011年版を政治部で担当した後藤新・高知支局長からは、データを全ていただき、指導してもらった。前回、組み版を担当された山口英明さんからも、本作りについて、一から教えてもらった。実際の編集作業では、ビジュアル報道局の小野完次編集委員、校閲部の母袋俊昭さんに、多大なる尽力をいただいた。メディアラボの鈴木維一郎室長、鳥井良二次長、堀内幸太郎さんにも、無理を言った。皆さま、本当にありがとうございました。そして、大洋社で編集を担当された矢部幸一さん、すてきなハンドブックになりました。感謝しています。
2015年5月31日
政治部担当部長 西野 秀